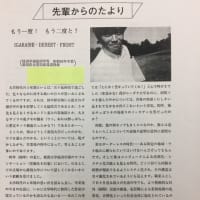新潟県の出先機関に身を置き、少しは地域のお役に立ちたいと思う日々。
****************************************************************
●令和6年10月7日(月)
倒伏した稲を刈る際は穂先のなびき方の違いに即してコンバインを細かく操作するなどと稲刈りの苦労話を新発田市の農業法人アシスト21の木村社長から聴く。3反田を1枚にした田圃では、傾斜を均すため補充した客土の厚みの違いによる地力差で伸び過ぎた部分だけ倒伏するなどのリアルな話は畔端ならでは。
倒伏した稲を刈る際は穂先のなびき方の違いに即してコンバインを細かく操作するなどと稲刈りの苦労話を新発田市の農業法人アシスト21の木村社長から聴く。3反田を1枚にした田圃では、傾斜を均すため補充した客土の厚みの違いによる地力差で伸び過ぎた部分だけ倒伏するなどのリアルな話は畔端ならでは。
●令和6年10月8日(火)
私が生まれて暫くして国道認定された新潟市からいわき市に至る289号。私が勤め始めた頃に三条市から只見町へ県境を跨ぐ最大の難所「八十里越」の新たな整備が起工され、いよいよ開通が見えてきた。目を見張る新工法などはないが40年近く豪雪地ゆえの半年工期の積み重ねは視察する心を熱くさせる。
●令和6年10月9日(水)
国道289号整備の難所「八十里越」の視察の折り返しに、福島県只見町の「手打ちそば処・八十里庵」に寄り”季まぐれセット”を頂く。細身だがコシのある蕎麦が異郷情緒を招き、天ぷらの茄子は子供の頃に夏を過ごした田舎の懐かしさが蘇る品種。新潟との交通利便向上に期待する女将の声が味わいを深めた。
●令和6年10月10日(木)
異業種から農業に転じて9年ほどで地域の中核として70haの稲作を担う新発田市の農業法人アシスト21の木村社長に、若者の参入を増やすべく農業への向き不向きを問うと、作業そのものは機械化が相当進み済なので、むしろ費用対効果の計算など経営感覚こそが重要という。農業の魅力発信の新機軸を感じる。
●令和6年10月11日(金)
経営効率化を重視する新発田市の農業法人アシスト21の木村社長は、ネギやオクラなど野菜も試行して、露地ものの端境期を狙うハウス栽培で利益も上げたが、温暖化等で戦術が難しく、基本は稲に注力する方針の模様。流通販売等にも手を広げず生産の高度化に専念するスタイルも生き残りの選択肢と感じた。
●令和6年10月12日(土)
令和の米騒動で苦労して入手した新米なのに、食卓で古米から切り替わったことに気付かず、新潟県民としての名折れと恥じるばかりだ。「新米ですよ」と言われて食べると何故に格別に美味く感じるのだろう。ヒトの味覚というのは気持ちも半分なのではないか。食材を話題にすることも味わいを増す薬味だ。
●令和6年10月13日(日)
遠い地に暮らす庶民の生活感がふわり鼻腔の奥あたりに浮かぶような感覚を得ることがある。自分勝手なイメージなのかもしれないが。新潟市ヒロクランツで時折買う素朴な洋菓子を味わうと、死ぬまでに訪れることもないだろう遥か東欧の地が香るようだ。映画や洋書にも劣らないスイーツの力に恐れ入る。
(「R6.10.7-R6.10.13新発田地域振興局長の細々日記」終わり。「へたれ県職員の回顧録」の「仕事遍歴」シリーズで現在進行形の日記形式「R6.10.14-R6.10.20新発田地域振興局長の細々日記」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
☆「活かすぜ羽越本線100年」をスピンオフ(?)で連載始めました。
☆「新発田地域ふるわせ座談会」を日記と別建てで連載してます。
☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。
①「へたれ県職員の回顧録」の履歴リストはこちら
②「空き家で地元振興」の初回はこちら
③「ほのぼの日記」の一覧はこちら
➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら
☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。
①「へたれ県職員の回顧録」の履歴リストはこちら
②「空き家で地元振興」の初回はこちら
③「ほのぼの日記」の一覧はこちら
➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら