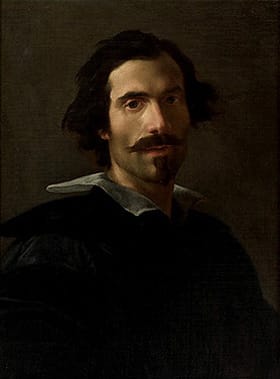「感動」とか「癒し」という言葉は決して安っぽい言葉ではなかったはずなのに、いつの間にか真顔で口にするのも恥ずかしいような単語に成り下がってしまいました。おそらく「絆」もそのうち同じ運命を辿ることでしょう。
それはさておき
1/5の続きでございます。
現代美術を集めた5F展示室へ行く前に、19世紀末の書物を描写したものとして興味を引かれたのが、アメリカの写実画家ジョン・フレデリック・ピートー作「学生の用具」でございます。

伏せて置かれているのは革装あるいはクロス装のソフトカバーのようです。本ではなくノートブックかもしれません。ヒラの部分が簡素なクロス装で背だけが革装のもの、全体がクロス装で背のタイトルラベルだけが革っぽいもの、革の部分の破損が著しいものなど色々ございますね。
それにしてもこれらの半革装本、あまりといえばあまりなボロボロぶり。
製本に使われている革の劣化についてちと調べてみますと、英国では早くも1900年には、過去一世紀ほどの間に製本された革装本の劣化の激しさについての問題意識が高まり、王立工芸委員会なる機関が委員会を設けて調査を行っておりました。それによると「一般に退化のはじまったのが1830年ごろからのことで、1860年以降になると退化がとくにいちじるしい」(『西洋の書物』A・エズデイル 1972 雄松堂出版 p.198)とのこと。その理由として考えられるのは、まず技術開発によるな革なめし方法の変化がございます。植物性で堅牢な仕上がりになる昔ながらの「タンニンなめし」から、鉱物性で時間がそれほどかからず、安価な上に発色よく仕上がる「クロムなめし」に移行したこと、また「燻煙なめし」に用いられたガスに含まれていた硫酸や亜硫酸も劣化の要因と考えられております。家畜の飼料や飼育環境の変化も、原料である皮の質の低下に寄与したと考えられましょう。要するに産業革命の大波を受けて、革という伝統的な素材すらも18世紀以前のようなクオリティを保てなくなったということでございます。
製本用クロスが普及しはじめたのが1820年代ということも考え合わせますと、この「学生の用具」はまさに当時の欧米製本事情を図示するものとして、史料的な面白さもございます。
さてキュビズムからビデオまで、20世紀以降の作品を集めた5階展示室、さすがに個性的な作品が揃っている中で妙に心惹かれたのがガラス作家ポール・スタンカードの「精霊のいるわすれな草」という小品でございました。
高さ10センチほどのガラスの立方体の中央に、何製なのかは分かりませんがワスレナグサの青い花が浮かび、その下にはふわりと根が絡まり、根の間には小さな真っ白い人間のようなものの姿が見えます。何とも乙女ちっくなテーマではございますが、それを臆面もなく作ってしまうという所にちょっと心打たれたのでございます。そう、臆面もなくするって、けっこう大事なことだと思うのですよ。それに、きっぱりと滑らかでクリアなガラスの、量感を感じさせない透明さや、ほんの少しだけ全体が面取りされ、またほんのわずかに上部をへこませた立方体の、いつまでも溶けない氷のような不思議なたたずまいは、それ自体たいへん魅力的なものであったのでございます。
いわゆるモダンアートとそれ以降を扱ったこのセクションにおいては、モチーフの変遷と共に絵画や工芸の役割そのものの変遷をも考えさせられました。モチーフにつけ表現方法につけ驚かされることが多いこの展示室の中で、ワタクシが一番驚いたのはモーリス・ルイスの「無題(死んだ鳥)」でございました。
画像は見つけられませんでしたが、↓とほぼ同じ作品でございます。おそらく同時期に描かれたものかと。
Here Be Old Things: New York City Auctions: January 12?18, 2009
ころんと仰向けになった小鳥の死骸が描かれた小さな作品、ごく地味な色調で、ペインティングナイフで引っ掻くように描かれた圧塗りの肌あい。これがあの、ゆるく溶いた絵具を広大なキャンバスの上にさあっと流し、美しい色彩の調和と観る者を包み込むような広がりを生み出した抽象画家モーリス・ルイスの作品とは、にわかには信じられませんでした。解説パネルによると、この作品の修復の再、今の画面の下に鮮やかな色が塗られていたことが分かったとのこと。うーむ、何があったんでしょうか。
描かれた鳥は古代の壁画のように素朴な造形でございまして、前回の記事でご紹介したモチーフは同じでも「死んだ鳥と狩猟道具のある風景」とは全く趣が異なります。単に技法の変遷ということ以上に、死んだ小さな生き物へ向けられる画家のまなざしが、裕福な顧客のために腕を振るう17世紀の画家のそれと、「芸術家=表現者」と言う概念が当たり前になった20世紀の画家のそれとではずいぶん違うということでもございましょう。
2つの「死んだ鳥」の間の隔たりは、人間の社会のありよう、そして人間とその周囲(=人間以外のものの世界)との向き合い方の変化を示すようでもございました。
それはさておき
1/5の続きでございます。
現代美術を集めた5F展示室へ行く前に、19世紀末の書物を描写したものとして興味を引かれたのが、アメリカの写実画家ジョン・フレデリック・ピートー作「学生の用具」でございます。

伏せて置かれているのは革装あるいはクロス装のソフトカバーのようです。本ではなくノートブックかもしれません。ヒラの部分が簡素なクロス装で背だけが革装のもの、全体がクロス装で背のタイトルラベルだけが革っぽいもの、革の部分の破損が著しいものなど色々ございますね。
それにしてもこれらの半革装本、あまりといえばあまりなボロボロぶり。
製本に使われている革の劣化についてちと調べてみますと、英国では早くも1900年には、過去一世紀ほどの間に製本された革装本の劣化の激しさについての問題意識が高まり、王立工芸委員会なる機関が委員会を設けて調査を行っておりました。それによると「一般に退化のはじまったのが1830年ごろからのことで、1860年以降になると退化がとくにいちじるしい」(『西洋の書物』A・エズデイル 1972 雄松堂出版 p.198)とのこと。その理由として考えられるのは、まず技術開発によるな革なめし方法の変化がございます。植物性で堅牢な仕上がりになる昔ながらの「タンニンなめし」から、鉱物性で時間がそれほどかからず、安価な上に発色よく仕上がる「クロムなめし」に移行したこと、また「燻煙なめし」に用いられたガスに含まれていた硫酸や亜硫酸も劣化の要因と考えられております。家畜の飼料や飼育環境の変化も、原料である皮の質の低下に寄与したと考えられましょう。要するに産業革命の大波を受けて、革という伝統的な素材すらも18世紀以前のようなクオリティを保てなくなったということでございます。
製本用クロスが普及しはじめたのが1820年代ということも考え合わせますと、この「学生の用具」はまさに当時の欧米製本事情を図示するものとして、史料的な面白さもございます。
さてキュビズムからビデオまで、20世紀以降の作品を集めた5階展示室、さすがに個性的な作品が揃っている中で妙に心惹かれたのがガラス作家ポール・スタンカードの「精霊のいるわすれな草」という小品でございました。
高さ10センチほどのガラスの立方体の中央に、何製なのかは分かりませんがワスレナグサの青い花が浮かび、その下にはふわりと根が絡まり、根の間には小さな真っ白い人間のようなものの姿が見えます。何とも乙女ちっくなテーマではございますが、それを臆面もなく作ってしまうという所にちょっと心打たれたのでございます。そう、臆面もなくするって、けっこう大事なことだと思うのですよ。それに、きっぱりと滑らかでクリアなガラスの、量感を感じさせない透明さや、ほんの少しだけ全体が面取りされ、またほんのわずかに上部をへこませた立方体の、いつまでも溶けない氷のような不思議なたたずまいは、それ自体たいへん魅力的なものであったのでございます。
いわゆるモダンアートとそれ以降を扱ったこのセクションにおいては、モチーフの変遷と共に絵画や工芸の役割そのものの変遷をも考えさせられました。モチーフにつけ表現方法につけ驚かされることが多いこの展示室の中で、ワタクシが一番驚いたのはモーリス・ルイスの「無題(死んだ鳥)」でございました。
画像は見つけられませんでしたが、↓とほぼ同じ作品でございます。おそらく同時期に描かれたものかと。
Here Be Old Things: New York City Auctions: January 12?18, 2009
ころんと仰向けになった小鳥の死骸が描かれた小さな作品、ごく地味な色調で、ペインティングナイフで引っ掻くように描かれた圧塗りの肌あい。これがあの、ゆるく溶いた絵具を広大なキャンバスの上にさあっと流し、美しい色彩の調和と観る者を包み込むような広がりを生み出した抽象画家モーリス・ルイスの作品とは、にわかには信じられませんでした。解説パネルによると、この作品の修復の再、今の画面の下に鮮やかな色が塗られていたことが分かったとのこと。うーむ、何があったんでしょうか。
描かれた鳥は古代の壁画のように素朴な造形でございまして、前回の記事でご紹介したモチーフは同じでも「死んだ鳥と狩猟道具のある風景」とは全く趣が異なります。単に技法の変遷ということ以上に、死んだ小さな生き物へ向けられる画家のまなざしが、裕福な顧客のために腕を振るう17世紀の画家のそれと、「芸術家=表現者」と言う概念が当たり前になった20世紀の画家のそれとではずいぶん違うということでもございましょう。
2つの「死んだ鳥」の間の隔たりは、人間の社会のありよう、そして人間とその周囲(=人間以外のものの世界)との向き合い方の変化を示すようでもございました。