「て」 出る杭になれ 打たれてこそ強くなる
・大自然の風雨にさらされ、耐えてこそ本物
よく「あの人は竹を割ったような性格だ」と褒めることがあります。男らしくて真っ直ぐで、真二つに綺麗に割れる竹に例えてさわやかな人柄、潔さを褒めてのことですが、竹は内部が空洞で、年輪も無いため繊維に沿って割れるのです。つまり「中身は空っぽ」で杭(アンカー)には使えません。ましてや「竹の大木」というのもありません。
元来、メタセコイアなどの一部例外を除いては、まっすぐに育たった大木というのはないそうです。度重なる風雨風雪に耐え、幹を割られ枝を折られてこそ大木の風格と年輪なのです。
大木といってすぐ連想されるのが、「縄文杉」「紀元杉」「夫婦杉」「大王杉」など、鹿児島県・屋久島の屋久杉です。
亜熱帯の屋久島は国連機関ユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録(1993/12/11)されるほど「豊かな自然に恵まれている」から「大木が育った」と考えがちですが、実はそうではありません。
屋久島は地下水も土壌も決して豊かではないのです。確かに「1ヶ月に35日雨が降る」といわれるほど年間降水量多いのですが、土壌が浅く花崗岩ばかりの地表では大部分が吸収されず流れてしまうのです。
驚くべきことに屋久島の保水力は木の根元に苔むしている「苔」。苔が大木を養える保水力を持つほどに繁茂するためには気の遠くなるような時間を必要としたに違いありません。
また、幹の直径に比べて木の高さが低い屋久杉は海抜が高い(1300m強)場所にあり、夏から秋にかけて台風通過の際は細い頭頂付近の折損被害や冬には凍結・積雪等の障害が存在するようです。
屋久島は自然条件が良い土地だったわけではないのです、むしろ劣悪な環境だったといえるでしょう。
その環境で3000年にも及ぶ年輪を刻んできた屋久杉こそ本物の大木。
寿命100年程度の霊長類。「天下御免の向う傷」の一つや二つ受けるつもりでがむしゃらに生きましょう。
・大自然の風雨にさらされ、耐えてこそ本物
よく「あの人は竹を割ったような性格だ」と褒めることがあります。男らしくて真っ直ぐで、真二つに綺麗に割れる竹に例えてさわやかな人柄、潔さを褒めてのことですが、竹は内部が空洞で、年輪も無いため繊維に沿って割れるのです。つまり「中身は空っぽ」で杭(アンカー)には使えません。ましてや「竹の大木」というのもありません。
元来、メタセコイアなどの一部例外を除いては、まっすぐに育たった大木というのはないそうです。度重なる風雨風雪に耐え、幹を割られ枝を折られてこそ大木の風格と年輪なのです。
大木といってすぐ連想されるのが、「縄文杉」「紀元杉」「夫婦杉」「大王杉」など、鹿児島県・屋久島の屋久杉です。
亜熱帯の屋久島は国連機関ユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録(1993/12/11)されるほど「豊かな自然に恵まれている」から「大木が育った」と考えがちですが、実はそうではありません。
屋久島は地下水も土壌も決して豊かではないのです。確かに「1ヶ月に35日雨が降る」といわれるほど年間降水量多いのですが、土壌が浅く花崗岩ばかりの地表では大部分が吸収されず流れてしまうのです。
驚くべきことに屋久島の保水力は木の根元に苔むしている「苔」。苔が大木を養える保水力を持つほどに繁茂するためには気の遠くなるような時間を必要としたに違いありません。
また、幹の直径に比べて木の高さが低い屋久杉は海抜が高い(1300m強)場所にあり、夏から秋にかけて台風通過の際は細い頭頂付近の折損被害や冬には凍結・積雪等の障害が存在するようです。
屋久島は自然条件が良い土地だったわけではないのです、むしろ劣悪な環境だったといえるでしょう。
その環境で3000年にも及ぶ年輪を刻んできた屋久杉こそ本物の大木。
寿命100年程度の霊長類。「天下御免の向う傷」の一つや二つ受けるつもりでがむしゃらに生きましょう。











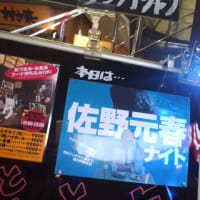

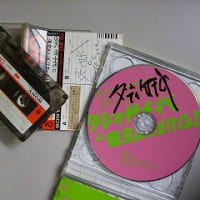






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます