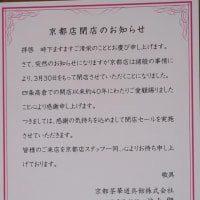「瀧」
前大徳積應師

糸巻棚 濃茶
今日は久しぶりに水滴茶入を使って
濃茶点前をしていただきました
置き合わせる道具に向けて
口の方向を変える扱いがあります
さて
これまで私達は何の疑いもなく
一碗の濃茶を当然のように飲み回しして参りました
しかしこの度の世界的騒動により
生活習慣がガラリと変わり
濃茶を飲み回すことが
できにくくなってしまいました
とは言え
あらためて考えてみますと
濃茶であれば
たとえ見ず知らずの方とでも
平気で飲み回ししていたにもかかわらず
例えば
それがコーヒーだとしたら
他人様が口をつけたコーヒーカップから
同じコーヒーを飲むことが
何の抵抗もなくできたでしょうか?
それが赤の他人でなくて
親しい友人だったとしても・・・?
同じコーヒーを抵抗なく飲むことができるのは
家族や恋人といった
ほんの身内同士の特別な間柄に
限られるのではないでしょうか
「利休 わび茶の世界」(著・久田宗也)によると
次のような記述があります
利休の頃は
四・五人の客の一人ずつにそれぞれ茶の量を加減し
天目茶碗で呈茶をしたという記録が残っている
古くは唐物天目茶碗を使い
また高麗茶碗を使ったにしても
客の一人ずつに茶をたてていたらしい
濃茶も薄茶もそうであった
天正十年を過ぎる頃
利休の茶室が二畳敷の小さい座敷となり
ここで少数の客に一碗から茶をすすらせることで
客の親しみを増し
心を一つにする効をねらったのが
濃茶の飲み回しであった
(以上抜粋)
一人一服ずつ飲むのが当たり前だった時代に
薄暗い小座敷にて
一碗の濃茶を飲み回しした人達は
私たちの想像を超えた
心の高揚と強い一体感を抱いたに違いありません
私達は
濃茶を飲み回しすることに
あまりにも馴れ過ぎていたような気がします
時代の要請とはいえ
今再び
一人ずつ濃茶を飲むという
過去のスタイルに戻るのも
悪くないように思います
一方
その上で敢えて
茶事において『濃茶を飲み回す』ということが
これまで感じ得なかった深く重い意味を持って
私達の心に迫ってくるような気がしてなりません

干菓子 唐板 水田玉雲堂製
疫病除けのご利益があると言われる
素朴な京都銘菓です