きょうの手話の教室で気がつくと右手の掌が血に染まっていた。
夕べ 蚊か何かに刺されて引っ掻いた傷が瘡蓋になっていたらしい?
その瘡蓋を無意識のうちに剥いで出血したようだ。
生憎と我輩はバイアスピリンを服用している。血が止まらない。
左手で血が出ているところをハンカチでふき取り そこを左手で押さえていた。
今日の教室は今月 末の田浦自治会館の文化祭で披露する手話による歌の練習だった。
3~5人が前に出て手話で歌を歌う。
我輩の番が来て前に並んだ・・・勿論 右手は左手で未だ血の出ている処を押さえていた。
我輩の隣に立たれた方がワイシャツに付いた血を指差しながら・・・
「どうしたの?」と聞かれた。ほんの小さな傷口を見せながら・・・。
「血が止まらないんだ」と言うと
「ちょっと待って・・・」と自分の席に戻られバックから なんと傷に貼る絆創膏を出されて・・・
「これを貼ったらいい・・」と・・・渡して戴いたが自分では貼れないので貼って貰った。
お陰さまで両手が使え手話の歌の仕草も出来たが・・こちらは なんと言っても歌は苦手で歌詞が頭に入らない。兎に角 皆さんの真似をしながら終わった。
席に戻ると指導の先生から「突っ立っていただけだったよ」と言われた。
自分では両手を動かしていた心算だが???仕草が小さかったらしい?
どうも小さいときから音楽は苦手だった。
まァ 上手く出来なくても出なくては・・・
先ほどから歌詞を見ながら一人練習をしている。
テープは戴いているがラジカセの音量を最大の音量にしてもよく聞こえない。
テープの音楽は聞えなくても・・・歌詞だけでも覚えておかないと・・・
耳が聞えないという不自由さを噛み締めながらの練習だ。
あの時に絆創膏を出して戴いた方に感謝しつつ練習を続けている我輩である。
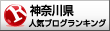
////////////////////////////////////////
http://mainichi.jp/opinion/news/20121016ddm003070160000c.html 以下全文
火論:長安のさざめき=玉木研二
毎日新聞 2012年10月16日 東京朝刊
<ka−ron>
東京・上野公園の東京国立博物館で開かれている「中国 王朝の至宝」展(毎日新聞社など主催)で、ああ、こんな感じだったか、としばらく見詰めたものがある。
統一王朝・唐の都、長安(ちょうあん)(現・西安市)で発掘された8世紀の「胡服女性俑(こふくじょせいよう)」2体の前に立った時だ。
胡服は異民族の衣装のこと、俑は人形(ひとがた)を意味し、副葬品として墓に納められた。当時の服飾や暮らしぶりを伝え、美術品として価値は高い。
長安はシルクロードに通じ、西方の民族と文化に交わった。最盛期の人口100万ともいう国際都市であり、遣唐使船で決死の渡海(実際多く落命した)をした日本の留学生(るがくしょう)らが集まった。
その中に空海(774〜835年)がいる。
司馬遼太郎は長編「空海の風景」でこう記している。
<歴史の奇跡といえるかもしれない大唐の長安の殷賑(いんしん)を、どう表現していいか。空海の幸運は、生身(なまみ)でこの中にいたことであった。かれはこの世界性そのものの都市文化の中で存在するだけで、東海の草深い島国にいるときに観念でしかとらえることができなかった文明とか人類とかというものを、じかに感得することができたにちがいない>(中央公論社刊より)
胡服の女性は、その風光のまぶしい象徴でもあろう。
同書は<紅毛碧眼(へきがん)の西域人が革(かわ)のコートを着、ひざをおおう革長靴をはいて悠然と歩いている光景におどろいたにちがいない>という。展示の俑もブーツをはき、唇に紅をさし、ピンクの化粧をして、1体はフェルトの帽子をかぶっている。
空海も振り向いたか。
こうした想像はひそやかな楽しみである。
長安の街のにぎわい、におい、多彩な装いや異文化、珍しい生き物。こうした東西南北の「るつぼ」にあった熱気のようなものを、陶製の人形がほのかに伝えてくれる。目を閉じれば、街のさざめきが聞こえてきそうでもある。
面白いものを見た。
唐よりずっと時代はさかのぼって紀元前16〜15世紀の殷(いん)。「爵(しゃく)」という、酒を温めて杯に注ぐ青銅の器がある。
取っ手を手前にすると必ず注ぎ口が左向きになるように作られている。この遠い時代にして「酒の作法」が確立していたことをうかがわせる、と解説されている。
.文化すなわち作法である。そうして注がれた酒をふくみ、どんな会話を弾ませたかは想像もつかない。
あるいは耳を澄ませば、かすかな酒気と共に今の世へ語りかけてくるものがあるかもしれない。(専門編集委員)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
つぶやき
きょうはちょっとした気遣いに随分と救われた。私も救急に絆創膏くらいは持って歩こう・・・
「爵(しゃく)」は知らないので検索してみた。↓
http://www.narahaku.go.jp/collection/d-1317-1-1.html
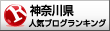
夕べ 蚊か何かに刺されて引っ掻いた傷が瘡蓋になっていたらしい?
その瘡蓋を無意識のうちに剥いで出血したようだ。
生憎と我輩はバイアスピリンを服用している。血が止まらない。
左手で血が出ているところをハンカチでふき取り そこを左手で押さえていた。
今日の教室は今月 末の田浦自治会館の文化祭で披露する手話による歌の練習だった。
3~5人が前に出て手話で歌を歌う。
我輩の番が来て前に並んだ・・・勿論 右手は左手で未だ血の出ている処を押さえていた。
我輩の隣に立たれた方がワイシャツに付いた血を指差しながら・・・
「どうしたの?」と聞かれた。ほんの小さな傷口を見せながら・・・。
「血が止まらないんだ」と言うと
「ちょっと待って・・・」と自分の席に戻られバックから なんと傷に貼る絆創膏を出されて・・・
「これを貼ったらいい・・」と・・・渡して戴いたが自分では貼れないので貼って貰った。
お陰さまで両手が使え手話の歌の仕草も出来たが・・こちらは なんと言っても歌は苦手で歌詞が頭に入らない。兎に角 皆さんの真似をしながら終わった。
席に戻ると指導の先生から「突っ立っていただけだったよ」と言われた。
自分では両手を動かしていた心算だが???仕草が小さかったらしい?
どうも小さいときから音楽は苦手だった。
まァ 上手く出来なくても出なくては・・・
先ほどから歌詞を見ながら一人練習をしている。
テープは戴いているがラジカセの音量を最大の音量にしてもよく聞こえない。
テープの音楽は聞えなくても・・・歌詞だけでも覚えておかないと・・・
耳が聞えないという不自由さを噛み締めながらの練習だ。
あの時に絆創膏を出して戴いた方に感謝しつつ練習を続けている我輩である。
////////////////////////////////////////
http://mainichi.jp/opinion/news/20121016ddm003070160000c.html 以下全文
火論:長安のさざめき=玉木研二
毎日新聞 2012年10月16日 東京朝刊
<ka−ron>
東京・上野公園の東京国立博物館で開かれている「中国 王朝の至宝」展(毎日新聞社など主催)で、ああ、こんな感じだったか、としばらく見詰めたものがある。
統一王朝・唐の都、長安(ちょうあん)(現・西安市)で発掘された8世紀の「胡服女性俑(こふくじょせいよう)」2体の前に立った時だ。
胡服は異民族の衣装のこと、俑は人形(ひとがた)を意味し、副葬品として墓に納められた。当時の服飾や暮らしぶりを伝え、美術品として価値は高い。
長安はシルクロードに通じ、西方の民族と文化に交わった。最盛期の人口100万ともいう国際都市であり、遣唐使船で決死の渡海(実際多く落命した)をした日本の留学生(るがくしょう)らが集まった。
その中に空海(774〜835年)がいる。
司馬遼太郎は長編「空海の風景」でこう記している。
<歴史の奇跡といえるかもしれない大唐の長安の殷賑(いんしん)を、どう表現していいか。空海の幸運は、生身(なまみ)でこの中にいたことであった。かれはこの世界性そのものの都市文化の中で存在するだけで、東海の草深い島国にいるときに観念でしかとらえることができなかった文明とか人類とかというものを、じかに感得することができたにちがいない>(中央公論社刊より)
胡服の女性は、その風光のまぶしい象徴でもあろう。
同書は<紅毛碧眼(へきがん)の西域人が革(かわ)のコートを着、ひざをおおう革長靴をはいて悠然と歩いている光景におどろいたにちがいない>という。展示の俑もブーツをはき、唇に紅をさし、ピンクの化粧をして、1体はフェルトの帽子をかぶっている。
空海も振り向いたか。
こうした想像はひそやかな楽しみである。
長安の街のにぎわい、におい、多彩な装いや異文化、珍しい生き物。こうした東西南北の「るつぼ」にあった熱気のようなものを、陶製の人形がほのかに伝えてくれる。目を閉じれば、街のさざめきが聞こえてきそうでもある。
面白いものを見た。
唐よりずっと時代はさかのぼって紀元前16〜15世紀の殷(いん)。「爵(しゃく)」という、酒を温めて杯に注ぐ青銅の器がある。
取っ手を手前にすると必ず注ぎ口が左向きになるように作られている。この遠い時代にして「酒の作法」が確立していたことをうかがわせる、と解説されている。
.文化すなわち作法である。そうして注がれた酒をふくみ、どんな会話を弾ませたかは想像もつかない。
あるいは耳を澄ませば、かすかな酒気と共に今の世へ語りかけてくるものがあるかもしれない。(専門編集委員)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
つぶやき
きょうはちょっとした気遣いに随分と救われた。私も救急に絆創膏くらいは持って歩こう・・・
「爵(しゃく)」は知らないので検索してみた。↓
http://www.narahaku.go.jp/collection/d-1317-1-1.html




















爵:台湾の故宮博物院でよく見ました。青銅製と思いますが、何か金属が解け込みそうで酒を飲むにはどうも~
木通:アケビ 早速使っています。先ほど奥方が、生き生きサロン(太極拳の関係で誘われたと)の紅葉狩りの帰りに道の駅でアケビを買って来たと。何たる偶然,白アケビと紫が5ヶで300円大きいので10cmほどです。何年かぶりです。皮が割れはじめでとても甘かったです。
血液さらさらも怪我の時は困りますね、ご注意ください。 草々
メタボ拝
新品の時はちがうのかも?でもい銅と知ると二の足を踏みます。形はとてもいいです。焼き物やガラスでは直ぐに壊れる?
アケビ 早速 食べられましたか?優しい奥様ですね~ 白いアケビは皮の色が違うのみでしょうか?見たことはありません。また こちらのスーパーで先日 探しましたがありませんでした。
バイアスピリン 利き目がある時と利き目を感じない時があります。その日の食べ物により効果が違うのかも?
心臓にステントを入れて7年目です。10年持つといわれていますのであと3年?
早い方は2年で再手術とされた言われて居ました。再手術できれば幸運です。
絆創膏はカバンに入れて持ち歩くことにしました。そうそ 髭剃りは電気カミソリのみです。安全カミソリは傷をつけますと血が中々止まりませんので・・・。
特別天然記念物・植物編鑑賞に御付き合い有り難うございました。
年を取ると傷の回復が遅くなるのは実感しますね。
薬飲用のせいで血が止まりにくくなるのも困ったものですね。
絆創膏やバンドエイドを持ち歩くのはちょっとした怪我に便利ですんね。
何時もの動画とDbにしましたので少し長編ですがご覧頂ければ幸せます!
バイアスピリンも長年 服用しているとその効果が薄れるのか?血が出ても困ったことは無くなり つい 忘れてしまいます。然し 今回は困りました。理由はわかりませんが血が止まらなくて・・・。
コメント&応援有難うございました。