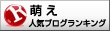軍事、国際政治の話となると普段の日常生活との接点がない上に、
こうした話は学者や識者が普段よりも小難しい用語を連発するせいで、
「あら、そう」と聞いているのか、聞いていないような態度になってしまいます。
が、本書はかなり分かりやすいです。
例えば最初に中国空母「遼寧」の半径45キロへの「航行禁止海域」に指定した中国。
この国際法への暴挙に対してアメリカ海軍の軍艦がそれを覆すべく行動した事実について、
落ちついた低い声で、ゴンバートは当直将校の若い大尉に短い言葉を伝える。
するとすぐさま、艦内のあちこちのスピーカーからその言葉が鳴り響く。
「モディファイド・コンディション・ゼブラ態勢、
モディファイド・コンディション・ゼブラ態勢」
命令を聞いて乗組員が艦内を走り回り、水密ハッチを閉じ、バブルを閉める。
ダメージコントロール班及び消化班がスタンバイし、
ソナーやレーダーや電子機器のオペレーターは一層気を引き締めてディスプレイを見つめる。
上級兵曹らがあらゆるシステムを再点検する。
コンディション・ゼブラとは「総員配置」に次ぐ、海軍の二番目に高い戦闘準備態勢を示す言葉だ。
GQは攻撃が差し迫っている状態であり、
コンディション・ゼブラはまもなくそうなるかもしれないという状態だ。
まるでトム・クランシーの軍事小説のワンシーンを読んでいるかのような描写で非常に読みやすいです。
そして、オバマ政権で米中間の緊張緩和という目標で軍の間で交流をするが、
こちらが個人の電話番号を教えても中国側は徹底的な秘密主義、面子とやらによる言い訳。
また過去これまで発生した緊張事案。
具体的には海南島でアメリカ軍の航空機が不時着した事件。
リムパックで中国が堂々とスパイ船を連れてきた事案など事細かく分かりやすく事実を描写しており。
その都度抗議するが中国は、
「俺たちはいいが、お前らはダメ」
と言わんばかりの態度をしていると告白。
兵器の技術についても空母キラーを筆頭に長距離対艦ミサイルの開発を進めてきた中国。
対してアメリカ軍といえば冷戦終結後兵力の削減と技術革新を怠っていた・・・。
などと驚きの事実に満ちており、
今日の安全保障を考えるうえで参考になるかと思います。