モノを作るのは楽しい。
パソコンが身近になって、文章を書いたり、
映像を作ったりが誰でも簡単にできるようになった。
それをYouTubeやFacebook、blogにアップすれば、
世界中の見ず知らずの人から「面白い」と誉められる。
しかしこれが商売となると大変になる。
いや大変になるどころか、
死に物狂いに作らねばならなくなる。
しかも素人が趣味で無料で、いとも容易く作るものだから、
発注者の目は肥えて、
生半可な自称「プロ」の価格は暴落し、当然仕事はなくなる。
一生懸命に思い詰める人の中には、プレッシャーに押し潰されて、
ノイローゼになる人まででてくる。

プロと素人の差はお金を取るか、取らないか、ただそれだけの違い。
しかしお金を取る限りは、感動を与えねばならない。
この「感動を与える」がままならないのだ。
よく言う「面白い」と、「感動」は微妙に違う。
感動は、面白いよりも重くて深い。
面白いなぁと「感心」しても、
心が震える「感動」にまでいたらない。
プロは、作る前からも、作っている過程でも、
出来上がった瞬間にも、感動を間断なく与え続ける。
その姿勢を見ているだけで感動してしまう。
さらにトドメの一刺。
それはお客さまが出来上がったモノを手にとって、
しみじみと「次もお願いしたい」というリピートだ。
リピートがあるからこそ、プロは仕事が続けられる。
続けることこそが、プロの証であり、
リピートがさらに良いモノを生み出すパワーとなる。
リピートを得るためには、血ヘドを吐くようなプレッシャーや
貧乏の毎日を乗り越えなければならないし、
仮に世間から認めら、ある程度の収入を得られるようになっても
「いつ仕事がなくなるかわからない」という不安にさいなまれ、
それでも「好きだから・・・」の一言を
羅針盤にして進まねばならない。
モノ作りのプロとは、かくも過酷なのである。
「モノ作りへのこだわりをお客さまのもとへ」
「できることのすべてをお客さまに」
「お客さまの笑顔をつくるために」
「使う人の品質を、しっかりつくる」
「あなたにピッタリの品質が見つかります」
巷に溢れるコピーを実践するのは、作り手の自己研鑽しかない。
それは作り手がいつも持つ自己嫌悪との戦いでもある。
自己嫌悪し続けること、研鑽し続けること、仕事をし続けること
それがプロの証なのだから・・・
パソコンが身近になって、文章を書いたり、
映像を作ったりが誰でも簡単にできるようになった。
それをYouTubeやFacebook、blogにアップすれば、
世界中の見ず知らずの人から「面白い」と誉められる。
しかしこれが商売となると大変になる。
いや大変になるどころか、
死に物狂いに作らねばならなくなる。
しかも素人が趣味で無料で、いとも容易く作るものだから、
発注者の目は肥えて、
生半可な自称「プロ」の価格は暴落し、当然仕事はなくなる。
一生懸命に思い詰める人の中には、プレッシャーに押し潰されて、
ノイローゼになる人まででてくる。

プロと素人の差はお金を取るか、取らないか、ただそれだけの違い。
しかしお金を取る限りは、感動を与えねばならない。
この「感動を与える」がままならないのだ。
よく言う「面白い」と、「感動」は微妙に違う。
感動は、面白いよりも重くて深い。
面白いなぁと「感心」しても、
心が震える「感動」にまでいたらない。
プロは、作る前からも、作っている過程でも、
出来上がった瞬間にも、感動を間断なく与え続ける。
その姿勢を見ているだけで感動してしまう。
さらにトドメの一刺。
それはお客さまが出来上がったモノを手にとって、
しみじみと「次もお願いしたい」というリピートだ。
リピートがあるからこそ、プロは仕事が続けられる。
続けることこそが、プロの証であり、
リピートがさらに良いモノを生み出すパワーとなる。
リピートを得るためには、血ヘドを吐くようなプレッシャーや
貧乏の毎日を乗り越えなければならないし、
仮に世間から認めら、ある程度の収入を得られるようになっても
「いつ仕事がなくなるかわからない」という不安にさいなまれ、
それでも「好きだから・・・」の一言を
羅針盤にして進まねばならない。
モノ作りのプロとは、かくも過酷なのである。
「モノ作りへのこだわりをお客さまのもとへ」
「できることのすべてをお客さまに」
「お客さまの笑顔をつくるために」
「使う人の品質を、しっかりつくる」
「あなたにピッタリの品質が見つかります」
巷に溢れるコピーを実践するのは、作り手の自己研鑽しかない。
それは作り手がいつも持つ自己嫌悪との戦いでもある。
自己嫌悪し続けること、研鑽し続けること、仕事をし続けること
それがプロの証なのだから・・・

















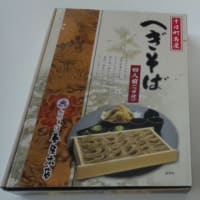


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます