いきなり下積みもなく監督になるのも悪くない。
私がこの世界に入った頃、PR映像のメディアはフィルムか写真であり、
それに代わってビデオが登場した頃から、
下積みなく監督になる人もチラホラ出てきた。
かくゆう私も師匠ナシ派である。
それでもなんとか監督をしてこられたのは仕事が潤沢にあったからだ。
しかし仕事が潤沢にない場合は、下積みがないと経験不足で
突発的なことに対応できない。
それでもスタッフに優秀なチーフ助監督がいれば監督業に専念できるが、
いなければ新人監督はたちまち雑事に追われる羽目になり
作品演出をする前に雑事処理でパンクしてしまう。
優秀なチーフ助監督なら
例えば急な雨や、あるいは交通渋滞によるスタート遅れなどを
あらかじめ想定して、少なくとも5手先か6手先まで読んでロケに挑む。
万一突発的事態になっても、先手先手を打てるかがチーフ助監督として
優秀か否かを決める最大要因であり、監督はスタッフ人選時、
プロデューサーの意向やメインスタッフの意向も組み入れるが、
最低でもチーフ助監督とカメラマンだけは自分で人選する。
それほど核となるスタッフなのだ。

本来、監督は助監督を経験してからなるので
チーフ助監督の考えることはたいていわかっている。
しかし新人監督だと悲しいかなチーフ助監督の立てた対処法に
思考がついていかない。
というのも、新人監督でも台本の順に撮影できれば
たいていのことには対応できるが、
突発的事態でシーン8の次にシーン100を撮り、
続いてシーン50を撮るということが起こった場合、
頭の中でシーンがつながらないのだ。
しかしそういった突発的事態は製作には日常茶飯である。
優秀なチーフ助監督は監督がやりやすいように
役者のスケジュールをうまく調整し、
極力シーンを若い順にしかもブロック毎に集めてくれる。
それでも突発的事態でせっかくのブロックも崩れることがあるが、
そんな場合でもパズルを繰り返して被害を最小限に食い止めてくれる。
映画の場合、チーフ助監督は全体スケジュールを立てた上で
日々のスケジュール調整を日々行ない、
監督がやりやすいように配慮してくれる。
役者の面倒をみたり、シーンでの衣装確認、カチンコを叩くのは助監督でも
サードやフォースの仕事になる。
チーフ助監督は、役者のスケジュールを鑑みながら、
常に次の撮影の準備を行ない、手待ちなく進めるのが仕事である。
だから次の準備で撮影現場にいないことも多い。
チーフ助監督の立てたスケジュールを
関東では「ソウスケ」(総合スケジュールの略)といい、
関西では香盤(こうばん)、もしくは香盤表」という。
香盤の香とは役者のつける白粉(オシロイ)の香りを意味し、
役者の出番表ということで香盤表と呼ぶ。
いかにも時代劇の京都らしい命名である。

台本を読み込む力と現場の進行能力が、
手待ちのない香盤表を作る基本になることから、
香盤表が組めれば監督指名も近いといえる。
しかし、スケジュールが組めたからといって監督ができるわけではない。
なぜなら監督は台本を再現するのではなく、表現するのが仕事だからだ。
私の場合は会社なので、助監督は社内から人選する。
PR映像の場合はドラマ仕立てであっても助監督は一人ないし多くても二人。
そのため助監督として能力がついていない場合は、
私が監督をしながらチーフ助監督となって補佐する。
また私がプロデューサーで外部監督を招聘した場合でも
助監督は社内から人選する。
ちなみにまだ当社が創業の頃は、私が100%監督をしていたので、
助監督は今では当社取締役の森田 康高が全作品してくれていた。
彼の1年先輩にあたる岡 由紀子もまだ20歳の若い女性ではあったが、
汗を流すことを苦にしないタイプだったのでスタッフ受けは抜群だった。
しかしシビアーにいえば台本を読み込む力がついておらず
助監督でもサードかフォースの力量だった。
その点、森田は台本を読み込むので、
香盤表を立てることが次第にできるようになっていった。
まず設計図である台本を読み解けないと香盤表は作れない。
もし今、私が監督をする作品があれば迷わず田邊 暢平を指名する。
読み込む力がある上、伸び代は森田より上だ。
田邊のためにも、ぜひ私が監督をする作品を取ってこなければならないと思う。

監督はスタッフ論でいえば、三角形の頂点に立つ。
したがって課題については最終的に自分ですべて決めなければならない。
スタッフを決めるのはもちろんのこと、
何か迷いが出ても進むべき方向を決めなければならない。
しかし決めるからといって独壇場というわけではない。
スタッフから色んな意見を聞き出し、
偏りがちな思いをいつもクールに見れるようにしておかねばならない。
もしスタッフの意見を聞くのが嫌ならスタッフを引き連れる意味はないし、
監督などしなければよいのだ。
ただし色んな意見を聞けば当然迷うことになるが「迷うこともよし」とし、
すべてとはいかないまでも迷いを少しでも消化して自分のイメージに近づける。
スタッフからの意見は良き作品を作るためのヒントと思い、
作品作りへの努力と工夫をし続けなければならない。
またこの時行なうスタッフ会議を、
監督は台本具現化のための最も大切な会議であると認識しなければならない。
監督はいわばオーケストラのコンダクターであり、大工の棟梁なので
Plan→Do→Check →Actionを常に回していかなければならない。
助監督経験が大切なのは、このPDCAを身につけるための訓練期間であり
PDCAの視点が身についていれば、いきなり監督になるのも悪くない。
私がこの世界に入った頃、PR映像のメディアはフィルムか写真であり、
それに代わってビデオが登場した頃から、
下積みなく監督になる人もチラホラ出てきた。
かくゆう私も師匠ナシ派である。
それでもなんとか監督をしてこられたのは仕事が潤沢にあったからだ。
しかし仕事が潤沢にない場合は、下積みがないと経験不足で
突発的なことに対応できない。
それでもスタッフに優秀なチーフ助監督がいれば監督業に専念できるが、
いなければ新人監督はたちまち雑事に追われる羽目になり
作品演出をする前に雑事処理でパンクしてしまう。
優秀なチーフ助監督なら
例えば急な雨や、あるいは交通渋滞によるスタート遅れなどを
あらかじめ想定して、少なくとも5手先か6手先まで読んでロケに挑む。
万一突発的事態になっても、先手先手を打てるかがチーフ助監督として
優秀か否かを決める最大要因であり、監督はスタッフ人選時、
プロデューサーの意向やメインスタッフの意向も組み入れるが、
最低でもチーフ助監督とカメラマンだけは自分で人選する。
それほど核となるスタッフなのだ。

本来、監督は助監督を経験してからなるので
チーフ助監督の考えることはたいていわかっている。
しかし新人監督だと悲しいかなチーフ助監督の立てた対処法に
思考がついていかない。
というのも、新人監督でも台本の順に撮影できれば
たいていのことには対応できるが、
突発的事態でシーン8の次にシーン100を撮り、
続いてシーン50を撮るということが起こった場合、
頭の中でシーンがつながらないのだ。
しかしそういった突発的事態は製作には日常茶飯である。
優秀なチーフ助監督は監督がやりやすいように
役者のスケジュールをうまく調整し、
極力シーンを若い順にしかもブロック毎に集めてくれる。
それでも突発的事態でせっかくのブロックも崩れることがあるが、
そんな場合でもパズルを繰り返して被害を最小限に食い止めてくれる。
映画の場合、チーフ助監督は全体スケジュールを立てた上で
日々のスケジュール調整を日々行ない、
監督がやりやすいように配慮してくれる。
役者の面倒をみたり、シーンでの衣装確認、カチンコを叩くのは助監督でも
サードやフォースの仕事になる。
チーフ助監督は、役者のスケジュールを鑑みながら、
常に次の撮影の準備を行ない、手待ちなく進めるのが仕事である。
だから次の準備で撮影現場にいないことも多い。
チーフ助監督の立てたスケジュールを
関東では「ソウスケ」(総合スケジュールの略)といい、
関西では香盤(こうばん)、もしくは香盤表」という。
香盤の香とは役者のつける白粉(オシロイ)の香りを意味し、
役者の出番表ということで香盤表と呼ぶ。
いかにも時代劇の京都らしい命名である。

台本を読み込む力と現場の進行能力が、
手待ちのない香盤表を作る基本になることから、
香盤表が組めれば監督指名も近いといえる。
しかし、スケジュールが組めたからといって監督ができるわけではない。
なぜなら監督は台本を再現するのではなく、表現するのが仕事だからだ。
私の場合は会社なので、助監督は社内から人選する。
PR映像の場合はドラマ仕立てであっても助監督は一人ないし多くても二人。
そのため助監督として能力がついていない場合は、
私が監督をしながらチーフ助監督となって補佐する。
また私がプロデューサーで外部監督を招聘した場合でも
助監督は社内から人選する。
ちなみにまだ当社が創業の頃は、私が100%監督をしていたので、
助監督は今では当社取締役の森田 康高が全作品してくれていた。
彼の1年先輩にあたる岡 由紀子もまだ20歳の若い女性ではあったが、
汗を流すことを苦にしないタイプだったのでスタッフ受けは抜群だった。
しかしシビアーにいえば台本を読み込む力がついておらず
助監督でもサードかフォースの力量だった。
その点、森田は台本を読み込むので、
香盤表を立てることが次第にできるようになっていった。
まず設計図である台本を読み解けないと香盤表は作れない。
もし今、私が監督をする作品があれば迷わず田邊 暢平を指名する。
読み込む力がある上、伸び代は森田より上だ。
田邊のためにも、ぜひ私が監督をする作品を取ってこなければならないと思う。

監督はスタッフ論でいえば、三角形の頂点に立つ。
したがって課題については最終的に自分ですべて決めなければならない。
スタッフを決めるのはもちろんのこと、
何か迷いが出ても進むべき方向を決めなければならない。
しかし決めるからといって独壇場というわけではない。
スタッフから色んな意見を聞き出し、
偏りがちな思いをいつもクールに見れるようにしておかねばならない。
もしスタッフの意見を聞くのが嫌ならスタッフを引き連れる意味はないし、
監督などしなければよいのだ。
ただし色んな意見を聞けば当然迷うことになるが「迷うこともよし」とし、
すべてとはいかないまでも迷いを少しでも消化して自分のイメージに近づける。
スタッフからの意見は良き作品を作るためのヒントと思い、
作品作りへの努力と工夫をし続けなければならない。
またこの時行なうスタッフ会議を、
監督は台本具現化のための最も大切な会議であると認識しなければならない。
監督はいわばオーケストラのコンダクターであり、大工の棟梁なので
Plan→Do→Check →Actionを常に回していかなければならない。
助監督経験が大切なのは、このPDCAを身につけるための訓練期間であり
PDCAの視点が身についていれば、いきなり監督になるのも悪くない。

















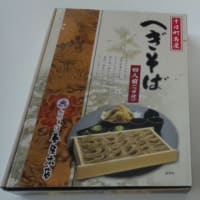


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます