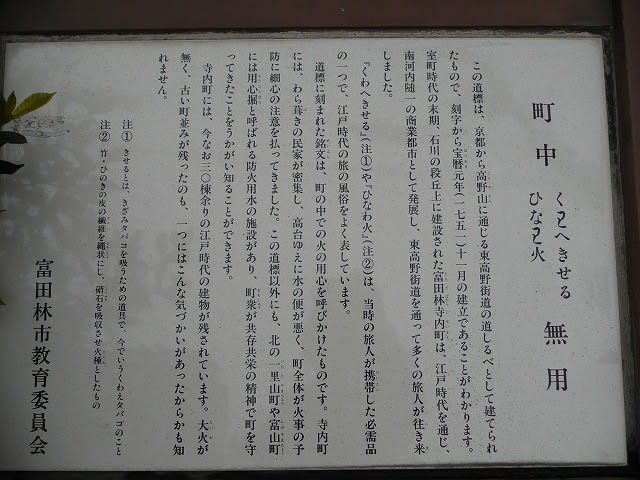若松にもコンクリート製ゴミ箱がありました。
ウェル本町の6台の手押しポンプを見に行った時に、他に手押しポンプやゴミ箱はないかと
探索した時に見つけました。
手押しポンプは見つけることが出来ませんでしたが、コンクリート製ゴミ箱は4台も見つけました。
最初のコンクリート製ゴミ箱は植木鉢として使われていました。

№31.北九州市若松区浜町。2009/1/15
次はこの路地で2台を見つけました。

№32・33.北九州市若松区白山1丁目。2009/1/15
足付きのコンクリート製ゴミ箱です。
今まで30台のコンクリート製ゴミ箱を見てきましたが、初めて見るタイプです。
足付きを造るのは面倒でしょうが、何か便利な事があったので改良されたのだろうが、
どんなメリットだったのだろう?

№32.北九州市若松区白山1丁目。2009/1/15
前扉はベニヤ板に変えてある。
№32と少し形状が違っている。32は正面から見ると台形の形だが、これは長方形だ。

№33.北九州市若松区白山1丁目。2009/1/15
コンクリート製ゴミ箱と防火水槽が並んでいる。天理教の教会で使用しているようだ。

№34.北九州市若松区大井戸町。2009/1/15
若松のコンクリート製ゴミ箱は3台も現在も使われているのは嬉しい事だ。
コンクリート製ゴミ箱は東京オリンピックの時ぐらいから見ることが無くなっているので、
もう40年以上は使われている事になる。
まだまだ使える。
ウェル本町の6台の手押しポンプを見に行った時に、他に手押しポンプやゴミ箱はないかと
探索した時に見つけました。
手押しポンプは見つけることが出来ませんでしたが、コンクリート製ゴミ箱は4台も見つけました。
最初のコンクリート製ゴミ箱は植木鉢として使われていました。

№31.北九州市若松区浜町。2009/1/15
次はこの路地で2台を見つけました。

№32・33.北九州市若松区白山1丁目。2009/1/15
足付きのコンクリート製ゴミ箱です。
今まで30台のコンクリート製ゴミ箱を見てきましたが、初めて見るタイプです。
足付きを造るのは面倒でしょうが、何か便利な事があったので改良されたのだろうが、
どんなメリットだったのだろう?

№32.北九州市若松区白山1丁目。2009/1/15
前扉はベニヤ板に変えてある。
№32と少し形状が違っている。32は正面から見ると台形の形だが、これは長方形だ。

№33.北九州市若松区白山1丁目。2009/1/15
コンクリート製ゴミ箱と防火水槽が並んでいる。天理教の教会で使用しているようだ。

№34.北九州市若松区大井戸町。2009/1/15
若松のコンクリート製ゴミ箱は3台も現在も使われているのは嬉しい事だ。
コンクリート製ゴミ箱は東京オリンピックの時ぐらいから見ることが無くなっているので、
もう40年以上は使われている事になる。
まだまだ使える。