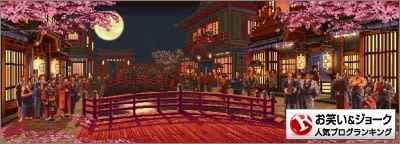防御機制はフロイトのヒステリー研究から生まれた概念で、不快な感情、嫌な体験などから社会に適応が出来ない状態に陥った時に行われる自我の再適応作用のことだ。
従来の精神分析の見方では、成長した自我が幼児的な超自我から自身を守ろうとすることで防御機制が生じるとされている。防衛機制を常習的に用いていると、それが病的な不適応症状などとして表面化されることがありる。
米ペンシルベニア州ヴィラノヴァ大学の心理学者、ダニエル・ジーグラー(Daniel Ziegler)の2016年の論理情動認知行動療法(Rational Emotive Cognitive Behavior Therapy/RECBT)に関する論文によれば、防衛機制の由来である精神分析から切り離し、新たなる解釈を加えることで、防衛機制を抑制することができるという。”不合理”な信念があなたを不幸にする
論理情動認知行動療法(RECBT)の基本的な前提は、ポジティブな感情状態は経験から自分自身の存在を肯定できるときに生じるというものだ。
私たちが守ろうとしているのは低い自尊心や自身に対する失望感からだ。心配や鬱といったネガティブな感情は、いわば”不合理”な信念から生じている。”完璧でなければならない”、”失敗があってはならない”、”誰からも愛されなければならない”などだ。
ひとつ例を挙げよう。
誰ががあなたを好きではないと知ってしまった。このことで悲しい思いをするのなら、それはあなたが”誰からも愛されなければならない”という不合理な信念を抱いているからである。
あなたの非論理的な論理は、「Xは自分を愛していない、私は皆から愛されなければならない、ゆえに自分はダメで惨めである」というものだ。
私たちを苦しめるのは機能不全の感情であるというのが、RECBTの見方の核だ。ゆえに体験を合理的に解釈できるようになれば、想像上の失敗や損失のために自分を不必要に罰したりしなくなるだろうと考える。
防衛機制は幸せを阻害する
防衛機制もまた「現実の認識を歪め、否定し、偽る」とジーグラーは論じる。その意味で、それはRECBTによる人格の見方の自然な延長である。
精神分析と対照的に、RECBTでは、防衛機制は無意識に埋め込まれてはいないと説く。フロイト学派の理論は、最高の状況下においてさえ私たちには防衛機制が必要であると考える。一方、RECBTが提唱するのは、防衛機制は幸せを阻害しており、のびのびと生きるにはこれを捨て去らねばならないということだ。これは朗報だろう。
無意識に埋め込まれたものでないのであれば、ネガティブな感情、不安、自己疑念といった罠に捉え続ける防衛機制をはっきりと認識して、取り除くことができるはずだ。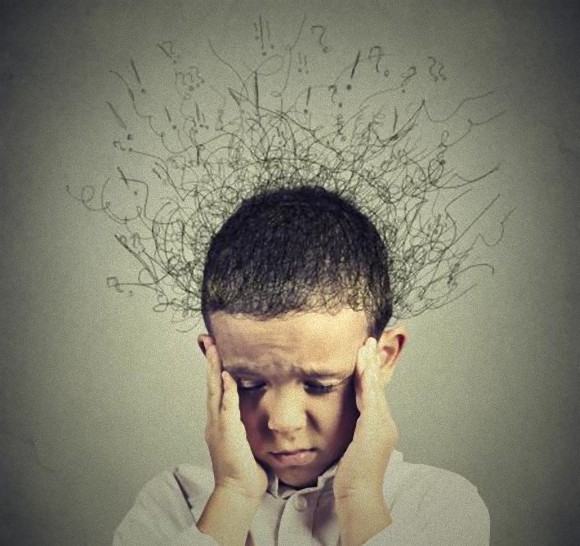
以下ではRECBTにおける各防衛機制の解釈ついて説明する。
1. 抑圧
抑圧とは、醜い衝動を無意識の中に押し込むことである。フロイト学派の理論では基本的な防衛機制である。
RECBTにおいて、抑圧には醜い衝動だけでなく、意識下で機能する不合理的な信念(誰からも愛されねばならないなど)も関与する。RECBTが惨めな気持ちへと駆り立てるいわゆる”自動思考”を取り上げるのは、それがはっきり認識できない不合理な信念から生じているからだ。こうした不合理な信念をはっきり意識させることができれば、あなたもセラピストも自動思考を変えられるようになる。
2. 投影
投影とは、自分が受け入れることのできない衝動を取り上げ、それを他人に対して文字通り”投影”することだ。
フロイト学派ではそれらを反道徳的な情動とするが、RECBTでは自分たちが受け入れられない考えであると説く。それを受け入れることができない理由は、”斯くあるべき”という感じ方をネガティブに反映しているからだ。
例えば、あなたは厳しい家庭で育って、性はよくないものという信念を持っているかもしれない。淫らな考えを抱くあなたは”ろくでなし”ということになる。
「妻以外の女性に淫らな思いを抱くべきではない。そうすることは、ひどく、おそろしく、どうしようもなく、とんでもないことだ!」という具合だ。そこで、時折淫らな考えを抱くことを認める不安から身を守るために、それを他人に移してしまう。汚らわしいのは他人である、と。
RECBTでは、不合理な信念(性はよくない)を合理的な信念(性的な感情があっても問題ない)に変えてしまうことで、投影の悪影響を克服できるとする。
3. 置き換え
愛する(あるいは恐れる)人への受け入れられない感情を安全な対象に移してしまうことが、置き換えだ。
古典的な例は、上司からひどい扱いを受けたとき、帰宅後に家族に向かって怒鳴り散らして怒りを発散するというものだ。
RECBTでは、扱いが不当であると感じているために置き換えを利用すると分析する。不当に扱われることは正しいことではない。実際、人の身に起こりうることとしては最悪の部類である。 最悪であり不正であるがゆえに置き換えが起こる。
もちろん、この反応は事態を悪化させるうえに、職場での状況は変わらない。RECBTでは、”自分が常に正当に扱われるべきである”という信念を変えることで、置き換えの欲求を克服できると説明する。また、それを怒りではなく、不満や失望と定義することで、自分の反応を変えることもできる。そうすれば、職場とは一切関係のない愛する人たちへ怒りを向けることもなくなる。
4. 合理化
自分にとってネガティブな体験を正当化する言い訳を用いることが合理化である。合理化をする人は言い訳であることは知っているのだが、自分が言い訳をするかには気がついていない。
RECBTによると、言い訳をせず、「真実と向き合う」ことで克服できる。何かに失敗したり、大切な仕事をうっかり忘れてしまったりすることがあるだろうが、自己を正当化する理由を延々と思い浮かべるのではく、ひとまずその事実をきちんと受け止めるのだ。
5. 反動形成
自分の思っていることと反対のことをする。この回りくどい防衛機制の基本的な考えは、受け入れられない衝動を正反対にしてしまうというものだ。
RECBTにおいて、人を正反対に駆り立てるのはネガティブな衝動ではなく、怒りや心配といったあたりまえの感情が望ましくないと考える不合理な信念とされる。
反動形成は自尊心を守るための手段であるが、生産的ではない。例えば、あなたの子供の行為に関して不満を感じたときであっても、子供を怒らないかもしれない。そうしてしまえば、自分がひどい母親になってしまうからだ。そこで、悪さを過度に大目に見ることになる。反動形成から離れてしまえば、時折苛立ちや怒りを覚えることもある子供などの大切な人たちと葛藤のない関係を築くことができる。
6. 否認
古典的な否認の意味は、自分の中にネガティブだったり、有害だったりする衝動があることを認めてしまうと、不安で圧倒されてしまうために、衝動の存在を認めないということだ。
そうした衝動は性的なものや攻撃的なものだけではない。自分自身や世界に関する心地良い見方にとって都合の悪い経験や出来事の認識である。
現実から目を背けることで気分よくあろうとするのだが、REBCTはそれで状態がよくなるとは考えない。その見聞きした物事が真実であることは明らかだからである。
真実を受け入れるには手助けが必要かもしれないが、ジーグラーは徐々に現実に沿うようにするのがもっともよい方法だと考えている。脅威と感じる自分に関する情報に立ち向かっても状況を好転させない。少しずつ真実に慣れるほうがずっと生産的であるという。
7. 退行
フロイト学派は、ストレスを受けた際に、幸せだった幼い頃の性心理に戻ることを退行を捉える(指しゃぶりなど)。
REBCTでは、不満が高まりすぎて実際に子供のように感じるようになったとき、子供じみた行動を取り始めると考える。
この防衛機制から抜け出る道は、子供じみた行動をとれば余計に自分を邪魔してしまうと理解することだ。不満が溜まる状況があることを認め、不満を感じることを許すことで、こうしたネガティブな感情に対処できる。
8. 知性化
合理化と同様、知性化とは出来事や体験などのネガティブな結果から言い逃れる理由を考えることだ。お気に入りの砂糖のケースを割ってしまったと想像して欲しい。しかし、たとえ一時であっても自身に苛立ちを感じさせることなく、自分と完全に距離をとり、何事もなかったかのように淡々と砂糖を別の容器に入れ始める。
REBCTでは、適切な場合は怒りを表現することが健康的な反応であると説明する。感情を体験することを恐れるべきではない。
via:A New Way to View the Top 9 Defense Mechanisms/ translated hiroching / edited by parumo
▼あわせて読みたい 「認知の歪み」ゆがんだ思い込みが自分を不幸に陥れる。危険な12の思い込みから身を守る方法
「認知の歪み」ゆがんだ思い込みが自分を不幸に陥れる。危険な12の思い込みから身を守る方法 プラス思考には痛みを和らげる効果が。5分間のイメージトレーニングで最大60%痛みが緩和(英研究)
プラス思考には痛みを和らげる効果が。5分間のイメージトレーニングで最大60%痛みが緩和(英研究) うつ病の人も、統合失調症も、誰もが幸せな気分になれる脳トレ「3つの祝福」
うつ病の人も、統合失調症も、誰もが幸せな気分になれる脳トレ「3つの祝福」 不眠症対策の鍵は感情を制御すること(スウェーデン研究)
不眠症対策の鍵は感情を制御すること(スウェーデン研究) 自分の能力を過小評価するあまり、成功すると周囲を騙しているように感じてしまう「インポスター・シンドローム(詐欺師症候群)」とは?
自分の能力を過小評価するあまり、成功すると周囲を騙しているように感じてしまう「インポスター・シンドローム(詐欺師症候群)」とは?