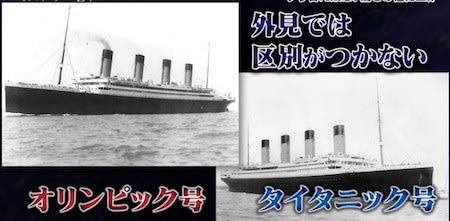前回(第465回ー文末にリンクを貼っています)に引き続き、パート2をお届けします。「へんないきもの」(早川いくを 新潮文庫)をネタ元に、造物主のきまぐれとしか思えない変な生物たちの話題をお楽しみください。
★ザトウムシ★
パート2もインパクトのある生物からいきましょう。まずはご覧ください。

一体これは何でしょう、ってクイズにしたくなります。長い脚を杖のようにしてあたりを探る様子から、「座頭市」ならぬ「座頭虫」と呼ばれています。この脚に、触覚、聴覚、雌雄の認識などの感覚器官が集中しています。クモのように見えますが、ダニの一種です。世界に2000種いるといわれ、日本にいる種の脚は18センチにもなり、世界最大です。
脚の感覚を総動員して、昆虫やクモなどのほか、植物性のものもエサにします。集団でゆらゆらしていることが多いです。少しでも大きく見せようという工夫なのでしょうが、健気な生き方です。
★メダマグモ★
クモといえば「網」ですが、このクモは、投網(とあみ)で使うようなコンパクトな網を、夜間30分ほどで作ります。格別に暗視能力が高く、ご覧のように、エサが近づくと、パッと網を広げて捕獲します。

体長は2~2.5センチほどで、南アメリカ、アフリカ、オーストラリアの森林に棲息します。その糸の強度は、同じ太さの鋼鉄の5倍で、伸縮率はナイロンの2倍です。こんな素材を人工的に作る研究が続けられていますが、いまだに実現していないとのこと。こんなところにも自然界の驚異がありました。
★ヤツワクガビル★
画像は、この生き物の「食事風景」です。手前のミミズを、のたうちまわりながら呑み込もうとしています。

ラテン語みたいな名前ですが、「ヤツワ」は、八つの輪、つまり体節が八つあることを示しています。「クガ」は「陸」で、ヒルの仲間では珍しく陸生です。画像は白黒ですが、実物は、毒々しい黄色と紺のツートンカラーで、体長は最大で40センチにも及ぶ日本最大級のヒルです。なんだか同士討ちみたいな食事風景で、見る方は食欲が減退しそうになります。
★ウロコフネタマガイ★
入口というか出口というか、ウロコのようなものが見えていますが、これが身をびっしり覆っている巻貝です。

このウロコの素材がなんと硫化鉄で、磁石を近づけるとくっつきます。2003年に、海底2500メートルの地点で発見されました。有毒の硫化水素を含む熱水が噴き出している地獄のようなエリアです。ところがここには硫化水素を酸化してエネルギーを得るバクテリアが多く棲息しています。そのため、この巻貝も含めて結構多くの生き物が密生しているのです。住めば都、ということなのでしょう。それにしても、ここまで重装備しなければならないワケは謎です。
★ヒライソガニ★
最後はほっこりできる生き物を紹介しましょう。

2003年に三重県の小学生が見つけました。最初は、マジックでいたずら描きしてるとおもわれたそうですが、脱皮してホンモノと確認されました。造化の神さまも、時にはこんな遊び心を発揮してくれるんですね。おかげで最後を楽しく締めくくることができました。
それでは次回をお楽しみに。