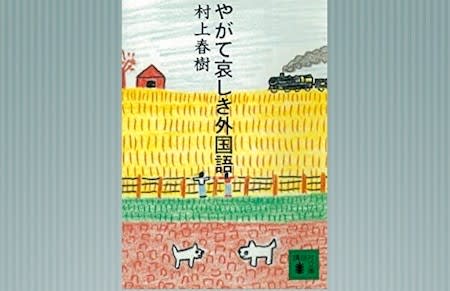シリーズの第5弾をお届けします。文末に過去分へのリンクを貼っていますので、合わせてご覧いただければ幸いです。で、今回は英語圏を中心に海外の人名のあれこれを話題にします。なお、清水義範さんのエッセイ「名前の起源あれこれ」(「雑学のすすめ」講談社文庫所収)を、一部、参考にしました。
英語圏で割合目にするのが"son"が付く名前。元々は、「あれは、○○の息子(=son)だ」と呼んでいたのが、一家の名前として引き継がれているもので、そのまんま、分かりやすいです。
ジョンソン(Johnson)、ジャクソン(Jackson)などの例を思いつきます。
英国では名前に"s"を付けて、「~の息子」または「~家」を表す方式もあります。
"Williams(ウィリアムズ)"、"Adams(アダムス)”のように。
デンマークだと、"son"が「セン(sen)」になります。童話でお馴染みのアンデルセンは「アンドリューの息子」というわけです。ドイツ語で息子は"sohn(ゾーン)"です。音楽家のメンデルスゾーンは、「メンデルスの息子」という意味だったんですね。
スコットランドでは、"Mac"または"Mc"が「息子」を表し、姓になります。
"McDonald(マクドナルド)"がお馴染みです。戦後日本の総司令官マッカーサも、
"MacArthur”、つまり、「アーサー(アーサー王の伝説のアーサーです)の息子」というなかなか由緒ある名前だったんですね。
そして、コンピュータのアップル社の初期の製品ブランド名です。
実は、"McIntosh(マッキントッシュ)"という名前のリンゴの品種があるんですね。アップル社にふさわしいと社長のジョブスも気に入って、綴りは、"Macintosh”として、世に送り出したと伝えられています。
その後、"Mac"が、MacBook、iMacなど主力製品群のブランド名として、また、愛称として定着しているのはご存知のとおりです。
さて、欧米人には、聖書に由来する名前が多いです。
代表的なのは、聖ヨハネにちなむもので、"John(ジョン)"、"Jack(ジャック)"、"Jan(ジャン)"などのバリエーションがあります。聖パウロが、"Paul(ポール)になります。ポール・マッカートニーを思いだす人が多そうです。大天使ミカエルが、"Michel(マイケル)"で、思いだすのが、こちらのマイケル・ジャクソン。
フランスではミッシェルとなり、アメリカのオバマ元大統領の夫人がこの名前です。女性名になるのが面白いですね。
聖ヤコブが、"James(ジェームズ)"、ダビデ王にちなむのが、"David(デイビッド)"など、この辺にしておきましょう。聖人とか偉大な人物にあやかった名前をつけるのって、日本人的には、ちょっと恥ずかしい気もします。
名前の由来といえば、ご先祖様が携わっていた職業に関わるものも多いです。有名人にちなむものをご紹介してみます。
小説、映画のシリーズで人気を集めたハリー・ポッターですが、ポッター(=potter)は、ポット、つまり、壷などの土器を作る職人さんのことなんですね。
アメリカの元大統領のジミー・カーター(Jimmy Carter)さん。カート(=cart 荷車、二輪車)を作る人、または、御者という意味です。これは気がつきませんでした。
カーペンターズ(Carpenters)という兄妹デュオが、アメリカにいました。トップ・オヴ・ザ・ワールドなんてヒット曲を懐かしく思いだします。ご先祖様の職業は・・・そう、大工さんですね、
シェパード(Shephard)は、羊飼いですね。同名の犬種があります。牧羊犬として利用されていたことから名付けられました。歌手の千昌夫さんの最初の奥さんがシェパードさんでした。彼が「うちの奥さん、シェパードっていうんだよぉ、なんかさぁ、ワンちゃんの名前みたいで・・」とテレビで笑いを取っていたのを思いだします。
エリザベス・テイラーという大女優さんがいました。テイラー(Tailor)は、洋服の仕立て屋さん。ご先祖様も、あの世でさぞ誇らしく思っておられることでしょう。
昔、アブドラ・ザ・ブッチャーというリングネームのプロレスラーがいました。ブッチャー(Butcher)は肉屋さんです。凶器攻撃専門の悪役(ヒール)で、たいしたワザはなかったですが、肉屋みたいにお前のカラダを切り刻むぞ、といわんばかりのファイトぶりが印象に残っています。
喜劇王のチャップリン(Chaplin)は、礼拝堂の牧師さん。ご先祖様は、随分お堅い職業に従事しておられたのですね。
名は体を表す、といいますが、ご先祖様のお仕事を表すのが結構あるというのをあらためて知りました。
それでは次回をお楽しみに。
 芦坊拝
芦坊拝 芦坊拝
芦坊拝
 芦坊拝
芦坊拝