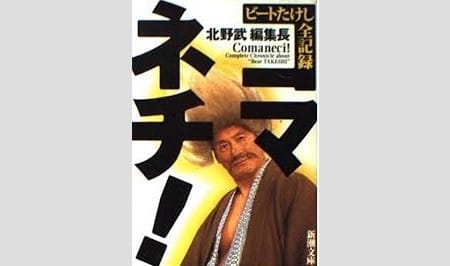シリーズ最終回の第5弾になります(文末に、直近2回分の記事へのリンクを貼っています)。ネタ元は、作家・半藤一利さんの「21世紀への伝言」(文藝春秋刊)です。著者が21世紀に伝えるべく選んだエピソードの中から、楽しい、スゴい、興味深い、ものなどをセレクトしてお届けしてきました。今回は、1970年代を中心とした時代の話題をご紹介します。
< >内の私なりのコメントと併せて、気楽にお楽しみください。
★いい夢を見させてもらった★
プロ野球での金字塔、空前絶後の記録はいろいろあります。タイガースファンにとっては、オールスター戦での9打者連続奪三振にとどめを刺しそうです。達成されたのは、1971(昭和46)年、西宮球場での試合です。スポーツニュースだけでなく、一般のニュースまでが大きく取り上げました。
誰も達成したことがないこの記録を本人が予告していたのも驚きです。日本での18年の現役生活を終え、大リーグに挑戦しましたが、夢は叶いませんでした。「いい夢を見させてもらった」という江夏の言葉が残されています。こちらは、記録達成の瞬間です。

<テレビのニュースで何度も見て、興奮したのが懐かしいです。一塁ファールフライを「取るなっ!」と捕手の田淵に叫んだ、との噂(真偽は不明)を耳にしたのを覚えています>
★すぐやる課★
市民からの要望があればとにかく駆けつけて相談にのる、処理する、
をモットーに、千葉県松戸市の「すぐやる課」ができたのが、1969(昭和44)年10月です。どぶさらいから蜂の巣処理まで、名前に違わぬ活動ぶりが随分マスコミでも話題になりました。
当時の松本清市長(故人)の思いは脈々と受け継がれ、98年度で年間3千件あまりを処理していると本書にあります。
<現在も立派に活動しています。もっと追随する自治体が出てもいいと思うのですが、組織の壁は厚いようですね>
★サングラスを買った男が最初の客★
1960年頃、大半の日本人は、夜は10時前に床に入っていました。それが、1975年には、その時間に寝ているのは4人のうちわずか1人。そんな生活時間の変化に合わせるように、日本初のコンビにであるセブン・イレブンの1号店が豊洲でオープンしたのが、1974(昭和49)年5月15日です。
「どしゃぶりの雨の朝、サングラスを買った男が最初の客でした」との当時の店長が回想しているのが愉快です。
<ATMと公共料金、通販料金の支払いがもっぱらですが、ありがたい存在です。365日24時間営業の必要性なども話題に上るご時世に、時の流れを感じます>
★文章を書くのは脳なんです★
ハイテクなんて言葉も随分古びてしまいました。東芝から日本で最初のワープロが売り出されたのが、1978(昭和53)年5月のことです。今やパソコン、タブレット、スマホとその手の機器の進化はとどまる所を知りません。当時の開発者の言葉です。
「使う道具が万年筆でもワープロでも、文章を書くのは脳なんです」
<パソコンで「便利に」ブログの記事を書きながら、ハッとさせられました>
★歴史は遡るように読むべきだ★
「文藝春秋」の2000年2月特別号が、各界の著名人に行った「私のメモリアル・デイ」というアンケート結果を特集しています。
1位が太平洋戦争の敗戦、以下、2位が三島由紀夫の割腹自殺。3位、昭和天皇崩御。4位、太平洋戦争開戦。5位、アポロ11号月面着陸。6位、2・26事件。同順7位、ベルリンの壁崩壊、阪神・淡路大震災と続きます。
本書の最後で、著者は、フランスの歴史学者で、ゲシュタポに射殺されたマルク・ブロックの名言を引用しています。
「歴史を古代から時代順に読むから考えなくなってしまう。歴史は現代から遡るように読むべきだ」<この記事を締めくくるにあたり、この言葉をしっかり噛みしめました>