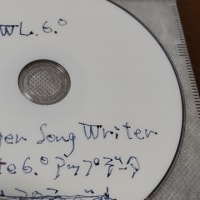とても印象と感慨の深い演奏がある。
19歳からほとんど10年ほど,母校に通い後輩たちに合唱を教えていた。
学校には講師の方しかいなく,合唱指揮経験の無い方もおられたためと,逆に自分が合唱と指揮経験を続けていたこともあるが,結局は自己満足だった。
ある年度の生徒らは女2男1の計3名にまで減ったことがあったが私がたまに入ることでカルテットで「大地讃頌」「ハレルヤ」から小品までも歌っていた。
それでも,とても実力があり,自力で仲間や後輩を増やし,単独で演奏するまでになった。
けれど,私は何とか力試しというか人並みの場と言うか,結果はどうあれコンクールだけは出してあげたかった。
そして,私はコンクール向けに正式な学校長からの「特別コーチ」として辞令を頂き,講師の方と部長の女子の尽力で学校としての全面バックアップをいただき,さらに学生を中心としたOB・OG数名の協力で「一般の部」への出場となったのでした。
以下の演奏は,その時のものです。詳細は動画の下にYoutubeと同じものを掲載しました。
お聴きください。
混声合唱のためのカンタータ「土の歌」より 第2楽章 祖国の土 (選択曲)
作詩 大木惇夫(あつお)
作曲 佐藤眞(しん)
昭和57年(1982年)9月21日,第34回・全日本合唱コンクール山形県大会一般の部・銅賞の演奏です。高校としては過去に県大会優勝実績もありましたが,部員減少で,当年度の3年生はたった3人で冬を越した「折れない」メンバーです。
OBの私が学校長より「特別選任コーチ」として任命・指揮者に入り,OB,OG数名の協力と確か7名の「1年3組の助っ人」を含め約20名で出演,銅賞でしたが審査員からは真摯に「一般に混じって大健闘」との評価がありました。
(メンバー,姓は全て当時)
・指揮 池田修一(OB)
・伴奏 白旗玲子(音楽科講師)
・Sop. OGで新潟大音楽科(ピアノ専攻)の池田さん,3年生に後のソプラノ歌手として「トスカ」でタイトルロールの五十嵐さんら
・Alto 3年生に日常の伴奏を兼ねてくれた萩原(姉),2年生に後にソプラノ歌手の杉原さん(現大学教授?なぜアルトかは不知)ら
・Ten. OBで東京から学生で参じた生真面目なTerra三井君,3年生にSip.五十嵐さんの追っかけでブラス系のバーバー川崎君,2年生に後にプロ指揮者の工藤君,1年生に7人も「集客」した萩原(弟)君ら
・Bass OBで唯一地元の池田君,OBで東京から学生で参じた故・宮越君(善人だけに真に無念),1年に入部でいきなりpfの「展覧会の絵」を披露した酒井君ら
本番が近づくにつれ,皆の集中力に気押され,指揮者も早朝・昼・夕,土曜は丸一日と音楽室に入り浸っていました(昼飯抜きで19:30頃までとか..校長が現役時代の教頭だったので理解あり)
30年も経った今,人数の埋め合わせと思ったことが嘘のような,物凄いメンバーに恵まれていたということに感謝しています。
なお奇遇ですが大木惇夫氏は酒田E高校のアカデミックな校歌の作詞者でもありますが,「土の歌」は広島出身の大木惇夫氏ならではで,この曲は「土の歌」の2曲目,「かつて豊穣な土があり好きなときに自由に,安全に土を踏みしめていた」という,戦前の,奔放かつ,のどかな時代を表現しています。
3曲目で自滅的な「死の灰」が降り,最終章の有名な「大地讃頌」によって「国敗れて山河あり」と言える中での,この土の有難さ,そして感謝につながっていきます。
冒頭,A-Durの低いAの音(0:31)がほぼ聴こえないのは大減点で,低音の出ないメンバーではフェルマータレベルで伸ばすのが良かった。また「歩け歩け」(1:36)の文末の雑さ,山河よ(1:55)の移調のユニゾンが決まっていない&溜めなければ等,30年経過して,指揮者のダメダメなのが分かりますね。
それを教えてくれている,同輩・後輩たちの好演に感謝しています。これからも前進していきます。
19歳からほとんど10年ほど,母校に通い後輩たちに合唱を教えていた。
学校には講師の方しかいなく,合唱指揮経験の無い方もおられたためと,逆に自分が合唱と指揮経験を続けていたこともあるが,結局は自己満足だった。
ある年度の生徒らは女2男1の計3名にまで減ったことがあったが私がたまに入ることでカルテットで「大地讃頌」「ハレルヤ」から小品までも歌っていた。
それでも,とても実力があり,自力で仲間や後輩を増やし,単独で演奏するまでになった。
けれど,私は何とか力試しというか人並みの場と言うか,結果はどうあれコンクールだけは出してあげたかった。
そして,私はコンクール向けに正式な学校長からの「特別コーチ」として辞令を頂き,講師の方と部長の女子の尽力で学校としての全面バックアップをいただき,さらに学生を中心としたOB・OG数名の協力で「一般の部」への出場となったのでした。
以下の演奏は,その時のものです。詳細は動画の下にYoutubeと同じものを掲載しました。
お聴きください。
酒田E高校「若い芽の会」佐藤眞 土の歌より 2.祖国の土(コンクール山形県大会銅賞)
混声合唱のためのカンタータ「土の歌」より 第2楽章 祖国の土 (選択曲)
作詩 大木惇夫(あつお)
作曲 佐藤眞(しん)
昭和57年(1982年)9月21日,第34回・全日本合唱コンクール山形県大会一般の部・銅賞の演奏です。高校としては過去に県大会優勝実績もありましたが,部員減少で,当年度の3年生はたった3人で冬を越した「折れない」メンバーです。
OBの私が学校長より「特別選任コーチ」として任命・指揮者に入り,OB,OG数名の協力と確か7名の「1年3組の助っ人」を含め約20名で出演,銅賞でしたが審査員からは真摯に「一般に混じって大健闘」との評価がありました。
(メンバー,姓は全て当時)
・指揮 池田修一(OB)
・伴奏 白旗玲子(音楽科講師)
・Sop. OGで新潟大音楽科(ピアノ専攻)の池田さん,3年生に後のソプラノ歌手として「トスカ」でタイトルロールの五十嵐さんら
・Alto 3年生に日常の伴奏を兼ねてくれた萩原(姉),2年生に後にソプラノ歌手の杉原さん(現大学教授?なぜアルトかは不知)ら
・Ten. OBで東京から学生で参じた生真面目なTerra三井君,3年生にSip.五十嵐さんの追っかけでブラス系のバーバー川崎君,2年生に後にプロ指揮者の工藤君,1年生に7人も「集客」した萩原(弟)君ら
・Bass OBで唯一地元の池田君,OBで東京から学生で参じた故・宮越君(善人だけに真に無念),1年に入部でいきなりpfの「展覧会の絵」を披露した酒井君ら
本番が近づくにつれ,皆の集中力に気押され,指揮者も早朝・昼・夕,土曜は丸一日と音楽室に入り浸っていました(昼飯抜きで19:30頃までとか..校長が現役時代の教頭だったので理解あり)
30年も経った今,人数の埋め合わせと思ったことが嘘のような,物凄いメンバーに恵まれていたということに感謝しています。
なお奇遇ですが大木惇夫氏は酒田E高校のアカデミックな校歌の作詞者でもありますが,「土の歌」は広島出身の大木惇夫氏ならではで,この曲は「土の歌」の2曲目,「かつて豊穣な土があり好きなときに自由に,安全に土を踏みしめていた」という,戦前の,奔放かつ,のどかな時代を表現しています。
3曲目で自滅的な「死の灰」が降り,最終章の有名な「大地讃頌」によって「国敗れて山河あり」と言える中での,この土の有難さ,そして感謝につながっていきます。
冒頭,A-Durの低いAの音(0:31)がほぼ聴こえないのは大減点で,低音の出ないメンバーではフェルマータレベルで伸ばすのが良かった。また「歩け歩け」(1:36)の文末の雑さ,山河よ(1:55)の移調のユニゾンが決まっていない&溜めなければ等,30年経過して,指揮者のダメダメなのが分かりますね。
それを教えてくれている,同輩・後輩たちの好演に感謝しています。これからも前進していきます。