去る11月19日(土)に佛教大学 鈴木先生を招いて懇談会を開催しました。
当会からは鈴木先生へ当会をふくめた全国専攻科活動の御説明を経て、全国の専攻科の増加状況などの情報交換を交えながら、懇談を実施しました。鈴木先生からは「共生のルネサンス~人類史における障害のあある人々の位置」というテーマで、古代ルネサンス時期から現代に至るまで障の、碍者と健常者との関係から現代等興味深い講話をいただきました。
下記、御報告情報を御参照ください。
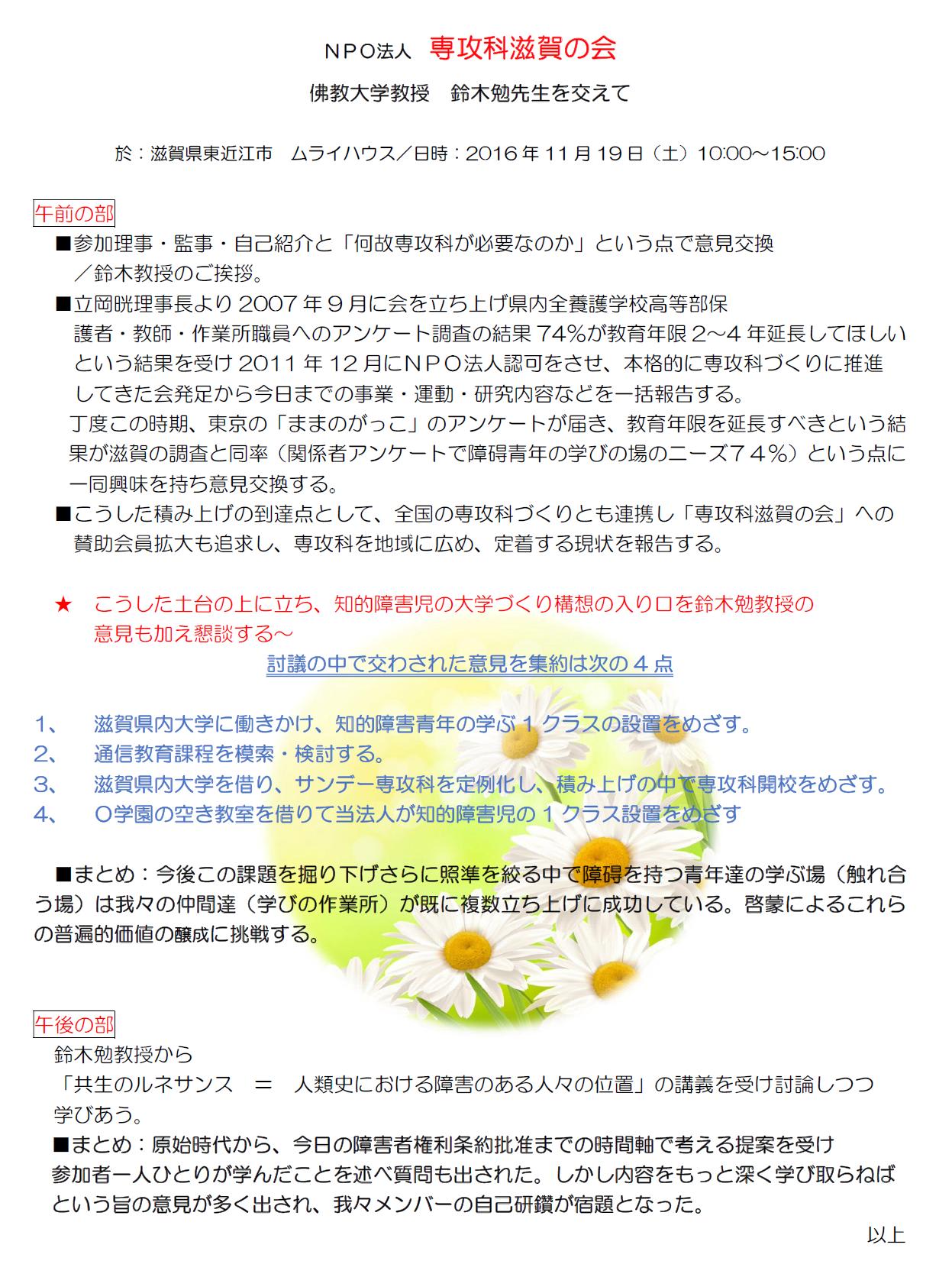
◆鈴木先生との懇談の様子


【御参考】 懇談時に鈴木先生にご高覧頂いた当会活動情報
専攻科滋賀の会、これまでの主な歩み
-2007年09月/県下全特別支援学校高等部保護者(279人)にアンケート調査を実施
-2008年11月/県下全特別支援学校高等部全教師(448人)にアンケート調査実施
-2009年10月/県下きょうされん加盟の事業所職員(196人)にアンケート調査実施
~アンケート調査結果、共通して74%が高等部卒業後2~4年の教育期間必要と判明~
-2010年02月/アンケート調査結果報告書「もっと学びたい」1,000部発刊
-2010年12月/第7回全国専攻科研究集会IN滋賀を開催し、全国から326人出席
-2011年03月/障害青年を対象にした「サンデー専攻科」開催し、以降開催を積み上げ
-2011年12月/専攻科滋賀の会、NPO法人を取得
-2012年11月/蒲生の会理事長と懇談以降、各組織、市長、知事などと懇談を積み上げ
-2013年07月/滋賀県教育委員会との懇談会開催
-2014年07月/国立鳥取大学に専攻科立ち上げた渡辺昭男教授を招いての学習会開催
-2015年07月/第7回専攻科滋賀の会総会で全国専攻科田中良三会長の記念講演
-2016年09月/障害者の生活と権利を守る連絡協議会主催の県との懇談会に出席
現在の専攻科滋賀の会の到達点と課題
■滋賀県下全特別支援学校高等部保護者、教師、ならびにきょうされん滋賀支部職員のアンケート調査結果により、高等部卒業後さらに2~4年間の学びの期間必要であるという願い実現に向け、NPO法人取得後、共感していただく賛助会員(約300人)に支えられ、全国専攻科の会とも力を合わせ地道にその必要性を世論に訴えてきた10年間でありました。
■この運動の成果が徐々に芽吹きかけている手ごたえを感じる現在である。その手ごたえとは、滋賀県内にも通称「学びの作業所」が近畿圏内23か所の内5か所(約2割)へと増加傾向にあること。全国では文科省管轄で13か所、厚労省管轄で36か所と毎年増加しており、現在では合計49か所の学びの期間2~4年が実現してきている。(全国55%に開校)
■今後は2年前に我が国が批准した障害者権利条約並びに今年度から施行された障害者差別解消法が述べるように、合理的配慮が求められる時代であり、学びを必要とする知的障害者への教育期間保障は避けては通れない。先ずは大学教育機関が自ら障害児を受け入れるインクルーシブ教育の可能性を研究する所まで来ている。




















