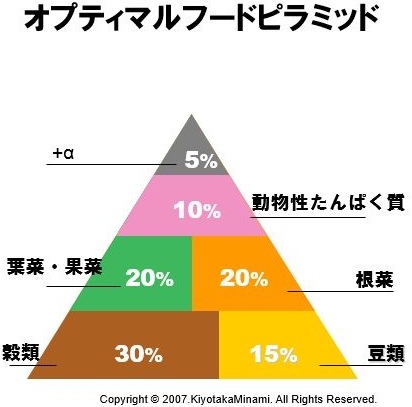https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170621-00010009-dime-life&pos=1
チェスター大学の研究によると、あらゆるフルーツで生と冷凍の栄養価の比較をしたところ、ほとんどのフルーツで、冷凍した方がビタミンCや抗酸化物質の含有量が高いという結果が出たという。
■冷凍するのに向いているフルーツ
冷凍するのに向いているのは、味の濃いものだ。フルーツは冷凍すると甘みや酸味を感じにくくなるが、濃い味のフルーツならば凍らせることで、ほどよい甘みと酸味になっていく。
さらに言えばシャキシャキとした食感で、繊維質が豊富で水分量が多すぎないものが理想的。冷凍しても固くなりすぎず、ほどよい食感が残りるはずだ。
逆に、ビワのような淡い味のフルーツは、冷凍すると水分が抜けて瑞々しさがなくなり、味もさらに薄くなるので向かないので注意しよう。
・バナナ
皮をむいてそのままラップで包み冷凍庫に入れれば完成。特に熟して食べられなくなるギリギリのものが凍らせると美味しいそうだ。さくっと簡単にスライスできるので、調理もしやすいはずだ。
バナナには抗酸化作用が期待できるポリフェノールや美容ビタミンと呼ばれるビタミンB群が含まれている。さらに、食物繊維とフラクトオリゴ糖を両方含み、整腸作用のある難消化性でんぷんも豊富。腸内環境の向上で、免疫力を高めることも可能だ。
・キウイ
皮をむき、輪切りやくし形切りなどにカットしてから冷凍しよう。食べるときは半解凍でそのままでも良いし、スムージーの材料にも向いている。
キウイに豊富に含まれているビタミンCやビタミンEは、紫外線やストレスで受けた肌へのダメージを回復する作用がある。さらにしみやシワ、たるみなどの老化改善にも効果が高い。食べ続けるとくすみのないハリのある肌を作ってくれるだろう。
・ぶどう
皮は向かずにそのままで、茎を少し残して実を一つずつ切り離し、そのまま密封して冷凍。冷凍したぶどうは、まるで「アイスの実」のようなサイズと食感で、スイーツとしても優秀。食後のデザートや3時のおやつに最適だ。
ぶどうの美容成分は、やはりポリフェノールが特出して多いのが特長。殺菌作用の強いカテキンや眼精疲労に効果があるアントシアニンがたっぷり入っている。
さらに血圧降下や脂肪を分解するタンニンや、若返り成分のレスベラトロールなど各種ポリフェノール満載のアンチエイジングフルーツなのだ。
・柿
ヘタも皮もついた状態のまままるごと冷凍庫に入れてしまってOK。ただしシャキシャキの状態で冷凍すると食感が悪くなってしまうため、柔らかくなってから冷凍しよう。
少しずつ食べたいなら皮をむいて、一口大に切って重ならないように注意して密封。半解凍くらいで食べると、アイスクリームのような食感で少しクリーミィな味わいになる。
なんとビタミンCの含量は、全フルーツの中でもトップクラス。日焼けやシミを防ぎ、できてしまったシミにも働くという。また、カリウムも豊富に含んでおり、体内の余分な塩分を外に排出する効果を持っている。二日酔い予防にも効くので、飲み会の前に食べておくことをオススメしたい。
冷凍したフルーツの保存期間は約1年。買いすぎてしまったら凍らせてストックしていくととても便利だ。しかし、長期間保存していると果肉が固くなって食べにくくなることがある。そういうときは少し溶かして半解凍の状態で食べるのがオススメだ。
また、冷凍して少し味が薄くなると物足りない場合は、アイスクリームやヨーグルトに混ぜて食べるのもいいだろう。