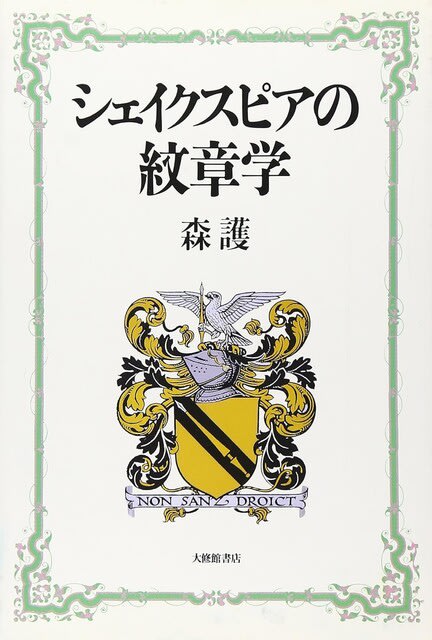
「シェイクスピアの紋章学」を読んで、「紋章官」についてわかったことがいくつかありました♪
最初、ローゼンクランツ城砦やメルガレス城砦あたりであった馬上試合については、スコットの「アイヴァンホー」を参考にしつつ、かなりのところ適当に書いただけだったんですよね(^^;)
それで、わたし的に「紋章官」という存在が気に入って、この紋章官に馬上試合の審判(レフェリー)をさせようと思ったわけです。というのも、前に引用させていただいた「ヨーロッパの古城」という本の中に、紋章官について>>「領主や富裕な騎士は、少なくともひとりの紋章官をやとい、紋章官は紋章以外にもさまざまな役務をこなした。もっとも重要な役割は領主の代理を務めることで、馬上槍試合では領主の代わりに号令をかけた。」と短く書いてあったため、ここから類推して「そういうことなら紋章官が馬上試合で審判をしてもおかしくないのでは? 」と思ったからだったり。
」と思ったからだったり。
そして今回森護先生の「シェイクスピアの紋章学」を読んでいて……実際のところ馬上試合や馬上槍試合などにおいて紋章官が審判をしていたと書いてあったので、これはわたしの憶測ではなくどうやら正しい事実となることのようです(^^;)
ユニークな職位ヘラルド
そのヘラルドであるが、この職位は紋章制度がはじまる前から活躍した、極めてユニークな存在であった。よく「伝令」と訳されるが、伝令という語感から受けるような軽い職位ではなく、身分こそ高くはなかったものの、極めて重要な役目を負わされた軍使ともいうべき職位であった。国王に仕えるものもあれば、領主に仕えるものもあり、戦闘中にあっては、休戦、和議など、必要があれば敵の本陣にまで出向いて交渉に当たった。ためにヘラルドは敵味方から、その生命と安全を保障され、目立つ手段として一見してヘラルドと分かる服装をしていた。紋章時代に入ると、ヘラルドは仕える国王や領主の紋章を縫い取った、独特のあでやかな陣羽織(タバード)を着用に及んだが、現在でも紋章院のキング・オブ・アームズ以下、各級の紋章官がそのような制服を着用するのは、かつての軍使時代の伝統をいまに伝えるものである。
またヘラルドは、平時においては騎乗槍試合などの進行や、審判も務めたことから、戦闘時にあっては敵の紋章に通じ、平時にあっては騎乗槍試合に出場する騎士の紋章に通じるといった具合で、やがて彼らが持つ紋章知識は、軍使以上に重宝な存在になって行く。彼らが職務上の必要から記録した紋章は、その後公的な記録(紋章鑑)となるとともに、貴重な紋章資料ともなった。そしてばら戦争当時までは、軍使兼紋章官兼儀典担当官であったヘラルドは、以後軍使の役は次第に消えて、ヘラルドすなわち紋章官ならびに儀典担当官という存在に変わって行った。
(「シェイクスピアの紋章学」森護先生著/大修館書店より)
とあって、他の中世騎士系の本などを読んでいて、何故わたしが紋章官が馬上槍試合などにおいて審判の仕事もしている……と気づかなかったかというと、このヘラルドという言葉がおそらく、「式部官」と訳されることもあるため……なんじゃないかなと思いました(^^;)
つまり、何度か引用させていただいている「最後の決闘裁判」でも、「決闘裁判」を行うに当たって、かなりのところ儀式的趣きがあったりもして、その一連の手続きを「式部官」や「紋章官」が行なっているのがわかります。つまり、わたしの理解としては「式部官」と「紋章官」というのは別物……といったように勝手に思っていたわけですが、イギリスにおいては(ちなみに「最後の決闘裁判」の舞台はフランスですが、以下、こちらの文章を読んで理解できるようになった箇所の抜粋となりますm(_ _)m)、
>>それらの個々の職位については後で触れるとして、系図Ⅲを見ると、「リチャード二世」で国外追放を命じられた、ノーフォーク公トマス・モウブレイ(1399年没)にアール・マーシャルとあり、アール・マーシャルの職位がモウブレイ家四代で占められて断絶した後、女系につながるハワード家の初代ノーフォーク公ジョン・ハワードがその職位に就いている。しかもハワード家に渡ったこの職位は、現在に至るまでノーフォーク公家の世襲職位として続くものである(※正式に世襲職と決められたのはチャールズ2世の1660年)。そしてこの職位こそが、英国の諸典礼、つまり王家の冠婚葬祭、戴冠式、皇太子の立太子式、ガーター・ナイトの叙爵式、そして議会の開院式などを司るものでもあれば、イングランドの紋章の許認可、統轄の最高職位でもある。
そしてアール・マーシャルの下で、実務の最高責任者が三人のキング・オブ・アームズ、その次席者が六人のヘラルド、そして最下位職が四人のパーシヴァントとなっている。
これらの紋章官で構成される紋章院が設立されたのは、1484年、リチャード三世の発意によるもので、前年の6月28日、ノーフォーク公に叙爵され、かつアール・マーシャル位を受けたジョン・ハワードの管轄下に置かれた。
「マーシャル」はもともとは王の馬係に始まる職位といわれるが、後に儀仗部隊の司令官のような職位に変わった。前記のノーフォーク伯トマス・ブラザートンが受けた、マーシャル・オブ・イングランドのような職位や、初代ノーフォーク公トマス・モウブレイのアール・マーシャル位も、後の紋章院総裁職ではなく、式部長官職というところであった。
史劇「リチャード二世」では、第一幕三場、コヴァントリーの試合場の場で、ロード・マーシャルが登場するが、これは実務に当たる式部職である。しかし後のアール・マーシャルの職位が、紋章院総裁と訳した方が適確であるように、リチャード二世時代のアール・マーシャルにしろ、騎士の紋章が制度として極めて重要な時代であっただけに、ヘラルドとともに、紋章制度と深いかかわりのある職位でもあった。
(「シェイクスピアの紋章学」森護先生著/大修館書店より)
ということのようで、式部官はおそらく紋章官(ヘラルド)よりも上の役職を示すものではないかと思われるわけです。そしてパーシヴァントというのは従者と訳されることもあるそうなのですが、ヘラルドよりも下の役職にある者、ということのようです。
いえ、これも前回の「ギャンベソン」と「ジャック」の違いと同じく、わたしが中世騎士系の本などを読んでいて「どっちだろ? 」とか、「どういうことだろ?
」とか、「どういうことだろ? 」とかはっきりわからなかったことのひとつで、ようやくわかって良かったという、ただの自己満足のために書いてみたことだったりします(^^;)
」とかはっきりわからなかったことのひとつで、ようやくわかって良かったという、ただの自己満足のために書いてみたことだったりします(^^;)
まあ、映画やドラマの感想などもそうなんですけど……結局、鳥頭
 なので自分でもすぐ忘れちゃうんですよね。「確かどっかにメモ書きとして残しておいたぞ
なので自分でもすぐ忘れちゃうんですよね。「確かどっかにメモ書きとして残しておいたぞ

 」ということだけ覚えておけば――あとから再び必要になった時に読み返せばいいので(特に最近自分でもひどいと思うことには、一度見た映画やドラマのタイトルが思い出せない現象がよく起きるので
」ということだけ覚えておけば――あとから再び必要になった時に読み返せばいいので(特に最近自分でもひどいと思うことには、一度見た映画やドラマのタイトルが思い出せない現象がよく起きるので
 )。
)。
それで、式部官=紋章官ということさえわかれば、他の本に書いてある騎士の馬上武術試合や馬上槍試合についても「なるほど~!! 」とわかることが出てきました。確かに、紋章官というのはユニークな役職で、自身は直接戦闘に参加しなかったにせよ、戦争においても馬上試合や決闘といった試合においても極めて重要な役割を果たしたと思うんですよね。それでいて身分はあまり高くなかった……ということなのですが、イギリスにおいては「紋章院総裁」という極めて輝かしい役職があって、最初わたし、この名称が何を意味するものなのかはっきりわかってなかったわけです(^^;)
」とわかることが出てきました。確かに、紋章官というのはユニークな役職で、自身は直接戦闘に参加しなかったにせよ、戦争においても馬上試合や決闘といった試合においても極めて重要な役割を果たしたと思うんですよね。それでいて身分はあまり高くなかった……ということなのですが、イギリスにおいては「紋章院総裁」という極めて輝かしい役職があって、最初わたし、この名称が何を意味するものなのかはっきりわかってなかったわけです(^^;)
ただ、映画の中でノーフォーク公が「公爵にして紋章院総裁でもあるわたしを逮捕しようというのか」というようなセリフがあって(例によってという言い方はなんですが、ようするに反逆罪の嫌疑をかけられて)、その時もわたしよくわかんなかったわけです。「紋章院総裁?なんか格好いい役職名だけど、具体的にどういった仕事をする役職なんだろう? 」と思ってまして。。。
」と思ってまして。。。
なんにしても、これでそうした謎も解けて良かったのですが、こうした本を「紋章学」に絞って書いてしまえる森護先生のような方は本当に貴重ですごい方だと思います


それではまた~!!
惑星シェイクスピア-第三部【38】-
その後、ラルドレッド・モルドレッド公爵とモルディラ騎士団の三騎士らも捕えられ、ハムレット王子軍の捕虜となった。宿営地にいた公爵軍の騎士も兵士も、鎧を脱ぐなどしてすっかり無防備だったため――頑なに抵抗した者らであっても、死には至らず、怪我をして気を失うといった程度で済んだようである。
槍や剣を手にし、死ぬ気で立ち向かって来た者もいたが、そうした者たちでも死体として地面に転がることまではなく、何人もの兵で雌鹿を網で捕える時のように囲い込み、抵抗するのを諦めさせたのである。当初の予定では、死者が出るのもやむなしとされていた作戦であったが、犠牲者が少なくて済んだのは幸いなことであったと言えよう。
マドゥールとソレントのレティシア兄弟に捕えられたラルドレッド・モルドレッドは、その後もあまり多くを語らなかった。マドゥールはこの友に対し、「ハムレット王子はまったく素晴らしい方だ」とか、「拷問を趣味とするクローディアス王に仕えるよりも、まったく仕え甲斐のある偉大なお方よ」とか、「あの方が王となった暁には長く平和が続こうぞ」など、降伏後も彼自身と家臣らの命は保証されようといったようにも語ったのだが、ラルドレッドは聞いているのかいないのか、むっつり黙り込んだままでいたのである。
こうして、ラルドレッドは同じように捕えられた近衛の三騎士とともに、ハムレット王子の御前に引き出されてきた。だが、マドゥールが彼の横で跪き、友の命乞いをはじめるなり――この新しく公爵の位を継いだばかりの男は「殺せ!!」と、男らしく怒鳴ったわけであった。
「おまえたちが殺した我が父、誇り高きモルディガン・モルドレッドのようにな!!確かに、家臣らの命をみな救ってくれるということには心から感謝しよう。だが結局、見せしめは必要だ。その点、軍の総大将である公爵の俺を殺せば、間違いなく後の禍根を断てようというもの。このラルドレッド、命ならば惜しくはない。ただ、我が一族のことは砂漠に追放処分にするにしても、命までは奪わないとそう約束さえしていただければ……」
「何をおっしゃいますか、ラルドレッドさま!!」と、落馬した時に右のこめかみに怪我をしたモーリスが、まだ赤黒い血をそこにつけたまま、叫ぶように言った。「まだお子さま方もお小さいのですぞっ!!ここは心の広いハムレットさまとおとりなししてくださったレティシア侯爵の御慈悲にお縋りすべきです!!」
「そうです!!」と、同じように縄で後ろ手に縛られたまま、モンマス=オブ=モントネイルが言った。「これからも我々の主君はラルドレッド様おひとりのみ!!もしここでラルドレッドさまが死ぬとあれば、我々も運命を共にする覚悟です!!」
「どうか、ここはお父上のことは堪えてくだされ」と、モーゼス=オブ=モンテスキュウ。「そして今はどうか何卒、ご自身が生き延びられることだけお考えくださいませ。ハムレットさま、我々の命は取ってくださっても構いませぬ。ただその代わり、どうかラルドレッドさまのお命だけは……」
三騎士は、三人が共に涙を流していた。モーリスもモンマスもモーゼスも、ラルドレッドを守ろうと最後まで抵抗したため、それぞれ傷を負っていた。彼らは三人とも、自分の主君が今どれほどの屈辱を耐え忍んでいるかと思い、そのことを思ってみただけでも自然と涙が溢れてくるのであった。
「ハムレットさま、いかがなされますか?」
カドールが天幕の前に設営された玉座に座るハムレットの右後方からそのように囁いた。左後方にはいつも通りタイスが控えている。他に、この場にはランスロットやギネビアやレンスブルックといった仲間、ロドリゴ・ロットバルト伯爵、エレアガンス・メレアガンス子爵、それに各騎士団の騎士団長など、軍の主だった面々も勢揃いしている。
「ラルドレッド・モルドレッド公爵よ」と、ハムレットは静かに呼びかけた。「確かにそなたの命を奪ったほうが、のちの禍根は断てようというもの。だが、そなたのことは生かしておこう。レティシア侯爵の友としての懇願と、そなたの近衛騎士らの嘆願の涙に心を動かされたゆえにな。まこと、その人物の本当の人柄を知りたくば、その友や部下に尋ねよとはよく言ったもの。ラルドレッド殿、そなたはきっと部下たちが命を懸けるに足ると信じる軍の総大将であり、マドゥール・ド・レティシア侯爵が『ひとりの人間としても男としても素晴らしい人物です』とおっしゃるほどのお方で間違いないのだろう。このハムレット、そのような素晴らしい人柄を有すると評判の男を無用に殺害するほど、愚かではないつもりだぞ」
「では、ラルドレッド殿のお身柄は、我、マドゥール・ド・レティシアの陣営にてお引き受け致しまする」
「ああ。是非ともそのようにしてくれ、レティシア侯爵殿」
――ラルドレッド・モルドレッド公爵の件は、大体のところこれで片付いた。とはいえ、ラルドレッドはハムレットやマドゥールの温情に感謝しつつも、内心では複雑な感情を味わっていた。そして、確かに降伏を薦める書面にあった通りのことが実現したのだとも思った。第一の雹の難、第二の暗闇の難、第三の蛭の難と……これこそは、ハムレットが確かに星神・星母の導きによって選ばれた王の器であることを意味していたのかもしれない。
だが、実をいうとラルドレッドは、かなりのちの日になって、ハムレット王子軍が、そのような書状を使者に持たせて遣わしたことはないという事実を知り――狐につままれたような思いを味わうことになるのであったが。
* * * * * * *
ハムレット王子軍の使者を装い、例の書状を送り届けたのは結局のところ何者で、どこの誰であったのであろうか?ここまでのことを仕組んだのは、ギべルネスでないことだけは確かである。
実はユベールとギべルネスに、このままハムレット軍を勝利へと導いて欲しいと頼んだ精霊型人類であったが、宇宙船カエサル側にいた精霊型人類アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロンらは、彼らふたりのやり方を見ていて(どうにも生ぬるい)ということで意見を一致させると、惑星シェイクスピア側の仲間たちにそのことを伝えたわけであった。彼らは一度行ったことのある場所でさえあれば一瞬にして移動が可能であったから、そんな形で何体もの精霊型人類が宇宙船カエサルへやって来たり、また外の宇宙を漂ってみたり、あるいは地上へ戻ったりということを遊び感覚で何度も繰り返していたわけである(ちなみにユベールがラップ音のように認識したものは、彼らという存在が移動する時に生じることのある音だったようだ)。
彼らはギべルネスがAIクレオパトラに、「気象コントール装置を使って、怪我をしない程度に雹を降らせることは可能ですか?」などというのを聞き、とうとう痺れを切らしていたわけである。その時の、ギべルネスとユベールの驚きようについては――どう表現したものかわからぬほどのものであったに違いない。
たとえて言うなら、アグラヴェイン公爵軍の前に姿を現したあの気味の悪い老婆や、モルドレッド公爵軍がラモン・ストラルド卿の城で経験したり見たりした幽霊現象もそうであろうが、精霊型人類というのは見る人間によっていかようにも姿を変えられるようである。
ゆえに彼らはこの時、少なくとも相手を驚かさぬよう配慮したつもりであったが、結局のところふたりは心底驚くということになった。というのも、精霊型人類アルファは、ユベールの目に身の丈三メートルほどの、足が十本もあるイカ人間に見えたのだし、精霊型人類オメガはギべルネスの前に、透明な虹色のクラゲ人間として姿を現していたからである。
「あ、あの……っ!!」
「なっ、ななな、ななっ……!!」
『はーっ、まったく想像力が貧困な奴らよの』と、精霊型人類アルファがボタンのような黒い目の下に、唇らしきものを表して笑った。『異星人と聞いて思い浮かべるのが、こんな程度のものとは……』
『そうじゃな』と、オメガも頷く。彼は頭の中が透けて見えており、頭に当たる部分の中では、いくつもの虹色の星がキラキラと明滅している。『どうせならわしも、もうちょっとはマシな姿のほうが良かったわい。が、まあ我々にはおまえらの視覚を通した姿がどのようなものであれ、ある意味どうでもいいのでな。それより、おまえらのプランはまったくなっとらん。あとは我々でうまくやってハムレット軍を勝利へ導くゆえ、黙ってそこらへんで見ておれ』
この時、ユベールはこっそりカメラを覗き見、ここメインブリッジの映像自体にはイカ星人の姿もクラゲ星人の姿も映っていないことを確認していた。また、同様に彼らの話した言葉をAIクレオパトラがスピーカーを通して聞き取っていないことも確かなことであった。ということは、一体どういうことになるだろうか?
『やれやれ。ニンゲンというやつはまったく不便なものよの』と、精霊型人類アルファ。『ほれ、わしらと言語を通して――つまりは口を動かしてしゃべったとすれば、このこんぴーたーとかいう奴が、「あなた方は一体誰と何をしゃべっているのです?」と、不審に思いだすのじゃろ?だったら、頭の中でしゃべることを覚えるんじゃな。それでわしらには十分通じる』
『左様、左様』と、虹色クラゲ星人。『どれ、ギべルネスよ。わしらの手並み、とくと見せてやるゆえ、おぬしは適当に仕事でもしとる振りでもしとるんじゃな』
とはいえ、ギべルネスにもユベールにも、何をどうして良いかわからなかった。何より、自分たちの心に思い浮かんだことはすべて、彼らに一秒とかからずして読み取られてしまうことから……ある種の念話というのか、心話をしようにも、慣れるまではなかなか難しいところがあったものである。また、そうしたある種の照れくささから、ユベールもギべルネスも相手に話しかける振りをしていながら、実は精霊型人類たちに言いたいことを語っているということが、実は一番多かったに違いない。
また、AIクレオパトラは、疑似人格プログラムによってではなく、単にこちらの命令のみを行使するヴァージョンもあるため、彼らはそちらを選択し、エジプトの女王を混乱させないようにすることを忘れなかったものである。
時系列的なことで言えば、アクロイド・アグラヴェイン公爵の死とラルドレッド・モルドレッド公爵軍の捕縛劇とは前後して起きたことであったが――衛星を通した映像によって、ユベールもギベルネスも彼らに何が起きたかを、まるで映画の一場面でも見るかのように交互に目撃していたわけである。
『さあてっと、あとは大体のとこ、ハムレット王子は王都テセウスへ向かえば良いといったところじゃろ』と、イカ星人はユベールとギべルネスがスクリーンを通し、王子軍が再び兵をまとめあげ、北上を開始するのを見守りつつ言った。
『わしらは一度姿を消すが、ぬしらはこのままスクリーンで見て、ハムレット王子軍が王都テセウスへ攻め上るさまを見ておれば良ろしかろう』
「あっ、待ってください」
ギべルネスがそう言うと、半ば姿を消しかけていた精霊型人類二体は、再びその部分の存在の色を濃くしていた。
「私たちはなんというか、ハムレット王子たちが、あなた方精霊型人類の御守りによって無事勝利を得、王冠を戴くことが出来るとわかっていればそれで十分なんです。ということは……」
「そうそう」と、頷いてユベール。「俺たちはこれから、はるばる旅して本星エフェメラのほうまで戻らなきゃなんない。もちろん、本部にはあんたらのことは必要最低限何も言わんよ。ほら、惑星シェイクスピアのほうで、ハムレット王子が王位に就くために色々協力したりしたなんてことがわかったら……俺もギべルネスも法律違反で訴えられるということになるもんでな。つまり、ここ惑星シェイクスピアに精霊型人類と呼ばれるあんたらがたくさんいるなんてことは、口が裂けても絶対言わない。これで取引成立ってことで、俺たちは本星へ帰るが、それでいいのか?」
こののち、八秒ほど間があった。惑星シェイクスピアにいる仲間たちとでさえも、一秒とかからずして連絡を取り合える彼らとしては長い時間である。
『よかろう』と、クラゲ星人が頭の中の金色の星を虹色の膜の中でキラキラ明滅させながら言う。『無論、ユベール・ランバート、おぬしがわしらのことを誰にも言わぬという保証はどこにもあるまい。が、貴様が本星エフェメラのほうへ戻り、もし仮にわしらのことをしゃべって気違いだと思われなかったとて、ここへおまえら地球発祥型人類がやって来る前にわしらはここを出発していなくなることも十分可能であるからの。それで十分じゃろ』
「その、ここまで色々と助けていただいて……」
ギべルネスは彼らという存在に対し、どう礼の言葉を言っていいかもわからなかった。ただ、『色々よくしていただいてありがとう』といったような、月並みな言葉しか頭には浮かんでこない。
イカ星人は、その吸盤もなければぬめりけもない、ぬいぐるみのような細い腕をギべルネスに差し伸ばすと、彼の頭をぽんぽん叩いていたものである。
『礼など良いのじゃ。いや、むしろおぬしに「ありがとう」と言わねばならんのはわしらのほうやも知れぬ。ニディア・フォルニカという我らの仲間が、色々と迷惑をかけたな……じゃが、地球発祥型人類におぬしのような人間がいるとわかっただけでも、わしらには新たな収穫であった。そう思うと、返すがえすも残念ぞ。ギべルネスよ、今からでも我らの仲間となって広い宇宙へ旅立つつもりはないのかえ?』
『まあ、そう言うな』ギべルネスの決心が固いのを見て、クラゲ星人がその虹色の触手で、イカ星人の肩をぽんぽん叩く。『彼がそのように決断するのではないかと想定し、わしらはプランBについても用意しておいたのじゃ。いや、もしかしたらそれはプランCやも知れぬが……』
『そうじゃな。わしらにはプランBがあったわいな』と、イカ星人は何かを納得すると、何故かにんまり笑って姿を消した。その後、クラゲ星人も姿が見えなくなり、あとには『プランBか。ウフフフ……』、『うんにゃ、プランCやも知れぬぞ。グフフフ……』、『クスクス。プランB……』、『ウフフ、アハハ、プランC……』といったような、ある意味愉快気でありつつ気味の悪い声だけが、最後まで木霊のように尾を引いて残っていたものである。
「そいじゃ、本星エフェメラの情報諜報庁へ連絡すっけども、ギべルネスどんはそいで良かったかいな?」
「ええ……」と、ギべルネスはまだ少し、ぼんやりして言った。「向こうからお迎えがやって来るまでの間に、おそらくハムレット王子は王都テセウスへ攻め上り、その頃には王冠を戴いて王になっているか、事態も落ち着いて戴冠式を待っているとか、そんなことになっているでしょうから、ユベール、あなたの準備さえ良かったらそれでお願いします」
結局、こんなにも長い間、非常緊急コードで連絡しなかったのは何故かといえば、ユベールが自分ひとりの証言だけでは殺人の疑いが自身にかかるのではないかと恐れ、やっきになって惑星学者であり医務官でもあったギべルネス・リジェッロを捜索していたから、という説明をすることで落ち着いていた。
『だって、本星情報庁のIDがなくなった途端、俺なんか生命再生権はあっても、次のボディのほうはオーダーメイドじゃなくて中古のポンコツで甦らにゃあならんところだかんな。その上、殺人の疑いをかけられただけでも、裁判が結審するまでには相当時間がかかる……そんなことがわかってりゃ、当然やっきになってあんたのことを捜すってことでさ』と、ユベールはそう言っていたものだ。
『でも、お給料のほうはいいでしょう。私だって、ここへ来て五十年の任期で戻れば、本星エフェメラの永住権その他、特典のほうはすこぶる良かったですからね。べつに貰える金額のほうは、同じように働いてもあなたのほうがいいんじゃないですか、なんて聞きたいわけじゃないんです。むしろそのくらいじゃないと、命の危険も顧みず、こんな辺境惑星へなんてやって来ようとも思わないというか……』
『んだんだ』と、何故か田舎者のようにユベールは頷いている。『実際のとこ、俺、貯金なんかほとんど全然ねえの。けど、本星のほうじゃそこらへん、実に寛容だかんな。ギべルネス、あんた電子サインした書類のほう、隅から隅までちゃんと読んだか?そこには何か緊急の事態が起きて任期未満で帰還することになっても、後金のほうはきっちり支払われるって記載されてんだ、これが』
『なるほど』
――というわけで、ユベールは非常緊急コードを使い、本星エフェメラの情報諜報庁・辺境惑星担当課の上司と連絡を取り合い、随分長くあれこれと話し込むことになったようである。さらには、提出しなければならない書類が山のようにあるということで、ギべルネスはそれらについては一部手伝った。というのも、聞き取り調査の証人として、証言を撮影したものを映像として添付したり、今後本星へ戻り次第、もう一度諜報庁本部へ呼ばれ、色々聞かれることになるだろう……とのことだったので、矛盾が生じぬよう、ユベールの作成した書類の文言については彼もしっかり頭に入れておく必要があったのである。
彼らはこうした作業中も、絶えずスクリーンのほうでハムレット軍の動向を気にしており、彼らが王州テセリオンへ足を踏み入れようかという場面においては――パソコンのデータに目を通す手が一度止まったほどであった。
「なんだ!?もしかして地震か?」
映像のほうに揺れやブレはない。だが王州へと続く、半ば天然の要害のようになっている、長さ約十八キロメートル、高さはもっとも高い場所で十五メートルもある、城塔を三十以上も戴いたテセリオン要塞の入口が、激しい衝撃を受けたように一瞬にして瓦礫と化していたのである。
「そうですね。ハムレット王子たちも、地面の揺れについては驚いたようですが、あまり大きな被害らしきものは……」
カドールやランスロット、ギネビアらが、ヒヒーンと嘶いて驚く馬たちの首筋や鬣を愛撫し、優しくなだめているのがわかる。他の兵士らの間でも、興奮した軍馬を落ち着かせようとする姿が見受けられたが、このせいで怪我をしたりした者は誰もいなかったようである。
(馬鹿な……あれほどの城塞の城門と城壁が一瞬にして崩れ去ったんだぞ。最低でも震度六~七クラスの大地震であったはずだ。それなのに、そこを望む場所に集結していたハムレット軍側に何も被害がないなどとは――)
科学的にありえない、とギべルネスがそう思い、ユベールのほうを振り返ると、彼は言った。
「クレオパトラ、今の地震の震源はどこだ?」
『震源はフォルトゥナ山です。震度七、マグニチュード7.3』
「被害状況は?」
『被害のほうは、王州テセリオンのすべての県に及んでいます。被害者数のほうは完全には把握できません。ですが、多くの町や村で建物が倒壊し、下敷きになった者も多数いる模様です』
「な、なんだって!?」
ギべルネスはそう叫んで立ち上がった。確かに精霊型人類たちは、自分たちのやり方を『手ぬるい』といったようには言っていた気がする。だが、まさかここまでのことが彼らに出来るとまでは、ギべルネスにしてもユベールにしても想定していなかったのである。
「だがよく考えてみりゃ、それもそっか……」
スクリーンに映し出された被害の大きさに茫然とするあまり、ユベールはぺたりと尻もちでもつくように、再び椅子に座り直していた。クレオパトラが見積もった建物の倒壊率は全体の53.7%だということであった。まるでその数字を裏書きするように、貴族たちの城館も邸宅も、また庶民が都市で住んでいる四階建てのアパートメントのような建物も、商家も何もかも――特に都市部はメルガレス城砦のように込み入っていたため、被害状況がもっとも深刻だった。
「あの精霊型人類さんたちってのは、ようするに自分の惑星であるマルジェラにおいては砂の一粒に至るまで、ある意味その全部を自分であるかのように認識するという生命体なわけだろ?となれば、どこの火山の活動を活発化させるかも、そのタイミングも何もかも、そうしたことは彼らの思いのままってことだ……なるほど。おそらくはそうしたことなんだろう……」
「ですが、こんなことを神の奇跡とかいうのは、絶対にどうかという話です……」
目を覆いたくなるような悲惨な状況に、ギべルネスは胸を痛めた。最初は口々に、「星神・星母にとわに栄光あれ!!」、「これぞ神の奇跡!!」、「ハムレット王万歳!!」などと叫びつつ、王州テセリオンに向け進軍していった彼らであったが、テセリオン要塞はじめ、向かう城砦都市、町々や村々において、あまりに被害状況が徹底して悲惨であったことから――ハムレット軍は突然にして、この自然災害に対する救援軍へ早変わりすることになっていたのである。
何分、それが敵兵かどうかということすら関係なく、すべての人に助けが必要であった。彼らは水や食料を与えられると、とにかく有難がってそれを食べ、家屋の中から引き出してもらうと、涙を流して怪我の手当てを受けていた。
「私がもう一度、こちらへ行くというのは……」
ギべルネスが茫然としつつそう呟くと、「だーめーだ!!」と、ユベールは断固たる強い口調で止めた。
「もちろん、あんたの気持ちはわかるよ。このことのうちにも自分に責任があんじゃねえかとか、どうせ思ってんだろ?けど、はっきり言ってそんなの関係ないぜ。それに話がややこしくなるし、俺も本星諜報庁と連絡をとっちまった以上、なんであんたにもう一度降下を許可したのかとか、詰問された場合、答えに窮するからな」
「確かに……そう、ですよね………」
果たして、精霊型人類は初めからこのつもりだったから姿を消し、惑星シェイクスピアへと戻ったのであろうか。(わからない)と、ギべルネスは思う。確かに王州テセリオンという場所は、他の内苑州や外苑州から重税を取り立てることで成り立っており、そこに住む者たちの多くが特権階級にあったと言ってよかったろう。特にテセリオン要害とそこに隣接する都市においては、そこを出入りする者たちから日々税を徴収できるため、賄賂のやりとりなどは当たり前のように行われており、こうした不正金によって人々の暮らしは潤っていたというのは事実である。
(だが、これを神の罰と呼ぶのはあまりにひどい………)
ギべルネスは建物の多くが倒壊し、下敷きになって死んだ母親の隣で泣き叫ぶ小さな子や、助け出されたものの、足が潰れて動かなくなった者や、孫を守って自分は背中に大怪我を負った瀕死の老人たちや……スクリーンに映し出された映像を五分見ただけですぐに目を覆いたくなった。火事場のなんとやらで、盗難やそれに付随した暴力も横行していた。盗まれた物を奪い返そうとしてレイプされた身なりのいい娘や、そうしたやくざ者から子供を守ろうとして、金貨を投げつけて追い払おうとする父親や……そんな映像を十分も見るうち、ギべルネスは(もうたくさんだ)という気持ちになっていたのである。
一方、ハムレット軍はこうしたならず者たちを蹴散らし、怪我をした女子供や老人たちを優先して助け、その手当てをしていった。突然のことであったにも関わらず、彼らの動きは実に迅速で統率が取れていたと言える。人々はみな、このことでハムレット軍や各騎士団の騎士たち、兵士らに感謝し、拒むことなくその助けの手を受け入れていった。
新しく天幕を立て、そこに怪我人を集め、食事や水を提供した。埋まった井戸の修復をし、人だけでなく、馬や牛や羊など、大切な財産であるものを集め、その世話もした。とにかく、手当たり次第に出来ることをし、進軍すると同時、その救援の輪を広げていったのである。
また、人々のほうでもハムレット王子軍のそうした噂を聞き、助かった人々は率先して集まってきた。貴族たちはこの時素早くクローディアス王からあっさり彼に鞍替えしていたのである。一応、ガートルード王妃が先王エリオディアス王との間に出来た子のハムレットは、赤ん坊の頃に死んだと言っているという話は誰もが知っていた。だが、今や王都テセウス自体が混乱の極みにあり崩壊状態にあるのである。そのような、今この瞬間なんの助けにもならぬ無政府状態にも等しい政権より、具体的に助けの手を差し伸べてくれるハムレット王子軍を誰もが支持したというのは、あまりに当然のことであったろう。
さて、こうしてハムレット王子は、十万の兵士を地震に対する救援軍に変え、四十日ののち、正式に王都テセウスにて、今後は彼がクローディアス政権を引き継ぎ、この国の王となることが宣言されることになるのであったが――そのような結果になる前まで時間を巻き戻し、王都テセウスにいるクローディアス・ペンドラゴン一族がどうなったのか、次の章では語ってみたい。
>>続く。

























