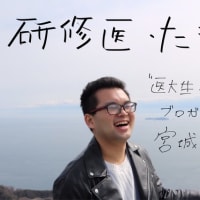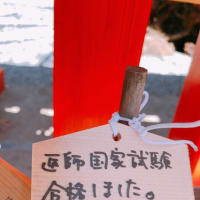秋の夜長には読書もいいものですね。医大生・たきいです。
本日ご紹介する1冊は、こちら。
 | こわいもの知らずの病理学講義 |
| 仲野徹 | |
| 晶文社 |
著者の阪大病理学の仲野徹先生はネット界でもご高名。最近ではこのツイートが印象深かったという方もおられるでしょう。
阪大医学部医学科3年生のよい子のみなさん、業務連絡です。病理学総論の試験、採点中ですが、失神しそうに成績が悪くてびっくりです。教科書持ち込みで、どうやったらこんな成績がとれるのか不思議でたまりません。
— なかのとおる (@handainakano) 2017年5月18日
いつも試験に怯えている一介の医学生としては、正直なところ、「なんてこわいセンセーなんだ……」というのがファーストインプレッションでした。
阪大の先生が言う「成績が悪い」と、ネットで揚げ足をとる批判ばかりしている人たちが言う「成績の悪い」とでは意味が違うと個人的には考えるので、可燃性が高い「医学生不勉強ネタ」をバズらせるのはちょっと……というのが正直な気持ちですが、一方で、「学生の『学ぶ』ということに対する姿勢」について言及されたエッセイを拝読すると、身の引き締まるような思いも感じさせられます。
なかのとおるのつぶやき
さておき。「ごく普通の人にも、ある程度は正しい病気の知識を身につけてほしいなぁ」という魂胆のもとご執筆されたのが本著のようです。仲野先生的には医学部6年生の私が読む本ではないのかもしれませんが、いまから『ロビンス』を紐解く余裕は国家試験を前にしたぼくにはありませんし、秋の夜のお供にさせていただくということで、そこはどうかご容赦いただきたいところです。笑
「身近に医学生がいたら、膨大な病名、それも脈絡なくつけられた名前も含めて、を覚えなければならないのですから、ぜひ、いたわってあげてください」という心温まるメッセージにまず、「鬼の先生」という誤解を氷解させながら、「私は毛髪が不自由です」というハゲネタに抱腹絶倒し、「知らないことを学ぶときに大事なこと」に深く傾聴し、分子標的薬の歴史の話の章は、知らなかったエピソードばかりで大変勉強にもなりました。
あとがき含めて373ページの本著ですが、一気に読み進められました。きっと講義も面白いんだろうなぁ。生で聴講してみたい。そして、真面目な内容をエッセイにしてしまうというのが感動で、さすがは阪大の病理の先生という印象が強かったです。
私が読む分には非常に面白い本でした。私も一応医学部6年生なので、本文中に出てくる疾患名に知らないものはありませんでしたし、そのおかげかスッと読めました。
しかし、壮大な構想である「ごく普通の人にも、ある程度は正しい病気の知識を身につけてほしいなぁ」を実現させるには、少々難易度が高い内容だった気も……?
あとがきに「わかりやすく説明するのは難しいと悩んだのも事実です」という先生の本音もポロリと出ておりましたが、知らないことを学ぶには努力が必要なのだという裏のメッセージが隠れているような気もします。本書は「がん」の話が最大の山場です。もし「ごく普通の人」が「がん」に悩んだとき、もっと知りたい、学びたいと思ったとき、「がん」についての正しい知識を自分の頭で考えるための取り掛かりとしては、これ以上いい本はないと思います。
さらには、「わかりやすく説明する」ためには人一倍の勉強が必要なのだという事実も改めて感じさせられました。私は、患者さんに「わかりやすく説明」できる医師になりたいです。仲野先生が求めるレベルに到達するためには相当な努力が必要だと思いますが、いつかは自分が「ごく普通の人」に向けた本を書けるくらいの人物になりたいと決心させられた本でした。精進します。
国試の点数に直結するとは思えないけど、小気味いい知的エンターテインメントのご紹介でした。
(ブログに書こうと思うと読むスピードがあがる気がする人(笑))