3月に予定している医大生ブロガーオフ会は過去最多の参加人数となりそうですが、会場どうしようかと候補をググりながら幹事は嬉しい悲鳴をあげております。引き続き、あなたの参加表明をお待ちしております。医大生・たきいです。
週に3回も先生方の外勤先に連れて行ってもらうという慌ただしい1週間でした。移動は先生の車に乗せていただくわけですが、道中病棟では聞けないような業界事情を聞かせていただいて本チャンの実習と同じくらい勉強になっています。
稼ぐのはあくまでもバイト先だという、大学病院の安月給話。現在の業界の仕組みは概ね理解したつもりですが、些か現状を疑問に思います。もちろん大学という場所は研究のための場所なのでしょう。ここから医学は発展していきます。それに次いで、大学は社会から、教育の役割も期待されているのではないでしょうか。
小学校にも中学校にも高校にも教えるプロの教員の先生がいるように、医学教育の現場にも教えるプロの先生がいてもいいのではないかと思います。国試の全ての問題が解けて全診療科の補講もできる神みたな先生もいらっしゃるのですが、それは稀有な例。医師のほとんどは「教える」ことは本職ではなく、そのためレジュメ棒読みという残念な講義もゼロではないのが医学教育の現状です。授業を受けるだけの下の学年のときは文句を言うか、お恥ずかしながら私はその時間意識が飛んでいるかしていましたが、先生方から直接、「病院に居場所はあっても家庭には居場所はない」なんて話を伺うと、あんな授業が存在したことも納得がいきます。もちろん、親身になって情熱的に教えてくださる先生には最大限の敬意を表しています。
「教える」ことが本職の医者がいたっていいじゃないか。仮に各診療科に教育専門のプロの医師が配置されれば、若い世代が情報が膨れ上がる現代医学を学ぶ上での羅針盤となって、面白いことが起こる予感がします。MTM先生もKSR先生もHZM先生もわれわれ医学生にとって偉大な存在ですが、医学生がそちらに傾倒しているうちは、教育という側面において大学は敗北しているような気がしてなりません。大学の欠点を補っているので、ビデオ講義の各種予備校がビジネスとして成り立っているのでしょうが。
「病棟実習で教えてもらうという姿勢がそもそも間違っている」というお叱りもしばしば受けるところで、これには私は反論できる立場にありません。教育の受け手側の態度も重要だということは仰る通りです。ただ、お忙しいところ身を粉にして学生教育に力を注いでくださる先生方には頭が上がらないのです。大学病院の先生方がバイトに出ないと困る病院がたくさんあるという事情も重々承知しております。それでも、せめてバイトにでることなしに、トータルで現在と同じだけの待遇を大学病院が用意できるような制度がつくられたならば。バイトに行かずにその時間を教育のために充てられる先生を雇って、教育と研究とで役割分担をするという考え方もあるかもしれません。
私自身は大学病院で将来働くことは今のところはあまり考えていません。それでも、大学病院の医師の待遇改善が、ひいては日本の医療を守っていくことに繋がる可能性を私は考えます。
(この週末が待ち遠しかった人(笑))











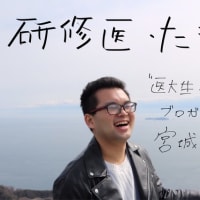

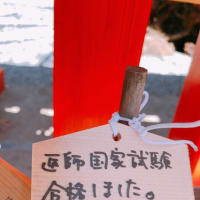







私は近親者に大学病院で働いている医師がいるのですが、
平日は病院での仕事に加え、教壇に立って教え、
休日はバイト。
家族と過ごす時間の少なさに嘆いています。
うちの大学では近年新たに医学教育という研究室を設け、「医学教育のプロ」を大学内に置いたことで、
ずいぶん教育プログラムの組み方などは改善されたようですが、
講師の先生方一人一人にかかる負担と、それに対するお給料の少なさは変わらず、(むしろ近年さらに減ってるとか)
医学教育って、次世代を育てるためにも本当に大事だと思うので、今後改善されることをお祈りしています。
教育機関として、研究機関としての役目の上に「病院」として役目を担った大学医学部が働く場としてもよい環境になるといいですよね。
他の業界ならば、社会的責任も重く、勤務時間が長い職務に対して正当な報酬が支払われないことはほぼありえないといっていいでしょう。バイト先の方が給料が高いという「ねじれの関係」はあまり健全だとは思えません。
報酬とは仕事への評価です。医者業界はこれまで医師の崇高すぎる倫理観と精神力だけが美化されてきたように思いますが、拍手で讃えるべきところには正当な評価を与えるという、他の業界では当たり前のことをそろそろ考え始めてもいいのではないかと思います。