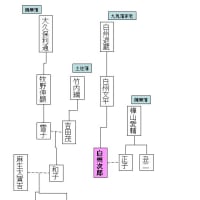薬剤耐性菌が1970年以降増加傾向にあり、抗生物質の多用が原因ですが、今回のニュースの不気味さは、今までは健常者なら感染しない、もしくは感染しても注射や薬を飲めば簡単に治ると考えられていた感染症でも、重篤化して死に至る可能性が身近な例として出てきたことです。帝京大学病院で院内感染が判明した多剤耐性アシネトバクターは、土の中などに生息する細菌が多くの抗生物質が効かない性質を獲得したもので、従来日本では海外からの転入患者などで見つかるだけでした。しかし、報道によれば今回の感染経路はわかっておらず、長期間にわたって多くの感染者が出ていることから、多剤耐性アシネトバクターの感染が日本国内にも定着し拡がっている可能性があります。さらに、独協医科大学病院で確認された新型の多剤耐性大腸菌は、NDM1という抗生物質分解酵素を持っています。昨年5月にインドから帰国して同病院に入院した患者が約38度の発熱をし、その菌を病院で保存していたところ、今年8月に英国でNDM1遺伝子を持つ大腸菌の感染拡大が指摘され遺伝子検査によりこの大腸菌であることが判明した、という報道でした。大腸菌はアシネトバクターとは違い、健康な人にも感染してぼうこう炎などを起こすため、抗生物質が効かないとなれば治療が困難になります。
明治から太平洋戦直後の小説を読むと、赤痢、疫痢、腸チフス、結核、インフルエンザからの肺炎などで子供を初めとして多くの人が亡くなっていたことが分かります。衛生状態が良くなり、医学の進歩で今ではそういうことはなくなった、と多くの方が考えていると思いますが、耐性菌の出現、特にNDM1のような遺伝子を持つ大腸菌の感染拡大というのは、健康な人の体内にもある赤痢菌や大腸菌、サルモネラ菌などのありふれた菌にNDM1遺伝子が入り込み、既存の薬剤への耐性を持って広がる危険性があるということなのです。
薬剤耐性菌については、近年医療施設でメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)やバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)、多剤耐性結核菌などが検出され、院内感染で死者も出ています。インフルエンザウイルスに関してもタミフル耐性を持ったウイルスも国内外で検出されており、薬剤耐性化したウイルスが拡大するおそれも出ています。また、薬剤耐性を持った細菌やウイルスが河川や池などに拡がってしまっているのではないかという懸念もあります。強毒性といわれるA/H5N1が人から人へ感染するようになって薬剤耐性を持ったらそれこそ大変なことになります。
私たちの振る舞いによってこうした薬剤耐性菌が拡がっている可能性も指摘されています。医師によって正しい服用や消毒の方法が指導されているにもかかわらず、抗生物質などの服用法を間違えたり、途中で服用を止めてしまうために、菌が生き残り耐性を獲得する、ということが起きる可能性があります。昨年の新型インフルエンザ流行時にタミフルを処方された方、医師の指示通り最後まで飲みきったでしょうか。また、病院内での消毒剤の選択ミスや不適正な消毒により、医療機器や用具、衛生材料、院内などの消毒が正しく行われず、生き残った菌の一部が薬剤耐性化する、という可能性もあります。使用済消毒剤などや抗菌薬、抗菌薬が含まれた患者の排泄物が、下水と一緒に河川に排出され、河川に生息する菌が薬剤耐性化する可能性が指摘されているのです。
公園にある湖や池、自然環境に生息するアヒルや白鳥などに近づいて、餌を与えている方がいます。また、飼い犬や猫でも与えられた餌以外の食べ物を獲っている場合には、薬剤耐性を持った感染症起因菌や食中毒菌などを保菌しているおそれがあり、感染予防の面から考えると危険性が気になります。昨年A/H5N1の鳥インフルエンザに感染した渡り鳥が大量に死んでいたという報道がありましたが、鳥、犬、猫などの野生動物や、動物の排泄物や体毛、羽毛などには、不用意に接触しないほうが安全です。また、抗菌薬を服用する場合には、医師の指示通りに服用することが重要です。
アメリカのメリーランド大学のチームは、ワシントン州内各地のスーパーで買った 200 検体の食肉を調べた結果、鶏の 35 %、七面鳥 24 %、豚 16 %、牛 6 %が抗生物質耐性のサルモネラ菌で汚染されていた、と報告しています。見つかったサルモネラ菌の 53 %は3 種類以上の抗生物質に耐性をもつ多剤耐性菌で、中には 12 種類の抗生物質に耐性をもつ菌もあって人への感染が危惧されています。アメリカの疾病予防センターとオレゴン、ジョージア、ミネソタなどの各州保健局とメリーランド大学の研究者の協同調査では、病院の外来患者の便 334 検体を調べた結果、 76 検体( 23 %)の患者に抗生物質耐性菌が見つかったのです。この結果は、保菌者が院内感染ではなく、通常の家庭生活の中で耐性菌に感染したことを示唆しています。アメリカでも抗生物質耐性菌は家庭にまで拡がっていると考える必要があります。EU では 1998 年に家畜飼料への抗生物質添加が禁止されましたが、日本やアメリカでは畜産・養殖業の競争力維持、経済効率などからEUほどの厳しい規制はないのが現状のようです。薬剤耐性菌問題だけではなくて、BSE(牛海綿状脳症)事件でも問題になった配合飼料や、成長ホルモンなどによる行きすぎた発育促進にも問題があると感じます。BSE問題以降飼料への添加物規制についてずいぶん検討が進んできたとの報道もあります。今後家畜への飼料原料等を通した抗生物質投与などにはさらなる規制が必要なのではないでしょうか。
(参考 http://www.alive-net.net/world-news/wn-farm/43.html http://www2.odn.ne.jp/~cdu37690/yunyuunikunokikensei.htm )
どの程度の抗生物質耐性菌が含まれているかは調査をしてみないと分かりませんので、海外からの輸入食肉だけでなく国産肉も今回の耐性菌報道を受けた厚生労働省による調査の対象として選定されることを期待します。実際、栽培されている穀物や果実は成長段階で大量の農薬を撒布され、収穫後には、防腐剤、防カビ剤が使われ、果実は綺麗に見せるためにワックスで磨かれて光っています。穀物や果物は人が食べるだけではなく、家畜にも与えられています。
対策をまとめると次のようなことが考えられます。
1. ウイルスの世代交代は人間のスピードとは比べものにならない速度で行われますので、抗生物質の投与はできるだけ控える必要があります。一方で、現存する抗生物質には次世代抗生物質が登場するまでなんとか持ちこたえてもらわなければなりません。製薬会社は薬の研究開発に多額の投資をしていますので、投資回収が必要です。医師は目の前の患者から「なかなか治らない」と苦情を言われたくないので抗生物質を投与しがちです。患者の中には病気の症状がなくなれば「なるべく薬など飲みたくない」と完治する前に治療をやめてしまう方がいます。本来、抗生物資は本当に必要な人だけに投与すべきで、これを制御するのは医師や患者のモラル、製薬会社の社会的責任だと考えます。法的強制力ある薬剤使用のガイドラインが必要なのかもしれません。
2. 数種類の抗生物質を交互に服用することにより、同じ薬剤を連続服用するよりも耐性菌の発生する確率が低くなります。医師からの服用指示を守り、症状が治まったからといって服用を止めずに指示された分はきちんと服用することにより耐性化する前に菌を死滅させることが重要です。
3. 最近では非常に多くの抗菌グッズが出回っており、手に触れるすべての商品に抗菌処理が施されている気がします。日本人がアジア諸国を旅するとお腹を壊す人が大勢でますが、もとより人体は細菌に触れることで免疫力を獲得し、自然に治癒する力を高めることができます。過剰な抗菌グッズ使用は考え物ではないでしょうか。子供の頃は菌に慣らすことも重要、親が気にしすぎて子供を清潔にしすぎることは子供が免疫力を高めるのを阻害していると考える必要があります。また、様々な抗菌剤の使用は菌に薬剤耐性を獲得させることにもつながります。
4. 野生動物には不用意に接触しない、飼い犬や猫でも飼い主以外が与える餌を食べている場合には感染症の心配があります、注意が必要です。
5. 畜産・養殖農家での抗生物質使用規制が甘い国、例えばアメリカや日本、中国では今でも抗生物質を病気の予防、ホルモン物質を成長促進のために畜産飼料に添加し、家畜に与えられている可能性があります。多くの感染症が豚などの家畜を媒介として人への感染力を獲得することを考えると、薬剤耐性菌の多くが家畜への抗生物質投与から生じている可能性もあるといわれています。国としての規制に加えて、畜産業者の社会的責任の問題意識に問いかける必要もあるでしょう。
食品表示や添加物問題、遺伝子組み換え野菜や養殖魚への抗生物質投与などは人類がとる食物として直接被害を与える可能性があるということ、加えて、前記のような薬剤耐性菌拡大という問題も出てきました。畜産業や養殖業は国際競争に晒され、経済効率が重視される傾向にあり問題は単純ではありませんが、BSE問題でクローズアップされたように、食の安全問題は経済効率に優先されることは明らかです。これは畜産や養殖を事業としている企業、製薬会社、病院などの社会的責任であり、さらに患者や消費者の一人としてもできることがありそうです。科学技術が日常生活に入り込む時代、一般人にも科学リテラシーが求められる時代になったのだと思います。こうした問題に関し、私たちは企業の社会的責任と消費者責任の両面から認識する必要があると考えます。
参考文献
科学は誰のものか―社会の側から問い直す (生活人新書 328)
疫病と世界史 上 (中公文庫 マ 10-1)
疫病と世界史 下 (中公文庫 マ 10-2)
銃・病原菌・鉄〈上巻〉―1万3000年にわたる人類史の謎
銃・病原菌・鉄〈下巻〉―1万3000年にわたる人類史の謎