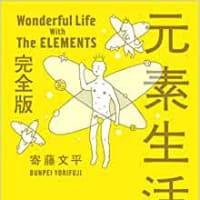若い市会議員であるが、現場主義を貫き、現地に赴き現場で人の話を聞いているので、ひとりよがりがない。昔からの根深い同和問題にも理解を示す。京都や大阪、関西地方にはまだまだ差別をベースとした同和問題があるが、ここ20年ほどでずいぶんその様相は変わってきたはずだ。経済発展が差別の原因の大きな要因であった貧困問題を底上げしたのである。今残っているのは差別の逆、逆差別。なぜ同和問題にだけは手厚い予算がついて、そして文句をいう人間は「差別者だ」というレッテルを貼られるのか、という状態になっているのだ。
筆者が市会議員になって取り組んだことの一つにごみ処理問題があった。京都市のごみ処理には三種類の契約形態があった。直営、民間委託、そして傭車制度である。問題はそのコスト、直営は収集単価が1トンあたり2万円で全国平均より2000円ほど高い。民間委託はそれ以上で22000円で直営より高いのだ。さらに傭車制度では26000円となっている。原因は一部の業者への委託の集中であり、以前のし尿処理が下水の普及に伴い仕事がなくなった代わりにごみ処理が特定業者に委託されるようになった。
そしてその直営でも問題はあった。筆者は直営のごみ処理の勤務実態を張り込みで観察、実働は一日4時間程度で無駄で過剰な人員が高コスト構造の原因であった。さらにこうした市職員の業務実態を調べていくと、暴力行為、覚せい剤、人身事故のもみ消しなどが出てきたのだ。これらの背景には旧地区からの優先雇用という採用形態があったこと、採用後の指導研修の不徹底、懲戒処分にの勢力への遠慮があり、腰が引けたままそれが慣習化してきたことを突き止めた。職場には影のボスが居て、そのボスには逆らえない、という不文律がまかり通っていたというのである。そのボスは地区の代表であったり、活動家であったりしたという。
筆者は同和行政の問題に切り込んだ。京都市では同和行政はすでにその役割を終えたとして平成14年度にピリオドが打たれたとされていた。調べてみると、表面上は予算は計上されず終わったことになっている事業がほとんどであり、継続しているものも一般事業への移行をしたとされていた。そこで実際の現場に足を運んだ。
代表的な同和行政の施策に隣保館(現在のコミュニティセンター:コミセン)があった。形態としては公民館に近いが、その利用対象が地区に集中していて格安、もしくは無償の利用料金で使われていた。現在のコミセンは全市民に解放されているはずだったが、現場を見るとそうではない実例がうようよと出てきたのだ。利用者はそれは権利と考え、一般市民は存在を知らない、「怖いものには近づきたくない」という気持ちから問題視されていなかったという。福祉センター、学習センター、市立浴場、診療所、保健所分室、保育所などの施設が地区には特別な対応予算を付けられ運営されていた。それが現在でも形を変えて残っているというのである。
市会議員の調査権を使って全ての施設を視察して回った筆者は、それらの施設のほとんどは予算を使って維持する意義はなく、多くの施設は無用の長物であると結論づけている。問題は多くの市民や市会議員が同和問題を避けていること、触りたがらない問題だと思い込んでいることだと指摘している。筆者の政治家としての信条は次の通り。
・自己保身に陥らず、正しいと思うことを貫ける政治。
・なにものもおそれず、利益誘導にとらわれない政治。
・いまだけでなく、次の世代を見据えた政治。
・当たり前のことを当たり前に実行できる政治。
中央政権でもこうした政治家が長生きできるように応援したいものである。