【各話末エッセイ③−2】
カナダの歴史学者・中国学者
ティモシー・ブルック氏の著作
「セルデンの中国地図」という本によると、
ジョン・セルデンは英国サセックス州出身。
法律学者として頭角を現し、
かのグロティウスとは良きライバル同士だったようです。
著書に「十分の一税の歴史」「閉鎖海論」があり、
「十分の一税の歴史」では、
国王ジェイムズ1世から尋問され、軽い罰を受けます。
そしてこの書物は禁書となってしまうのでした。
法律畑での活躍の他にも下院議員の経験があり、
投獄もされ、東洋研究もしていたそうです。
そんな彼がある時、現在でも謎の多い中国地図をどこからか手に入れ、後に「ハリポタ」で有名になるボドリアン図書館へと死後寄贈しました。
その地図の謎を解き明かすというのが
「セルデンの中国地図」の主旨です。
ジョン・セルデン氏の肖像画2枚が、
冒頭カラー資料ページにありました。
「日本人でもこういう顔の人いるよな」という顔立ちで、
▶ 若い頃は 痩せてる(霜降り明星のせいや+濱田岳)÷2
▶ 晩年は役所広司似
そういう人物が栗色のゆるふわ・前髪ぱっつんのセミロングの髪型してるといった所でしょうか?
それでも、真面目そうな雰囲気は相当漂わせていました。
なので、私の
「不真面目な人だったのでは?」という印象は
大外れだったのです。
「セルデンの中国地図」にも冷静沈着な人だったと書かれていました。
きっと「卓上談」も報復の原則を説明するための硬めの文章だったんでしょう。
セルデン氏の持っていた中国地図は、
日本史とも無関係ではないようです。
「セルデンの中国地図」には
戦国末期〜江戸幕府が鎖国を始めた頃の日本が
海外とどのような関係を結んでいたのかも書かれています。
あの三浦按針も登場しています。
驚くのは、日本の地名が当時の外国からは
何て呼ばれていたかが分かる所です。
この本を読むと、ジョン・セルデンはローレンス・スターンの「トリストラム・シャンディ」よりも
ジョナサン・スウィフトの「ガリバー旅行記」や、
ダニエル・デフォーの「ロビンソン・クルーソー」の方に縁がありそうです。
「ガリバーが日本に上陸したのが、本当に神奈川県三浦半島の観音崎からだったのか?お隣の静岡県伊豆半島下田の爪木崎なんじゃないの?」という疑問すら湧いて来るのでした。(観音崎の「ガリバー祭り」には行ってみたいんですが…)
あとこの本には、ヨーロッパにおける中国の孔子受容の歴史も書かれています。
「トリストラム・シャンディ」の中で〈孔子〉は
「話を難しくして訳を分から無くする人」という意味で使われているのですが、
「何でこの人が孔子を知ってんの?」
と思うほどの異様さです。
中国布教に向かい、孔子の教えと出会ったイエズス会宣教師達が、17世紀に儒教経典を翻訳・出版していて、
ヨーロッパ諸国の貿易での東洋進出と相まって、
人々の東洋への関心を掻き立てたという歴史があったからのようです。
それにしても、鹿児島県の古名「薩摩」は、
セルデン地図では
「殺身」なんて書かれてあるのでした。
著者は〈ノストラダムス超絶解釈第一人者と称えられる川尻徹博士ばりの〉暗号解読みたいな事をしていましたが、
日本人からすると
「そのままでも、ただの訛なんだって事でOK」なんじゃないかと思えちゃいます。
「幕末〜明治初期に20世紀末の暴走族のセンスを持つ事ができた反薩摩派の人」が使いそうな漢字だけど。
平戸を意味する「魚鱗島」も
著者は色々考察していますが、
やはり日本人からすると、オランダかホランドが
地図製作者でニホン語少シワカルアルヨな中国人には「ウォリンド」か「ウォリン」と聞こえ、
『「うおりん 🐟(何かカワイイぞ!) 」(の人達)が住んでいる島』→オランダ島
」(の人達)が住んでいる島』→オランダ島(勝手に別名付けられてた?!)って意味に、
テケトーに漢字当てはめて
平戸島って事にしてたんじゃないの?って思えてしまいます。
「十分の一税の歴史」
日本でもこのタイトルで本書いてくれる人いないかな〜?
日本の場合では現在の
消費税の事なんだよね?
そもそも消費税の始まりから書き起こしてほしい!

 この続きは明日(12月13日/月曜日)
この続きは明日(12月13日/月曜日)










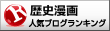


 」(の人達)が住んでいる島』→オランダ島(勝手に別名付けられてた?!)って意味に、テケトーに漢字当てはめて
」(の人達)が住んでいる島』→オランダ島(勝手に別名付けられてた?!)って意味に、テケトーに漢字当てはめて





