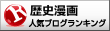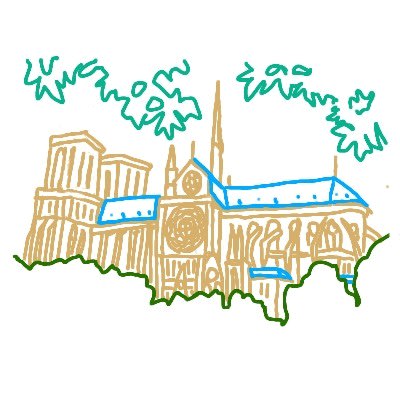昨日の続きでもう1曲、
ペロティヌス原曲の
「支配者らは集まりて」
Sederunt principes
の編曲。
日本だと12月25日には
クリスマス終わり〜で
もうベートーベンの「第九」
や童謡「お正月」の
編曲がスーパーとかの
有線でかかってるけど、
12月26日は聖ステファノの日
で欧米はまだクリスマス期間。
「支配者らは集まりて」は
聖ステファノの日のために
作られた曲なのだけど、
この人が敵方に
捕らえられて
石打ち刑で死ぬ時の
歌なので、
後半から光が
差すようなマイルドな
明るさに曲調が変わっても
「地上のすべての国々は」
とは違う雰囲気。
が、
ペロティヌス独特の
リズム感覚が
この曲にも色濃〜く
あるのです。
調べてみると
「地上のすべての国々は」
で衝撃を受けた後に
ペロティヌスに
ハマったというのを
本やネットに書いている
人が思った以上にいるの
でした。
しかも、
絶賛してる人ばかりで
貶している人が
今の所見当たら無いのは
何故なのか?
曲全体から漂う
チャンカチャンカ感と
出だしのロングトーンが
「水戸黄門」風で、
海外人が作曲してるのに
日本人の心の
掴み所をちゃんと
押さえてるってのが
「鎌倉殿の13人」的
だからかっ?!
ともかくも、
ペロティヌスによって
合唱曲に華やかさや
迫力が加わり、
18世紀にはオーケストラ
伴奏が付いてるのが
普通になって、
バッハやヘンデル、
→モーツァルトやハイドン、
→ベートーベン年末第九の
てっぺんに繋がってく
って訳さね。