「まったくコロのやつ・・・」
長男が何やらぶつくさ言いながら私の前を通り過ぎた。
「何だ、なにかやったのか?あいつ」
私が呼び止めると、長男はこちらをくるりと振り返り、私に右の手を差し出した。
「ほら、ここみてよ、・・・ここ。あいつおれの右手にかみつきやがんの。寸でのところでかわしたつもりだったけど、遅かったみたい」
みると長男の手の甲が微かに血で滲んでいる。それほど深くかみつかれたのではないようなので私はほっとした。
「なにか、コロを興奮させるようなことをしたのか?」
「別に・・・。ただ、俺を見てあんまり吠えるもんだからさ、ケージを開けていいこいいこしてやろうとしたらこのざま・・」
「あいかわらずあいつはお前にはきびしいんだな」
「うん、仙台行ってからあいつとは顔を合わせていなかったから、忘れてると思ったんだけどなあ。やっぱダメだわ」
「小さいころ、さんざんお前、コロを追いかけまわしたからなあ、その記憶が今でも忘れないって訳か・・・」
私が長男の顔を見ると、彼は鴨居の上に飾ってある私の父、つまり彼の祖父の写真を見上げていた。
「・・・俺もよく祖父ちゃんにかみついたっけ・・・・」
彼は何かを思い出したように感慨深げにそう言い、どこか遠くを見る目をしていた。
私は彼のそんな姿を見、そういえばと過去の父と長男のことを思った。
そういえば私の長男と私の父は仲が悪かった。
普通は祖父さんは孫を可愛い可愛いで済ませるものであるが、わが父は違った。
長男が小さいころから、父は彼の素行に目を配り、ことあるごとに雷を落としたのだ。
幼い長男は、そのたびに泣き叫び、父に向かっていった。
普通なら父が軽くいなしてお終いとなるところだが、長男は違った。
なんと父に怒られるたび、父の腕にかみついたのだった。
いてて、長男を引きはがしながら怒るのをやめ、その後、父はよく私に言ったものだった。
「この子は素直じゃない。将来どんなもんになるか分からん。今のうちに矯正せんとな」
父は何度も長男にかみつかれながらも、その後も決して雷を落とすことをやめなかった。
ある日、そう、もう長男が中学3年になった年の12月、夕飯後に父と長男は例によって大喧嘩を繰り広げていた。
さすがに、長男はもうかみつくことはなくなったが、その代わり言葉でかみつくことを覚えた。
「だから、じじいはだめなんだ」
「じじいだと!じじいとはなんだ、じじいとは!!」
「古いんだよな、考え方が・・・」
「古いだと?古いも新しいもないわい、見苦しいのは一緒だ」
「このセンスが分からないなんて世も末だな」
喧嘩の原因は長男の髪型について父が注意したのが発端だった。
見ると長男の頭は両脇を軽く刈り上げ、頭の中心をちょんと軽く立てている流行の髪型だった。
私は子供には自分で考え、自分で行うことを推奨していたので、彼のすることによっぽどでない限りは文句をつけない主義だった。だから、父が「なんでお前が注意しないんだ」といってきたとき、「学校では校則違反にならないんだろ?ならいいんじゃない?」と呑気に返事をかえした。
「まったく!子が子なら親も親だ」
父は憤慨やるかたないといった様相でまた長男に向き直り、「俺は許さんぞ!」と吠えた。
すると長男は飽きれた顔をしてもう議論の余地がないと思ったのか、部屋を出て行こうとした。
「何処へ行く?」
私が声をかけると彼はうんざりとした顔で「明日は土曜日だし今夜は友達のところに泊まってくる。こんなもうろくじじいといるとろくなことねえし」と言ってでていってしまった。
父は喧嘩相手がいなくなるととたんに静かになり、「俺は飲みにいってくる」と言い残して出かけて行った。
私はこうなるとどうしょうもないなと思い、ごろりと横になってテレビを観ながら父の帰りを待つことにした。
それから何時間か父の帰りを待っていたが、父は一向に帰ってこなかった。
いくら酒が強いとは言っても、80過ぎの老人だ。心配になり、父の馴染の飲み屋に迎えに行こうと玄関を出ると”ワン”とコロの鳴き声がした。
もしやと思い、庭に回ると果たしてコロのケージの前に父は胡坐をかいて座り込んでいた。
親父、なにやってんだ。
そう声をかけようとしたが、やめた。
酔った勢いで父がコロに必死に語りかけている様子が見て取れたからだ。
恐らく父は愚痴を聞いてもらいたかったのだろう。コロの困ったような表情が窺えた。
ごめん、コロ。しばらく親父の話を聞いてやってくれ。
私は静かにゆっくりと父に気付かれぬようその場を立ち去った。
父に異変が起きたのはその次の日だった。
私は二階に居て、父は庭で盆栽の剪定をしているはずだった。
妻はコロを連れて散歩に出ていた。
親父ー。階下から長男の声がした。
私は長男は友人のところへ行ったままだと思っていたので、気のせいかと思ってそのままにしていた。
すると、親父ー。大変だ、となにやら差し迫った長男の声が今度は確かに聞こえ、私は急いで階下に下りた。
親父、じいちゃんが、・・・じいちゃんが・・・。
長男の声がする方に向かうと、父が縁側に横たわり、長男が傍に寄り添っていた。
「どうしたんだ」
私が声をかけても、彼は取り乱し、じいさん、じいさんと必死になって祖父に呼びかけるばかりだった。
私は諦めて、父の様子を冷静に見ることにした。
「どこか悪いのか?」父を抱き起し、問うと、彼はたどたどしい言葉で「た・た・いし・たこと・ない」と答えた。
言葉がはっきり出てこない。右手もうまく動かせないようだ。私は即座にこれは・・・、と思った。
もしかして、血管やったのか?
取り乱す長男を落ち着かせ、ともかく119番するように言った。
長男はおろおろしながらも居間にある電話を取って何とか救急車を呼んだ。
それから私たちは待った。待っている間とてつもない時間が経っているように感じた。
しばらくして、救急車のサイレンの音が近づいてきたのだが、その音さえもなんだかスローモーションの世界で聴いているようなそんなもどかしさがあった。
救急車が到着したのは長男が連絡してから僅か15分のことだった。
救急隊員たちは、まず父の容態を確かめ、担架を運び込むと手際よく父を乗せ、救急車の後部に運び込んだ。
どなたか一緒に来てくださいという言葉に誘われて、私が救急車に乗り込んだ。
何事かとコロとの散歩から帰ってきた妻が近づいて来たので、私は妻に「後で電話するから。詳しいことはあいつに聞いてくれ」と家の前でおろおろしている長男を指さした。
そうして私と父を乗せた救急車は動き出した。途中でどこか希望の病院はありますかと聞かれたので迷わず私は答えた。
〇〇脳外科病院へやってください。
〇〇脳外科病院に運ばれたあと、父は脳梗塞と診断され、一か月ほど入院したのち、今度はリハビリ病院に転院した。
そこで三か月ほどリハビリを行い、その次は長期療養専用の病院に移った。そのころには父の右手、左足は完全に動かなくなっていた。
二年、三年と経つうちに筋力も弱まり、もう立ち上がるのも困難になるようになっていた。父は寝たきりになった。
悪くなることはあっても、決してよくなることはなかった。父は次第に衰弱していった。
そんな父の病状に比例するように、長男は大人になっていった。大人になって私と妻が病院に行くと言うと必ずついて行き、父の話し相手になった。
かつての父に歯向かう長男の姿はすっかり身をひそめてしまった。
そして父が入院して四年目のことだっただろうか、長男が私に密かに打ち明けてくれた。
「俺、旧帝大へ行くよ」
長男はその年大学受験に失敗していた。いや、受かった大学はあったのだが行かなかった。
「俺は今まで大学なんてどこ行っても同じと考えていたけどやっぱ行くからには上を目指すわ。・・・・じいちゃんも俺にちっちゃいころから”旧帝大、旧帝大”って言っていたもんな。よっぽど自分が行きたかったんだろうな。俺がリベンジしてやるよ」
父は高卒だった。父の年なら高卒でも大したものだが、よっぽどその上に行きたかったのだろう、父は旧帝大を目指し見事に散った口だった。
「リベンジかあ・・・、まあそれもありだろう」
それから彼の猛勉強は始まった。それは彼の決意の確かさをあらわしていた。
二か月、三か月と続け、センター試験を一か月後に控えたころには、旧帝大のそれも上位校を受けられるだけの成績を上げるに至った。
長男が父の入院している病院に行き、それを報告すると父は微かに笑い、「よかったなあ」とかすかすの声で答えた。
そのころの父はほとんど食べ物を受け付けられない状況で、医者にはもういつ容態が急変してもおかしくないと告げられていた。
内臓もかなり弱っており、いつ機能停止してもおかしくない状況だ。
あと三か月もってほしい、それは長男のみならず家族全員の望みになっていた。せめて長男が合格の吉報をもってくるまでは・・・。
その望みがあっけなく散ったのは、年が明け、長男のセンター試験も無事終わり、ほっと一息ついたころだった。
私と妻と長男がとりあえず住むところを押さえておこうと全国規模の不動産屋を回っていたときだ。不動産屋の説明を聞いている最中に携帯が鳴った。
病院からだ。私はすぐに電話に出た。
「・・・〇〇さんの携帯ですか?」
「はい」
「いま、うちの看護師が見回ったところ、お父さまが息をしていないとの報告を受け、私が診ました」
「・・・それで」
「・・・残念なことですが、お父さまはお亡くなりになりました」
「そうですか」
「それで、いつこられます?」
「多分、一時間後に」
「分かりました。お待ちしております」
私は医師の事務的な口調に合わせていたって冷静に受け答えをした。
そして電話を切るとその口調のまま妻と長男に告げた。
お祖父ちゃんが亡くなったそうだ。
長男の悔しそうに唇を噛む姿が一瞬目に映った。
それからの三日間はせわしく忙しい毎日だった。
葬儀屋さんと打ち合わせをし、それから親戚に連絡。
家は神道なので、神主さんに来てもらいまた打ち合わせ。近所の人にも来てもらい、葬儀の手伝いを頼む。
それからいよいよ通夜と告別式。
全ての行事を終えて家に帰ったころには私たちはほとほと疲れ果てていた。
「あれ?〇〇は?」
私が長男の姿が見えないことに気が付き、妻に問うと、
「トイレに行ったわよ」
と何か含みのある言い方をした。
そういえば、彼は葬儀のあいだ抜け殻のような顔をしていた。
自分の祖父ちゃんが亡くなったことが相当ショックだったのだろう。
でも受験は一か月後にせまっている。
そう思うと私はいてもたってもいられなくなり、長男に声をかけるべく立ちあがりトイレに向かおうとした。
するとそれを見ていた妻が「どこいくの?」と私を呼び止めた。
「どこって、トイレに行くんだよ。あいつがいつまでたっても戻ってこないから」
「よしたほうがいいわよ」
「えっ?なぜ?」
「まったく、気の利かないひとねえ。あのこは葬儀の間ずっと我慢してたのよ」
「我慢?」
「そう、我慢」
妻にそう言われて私も気が付いた。そう、彼はずっと我慢をしていたのだ。
父が亡くなった日も、葬儀の間中もずっと・・・。
私は長男のもとに行くのをやめ、その場に座り込んだ。
「なあ、なにぼーっとしているの?」
長男に言われて私ははっとした。
「ああ、ちょっと昔のことをな、思い出していた」
「昔のこと?いやだなあ、そんなこと思い出す暇があったら息子の身体の心配してよ。・・・かまれたんだぜ、大事な息子の手をさあ」
彼はよく見てよとばかりに手の甲を私の前でひらひらさせた。
「ああ、こりゃ大変だ。コロが食あたり起こさないか、心配だな」
私がそう茶化すと長男は「こりゃあかんわ」という顔をして手を引っ込めた。
そして、オロナイン、オロナインといって部屋を出て行った。
・・・あのあと長男は見事に立ち直った。
最終試験も終わり、合格発表の日、この部屋で彼はインターネットの画面を見つめていた。
41256、41256、彼は大学の合格発表のサイトで必死に自分の受験番号を探していた。
そして自分の番号を発見すると大の字に寝ころび、鴨居の写真に目をやった。
彼は満面の笑顔を浮かべ、そして静かに呟いた。
やったぜ、じいちゃん。
小谷美紗子 - 自分

















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


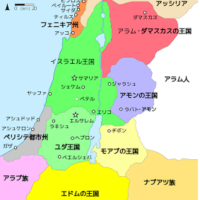






しんみり胸を打たれました。
すばらしい出来です。感心しました。
ヒゲジイさま、コメントありがとうございます。
今回は少し長くなってしまいました。
そのため少し冗長的になってしまったように思ったのですが・・・。
満足していただいて光栄です。これからもよろしくお願いいたします。