Joni Mitchell - Both Sides Now (The Johnny Cash Show)
日食なつこ - '√-1' Live Video / ピアノ弾き語りver.(2022.03.30)
嘘(Live) | grapevine in a lifetime presents another sky(official teaser)
First Aid Kit - The Lion's Roar (Official Music Video)
The Beatles - Eight Days A Week
(ちんちくりんNo,88)
「……書こうか」
「え、何を」
「いや違った。俺に書かせてもらえないだろうか」
「書く?あなたが?この仕事を、新聞小説を代りに書こうって言っているの」
僕の突然の申し出に裕子は、テーブルの上に両手を突き、身を乗り出すようにして僕の顔を見た。
「できるの?あなたはもう二十年近くも小説を書く生活から離れている」
「また始めている」
「え」
「きっかけがあってね。昔のことを思い出した。思い出したら無性に書きたくなったから、パソコンを開いてともかく思い浮かぶままに文字を打ち込んでいった。」
「震えは…」
「それが、まったく。不思議なくらい気にならなかった」
そこまで訊くと、裕子は暫く何か考えている風に目を瞑り、右のこめかみに人差し指を当て沈黙した。その間、僕は目の前に置かれていたビール缶を手に取り、プルトップに指をかけて開けると、中の黄金色の液体を口から喉を鳴らしながら流し込んだ。僕自身も久しぶりのアルコールだった。何だか胃の底が熱くなるような気がした。裕子を見た。別に「思惑」があって僕に話しかけてきたわけではないのか。僕は少し残念に思った。沈黙は長く感じたが、実際は五分程度だったと思う。ゆっくりと瞼を上げた裕子が口を開いた。「……で、何か出来上がったものでもあるの?あるのならその原稿を見せて。良さそうだったら明日編集長にかけあってみるわ」
結果からいうと、甲斐日日新聞の朝刊に僕の小説が載ることとなった。パソコンに保存してあった二百枚程の原稿をUSBメモリに落とし、裕子に渡すと、彼女はそれを持って二階の寝室へと向かった。翌朝キッチンで目を合わせたら、白目が赤く血管が浮いているように感じられたので、「無理はしないでいい」というと、裕子は上下の瞼がくっつきそうになりながらも優しく笑った。「これいいよ。いい、とても」
驚いたのはその夜にもう結果を知らされたことだった。裕子が帰ってくるなり「この原稿をもとに、月曜日から金曜日、一回分が千文字、半年間の連載よ。いい」といきなり早口で言ってきたので「何それ」と返すと「何それって、新聞の小説。決まったんだからぐずぐずしないで」と激せられた。実は僕自身「書く」と言ったはいいが、それが認められるとは思っていなかった。昔は「売れた」とはいえ、その時出した殆どの書籍が絶版になっているし、やはりよく考えてみれば二十年もブランクのある作家の小説など誰も見向きもしないだろうと思っていたのだ。あとでそれとなく裕子に訊いてみたら、以前から、編集長に何とか書いてもらえないだろうかと言われていたのだそうだ。僕はずっと引退したような状況だったし、また書き始めたことも裕子に話していなかったので、彼女は編集長に言われるたびに「もう、書いていないので」と断っていた。因みに編集長は僕の小説の古くからの熱心な読者だった。もうとっくに忘れ去られたと思っていたのに、僕は一人でもそんなに熱心な読者がいたことにいたく感激したのだった。
日食なつこ - '√-1' Live Video / ピアノ弾き語りver.(2022.03.30)
嘘(Live) | grapevine in a lifetime presents another sky(official teaser)
First Aid Kit - The Lion's Roar (Official Music Video)
The Beatles - Eight Days A Week
(ちんちくりんNo,88)
「……書こうか」
「え、何を」
「いや違った。俺に書かせてもらえないだろうか」
「書く?あなたが?この仕事を、新聞小説を代りに書こうって言っているの」
僕の突然の申し出に裕子は、テーブルの上に両手を突き、身を乗り出すようにして僕の顔を見た。
「できるの?あなたはもう二十年近くも小説を書く生活から離れている」
「また始めている」
「え」
「きっかけがあってね。昔のことを思い出した。思い出したら無性に書きたくなったから、パソコンを開いてともかく思い浮かぶままに文字を打ち込んでいった。」
「震えは…」
「それが、まったく。不思議なくらい気にならなかった」
そこまで訊くと、裕子は暫く何か考えている風に目を瞑り、右のこめかみに人差し指を当て沈黙した。その間、僕は目の前に置かれていたビール缶を手に取り、プルトップに指をかけて開けると、中の黄金色の液体を口から喉を鳴らしながら流し込んだ。僕自身も久しぶりのアルコールだった。何だか胃の底が熱くなるような気がした。裕子を見た。別に「思惑」があって僕に話しかけてきたわけではないのか。僕は少し残念に思った。沈黙は長く感じたが、実際は五分程度だったと思う。ゆっくりと瞼を上げた裕子が口を開いた。「……で、何か出来上がったものでもあるの?あるのならその原稿を見せて。良さそうだったら明日編集長にかけあってみるわ」
結果からいうと、甲斐日日新聞の朝刊に僕の小説が載ることとなった。パソコンに保存してあった二百枚程の原稿をUSBメモリに落とし、裕子に渡すと、彼女はそれを持って二階の寝室へと向かった。翌朝キッチンで目を合わせたら、白目が赤く血管が浮いているように感じられたので、「無理はしないでいい」というと、裕子は上下の瞼がくっつきそうになりながらも優しく笑った。「これいいよ。いい、とても」
驚いたのはその夜にもう結果を知らされたことだった。裕子が帰ってくるなり「この原稿をもとに、月曜日から金曜日、一回分が千文字、半年間の連載よ。いい」といきなり早口で言ってきたので「何それ」と返すと「何それって、新聞の小説。決まったんだからぐずぐずしないで」と激せられた。実は僕自身「書く」と言ったはいいが、それが認められるとは思っていなかった。昔は「売れた」とはいえ、その時出した殆どの書籍が絶版になっているし、やはりよく考えてみれば二十年もブランクのある作家の小説など誰も見向きもしないだろうと思っていたのだ。あとでそれとなく裕子に訊いてみたら、以前から、編集長に何とか書いてもらえないだろうかと言われていたのだそうだ。僕はずっと引退したような状況だったし、また書き始めたことも裕子に話していなかったので、彼女は編集長に言われるたびに「もう、書いていないので」と断っていた。因みに編集長は僕の小説の古くからの熱心な読者だった。もうとっくに忘れ去られたと思っていたのに、僕は一人でもそんなに熱心な読者がいたことにいたく感激したのだった。

















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


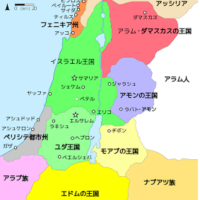






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます