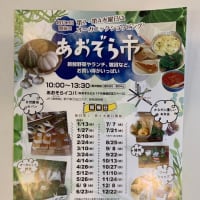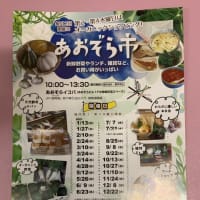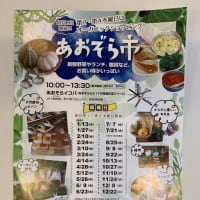『粥有十利』 道元禅師著
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月11日 - 09:53
1.肌の色艶をよくする
2.気力が増す
3.寿命が延びる
4.食べ過ぎることがなく、体が楽になる
5.血流がよくなり頭が冴え、言葉もなめらかに出る
6.胸やけをしない
7.風邪を引かない
8.飢えを満たす… twitter.com/i/web/status/9…
*睡眠と風邪*
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月11日 - 09:55
アメリカの研究では睡眠時間が6時間未満の人は7時間以上の人に比べて約4倍風邪をひく”と分かっており、さらに5時間未満になると、約4.5倍になるそうです。
ただし、寝れば寝るほど免疫力が上がるわけでなく7~8時間が1… twitter.com/i/web/status/9…
50年前と比べると体温が1℃近く下がっていると言われます。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月11日 - 09:58
体温が1℃下がると代謝が約10〜20%、免疫力が約30%も低下します。
冷たい飲食物を摂りすぎも低体温に繋がります。
常温以下の飲食物を摂る時は、まず口の中で少し温めてか… twitter.com/i/web/status/9…
夜は「陰陽」の力が1番弱まる時。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月11日 - 13:57
亡くなる人も夜中が多いのはそのため。
生命力も1番弱くなるから、休むべき。
なるほど。 pic.twitter.com/9Eayxhbs7Y
女性の体質の8割は
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月11日 - 14:19
「血液、元気不足、気が余る」
体質の人が多い。
やっぱり補気、補血、理気は大切ですよね。
そう思うと
睡眠をしっかりとる。
体を動かす。
はすごく大切ですよね✳︎
今日朝から「甘いものが止められないんです」という人が多いというか、全員そうか。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月11日 - 14:17
なんだ?寒くてエネルギー消耗してるのか?
なんだろ、なんか理由がありそうだな。
まあそれでも「やめなさい」としかいえないんだけどね。特にジュース類や甘い飲み物とチョコ。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月11日 - 14:27
買うな、家に置くな。
甘いもの食べたくなったら、まず果物食べてください。
甘いもの止まらない人は、熱がこもってるかもしれないので、苦いもの食べてみてください。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月11日 - 15:01
きゅうり、苦うり、緑茶、レバー、セロリ、ごぼう、パセリ、ピーマン、ふき、ふきのとう、みょうが、タラの芽、くわい、米糠、紅茶、プーアル茶などが有ります。
薬膳で苦味には、利尿・消炎・解毒・解熱の他、鎮静という力があります。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月11日 - 15:03
高ぶった精神を鎮めてくれるので、甘味を欲しすぎるのにも良いかも。
不養生は自害と同じ。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月11日 - 14:58
遅いか早いかの違いはあれ、自らを傷つけていることには変わりない。
(養生訓より)
養生訓では、飲食の欲、好色の欲、眠りの欲、好きなことをしゃべりたい欲を「内欲」として慎むべきものとされています。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月11日 - 14:59
内欲を慎むことで、乾燥や冷え、熱、湿気などの外敵から身を守ることが出来、病から身を遠ざける事ができると書かれています。
「慎む」が養生の真髄ですね。
中医学では、肝は筋肉と関係していると考えます💡
— 歳森和明@漢方の福神トシモリ薬局 (@kampo_toshimori) 2018年2月9日 - 16:30
筋肉運動(ストレッチも含めて)をすることで、肝にこもったエネルギーが消費されて、心も身体もほぐれます☺️
春も近づいてきたので、肝の不調の人は身体をゆったりと動かしてみるのが良いです… twitter.com/i/web/status/9…
【泣くこととストレス解消】
— 歳森和明@漢方の福神トシモリ薬局 (@kampo_toshimori) 2018年2月9日 - 16:44
・ストレス
・負担
・無理
これらのことが重なると「肝」に負担がかかり、肝の気の巡りが悪くなります。
肝は目と繋がり、さらに泪と繋がっています。
泪を流すことで、たまった肝のエネルギーが消費されるので、… twitter.com/i/web/status/9…
【ストレスでカチコチになる理由】
— 歳森和明@漢方の福神トシモリ薬局 (@kampo_toshimori) 2018年2月9日 - 19:03
ストレスを受けると肝に負担がかかる場合が多く、肝は筋と関係しているのでストレスを受けると筋肉が収縮したり、硬直したりします。
例えば、
・頭痛
・肩こり
・排尿困難
・性交痛など
どこに出るか(ど… twitter.com/i/web/status/9…
睡眠不足によるホルモンの乱れも肥満の原因と言われています。
— 歳森和明@漢方の福神トシモリ薬局 (@kampo_toshimori) 2018年2月10日 - 16:28
睡眠の質はダイエットにも関係しているんですよ💡
22時から2時の間に深い眠りに入っていると、脂肪を燃焼させる働きがある成長ホルモンが最も分泌されます。
早寝は美容にも健康… twitter.com/i/web/status/9…
【春は睡眠をしっかりとって、早起きを】
— 歳森和明@漢方の福神トシモリ薬局 (@kampo_toshimori) 2018年2月10日 - 16:55
太陽の光を浴びると、体内時計が正常に動くようになります。
特に朝の太陽の光を浴びると、体内で「セロトニン」が出来て、
日が暮れると、このセロトニンはメラトニンに変化します。
春は冬の寒さで弱… twitter.com/i/web/status/9…
【腸内細菌を喜ばせる食べ物】
— 歳森和明@漢方の福神トシモリ薬局 (@kampo_toshimori) 2018年2月10日 - 17:29
お:オリゴ糖 玉ねぎ、ごぼう、長ねぎ
な:納豆などの大豆製品 納豆、豆乳、おから
か:海草類 わかめ、ひじき、めかぶ
は:発酵食品 味噌汁、納豆、ぬか漬け
す:酢 酢玉ねぎ、黒酢
き:きのこ しいたけ… twitter.com/i/web/status/9…
腸内細菌、腸内環境は自分でデザインする事ができます!
— 古武孝仁@ふたば漢方薬局 (@tako_kotake) 2018年2月11日 - 16:28
善玉菌が喜ぶ食べ物を食べれば、善玉菌がたっぷりの素敵な腸内環境に!
腸内環境はがん、免疫、自己免疫疾患、肥満、糖尿病、最近では脳との関連も報告されています。
1〜3ヶ月間、… twitter.com/i/web/status/9…
【喜べばすなわち気緩む(喜則気緩)】
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月10日 - 16:27
適度な喜びは、気を巡らせストレスを解消します✳︎
しかし、度を越した喜びは心気を弛緩させ、動悸、息切れ、不眠などの症状を出し、さらに過ぎると精神に異常をきたします。
古典には難しい試験にやっと… twitter.com/i/web/status/9…
悲則気消「悲しめばすなわち気消す」と言われ、悲しみは気を消耗します。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月6日 - 11:29
この時期に悲しみ過ぎて肺の気を消耗すると花粉症や、鼻炎はより悪化します。
肺を潤して強化する山芋、はちみつ、卵、大豆、くるみ、たまねぎ、りんご 、みかんなどに辛… twitter.com/i/web/status/9…
「憂い、悲しみ」には気を消す働きがあります。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2018年2月6日 - 11:30
「肺」は呼吸や免疫、汗、水分代謝などを調節する働きがあります。
憂いたり、悲しみ過ぎると咳や息切れ、声が小さい、異常な汗、風邪をひきやすくなるなど見られます。
肺が病むと気が塞いだり、訳もなく涙が流れたり、悲しくなりやすくなります。