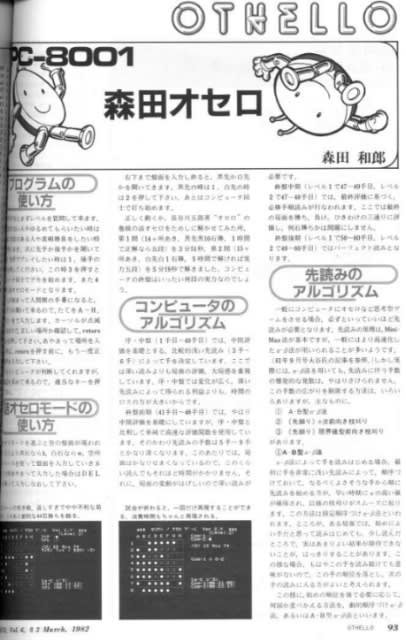さらに森田オセロのマニュアルより。
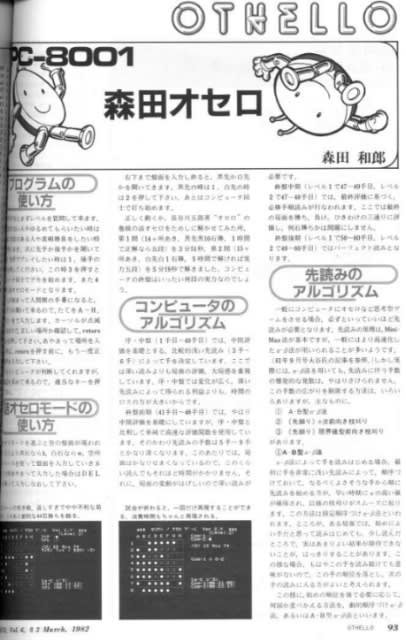
コンピュータの アルゴリズム
序・中盤 (1手目~40手目)では、中間評価を基礎とする、比較的浅い先読み (3手~ 6手) によって手を決定しています。ここでは深い読みよりも局面の評価、大局感を重視しています。序中盤では変化が広く、深い先読みによって得られる利益よりも、時間のロスの方が大きいからです。
終盤前期 (41手目~46手目) では、やはり中間評価を基礎にしていますが、序・中盤と 比較して単純で高速な評価関数を使用しています。そのかわり先読みの手数は5手~9手とかなり深くなります。このあたりでは局面はかなりせまくなっているので、このくらい読んでもそれほど時間がかかりません。それに、局面の変動がはげしいので深い読みが必要です。
終盤中期 (レベル1で47-49手目、レベル2で247-48手目) では、最終評価に基づく必勝手順読みが行なわれます。ここでは最終の局面を勝ち負け、ひきわけの三通りに評価し、何石勝ちかは問題にしません。終盤後期 (レベル1で50~60手目、レベル2で49~60手目) ではパーフェクト読みとなります。
先読みのアルゴリズム
一般にコンピュータにオセロなど思考型ゲームをさせる場合、必ずといっていいほど先読みが必要となります。先読みの原理は、 Mini Max法が基本ですが、一般にはより高速化しα-β法が用いられることが多いようです。 (81年9月号大谷氏の記事を参照。)
しかし実際にはα-β法を用いても、先読みに伴う手数の爆発的な発散は、やはりさけられません。この手数の広がりを制限する方法はいろいろありますが、 主なものに、
① A-B型α-β法
② (先細り) n次前向き枝刈り
③ (先細り) 限界値型前向き枝刈り
があります。
① A-B型α-β法。
α-β法によって手を読みはじめる場合、最初に手を非常に浅い先読みによって、順序づけておいて、なるべくよさそうな手から順に先読みを始める方が、早い時期にの高い値が確保され、以後の枝刈りがスムーズに起ります。この方法は固定順序づけ法といわれます。ところが、ある局面では、始めによ い手だと思って読みはじめても、 少し読んだところで、実はあまりよい結果が期待できないことが、はっきりすることがあります。この様な場合もはやこの手を読み続けても意味がないので、この手の順位を落とし、 次の手の読みに入る方がよいと考えられます。
この様に、始めの順位を後で必要に応じて、何回か並べかえる方法を、動的順序づけ α-β 法, あるいはA-B型α-β法といいます。