
このブログを読んでくれている複数の人から、「グレーバーは難しすぎる」「ちょっと着いて行けない」という意見を聞いた。確かにそういうイメージがあるかもしれない。たとえば、この章のはじめにつぎのような一節がある。
「市場の言語におもてむき対抗してあげられたモラル上、宗教上の声に語彙を与えることでもある」
「モラル上、宗教上の声に語彙を与える」とはどういう意味なのだろうか。正直に言って、私にはよくわからない。「語彙」とは「ある一つの言語、あるいはその中の特定の範囲における単語の総体、総数」という意味である。一方、「市場の言語におもてむき対抗してあげられたモラル上、宗教上の声」は「声」というからには、ことばで発せられていると思うのであり、したがって、「その範囲における単語の総体、総数」すなわち「語彙」を持っているわけである。そうなると、「語彙」に「語彙」を与えるとはどういう意味なのかよくわからなくなる。「従来の声は、市場の言語に対抗することばではあるが、それはおもてむきであり、実際にはそうでない。だから、その実質を表すことばに置き換える必要がある」ということなのだろうか。
しかし、なぜこのような言い回しをする必要があるのだろう。他の日本語では表現できないということなのだろうか。原書を持っていないので、どういう原文をこのような日本語に訳したのかはわからないが、少なくとも、訳者は理解したわけで、そうであれば、普通の日本人がわかるような日本語にしてもらいたいものだと思う。
別の例をあげると、上記の一節のすぐ後につぎのような一節がある。
「ヴェーダもキリスト教の教義も……まず、すべてのモラルを負債として語り、ついでその身ぶりそのものによって、モラルは実際には負債に還元できないこと、なにかべつのものに基盤をおく必要があることを提示する」
「身ぶりそのものによって……提示する」ということは、「ことばによって」提示したのではないということなのだろうか。ヴェーダもキリスト教の教義も文書だと思うが、その身ぶり=「文書の身ぶり」とは一体何だろう?「その身ぶりそのものによって」を削除し、「ヴェーダもキリスト教の教義も……まず、すべてのモラルを負債として語り、ついで、モラルは実際には負債に還元できないこと、なにかべつのものに基盤をおく必要があることを提示する」としてはダメなのだろうか。もし、提示の仕方が「身ぶりそのものによって」であることが重要なのだと言われると、詳しく説明してもらわないと私のような凡人には理解できない。
この本の、このような細部にとらわれると、読み進むことが困難になる。大変難しい本であるかのように感じてしまう。しかし、一方で、肝心なところは大変わかりやすく、すっと頭に入ってきて、いままで何の疑いもなく抱いていた常識や思い込みを取り払ってくれる。だから、細部の表現にこだわらず、読めばそれほど難しくはないと思う。ただし、個別のお話は難しくはないとしても、つぎつぎに語られるそれぞれのお話の関係を理解することが少し難しいようには思われる。
これまでのブログでは、できるだけ私の勝手な解釈を排除するため、『負債論』本体からの引用が中心になってしまい、読みづらく、わかりにくいものになってしまっていたようだ。それが、冒頭の意見として現れたものと思われる。そこで、この章からは、私の理解したことを、私のレベルに合わせて書いてみることにする。当然、誤解も多くなるとは思う。「おかしいな?」と感じたら、ぜひ『負債論』を買って、あるいは図書館などで借りて読んでいただきたい。
このブログは、『負債論』の要点を備忘録的にまとめ、それによって、内容の再確認をし、私自身の理解を深める目的で始めた。しかし、再読してみると、どこの部分も重要に見え、それを書きながら、しかも、それだけを読んで理解できるようにしようと思ったところ、引用だらけの長文になってしまった。今回もそうだ。もっと短くしたいとは思っているが、なかなかそれができない。どうしてだろう。
その主な理由は、デービッド・グレーバーが文化人類学者であり、この本はその研究成果を示したものであるという点にあるように思われる。「文化人類学」とは、「人間について、[文化]という概念を中心に、経験的な調査法(=おもにインタビューと参与観察)を動員して、〈他者〉と〈他者がおりなす社会〉を観察し、そのことを 具体的に考察する学問分野(文化人類学者 池田光穂 大阪大学教授の定義)」であり、したがって、この本も、その主張を裏付ける調査、観察結果などが膨大に記述されている。その主張は従来の常識を覆すものが大半である。だからこそ、その結論部分だけを紹介しても、「どうして?」という疑問だけが生まれてくるだけである。そこで、その主張の根拠となる個別の調査、観察結果を紹介してゆくと、その結果としていつも長文になってしまう。
今回は第五章であり、全十二章とすれば、まだまだ先は長い。何とかしたいとは思っている。また、全部終わったところで、さらなるまとめが必要な気もしている。
*******
第五章 経済的諸関係のモラル的基盤についての小論
「負債の歴史」を語ること、それは、「いったいどうして[市場の言語]がこれほどまでに人間の生活のあらゆる側面に浸透するようになったか」ということについての従来の考え方を見直すことであるとして、この章は始まる。
モラル上、宗教上の声は、表向きは市場の言語に対抗している。しかし、その語り口は、まず、すべてのモラルを「負債」という、やはり[市場の言語]で語り、ついで、モラルは実際には負債に還元できないこと、なにかべつのものに基盤をおく必要があると語る。そして、その「べつのものとは何か?」という問いに対しては「壮大な宇宙論的答え」を提示する。宇宙との連続性の認識/切迫する宇宙の崩壊の予感期待のなかでの生のいとなみ/神性への絶対的服従/別の世界への撤退など。
グレーバー自身は、「目標はより控えめなものなので、正反対の手法を採用したい。もしわたしたちが、経済生活のモラル上の基盤、より拡げていえば、人間の生活を本当に理解したいなら、とても小さなことがらからはじめなくてはならない」と言う。
「とても小さなことがら」とは、「友人や敵、子どもたちに対するわたしたちのふるまい、それらのふるまいにともなうのは多くの場合(塩をとってあげたりタバコを一本ねだったりといった)あまりに小さな身ぶりだから、通常それについて考えることはほとんどない」といったものである。
人類学は、人間が自分たちを組織化する方法がいかに多様で、いかに膨大であるかということを提示してきた。同時に、人びとが物品のやりとりをおこなうとき、あるいは他者が自分たちになにを負っているか議論するとき、どこにでも出現し、常に呼びだされる、根本的なモラルの原理を、注目すべき共通点として明らかにした。
しかし、それらの原理の多くは互いに矛盾しており、完全に異なる原理が共存する傾向にあり、それらが共に影響力を及ぼすこともある。ある意味で、モラルの思考は、この緊張の上に築かれている。
*******
したがって、負債とは何かを本当に理解するためには、負債以外の義務(人のこころに対し、それに従うよう迫って圧力をかけてくる何ものか、すなわちモラルを指しているのだと思う)について、それが何であるのかを明確する必要がある。しかし、現代の社会理論は――経済人類学をふくめ――この点についておどろくほど参考にならない。
たとえば、フランスの文化人類学者マルセル・モースは『贈与論』という論考を発表した。それ以降、贈与についての文化人類学的文献は膨大な数にのぼる。しかし結局、こういった文献のほとんどすべてが、ひたすら「贈与交換」に焦点を絞っている。人が贈与をするときにはかならずや負債が発生し、受けとる側はのちに同種の返礼をせねばなないという想定がある。つまり、ここでも、偉大な宗教の場合とおなじように、市場経済の論理が浸食してきている。
問題の一端は、現在の社会科学において経済学の占める並外れた地位にある。経済学はいろいろな意味で主導的な学問分野とみなされている。その基本的な教義を知らないものは馬鹿にされる。それらの教義はあまりにも自明な真実とみなされ、反対することなどありえないと考えられている。
「人間とは、あらゆる状況下で可能なかぎり最良の条件を、すなわち、最小の犠牲ないし投資で最大の利益と快楽と幸福を手に入れることをひたすら計算する利己的な行為者である」という「合理的選択理論」など、われこそ「科学的」なりと大声で唱えている社会理論の諸分野も、人間の心理について、経済学者とおなじ仮定から出発している。しかし、実験心理学者たちは、そのような仮定は端的に誤りであるといくどもくり返し表明してきている。
社会的相互作用の理論を、もっと幅広い人間本性観のうちに根拠づけながら構想したいと考える人々がいて、モラルの生活とは、相互利益以上のなにか、なによりも正義の感覚に動機づけられていると考えた。ここで鍵となる言葉は「互酬性(reciprocity)」である。つまり、公平、均衡、公正、対称性といった感覚である。すべての人間関係は互酬性の特定の変異体上に基礎を置いており、経済取引もまた、均衡のとれた交換原理の変種にすぎないということになる。
1950年代から70年代にかけてこのような思潮の大流行があった。それは、合衆国におけるジョージ・ホーマンズの「社会交換理論」からフランスにおけるクロード・レヴィ=ストロースの構造主義にいたるまで、当時「交換理論」と呼ばれた装いのもとに無限の変奏へと発展していった。
レヴィ=ストロースは、人間生活は、(言葉の交換からなる)言語、(女性の交換からなる)親族、(物の交換からなる)経済の三つの領域からなるという議論を提起した。彼によれば、この三つの領域はすべて、おなじ互酬性の基本法則によって支配されているという。いまやこれらの仮定は背景に引っ込んだが、その後も、ほとんどだれもが、社会生活は、その根本的性質から互酬性の原理にもとづいており、そのため人間のすべての交わりは、ある種の交換として理解するのが妥当であると想定しつづけている。だとするなら、負債こそが実にすべてのモラリティの根底にあることになる。負債とは、いまだ均衡が回復されないときに発生するものだからだ。
しかし本当にすべての正義は、互酬性に還元可能なのだろうか?「目には目を」「魚心あれば水心」はそれぞれ互酬性を表しているが、正義とは言えまい。また、親子の関係をとくに互酬的「相互関係的」であるとみなすのは、きわめて困難であるが、それがモラルや正義と関係がないとは言えない。両親に負うものを一種の負債として想像できるとしても、それが実際に返済可能である、とか、それが返済されるべきものだとすら考える者はほとんどいない。
『動物記』の著者として有名なシートンは、21歳の誕生日に父親から、出産時の費用を含む、シートンに対するあらゆる支出の明細を示され、支払いを要求されたという。シートンは支払いに応じ、その後、二度と父親と話すことはなかったとのこと。返済をするということは、双方が決別できる関係になったということである。
*******
19世紀の旅行記には、互酬性とは無縁の社会の事例を山のように見ることができる。だれかの命を救ったりすると、まもなくその人物が決まって訪れ、彼に贈り物をしないかぎり追い払うことはできないというような事例が各地にある。だれかの命を救うと永久にその人物の面倒をみる責任があるとみなされるという話である。これは、わたしたちの互酬性についての感覚に逆らっている。
だがどういうわけか、それはまた妙に理にかなってもいる。命を救ってくれた人にお返し「お礼」することは、父親に対するシートンの身ぶりとおなじく侮辱であることになる。つまり、じぶんの命を救ってくれたにもかかわらず、これっきり宣教師とはなんの関わりももちたくないということなのだ。ただし、これは一つの推論であり、実際に上記の命を救われた人たちが何を考えていたかはわからない。
しかし、このような社会がこの世界には存在していること、それぞれが固有のモラリティ、つまり任意の状況下で正しいこととまちがったことについての固有の思考と論拠を有していること、そして、これらのモラリティは報復的応酬とはまったく異なったものであるということは事実である。
「以下、本章の残りでは、経済的関係が基盤をおくことのできる三つの主要なモラルの原理の存在を提示することで、主だった可能性をおおざっぱに図示しておこう。その三つはあらゆる人間社会にみいだされるものであるが、わたしはそれらを、それぞれ、コミュニズム、ヒエラルキー、交換と呼びたい」ということで、その話に移る。
【コミュニズム】
ここでは、コミュニズムを、「各人はその能力に応じて[貢献し]、各人にはその必要に応じて[与えられる]」という原理にもとづいて機能する、あらゆる人間関係と規定される。
「コミュニズム」ということばは、「共産主義」体制と同一視されてしまう傾向にあって、強力な感情的反応を呼び起こしうることばである。しかし、ここで定義される「コミュニズム」は、魔術的ユートピアのようなものではないし、生産手段の所有ともなんの関係もない。それは、いま現在のうちに存在しているなにかであり、程度の差こそあれあらゆる人間社会に存在するものである。わたしたちは皆、かなり多くの時間をコミュニストのようにふるまって過ごしている。あらゆる社会システムは、資本主義のような経済システムさえ、現に存在するコミュニズムの基盤のうえに築かれている。
以下、大変面白い部分であり、また、よくわかる文章なので、少し長くなるが、そのまま引用する。
「各人はその能力に応じて、各人にはその必要に応じて」という原理から出発すると、(しばしば形式的な合法性の問題にすぎない)個人的所有権または私的所有権の問題、そしてより直接的かつ実践的である、だれがどのような条件でなにを入手しうるのかという問題を無視することが可能になる。その原理が行為を統御する原理(operative principle)である場合には常に、たった二人の人間の交流であってさえも、わたしたちはある種のコミュニズムの現前に立ち会っているといえるのだ。
なんらかの共通のプロジェクトのもとに協働しているとき、ほとんどだれもがこの原理にしたがっている。水道を修理しているだれかが「スパナを取ってくれないか」と依頼するとき、その同僚が「そのかわりなにをくれる?」などと応答することはない。たとえその職場がエクソン・モービルやバーガー・キング、ゴールドマン・サックスであったとしても、である。その理由はたんに効率にある(これを「コミュニズムは端的にうまくいかない」という旧来の思考に照らして考えると実に皮肉である)。真剣になにごとかを達成することを考えているなら、最も効率的な方法はあきらかに、能力にしたがって任務を分配し、それを遂行するため必要なものを与え合うことである。ほとんどの資本主義企業がその内側ではコミュニズム的に操業していることこそ、資本主義のスキャンダルのひとつである、ということさえできる。なるほど、たしかに資本主義には民主主義的に運営されるという傾向はみられない。それどころか、多くの場合、軍隊式トップダウンの指揮系統によって組織されている。だがここには、しばしば興味をひく緊張がある。トップダウンの指揮系統は、とくに効率的とはいえないからだ。それは、上にいる者の愚かさと、下にいる者の怒りに充ちた不活性を促進する傾向にあるのだから。即興の必要性が高まれば高まるほど、協働はより民主主義的になっていく傾向がある。発明家たちは常にこのことをよく理解してきたし、起業する資本家もしばしばそのことに気づいている。さらに近年ではコンピューターエンジニアたちがその原理を再発見した。だれもが話題にするフリーウェアのようなものの原理のみならず、企業組織の原理としてさえである。
このことがまた、洪水や停電、経済恐慌といった大災害の直後に人びとが同様にふるまい、まにあわせのコミュニズムに立ち返る傾向があることの理由であろう。たとえ短期間であっても、ヒエラルキーや市場などは、だれにも手の届かないぜいたく品になる。このような時間を生きた者はだれもが、赤の他人が姉妹兄弟になり人間社会が再生したように感じる特別な経験におもいあたるはずだ。このことが重要なのは、そこに示されているのが、たんに協力関係があるという以上のことだからである。実に、コミュニズムこそが、あらゆる人間の社交性[社会的交通可能性](sociability)の基盤なのだ。コミュニズムこそ、社会を可能にするものなのである。だれに対しても、その人が敵対関係にないとすれば、少なくともある程度は「各人はその能力に応じて、各人にはその必要に応じて」の原理にもとづいて行為することが期待できるそうした想定は常に存在している。たとえば、ある場所への行き方を知りたい者がいる、べつのある者は道を知っている場合などである。
………
道を教えることだけでない。会話は、とくにコミュニズムにかかわる領域である。嘘や侮辱や酷評などなど、言葉による攻撃は重要である。だがそうした言葉は、その力のほとんどを、ふつうひとはそんな風にふるまうものではないという共通観念からみちびきだすのである。ひとは他人の感情を配慮するものだという想定がなければ、侮辱がひとを苦しめることはない。それに、ひとは本当のことをいうものだと想定しない人間に対して、嘘をつくことはできない。だれかとの友好的な関係を解消したいと心底望むとき、わたしたちはその人間に言葉をかけることを完全にやめる。
火やタバコを分けてもらう、といったちょっとした親切にかんしても同様である。他人にタバコをねだることは、同額の現金や食物を求めることより無理がないようにみえる。実際、同好の喫煙者と認知されると、そのような依頼を拒絶するのはむずかしくなる。そうした事例――マッチ、ちょっとした情報、エレベーターをあけておくといった親切――においては、「各人はその能力に応じて」の要素が非常に小さいので、わたしたちの多くはそれについてあえて考えずに応じているといえる。その逆に、べつの人間――それが見知らぬ者であっても――の要求がきわめて大きいかあるいは極端であったとしても、このことはあてはまる。たとえば、だれかが溺れているような場合である。子どもが地下鉄の線路に落ちてしまったとして、可能な状況にあればだれでも助けようとするはずだ、とわたしたちは想定しているのである。
これを「基盤的コミュニズム(baseline communism)」と呼びたい。たがいを敵どうしとみなさないあいだがらで、必要性が十分に認められ、またはコストが妥当と考えられるなら、「各人はその能力に応じて、各人に必要に応じて」の原理が適用されてしかるべきである、という了解である。(そのままの引用ここまで)
どんな社会でも――共有とは、人生の喜びが集中するひとときでもある。そのため、共有の必要性は、最良のときと最悪のとき、飢饉のときと極端に満ち足りたときの両極において、ことさら鋭いものになる。共有にはモラルのみならず快楽も関係している。孤独な快楽も常に存在するものであるが、最も悦ばしい活動にはほとんどだれにとっても常になんらかの共有がともなうものである。
「基盤的コミュニズム」とは、社交性の原材料、すなわち社会的平和の究極的実体であるわたしたちの根互依存の承認であると考えることができる。母親、子供、妻、夫、恋人、親友、近親者などにおいて、その強度は特に高いが、「個人主義的コミュニズム」とは、さまざまな強度と度合いにおいて「各人はその能力に応じて、各人にはその必要に応じて」の原理にもとづき形成される一対一の関係なのである。このおなじ論理は集団の内部に拡張されうるし、実際に拡張されている。
日常的コミュニズムの社会学は、広大に広がる潜在性を秘めた分野だが、わたしたちの奇妙なイデオロギー的見落としのため、十分それを認めることができず、それゆえ、これまで著述することもできなかった。ともかく、概要はここまでにして(え!!ここまでは概要?)、三つの決定的ポイントに絞ってみよう。
<第一のポイント>……互酬性ではない
わたしたちがここで実際に扱っているのは互酬性ではない。このコミュニズムを可能にしているのは、こうした諸関係が永遠を想定しているということである。社会はこれからもずっと存在するものだ。収支決算が必要にならないのはこのためである。収支決算をするということは、これまでに何度も述べられているが、両者の関係を精算する、終わらせるという意味を含んでいる。
<第二のポイント>……歓待の法
共同体の成員でないものはだれであれ敵としてみなすという「未開社会」に対する紋切り型理解と、実際に初期のヨーロッパ人旅行者が経験した「野蛮人」が示すおどろくべき寛大さとは、一見、矛盾するように見える。しかし、見知らぬ者たちが危険な潜在的敵対者であるとしたら、どこであっても、その危険を克服するふつうの方法は、大仰なまでの寛大な身ぶりである。まさにその身ぶりの壮大さによって、あらゆる平和な社会関係の土台である相互的な社会性のうちに、見知らぬ者たちを投げ込むのである。
こういった身ぶりはすべて、あらゆる人間の社会生活の土台としてすでに論じてきた「基盤的コミュニズム」の極端な表出にすぎない。ヨーロッパと中東で共通のよく知られた原理にあっては、パンと塩を分かち合う人びとは決してたがいを傷つけ合ってはならないことになっている。
<第三のポイント>……モラリティーの原理
コミュニズムをたんなる財産所有権の問題でなく、モラリティの原理として考えはじめると、この種のモラリティが、商業さえも含むあらゆるやりとりのうちで、ほぼ常に機能していることがあきらかになってくる。ある人間どうしが社会的関係を切り結んでいたら、相手の状況を完全に無視することはむずかしい。商売人が、じぶんの育った界隈でカネをかせぐことはほとんど不可能なのだ。貧しい親戚や幼なじみに、経済的優遇を与えろ、とか、少なくとも楽な返済条件でツケにさせろという圧力に、常にさらされことになるからである。
必要(たとえばさしせまった窮乏)や能力(たとえば想像を超えた富)がきわだって存在し、かつ社会性がまったく不在でない場合、いくぶんかのコミュニズム的モラルがほとんど不可避的に人びとの考え方に忍び込んでくる。
【交換】
交換とは等価性にまつわるすべてである。相対する双方が、それぞれ与えたぶんだけ受けとるといったやりとりのプロセスである。したがって、口論や殴り合い、撃ち合いについても交換として語ることができる。ここにあるのは、それぞれの側が他方をしのごうと努力する等価性にむかうやりとりの不断のプロセスであり、競争の要素がある。物質的な財の交換も同じである。また、ここには収支決算/損得計算があり、 (ある種の永遠という概念を内包しているコミュニズムとは異なって)常に関係全体が解消され、双方がいつでも終止符を打つことができるという自覚が存在する。
物々交換や商業的交換においては、――経済学者がそうすべきだと主張するように――彼らは最大の物質的利益を求めようとするだろう。他方、贈与交換の場合、そこに競争が入ってくると、まさに正反対に作用する可能性が高い。つまりだれがより多く与えることができるかを人びとに見せびらかし、寛大さを競いあうことになるのである。
商業的交換の特徴は、その「非人格性」である。ショッピングモールやスーパーマーケットにおいて、店員たちには、人間的なあたたかみや忍耐などなどの、ひとに信頼をもたせるふるまいが期待されてはいる。また、中東のバザールでは、模倣的友情を確立したあとでなければ、値切りの交渉が開始されることはない。しかし、すべては芝居の一場面でしかない。ひとたび物品の持ち主が入れ替わるやいなや、二人がこれ以上かかわりあいをもつことは、まったく期待されない。
交換はわたしたちの負債の解消を可能にしてくれる。交換は負債をチャラにする手段、つまり関係を終わらせる手段を与えてくれる。だからこそ隣人に対して、ひとは負債を返済しないことを好む。関係を終わらせたくないからである。ナイジェリアのティブ族の共同体では、隣人に何かをもらったときのお返しは、少しだけ多いか、少しだけ少ないか、どちらかでなくてはならない。「決してだれも最後に受けとった物品の等価を返すことがない、終わりなき贈与の循環」の中で関係を維持する。
この種の応酬的な贈与交換の変奏は無限に存在する。贈り物の交換、おごりおごられという関係もそうである。このような習慣の存在そのもの、とりわけ好意を必ずやお返しする必要があると人が感じることこそ、標準的な経済理論では説明できないものなのである。標準的な経済理論においては、あらゆる人間の相互作用は究極的には商取引であり、ひとはみな最小の経費ないし最小の努力で、じぶん自身のため最大の利益を手に入れようとする利己的個人であると想定されているからである。
この後、多かれ少なかれ平等[対等]の地位にあると承認し合う人々ないし集団内での贈り物、地位と威厳の微細な等級で分割された社会内での贈り物、王様(王はすべてを持っていることになっており、王への贈り物は他の王でなければ不可能。だから王への贈り物は、とりわけ慎重を要するややこしい企てである)への贈り物の話があり、それぞれの人間心理が語られる。
交換において取引される対象は等価とみなされる。それゆえ、そこにひそむ含みから、[交換にあたる]人びとも等価であるとみなされる。交換が成立した瞬間には、それ以上の負債や義務が存在せず、両者がそれぞれ等しく自由に立ち去ることができる。このことは自律を内包している。(「等価」も「自律」も君主とは相性が悪い。王が[交換]に手を焼くのは、まさにこのためである)。この潜在的な解消可能性と究極的な等価性という全般的な見通しの内部で、際限のない[交換の]変種、果てしのないゲームの可能性がみいだされる。
贈り物にしても、マルセル・モースの「贈与経済」のうちでも、見知らぬ者どうしのあいだでも、これらは、ある物とべつの物を直接に取り替える物々交換にとてもよく似たなにごとかへと次第に転化していくこともある。
【ヒエラルキー】
はっきりとヒエラルキーのある関係――つまり少なくとも二者からなり、そのうちの一方が他方よりも上位にあるとみなされる関係――が、互酬性によって作動する傾向はまったくない。関係の正当化のために、「農夫は食物を与え、領主は保護を与える」などの互酬性をあらわす言葉遣いが用いられるため、見えにくくはなっているが。
旧ソヴィエト連邦のある無法地帯では、あまりにひんぱんに旅行者や列車、バスの略奪が起きるので、ついに[当のギャングたちによって]被害者に小さな認可証を与える慣習が発展したという話を聞いたことがある。略奪ずみであることを証明させるためらしい。あきらかに、国家創設までもう一息の段階である。北アフリカの歴史家イブン・ハルドゥーンによれば、遊牧民の侵略者たちが、定住民たる村人たちとの関係を徐々に制度化していったという。略奪は貢納となり、強姦は「初夜権」または王宮ハーレムの候補者の強制的確保となった。かくして征服や気ままな実力行使は制度化され、補食関係ではなく、領主が保護を与え、村人が食糧を与えるという、モラルの関係として認知されるようになる。
このような制度化が実現したとしても、召し上げられる収穫の量と与えられる保護の質、量とを互酬的なものとして考えることはないだろう。召し上げられる収穫の量は、習慣と先例による。昨年は、あるいは祖先はどれだけ召し上げられたかとして考え、差し出すことになる。また、慈善による寄付があらゆる社会関係の基盤となるならば、それは互酬性にもとづくものにはならないはずだ。
優劣の線がはっきり引かれ、関係を規制する枠組みとしてすべての関係者に受け入れられ、さらに気まぐれな力の行使に悩まされないほど関係が十分に継続しているようなときは、常に関係は習慣と慣習の網の目によって統制されているものとみなされるであろう。これが、ヒエラルキーは互酬性とは正反対の原則にしたがって機能するということの意味である。
封建領主への贈り物はなんであれ、「とりわけ四回のうち三回くり返されると」先例として受けとめられ、慣習の網の目に追加される傾向にあった。いったん関係が「慣習」にもとづいたものであるとみなされてしまうと、なすべき義務や恩義のあることを証明するには、それが以前におこなわれていたことを示すだけでよくなってしまう。
しばしばこのような取り決めがカーストの論理へと転化することがある。式典の衣服を織ること、王室の祝宴に魚を献上すること、王の髪を切ることなどの責務が、それぞれ特定のクランにあてがわれるのである。つづいて、それらのクランは、織工や漁師や理髪師として知られるようになる。
アイデンティティの論理は、常に、そしてどこでも、ヒエラルキーの論理と密接にからみあっている。根本的に異質である種々の人間存在なるものについて人が意識するようになるのは、ある人間が他の人間よりも上位に位置づけられるとき、または王や高僧、建国の父などとの関係に従ってすべての人びとがランクづけられるときに、はじめてなのである。ある集団が、自分を他集団よりも上位や下位に位置づけて、通常の公正な取引の基準が適用されなくなるようになったとき、いつでもそれは生じている。カーストや人種のイデオロギーはその極端な例にすぎない。
ここで単純な定式を示すことができる。ある行為が反復されると、それは慣習となり、その結果、慣習は行為者の本質的性格を決定するようになる。貴族であることの大部分は、過去に他者がその人間を貴族として扱ったから、それが継続されるべきである、と主張することなのだ。貴族は特に何かをすることはなく、優越性が推定されるなんらかの地位に就いていることだけにほとんどの時間を費やしている。対極の事例がある。アメリカ合衆国では、中流階級の13歳の少女が誘拐され、強姦され、殺害されたなら、悲痛な国民的危機とみなされ、テレビを持っただれもが、その推移を数週間にわたって見守るだろう。だがその13歳の少女が児童売春婦で、長年にわたって組織的に強姦されてきたあげくに殺害されたことがあきらかになれば、たいしたことではないとみなされる。――そのような人間にありがちな出来事にすぎない、と。
優位者と劣位者のあいだで贈与や支払いのかたちで物質的富がやりとりされるさいの主要な原理とは、それぞれに与えられる物品は、それぞれ質において根本的に異なり、相対的価値を数量化することは不可能であるというものである。
ヒエラルキー的再配分というものがある。たとえば、ナイジェリアのポップスターのファンたちが、コンサートの最中にステージ上に投げ銭をする。ポップスターは、ファンの住む地域をときおり訪問しては、リムジンの窓から(おなじ)硬貨を投げる。パプアニューギニアの大部分において、社会生活の中心にいるのは、カリスマ性をもった「ビッグマン」である。彼らは、大宴会でばらまくための巨額の富を獲得すべく、人びとをいいくるめ、甘言を弄し、あやつることに多大なる時間を費やしている。アマゾンや北米先住民の首長たちは、常に気前よく与えるべしという圧力にさらされているため、個人所有という意味では村で最も貧しい人物ということもよくみられる。
社会が実際にどの程度に平等か、まさにここから判断することができる。おもてむき権威的な立場にある人物が、たんに再分配の経路になっているだけか、それとも富を蓄積するために自身の立場を利用できるのか、である。後者の場合、さらにべつの要素、つまり戦争と掠奪を加えるならば、ほとんど貴族制社会そのものであるようにみえる。
とてつもない富を手にしたらだれもが、少なくともその一部をしばしば大人数に対して寛大かつ劇的なやり方で分け与えることになるものである。
(マイクロソフトのビル・ゲイツ…900億ドルや投資家のウォーレン・バフェット…840億ドルはその例のようだ。Amazonのジェフ・ベソス…1,120億ドルはどうなのだろう。日本の孫正義…227億ドル=2兆5,400億円、柳井正…195億ドル=2兆1,800億円はどうなのだろう。数字は2018年3月フォーブス発表の資産額)
【様相間の移動】
くり返し強調しなくてはならないが、ここで話題にしているのは、いくつかの異なる種類の社会ではなく、あらゆる場所で常に共有している諸々のモラルの原理である。わたしたちはみな、親しい友人のあいだではコミュニストであり、幼い子どもに接するさいには封建領主となる。そうでない社会を想像することは、きわめて困難なのである。
ここで、互酬性とはわたしたちが正義を想像する主要な方法であるという事実に立ち返らねばならない。とりわけ抽象的に思考するとき、そしてとくに理念的社会像をつくろうとするとき、ひとはそこに退いてしまう。イロコイ族も中世の思想家も同じである。中世において、実際に活動する司祭や騎士や農民の関係とはまったく無関係に、「祈る者、戦う者、働く者」の互酬的関係として図式化されてしまう。公正な社会を想像しようとするとき、均衡と対称のイメージ、すべてが均衡している優雅な幾何学を喚起しないことはなんともむずかしいのである。
「市場」というものについても同じである。市場とは、だれもがまったく同じ動機とまったく同じ知識をもって、まったく同じ利己的計算のうえで交換をおこなう、自己充足した世界を想像することで生みだされた、数学的モデルなのである。市場とは現実ではない。経済学者たちもたいていそのことを認めるだろう。そのこと自体はなにも悪くない。
厄介なことになるのは、おおよそその経済学者が、そのモデルをふりまわして、市場の指令を無視する者はだれであれ罰せられるべし、などと断言してもいいということになるからである。また、人は市場システムの中で生きているのだから、政府の介入を除き、あらゆることが公正の原理にもとづいているとか、現行の経済システムは巨大な互酬性のネットワークであり、最終的にはすべて帳尻が合い、すべての負債は清算されるのだ、などといった断言に短絡してしまうからである。
もつれ合う諸原理には、一定の度合いの互酬性が、どんな状況においても可能性として存在している。だから、そのつもりの観察者は、そこに互酬性を常に発見できてしまう。さらに、特定の諸原理はべつの原理へとすりかわってしまう内在的傾向をそなえているようにもみえる。たとえば、極端にヒエラルキー的な関係の多くは、(少なくとも一時的には)コミュニズム的原理にもとづいて作用することができる。金持ちのパトロンは、必要なときにあなたを助けてくれるはずだ。しかし、根本にある不平等を覆してしまうほどの大きな支援は提供してくれない。
コミュニズム的諸関係も、実にたやすくヒエラルキー的不平等関係に変容してしまう可能性をはらんでいる――たいてい、だれも気づかないうちに。異なった人たちの「能力」と「必要性」は、ときにはなはだしく不均衡だということがその理由である。真に平等主義的な社会はこのことを熟知しており、だれかが極端に他をしのいでしまう危険性のまわりに、洗練された防衛手段をはりめぐらす傾向がある。注目の的になるほどの成果をあげた者は、冷やかしの対象になる。なにか意義のあることを成し遂げたときの唯一のつつましいふるまいは、じぶんを笑い飛ばすことである。
誰かの行為に感謝をするということは、その誰かはその行為をしなかったかもしれないのにそうすることを選択したということが前提としてあり、そのことがその行為を受けた側に義務と負債の感覚(したがって劣位)を生み出し、その結果として現れるものである。
合衆国のコミューンや平等主義的共同体は、しばしば同様のジレンマに直面し、忍び寄るヒエラルキーに対する独自の防衛を考案することを余儀なくされている。しかし、コミュニズムがやがてヒエラルキーに転化してしまう傾向は不可避だ、というのではない。そうではなく、ひとは常に警戒する必要があるということである。イヌイットたちのような社会は、何千年ものあいだそれを回避してきた。
それとは対照的に、コミュニズム的な共有を前提とした関係から平等な交換関係への移行が困難なこと――しばしばまったく不可能なこと――はよく知られている。わたしたちは友人関係のうちに、いつもそれを観察しているはずだ。すなわち、もし、だれかがあなたの気前のよさにつけこんでいると感じたとしよう。そういう場合、なんらかのやり方で払い戻しを求める(平等な交換関係を求める)よりも関係を解消してしまう方がはるかに簡単である。
マダガスカルでは、一緒に起業しようと考えている二人の男は、しばしば血の契りを交わす義兄弟になる。たがいの約束が疑い得ないものであることが確認されたら、二人の男は委託売買をおこなったり、資金の前払いをしたり、利潤を分配したり、あるいは、以後、信頼をもとに互いに協力しあって商売上の利益を追求するようになる。しかしながら、交換関係がヒエラルキーへと変質してしまうおそれのある瞬間がある。つまり、双方が平等にふるまい、贈り物をやりとりしたり競り合ったり商品を取引したりしながら、どちらか一方が均衡を完全に打ち破るようなことをしてしまうときである。
統治機構が弱体であるか不在であるかで、統治機構のかわりに戦士たる貴族を中心に組織された社会である「英雄社会」において典型的であるが、贈与交換が相手に一歩先んじるゲームに変容する傾向がある。また、いくつかの社会においてはこの潜在的可能性が大規模な公共の競技に形式化されている。敵に豪華な金銀の宝物を贈答する寛大さの競争を交互に行なっているうちに、贈り物があまりに豪勢であるために、それに対抗することができなくなり、当事者を窮地に追いつめることもあった。このような場合、じぶんの名誉を守ることのできるただひとつの応答は、おのれの喉をかっ切り、富を随行者に分配することであった。それはたんに名誉の問題である。だが、こういった人びとにとっては、名誉こそがすべてなのだ。負債、とくに名誉の負債を支払うことができないことが、これほどの危機となる主たる理由は、これこそ貴族が取り巻きを集めるやり方そのものだからである。
*******
帝政ローマから中世の中国にいたる多くの時代、少なくとも都市部において、最も重要な関係といえば、おそらくパトロン・クライアント関係であった。裕福で要職にある人物ならいずれも、追従者や幇間、終身的食客、その他の自発的寄食者たちにかこまれていた。人類史のほとんどにおいて立派な中流階級であるとは、毎朝、家から家を訪問し、地元の実力あるパトロンに敬意を表示することを意味していた。今日でも、相対的に豊かで力をもった人びとが、支援者のネットワークを集める必要を感じるときには、フォーマルなパトロン・クライアント・システムがいつでも形成される。
こういった関係性は、これまでこの章を通じて検討してきた三つの原理(コミュニズム、交換、ヒエラルキー)すべての場当たりの混合で構成されている。にもかかわらず、観察者たちは、それらを交換と負債の言語にあてはめることを主張してゆずらないのである。
最後の事例として、同じ共同体の中で、それまで対等な関係にあった男の一方が他方に仕事をくれないかと依頼し、もう一方が自分の会社で働けるようにした場合の話が示される。仕事をもらった男は、与えた男に対して大きな恩義を感じる。男は折りをみてはトマトの籠を携え社長の家をおとずれ、敬意を表しつつ恩を返す。さて、社長と従業員という関係に変わった後、従業員は社長にこの恩義を返すことができるのか?恩義は返すことが不可能であり、一生、恩義という負債を抱えながら生きることになるのか。
前の章(第4章)で、デンマークの探検家が出くわしたイヌイットの話が出てきた。もう一度紹介すると、ある日、セイウチ猟がうまくいかず腹を空かせて帰ってきたとき、猟に成功した狩人の一人が数百ポンドの肉をもって来てくれた。彼はいくども礼を述べたのだが、その男は憤然として抗議した。……「この国では、われわれは人間である」「そして人間だから、われわれは助け合うのだ。それに対して礼をいわれるのは好まない。今日わたしがうるものを、明日はあなたがうるかもしれない。この地でわれわれがよくいうのは、贈与は奴隷をつくり、鞭が犬をつくる、ということだ」という話だ。このイヌイットの世界では、折りをみてはトマトの籠を携え社長の家をおとずれ、敬意を表しつつ恩を返す男は奴隷になったとみなされるわけである。そして、このイヌイットの世界が決して特殊なものではないということで、前回、脳科学者の池谷裕二さんのツィートも紹介した。
【アリガトウなんて要らない】世界の様々な民族を調査したところ、多くの文化圏では助けてもらってもわざわざ感謝の言葉を言わないようです。手助けは当然という暗黙の前提で社会が成り立っているからだそう。(2018.5.23)
仕事をもらう、与えるという話は、現在の賃労働契約と同じようなものである。賃労働契約は対等の者たちのあいだの自由契約となっている。だが、どちらか一方のみがパンチカードを押すことになる合意が成立するや、もはや二人は対等ではありえない。法律的には、社長の絶対的権力は労働時間内に限定されており、また、労働者はいつでも契約を破棄し、もとの自由で対等な市民に戻ることができる。法律的には。
実際には対等ではないが、対等であると擬制する者たちのあいだのこの合意こそ、決定的に重要である。まさにこれこそ、わたしたちが「負債」と呼ぶものの本質だからである。
*******
では、負債とはいったいなにか?
負債は、本質的な次元において実際に対等であるが、現在のところ対等な地位にはない、しかし、事態を回復する方法はあるという二人の関係を必要とし、そこから生まれる。状況を回復するためにとりうる方法がまったく存在しないなら、わたしたちはそれを「負債」とは呼ばない。犯罪者が刑に服すこと、死刑になることも、社会に対する負債を返すことだとみなすこともある。つまり、犯罪者に刑を科すことで返済が可能だとみなすわけである。歴史上、多くの時代において、返済不能におちいった債務者を投獄することが可能であった、あるいは処刑することさえ可能であった。
負債が返済されていない間は、ヒエラルキーの論理が支配的になる。互酬性は存在しない。債務者と債権者は封建領主を前にした農民のごとく対峙し合うことになる。その関係を支配するのは判例法[先例からなる法]である。(債務者はお礼のつもりで債権者に対してちょっとした贈り物をすることがある。このとき、債務者は債権者からお返しがあるだろうとは期待しないが、債権者は債務者からこれからも贈り物があるだろうと期待することはある。しかし、負債は実際に返済されるのが当然であるという前提からすれば、このことはどこか不自然である。だが、「先例」を基準とすれば不自然ではない)
「負債は実際に返済されるのが当然である」という前提からすれば、実質的に返済不可能である負債を抱えた状況を、困難で苦しいものにする。債権者と債務者は究極的には対等であるため、(債務者が負債を返して)対等性[平等]を回復することができない場合、あきらかに債務者側になにか問題があるとされる。ヨーロッパの諸言語における「負債(debt)」の語源をさかのぼると、このつながりがはっきりしてくる。その多くが、「過誤(fault)」、「罪業(Sin)」、「罪責性(guilt)」と同義語である。債務者は常にある種の犯罪者なのである。
かくして負債とは完遂にいたらぬ交換にすぎないのである。
とすると、負債は厳密に互酬性の産物であり、(必要と能力のコミュニズム、慣習と特性のヒエラルキーといった)それ以外のモラリティとは、ほぼ無関係であるということになる。それでもなお、コミュニズムとは永続的に負債のある状態であるとか、ヒエラルキーとは返済不可能な負債から構築されているとして、それらを負債と結び付けて考える人がいる。しかし、その考えには人間の相互作用は交換の諸形式でなくてはならないという前提がある。しかし、その前提が誤っている。人間の相互作用には、交換の形式をとるものもあるというにすぎない。
交換が対等性「平等」を内包し、かつ分離をも内包しているため、それは、人間の諸関係を把握するためのひとつの特殊な方法を助長する。負債が清算されるとき、対等性「平等」が回復され、二人の関係は解消されるというわけである。
(「負債とは、あいだ[中間]で生起するものである」……「人間的な事象のおおよそすべてがあいだ[中間]で起こっている」とグレーバーがここで言っている「あいだ[中間]」ということばの意味がよくわからなかったが、たぶん下記のような意味だと解釈した。違うかもしれないが)
負債は、いずれ対等になるという含みを持つ2名の当事者が、いまだ対等ではなく、それゆえ、たがいに背をむけ合うことができないときに生起する。そして、対等性[平等]が達成されてしまうと2名の間の関係は解消される。人間的な事象のおおよそすべてが、関係の生起と解消との[中間]で起こっている。先の【交換】のところで出てきた話であるが、ナイジェリアのティブ族は、だれもがだれかに対して、いつもほんの少し負債があるようにすることによって、たとえそれが大変脆いものであったにしても、実際に人間社会を創造していた。
わたしたち自身の文明の習慣もそれほど異なっているものではない。「おねがいします(please)」や「ありがとう(thank you)」をたえまなく口にしているアメリカ社会の慣習を考えてみよう。一般に、こういった習慣は普遍的なものであると考えられがちである。だが、そうではない。(先に示したイヌイットの話や池谷裕二さんのツィート【アリガトウなんて要らない】を思い出してほしい)。わたしたちの日々の礼儀の多くと同様、それは、かつて封建的な敬意表現の習慣だったものの民主化である。
(ちょっとした親切を受けたり、与えたりしたときに交わすことばには、ティブ族やイヌイットとは形式は異なるが、対等な関係を壊さないようにするという配慮が含まれている……以下の部分はそういうことを言っているのだと思う。たぶん)
英語の”please"は”if you please"(もしよければ)、”if it pleases you to do this”(もしそうすることがあなたの意にかなうならば)の短縮形である。その文字通りの意味は、「あなたには、そうするいかなる義務もありません」である。「塩をとってちょうだい。でもそうしなくてはならないといっているわけではないけど!」実際は命令である。英語の“thank you"は“think(考える)”から派生している。もともとは「あなたがしてくれたことをわたしは忘れません」という意味である。それは実際には「わたしはあなたに借りがあります(I am in your debt)」を意味している。“You’re welcome"(どういたしまして)または“It's nothing"(なんでもありません)と口にすることは、その人のために塩をとってあげたことによって想像上のモラルの会計帳簿に借方を記載したわけではない「貸しとみなしたわけではない」、と安心させるひとつの方法である。”my pleasure"(喜んで)と口にすることで、「いや、これは貸しではなくて借りなのです。あなたはわたしに塩をとってくれと依頼することで、わたしがそれ自体で尊いとみなすことをなす機会を与えてくれたわけで、あなたがわたしに親切を施してくれているのです!」といっているのである。
始終”please”や“thank you"といい合う習慣が最初に定着したのは、一六世紀および一七世紀の商業革命のさなか、中産階級の人びとのなかにであった。それは官庁や商店やオフィスにおける言葉づかいであり、過去五〇〇年のあいだに彼らとともに世界中に拡がっていったのである。
*******
「歴史的な新時代の転換点において、先見の明ある精神には、頭をもたげつつある時代のその含意を完全に理解できることがある――ときには後続世代には不可能なやり方で。そのような人物の手による文書で本章をしめくくることにしよう」ということで、フランソワ・ラブレー(背教的修道士、医師、法学者)の、後に「借金礼賛」として知られるお話(1540年代に創作された)が紹介される。
気のよい巨人パンタグリュエルは、パニュルジュを家臣にし、相当の身入りを保障しもするのだが、パニュルジュは、それも湯水のように散財し、いつも借金で身動きがとれない首のまわらぬ状態にある。それがパンタグリュエルの悩みの種なのである。返済できるよう努力した方がよいのではないか?そうパンタグリュエルは提案する。
それに対し、パニュルジュが反論する。借金をしているからこそ、貸した方は貸金がふいになってしまわないように、いろいろと気を使ってくれる。それどころではなく、借財こそ天と地を結び繋ぐものであり、人類の血糖を保持する唯一の道、これなくしては、ほどなく人類も死滅する。つまり、お互いに貸し与えることで万物は成り立っているという話を滔々とする。
あらゆる人間の相互作用について、ある物をべつの物の代わりに与えることの問題と定義するなら、継続的である人間関係のすべては負債の形式をとることになる。つまり、パニュルジュの言っていることは正しい。そんなバニュルジュこそ、当時まさに生まれつつあった世界にふさわしい予言者とみなされるべきなのだ。(ただし、)彼の視点は、もちろん富める債務者のそれであって、返済にしくじると伝染病まみれの地下牢に閉じ込められてしまう恐怖に脅えねばならぬ[貧乏人の]債務者のそれではない。
負債がなければだれかがだれかになにか借りがあるということもなくなるだろう。負債なき世界は、原初的混沌へと、万人の万人に対する闘争へと逆行してしまうことだろう。他人に対してだれも、いかなる責任も感じなくなるだろう。人間であるという単純な事実に、なんの意味もなくなるだろう。だれもが、じぶん自身の正しい軌道の維持さえあてにできない、孤立した惑星になるだろう。
パンタグリュエルには、そもそもそんなお話自体、認めがたい。彼はこう述べる。この問題に対するじぶんの心情は「おたがいの慈しみや慈愛を除いては、汝は、だれにも、なにも借りてはならない」という使徒パウロの言葉に尽きている、と。そしてそれにふさわしい聖書的な身ぶりで、パンタグリュエルは宣言する。「過ぎ去ったことは、赦してつかわす[すべての負債から身を解放しよう]」
パニュルジュは返答する。「いかほど殿に御礼申しあげても申しあげ切れるものではござりませぬ」
*******
* 「コミュニズムこそ、社会を可能にするものなのである」ということについての感想
「各人はその能力に応じて[貢献し]、各人にはその必要に応じて[与えられる]」という原理」は、至極当然の原理ではないか。複数の人が共に生きてゆこうとするとき、これ以外の基本的原理があるのだろうか。「能力に応じて貢献」ということを裏返してみれば、さまざまな理由によって、あることをする能力がない人は、その範囲においては、その共同体に貢献することはできない。だから、その人がそれを必要とするときは、それができる人に頼るしかないことになる。
一方、人によって、あるいはその環境によって、できることは異なる。だから、それぞれの人が、これはできるが、あれはできないということになる。これは得意だが、あれは不得意だということになる。だからこそ、できる条件にある人、得意な人が、それを行ない、それを必要とする人がそれを受け取るのは当然のことではないか。個人的な資質も、自然環境も、人的環境も、生まれながらにして当然に異なる。そして、人はそれらを自分の意志で選んで生まれてくるわけではない。だとすれば、そういう多様な人間が共に生きてゆこうとするならば、それぞれ、自分ができることをしてその共同体に貢献し、必要なものはその共同体から受け取るということは当然のことのように思われる。
ここに「互酬」や「交換」という考え方を持ち込むと、その共同体はゆがみ始める。「互酬」や「交換」という考え方においては、互いに与え合う、あるいは交換するものの内容について、量、価値の等価性が要求されるようになる。しかし、上に述べたように、同じことをするにも、人の能力には差がある。個人的な資質、そして広い意味での環境が異なる中で、有利な条件が与えられた人はより多くの量、価値を共同体に供給できる。そこに互酬、交換を持ち込むと、有利なものが受け取る量、価値は当然多くなる。その有利さが偶然に与えられたものにすぎなくても。反対に、不利な条件が与えられた人はその逆になる。その条件が彼の選択や、意志、努力とは無関係であったとしても。
極端な例をあげれば、身体的、精神的に障碍を持った人が、その共同体に何も貢献できないとすれば、受け取るものはなく、生きていることができなくなる。赤ん坊や小さな子供、老人も同じことである。最近、「自己責任」ということばをよく聞く。それを言う人はこのような問題をどう考えるのだろう。無能なやつが惨めな生活をしなければならないのは当然だということだろうか。はっきりしているのは、不利な条件にあって、苦しい生活を強いられている人たちはけっしてそう考えないということだ。それでも社会が維持されているとすれば、そういう不満を力でねじ伏せる仕組みがあるということだ。
このように考えてみると、「コミュニズムこそ、社会を可能にするものなのである」というグレーバーのことばは、正に当を得ているものとして納得できる。













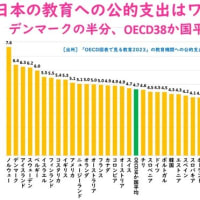



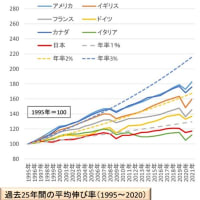


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます