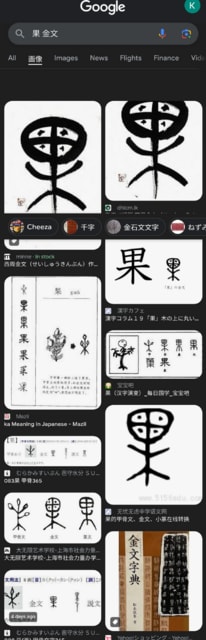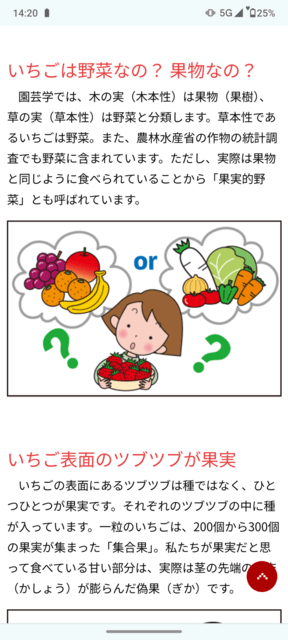岩波古語辞典を見ていて一つ発見しました。
接尾語「だ」です。
「だ」は、中身と外側を分け、外側だけで、
中が空っぽだということを強調する接尾語です。
包装されたお菓子の内、中身のチョコではなく、
箱やその周りのビニールだけだということを強調する印です。
「体(からだ)」という言葉は、
「身(み)」の類義語のようですが、
実(じつ)は対義語です。
人間の中身を魂(たましい)と考えて、
中身=魂の入っているものが「身」。
逆に魂のない外側、殻だけのものを
「体=殻だ」と言います。
お菓子で喩えると外側の箱の部分です。
更に「体」を内側と外側に分け、
一番外側、端っこの皮の部分を
「肌(はだ)」と呼びます。
体の外側=端(はし)の意味の
「端(は)」に接尾語「だ」を付けたものです。
「体」の一番外側の薄い部分なので、
お菓子で喩えるとビニールの包装紙のところです。
「合う」は、二つのものが近づいて向かい合うことです。
「合う」の名詞形(連用形)の「合い」は
近づいた二つのものの中間にある空間を指すことができます。
つまり「合い」だけで、「間(あいだ)」の意味を持ちます。
(「間合い」はその意味です。時間の間の意味で「合いの手」があります。)
「だ」は、間が空いていることの強調です。
とても興味深いのが
「仇、徒(あだ)」です。
「あだ花」という言葉は浮かぶのですが、
正確な意味を知りませんでした。
「あだ」自体で「花が実を付けない」という意味があります。
「あだ花」は、外見だけ良くて中身のない花、綺麗だけど空しいことです。

「あ」は、「これ」に対しての「あれ」のように遠くを指す言葉です。
また、田圃の畔(あぜ)を「あ」と呼ぶので、
外側、外枠というイメージがあるのかもしれません。
外枠という意味の「あ」と
外枠だけで中身がないことを強調する「だ」が
結びついたことになります。
もしかすると「あだ」が接尾語「だ」の語源かもしれません。
「あだ」を語の後ろに付けると母音が連続するので、
それを嫌って「あ」が脱落したということになります。
(意味があまりにビッタリなのでそう思いました。)
「(入り)江(え)」は、海が陸に入り込んで、
陸から見れば間(あいだ)が空いた形です。
逆に海側から見れば
海が陸の中に枝を伸ばしているような形になります。
子宮の内膜である「胞衣(えな)」の「胞(え)」は
体の外側の空間が体の中に入り込んで
中空になった様子です。
こちらも外側の空間が枝を伸ばして
体の中に入り込んでいるとも考えられます。
本体から伸びる意味で、
「え」と読む「江」「胞」「枝」「柄」は同根です。
「江」や「胞」の「え」に接尾語「だ」を付けて
「枝(えだ)」になります。
海や、外の空間といった大元(おおもと)となるところから
分かれて小さく伸びている中空のものという意味です。
まさしく枝分かれしているものを指します。

「だ」は、「だ」が付かなくても
間(あいだ)が空いているものに付いて、
間が空いていることを強調します。
そうだとすると、
木の「枝」自身に中空というイメージがあるはずです。
木の神様を「くくのち」と言い、
「くく」が木を表します。
「く」と「き」は頻繁に交換されるようです。
「くく」は、
「潜る(今はクグルですが、昔はククルです)」
「括(くく)る」と同根だと考えられます。
「潜る」には狭い隙間を通り抜けるという意味があります。
「木(き)」=「くく」は、
内部にある狭い管(くだ)で
地下の水を空に伸びる葉や花に運んでいます。
つまり「木」の語源が
「水を通す中空のもの」
という意味だったのだと思います。
「茎(くき)」も古くは「くく」と読みました。
「木」と「茎」は今ではイメージが違いますが、
古い日本では同じ言葉でした。
「茎」であれば、
中が空洞なイメージがピッタリきます。
なにせ麦の茎=麦わらの英訳は「ストロー」です。

木の幹から分かれて細くなる部分を
「枝(えだ)」と呼ぶのも、
接尾語「だ」のルール通りです。
今の話の中で、
「管(くだ)」の語源も分かりました。
「木=く(く)」、「茎=く(く)」+「だ」です。
「茎」=ストローのように細長く中が空洞なものを
「管(くだ)」と呼びます。

この議論から、
「果物(くだもの)」の語源も分かります。
「くだもの」の「く」は、
「木々(くく)」「茎(くく)」の「く」なので、
水を通す導管が沢山通っている
みずみずしいイメージになります。
また、接尾語「だ」が付いていることで、
「実(み)」=種の部分ではない外側を食べることが強調されています。
桃を想像すると分かりやすいですね。
農林水産省は木の実=種を食べるものを果物に分類しているようですが、
語源からするとおかしな分類になります。
(果実と呼ぶのなら同じ分類で良いと思います。)
私達が、果物と聞いて、
みずみずしいイメージを持ち、
くるみやアーモンドを果物と思えないのは、
果物の語源のイメージがあるからです。
このイメージは漢字文化圏でも共有されていて、
「果」の上の部分は、
田圃の畔(あぜ)の形をしています。
水を蓄える空間がある様子を表していて、
実(み)=種を食べるのではなく、
その周りのみずみずしい果肉を食べることが
表されています。
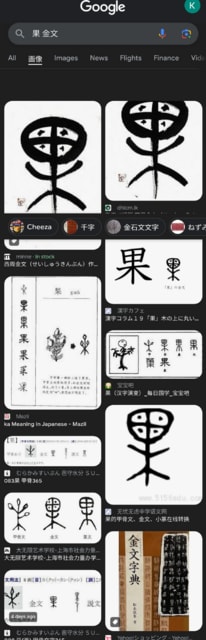
果物を「木の物」とする誤った解釈により、
スイカや苺は果物か、という議論があります。
私達はスイカも苺も間違いなく果物だと確信しています。
どちらもみずみずしいことと、
「くだもの」の「く」は、
「木(くく)」だけでなく、
「茎(くく)」の「く」でもあるからです。
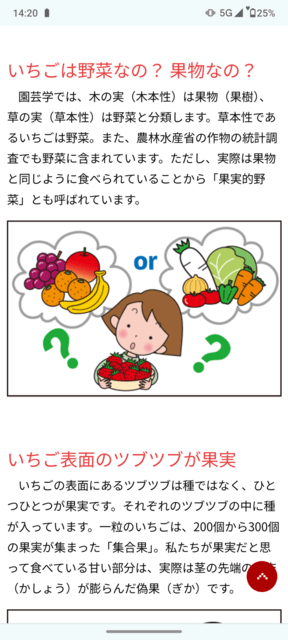
「札(ふだ)」もそれっぽいのですが、
「文板(ふみいた)」が変化したもので、
接尾語「だ」とは関係ありません。
「無駄(むだ)」は、
「無(む)」に中が空っぽ、空しいという意味があるので、
接尾語「だ」のルールにピッタリです。
ところが「無(む)」は漢字の音読みで、
大和言葉ではありません。
漢語に大和言葉のルールは違和感があります。
(「駄」の漢字は当て字のようです。)
岩波古語辞典の用例は
江戸時代の洒落本と咄本と呼ばれるものから取られています。
「無駄」は、おそらく新しい言葉なんだと思います。
「無(む)」が日本語として十分馴染んだので、
大和言葉の接尾語「だ」のルールを適用したのかもしれません。
そうではなく、「無駄」=「空(むな)しいこと」なので、
「空(むな)しい」の「む」に「だ」を付けたのかもしれません。
「むなこと」=実のない言葉、という語は万葉集にあります。