東京都教育委員会は、平成23年7月に実施した「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結果を報告書にまとめました。この調査は、「学習指導要領に示されている目標及び内容」の実現状況及び「読み解く力に関する内容」の定着状況を把握して指導方法の改善に結び付けることによる、児童・生徒一人一人の「確かな学力」の定着と伸長を目的としています。
調査報告書の概要は次のとおりです。
(中略)
(3)授業改善の視点
基礎的・基本的な知識や技能の習得を図る指導の徹底
学力調査問題をもとに、学習のつまずきに応じた指導や繰り返し指導、習熟の程度に応じた指導の充実を図っていく必要がある。また、観察・実験(操作)、作図や計算、資料活用などの基本的な技能の習熟を図っていくことが大切である。
思考力・判断力・表現力等を育む指導の充実
児童・生徒の多様な考えを引き出したり、互いに学び合ったりするなどの指導の充実を図っていく必要がある。
読み解く力を高める指導の充実
複数の資料(文書、図、グラフ、年表、マトリクス等)を意図的に提示し、比較・関連付けて捉えさせたり、調べて分かったこと・考えたことを論理的に表現させたりするなどの指導の工夫を行っていく必要がある。
授業規律の確立
授業の充実・改善を図っていくためには、その基盤となる授業規律を組織的な共通理解と実践により、確立していくことが大切である。(教育庁報)
結果を見ると全体の中で数学、理科、英語の「比較・関連付けて読み取る力」、「解決する力」の点数が著しく低い結果となっている。理数系の能力が劣っていると言えるかもしれないが、実際、文系、理系と簡単に割り切っていいものなのだろうか。思考の点で言えば双方に差はないように思える。国語の文章の構造を理解する思考と数学の公式を用い計算式を立てる思考は同一のように思える。アウトプットが「文章」か「数字」かの差だけである。当時そのように考えることが出来れば数学に対して別の観点から迫ることが出来たであろう。
報道番組で理科系女子の特集がされており、小学生の女子がサイエンススクールに通う姿が映されていた。自身で考え実際の作業を行うことで学習する体験型、能動的学習が理系の思考、ひいては文系の思考、総合的な「自身で考える力」を養うことが出来るのではなかろうか。
調査報告書の概要は次のとおりです。
(中略)
(3)授業改善の視点
基礎的・基本的な知識や技能の習得を図る指導の徹底
学力調査問題をもとに、学習のつまずきに応じた指導や繰り返し指導、習熟の程度に応じた指導の充実を図っていく必要がある。また、観察・実験(操作)、作図や計算、資料活用などの基本的な技能の習熟を図っていくことが大切である。
思考力・判断力・表現力等を育む指導の充実
児童・生徒の多様な考えを引き出したり、互いに学び合ったりするなどの指導の充実を図っていく必要がある。
読み解く力を高める指導の充実
複数の資料(文書、図、グラフ、年表、マトリクス等)を意図的に提示し、比較・関連付けて捉えさせたり、調べて分かったこと・考えたことを論理的に表現させたりするなどの指導の工夫を行っていく必要がある。
授業規律の確立
授業の充実・改善を図っていくためには、その基盤となる授業規律を組織的な共通理解と実践により、確立していくことが大切である。(教育庁報)
結果を見ると全体の中で数学、理科、英語の「比較・関連付けて読み取る力」、「解決する力」の点数が著しく低い結果となっている。理数系の能力が劣っていると言えるかもしれないが、実際、文系、理系と簡単に割り切っていいものなのだろうか。思考の点で言えば双方に差はないように思える。国語の文章の構造を理解する思考と数学の公式を用い計算式を立てる思考は同一のように思える。アウトプットが「文章」か「数字」かの差だけである。当時そのように考えることが出来れば数学に対して別の観点から迫ることが出来たであろう。
報道番組で理科系女子の特集がされており、小学生の女子がサイエンススクールに通う姿が映されていた。自身で考え実際の作業を行うことで学習する体験型、能動的学習が理系の思考、ひいては文系の思考、総合的な「自身で考える力」を養うことが出来るのではなかろうか。














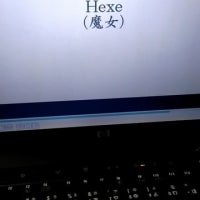





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます