
料金所を通って最初にパワースポットのくぐり岩を通り、
比較的楽だと思う奥の階段へ。

この付近は大津市歴史的風土保存区域となっているようです。
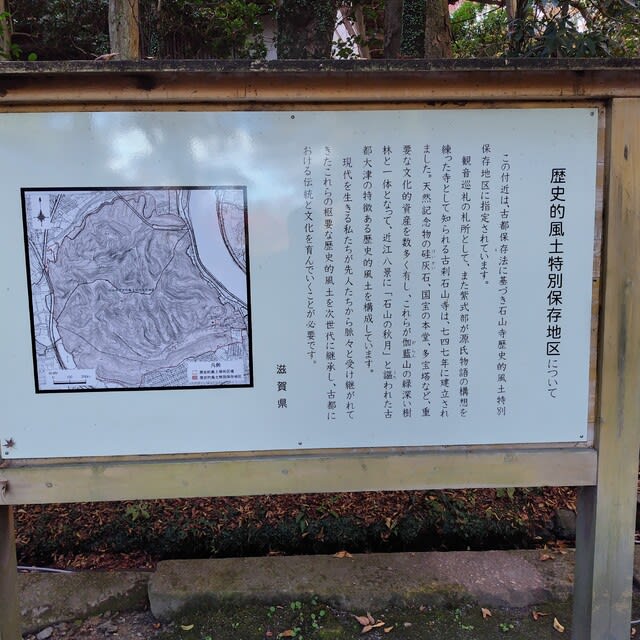
国土交通省告示第1465号 大津市歴史的風土保存計画の決定
(平成十六年十一月二十六日 国土交通大臣 北側 一雄)
大津市は、八世紀に石山寺、比叡山寺(後の延暦寺)、園城寺などの寺院が相次いで創設され、
平安時代以降仏都として栄えるとともに、後の中世仏教の指導者を数多く輩出するなど、
今日までわが国の仏教文化の中心地として繁栄してきた。
また、七世紀中頃に天智天皇が遷都した近江大津宮は、律令国家体制への転換を象徴する都であり、
わが国の歴史上重要な地位を占めている。市内にはこれらに関連する数多くの社寺や史跡が存し、
歴史上重要な文化的資産を現代に伝えている。
これらの歴史的資産の大半は、比叡山から長等山、音羽山、さらに伽藍山へと西方に連なる山並みの
恵まれた自然的環境と一体をなして、特色のある歴史的風土を形成している。
地区別の歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱は次のとおりとする。
①比叡山・坂本地区 ②近江大津京跡地区 ③園城寺地区 ④音羽山地区
⑤石山寺地区
本地区の歴史的風土保存の主体は、石山寺と一体となる伽藍山の自然的環境及び瀬田川河畔の
自然景観の保存にある。このため、瀬田川河畔においては、歴史的観光拠点としての機能を
高めることに配慮し、歴史的な景観の維持改善のための施策と協調しつつ、建築物その他の
工作物の新築等の行為の規制に重点を置くものとする。
また、背景となる伽藍山の山容の保存のため、土地形質の変更及び木竹の伐採等の行為の規制と
森林の育成等に重点を置くものとする。
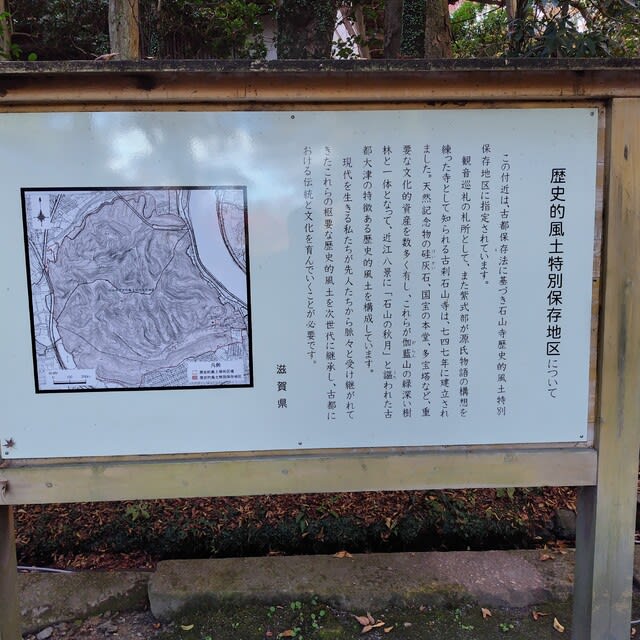



石山寺のご神木で「千年杉」と言われているとのこと。

ご神木「千年杉」の横の階段を登ると、雄大な天然記念物の硅灰石が現れます。
奥には多宝塔(国宝)が見えます。
「石山寺」の寺名はこの硅灰石に由来しているとのこと。

この先に「石山寺本堂(国宝)」があります。



国宝:石山寺本堂(いしやまでらほんどう)
種別:近世以前/寺院
時代:平安後期
年代:永長元、慶長7(礼堂)、 西暦1096年、1602年(礼堂)
構造及び形式等:本堂 桁行七間、梁間四間
相の間 桁行一間、梁間七間
礼堂 懸造、桁行九間、梁間四間
本堂及び礼堂 寄棟造、両棟を相の間の屋根でつなぎ礼堂の棟をこえて
破風をつくる、総檜皮葺。
重文指定年月日:1898.12.28(明治31.12.28)
国宝指定年月日:1952.11.22(昭和27.11.22)




























