日曜日に風邪をひいた。そして月曜日の雪に、玄関と道路の雪かきをして風邪をこじらしてしまった。「雨の日はオペラ」同様に外に出れないときは家に引きこもりオペラしかないと思い、ピエール・ブーレーズの追憶を込めて彼の振ったオペラ映像を観た。ブーレーズ追憶1で述べたように、彼との映像での出会いは、1967年の大阪フェスティバルのLIVEのVTRだった。その後カールベームの1966年のバイロイトLIVEを聴いたとき、1967年のブーレーズのテンポはカールベームのテンポではなかと思うほど音楽も似ていた。
1976年のバイロイトでそれこそストラビンスキー「春の祭典」初演時(私には知る由もないが)騒動になったのと同様の騒動がブーレーズの音楽、シェローの演出で起こったが、それはシェローの演出の問題でブーレーズの音楽には関係なかったことだった。ニーベルングの物語を西欧の産業革命期に置き換えた神話の読み替えで、ここ10年間毎年繰り返される悪しきバイロイトの慣習の発端の出来事だった。
 (ニーベルングの指輪1980年バイロイトLive)
(ニーベルングの指輪1980年バイロイトLive)
しかし音楽に関しては、戦後のバイロイトのリングとして一時代を築いたカール・ベームの演奏にトリスタン以上に似ているのだ。映像と音声だけの時間だがブーレーズの映像時間が826分、ベームの音声時間が817分わずか1%の違いだ。ちなみに近時バイロイトで評価を得たバレンボイムのリングは917分だ。11%の差と比べると、ブーレーズはベームの演奏を見習ったと思わざる得ない。シェローの演出ばかりが目立ったリングだったが、ブーレーズの音楽は、ベームが一時代を築いた贅肉をそぎ落とした引き締まったバイロイトのリングを見事なまでに継承していたのだと確信した。
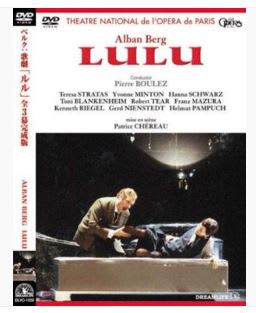 (アルバン・ベルク:ルル三幕版)
(アルバン・ベルク:ルル三幕版)
アルバ・ンベルクは私の好きな作曲家の一人だが、私の手持ちにリング同様にカール・ベームの二幕版がある。この版の違いはツェルハという他人により付け足された1幕の評価で結論が違ってくるがむしろ映像の出来不出来がこの作品の評価の決め手だろう。音声だけならばブーレーズのこの作品の価値はあまりないだろう。何しろ音の出来が良くない。しかし1979年三幕版の初演時Liveのカンムリがついて評価できるものだ。ただ私はベームの二幕版のほうが余韻を楽し方を選ぶ。
しかしこのDVDはブーレーズ+シェローのコンビがバイロイト同様に作り出した「歴史的価値」がある。
またこのオペラは誰がルルを演じるかで評価が出てしまうオペラだ。その意味からすれば3幕版を楽しみたいのならば1996年のグライドボーン音楽祭のクリスティーナ・シェファーのルルをおいてほかはない。
 (ヤナーチェック:死者の家から)
(ヤナーチェック:死者の家から)
このDVDはブーレーズ+シェローのコンビの最後の作品だ。したがって私が望んでいたバルトークの「青髭公の城」は永遠に見ることができなくなった。このDVDの完成度は高く、私の手持ちにあるアバド+ウィーン国立歌劇場盤をしのぐ出来だと思う。劇場の高さを利用しての空間が、収容所の閉塞感を出し、シェローの演出も動きのとれない囚人の拘束感を舞台をうまく使って描き出している。その意味では前二作より完成度の高い舞台で素晴らしい。2007年のプロダクションだが、「21世紀に明るい未来があるのか」といったシェローの疑問符で彩られた舞台は、ブーレーズの音楽も冴えている。
20世紀の音楽を語るには、やはりバーンステインではなくブーレーズなのだと思った。














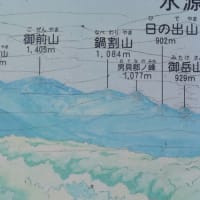






田んぼ作業で風邪をひかれたのでしょうか?
治療は睡眠と野鳥観察が一番です。今朝、いきふれで氷水で水浴びしているシロハラを見ました。鳥は風邪をひかないみたいです。
レコードはどんなふうに聞かれているのですか?
私はNikon D810Aに興味シンシンです。