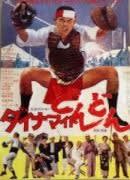「大誘拐 RAINBOW KIDS」 1991年 日本

監督 岡本喜八
出演 北林谷栄 風間トオル 内田勝康 西川弘志
緒形拳 神山繁 水野久美 岸部一徳
田村奈巳 松永麗子 岡本真実 奥村公延
天本英世 本田博太郎 竜雷太 嶋田久作
ストーリー
ある夏の日の朝、大阪刑務所に仲間の正義(内田勝康)と平太(西川弘志)を迎えに行った健次(風間トオル)は、二人に誘拐の計画を話す。
最初は反対する二人だったが、健次のねらいは紀州一の山林王・柳川とし子刀自(北林谷栄)。
さっそく計画を実行する三人。
ところがこのおばあちゃんただ者ではなく、やっと山中で拉致に成功した彼らに向かって和歌山県警本部長・井狩(緒形拳)の知るところとなれば逃げるのは難しい、と落ち着いた表情で論じ始める始末。
こうして三人は刀自に用意させた家に身を隠すことになる。
この家は柳川家の元女中頭だったくーちゃんことくら(樹木希林)の家だった。
そのころ、和歌山県警本部では“刀自誘拐”の連絡が届き、刀自を生涯最大の恩人と敬愛する井狩が火の玉のような勢いで捜査に乗り出して来た。
連絡を聞いた刀自の子供たちも次々と柳川家に到着。
騒然とした空気の中、刀自救出作戦が開始された。
一方、三人は隠れ家で身代金要求の策を練っており、その額が五千万円だと知った刀自はいきなり表情を変え、「大柳川家の当主なんだから百億や!」と三人に言い放つ。
それによって誘拐犯と刀自の立場は完全に逆転してしまい、事件はいつしか刀自と井狩との知力を尽くした戦いになっていた。
そしてついに身代金の受け渡しの日がやってくる。
それは前代未聞の全世界へ生中継されるにまで至っていた。
寸評
痛快コメディでこの作品を高く評価する人も多いようだが、この手の作品はどちらかと言えば僕の好みではない。
資産家の老女を誘拐し100億円の身代金を要求するという奇想天外な話なのでリアリティはない。
だったらもっとはじけても良かったように思うが、北林谷栄のおばあちゃんが若者3人を手玉に取って指揮していく様は面白く、北林谷栄なくして成り立たない作品である。
柳川とし子刀自は(刀自とは老女に対する敬称であることを初めて知った)は大阪府がすっぽり入ってしまう山林を有する資産家と言うだけでなく、皆に好かれているおばあちゃんである。
柳川家に君臨しているようにも見えるが、使用人からは慕われているようだ。
その代表がクーちゃんと呼ばれる元使用人の中村くら(樹木希林)である。
彼女は主人と使用人という立場を保ちながらも盲目的にとしこ刀自に尽くす。
北林谷栄が真面目に滑稽さを演じているのに対し、樹木希林はドタバタで滑稽さを演じて女性二人が面白い。
訪れた村の人々も心底から刀自を歓迎しているようだし、パイロットの本田博太郎までもが刀自の心酔者である。
彼等に反するように自分たちの財産だけを気にするのが4人の子供たちという図式になっても良さそうなものだが、そんな風には描かれていないので作品自体がメルヘンを感じさせるものとなっている。
あってもおかしくない金を巡る家族のドロドロした関係は排除されている。
明るいコメディ路線を外さず、次々と作戦を実行していくところは評価できる。
軽くなりがちな作品を引き締めているのが県警本部長の井狩を演じる緒形拳でさすがと思わせる。
誇張気味に描かれながらも作品に重みを生み出している。
井狩の優秀さを感じさせながら進む捜査状況も、刑事ものの如く描かれミステリー性を生み出している。
本来なら井狩とおばあちゃんの丁々発止の知恵比べが描かれ、勝負に勝ったり負けたりの様子が描かれるところなのだろうが、ここではおばあちゃんの完勝となっている。
おばあちゃんは井狩以上の切れ者なのだ。
おばあちゃんにとっては愛してきた広大な山林は小さな自分の庭のようなものである。
足腰も丈夫なのだろう。
人が行けそうもない場所に行っているし、通行できない道ばかりなのに車を持ち込んでいる。
山道を散歩する姿も描かれていたから、最後に明かされる犯行動機が可笑しく感じる。
そう言えば冒頭で体重計に乗っていたなあ・・・。
この映画のテーマが浮かび上がるのが事件の結末が語られる段だ。
仏間の遺影の中に若い三人の写真があり、刀自は戦争で二人の息子と娘一人を亡くしている事を語る。
戦争に国民を巻き込んだうえ三人の子供の命をも奪い、さらには巨額な相続税のために物納の形で美しい紀州の森林を略奪する日本国政府に対する怒りであり、反戦というテーマを感じさせるシーンとなっている。
刀自が自ら作戦を練って三人をこき使い誘拐事件を仕切っていったのは、刀自が国家権力に挑んだ一世一代の凄絶な戦いだったのだと明かされ、これこそが岡本喜八監督の叫びだったのだと思う。
それにしても北林谷栄は見事というほかない。
この時代におけるおばあちゃん役のNo1だろう。

監督 岡本喜八
出演 北林谷栄 風間トオル 内田勝康 西川弘志
緒形拳 神山繁 水野久美 岸部一徳
田村奈巳 松永麗子 岡本真実 奥村公延
天本英世 本田博太郎 竜雷太 嶋田久作
ストーリー
ある夏の日の朝、大阪刑務所に仲間の正義(内田勝康)と平太(西川弘志)を迎えに行った健次(風間トオル)は、二人に誘拐の計画を話す。
最初は反対する二人だったが、健次のねらいは紀州一の山林王・柳川とし子刀自(北林谷栄)。
さっそく計画を実行する三人。
ところがこのおばあちゃんただ者ではなく、やっと山中で拉致に成功した彼らに向かって和歌山県警本部長・井狩(緒形拳)の知るところとなれば逃げるのは難しい、と落ち着いた表情で論じ始める始末。
こうして三人は刀自に用意させた家に身を隠すことになる。
この家は柳川家の元女中頭だったくーちゃんことくら(樹木希林)の家だった。
そのころ、和歌山県警本部では“刀自誘拐”の連絡が届き、刀自を生涯最大の恩人と敬愛する井狩が火の玉のような勢いで捜査に乗り出して来た。
連絡を聞いた刀自の子供たちも次々と柳川家に到着。
騒然とした空気の中、刀自救出作戦が開始された。
一方、三人は隠れ家で身代金要求の策を練っており、その額が五千万円だと知った刀自はいきなり表情を変え、「大柳川家の当主なんだから百億や!」と三人に言い放つ。
それによって誘拐犯と刀自の立場は完全に逆転してしまい、事件はいつしか刀自と井狩との知力を尽くした戦いになっていた。
そしてついに身代金の受け渡しの日がやってくる。
それは前代未聞の全世界へ生中継されるにまで至っていた。
寸評
痛快コメディでこの作品を高く評価する人も多いようだが、この手の作品はどちらかと言えば僕の好みではない。
資産家の老女を誘拐し100億円の身代金を要求するという奇想天外な話なのでリアリティはない。
だったらもっとはじけても良かったように思うが、北林谷栄のおばあちゃんが若者3人を手玉に取って指揮していく様は面白く、北林谷栄なくして成り立たない作品である。
柳川とし子刀自は(刀自とは老女に対する敬称であることを初めて知った)は大阪府がすっぽり入ってしまう山林を有する資産家と言うだけでなく、皆に好かれているおばあちゃんである。
柳川家に君臨しているようにも見えるが、使用人からは慕われているようだ。
その代表がクーちゃんと呼ばれる元使用人の中村くら(樹木希林)である。
彼女は主人と使用人という立場を保ちながらも盲目的にとしこ刀自に尽くす。
北林谷栄が真面目に滑稽さを演じているのに対し、樹木希林はドタバタで滑稽さを演じて女性二人が面白い。
訪れた村の人々も心底から刀自を歓迎しているようだし、パイロットの本田博太郎までもが刀自の心酔者である。
彼等に反するように自分たちの財産だけを気にするのが4人の子供たちという図式になっても良さそうなものだが、そんな風には描かれていないので作品自体がメルヘンを感じさせるものとなっている。
あってもおかしくない金を巡る家族のドロドロした関係は排除されている。
明るいコメディ路線を外さず、次々と作戦を実行していくところは評価できる。
軽くなりがちな作品を引き締めているのが県警本部長の井狩を演じる緒形拳でさすがと思わせる。
誇張気味に描かれながらも作品に重みを生み出している。
井狩の優秀さを感じさせながら進む捜査状況も、刑事ものの如く描かれミステリー性を生み出している。
本来なら井狩とおばあちゃんの丁々発止の知恵比べが描かれ、勝負に勝ったり負けたりの様子が描かれるところなのだろうが、ここではおばあちゃんの完勝となっている。
おばあちゃんは井狩以上の切れ者なのだ。
おばあちゃんにとっては愛してきた広大な山林は小さな自分の庭のようなものである。
足腰も丈夫なのだろう。
人が行けそうもない場所に行っているし、通行できない道ばかりなのに車を持ち込んでいる。
山道を散歩する姿も描かれていたから、最後に明かされる犯行動機が可笑しく感じる。
そう言えば冒頭で体重計に乗っていたなあ・・・。
この映画のテーマが浮かび上がるのが事件の結末が語られる段だ。
仏間の遺影の中に若い三人の写真があり、刀自は戦争で二人の息子と娘一人を亡くしている事を語る。
戦争に国民を巻き込んだうえ三人の子供の命をも奪い、さらには巨額な相続税のために物納の形で美しい紀州の森林を略奪する日本国政府に対する怒りであり、反戦というテーマを感じさせるシーンとなっている。
刀自が自ら作戦を練って三人をこき使い誘拐事件を仕切っていったのは、刀自が国家権力に挑んだ一世一代の凄絶な戦いだったのだと明かされ、これこそが岡本喜八監督の叫びだったのだと思う。
それにしても北林谷栄は見事というほかない。
この時代におけるおばあちゃん役のNo1だろう。