吉田秀和「音楽のよろこび」(河出書房新社)を読んだ。氏の本は何冊か持っているが、この本は最近本屋で偶然見つけて面白そうだったので買ってみたものだ。
この本は氏が指揮者、文学者、作曲家などクラシック音楽に造詣の深い人たちと雑誌の企画などで対談したときの対談集である。巻末の初出一覧を見ると1955年から2011年までに行われた12の対談であり、古いものもあるが内容的には今に通用する議論が多いと思った。
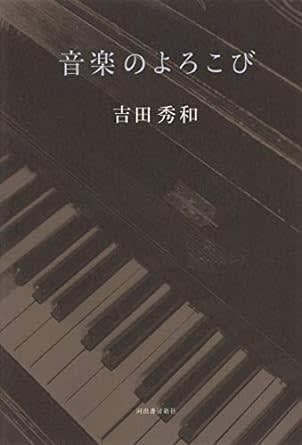
対談の相手を記せば
中島健蔵(フランス文学者、文芸評論家)
平島正郎(音楽学者、明治学院大学教授)
遠山一行(音楽評論家、東京文化会館館長)
園田高弘(ピアニスト)
高城重射(オーディオ評論家、音楽評論家)
斉藤義孝(ピアノ調律師)
藤原義江(オペラ歌手、(声楽家)
若杉 弘(指揮者)
柴田南雄(作曲家、音楽評論家)
武満 徹(作曲家)
堀江敏幸(作家、フランス文学者)
吉田氏や対談相手の各氏は音楽に関係した仕事のプロであり、私にとっては内容的にかなり難しい議論も多く、読むにはある程度の知識が必要だ。また、対談の内容は単に音楽に関するものにとどまらず、文化論的な話にもしばし及ぶなど広範囲であり参考になった。むしろ読んで参考になったのはそちらのほうの議論であった。
そこで、そう言った部分を中心に参考になったところを少し書いてみたい。そして自分が感じたことをコメントとして書きたい。
- 日本人が(海外の演奏家から)学ぶべきことは、とにかく演奏家が個性を持っているということ、これが実は大きなこと(中島p10)
- 金持ちでこういうことに(音楽)に金をまく人がふえるといい、ところが美術では松方コレクションとか、大倉とか、いるけど音楽にはどうして金が出ないのだろうね(吉田p20)
- 日本では新しいものというと、前のものをやめて新しいものをということになる、つまり革命ですよ、しかしヨーロッパでは、せいぜい進化だ、つまり前のものとの関係を全然断ち切ってしまうなんてことはない、新しいものだから良いというのはヨーロッパには通じないし、それが本物だと思い、そうでなければならないと考えています。文明というのは新しく変えなければならんと考えて、いつも日進月歩しているのは日本だけじゃないか、日本は古いものを徹底的にやっつけてしまう、古い、すなわち良くない、新しい、即ち良い、日本ではとかくそうです(吉田p69)
(コメント)その通りだと思う、明治維新では江戸の幕藩体制を否定した、昭和の敗戦後は戦前を軍国主義として否定した、その単純な発想が非常に危険だと思う。物事を単純化して黒か白かと決めつける発想から抜け出すことが日本の知的水準の向上のために必要だろう、吉田氏はそういうヨーロッパの知恵を指摘しているのだと思う。 - 日本の一般的な弊害というか、ある一つのところで成功すると同じルートをたどって店開きをしようとするわけですね、商社でも何でも。芸というものはあくまで個性なんだから、ある一つの形を同じように真似することが、害あって益ないということがあまりよくわからないじゃないか、日本はそれだから派閥なんかが発達する原因だろうと思う、同じような先生について同じような学びかたをしている、それじゃあまり意義がないと思いますね(園田p133)
- 外国から来た指揮者が日本のオーケストラは自発性がないと言うんですね、勘がすごく良くて、注文を出すとすごく敏感に反応するけれど、自発的な燃焼というものが足りない、これができたらすごく良いと思うんですけれどね、それは国民性もある(若杉p236)、国民性だったら直りっこないでしょう(吉田、P236)
(コメント)若杉氏がいう自発性や自発的な燃焼とは具体的にどういうことかはわからないが、仮に氏の言う自発性を持っていたとしても、外国から来た指揮者を前にそのような自発性をいきなり発揮することしないのが日本人だろうし、それは確かに国民性であろう。そして、それが悪いことだとは思わない。それは世界に誇るべき日本人としての奥ゆかしさである、信頼関係を構築しつつ徐々に自発性を出していくのが日本人であり、それは直すべきではないと思う。 - 日本の将来に育つべきオーケストラは、ある意味インターナショナルなものなっていくんじゃないかという気がする(若杉p232)、日本の方がローカルになるんじゃないか、日本というのはやっぱり非常に古い文化を持っている国ですから、日本の何千年の歴史を通して貫いている国民性というのはもっと深いところにあるわけですよ、それはなかなか変らないものがあるような気がするんです(吉田p232)
(コメント)若杉氏のインターナショナルというのは海外のオーケストラの音楽と取り入れて自分のものにし、ベートーベンもモーツアルトもドビュッシーもできるようになることを意味している一方、𠮷田氏は、インターナショナルとは日本の音楽が世界の音楽に影響を与えることができてこそインターナショナルと考えている、この違いで議論が少しかみ合わないところがあるように思えた。 - ジョセフ・コンラッドなんという人はポーランド人でイギリスに行って英語で書いた小説家だけれども、彼の作品は英国の文学の中でとっても大きな高い位置を占めている。なぜかというと英国人ではとても書けない、しかし間違っていない立派な英語を書くからだ(吉田p239)
(コメント)昨年読んだコンラッドの「闇の奥」(その感想を書いたブログはこちら)がこんなところで出てくるとは驚いた。 - 今でも終戦後に始ったいわゆる早期教育からきている技術偏重時代が続いている。外国から来るプレーヤーには、技術は随分ヘンテコでも、結構面白い音楽を聴かせる人が現にいくらでもいる、そういうのを押し出さないと音楽はつまらなくなってしまう、音楽とは本来そういう個性的なものであると言うふうにもっていく必要があるんじゃないか(柴田p250)
- ベートーベンの音楽にはやっぱり開放感があるんです、僕に取っては、それから非常に激励されるようなところがあるわけです(武満p268)
(コメント)良く言えばそういうことだと思うが、人によっては「人を扇動する危険な音楽」と評する場合もある(例えば、石井宏著「反音楽史」第3部第1章ベートーベンに象徴されるもの)、私もそういう気もしている - (日本の文化は)やっぱり「無」というところを目指していていたと思うんです、それはいまだに僕でさえそういうものに惹かれるし、憧れがある。けど、そこではやっぱり人間は生きられないね、だから、そのあとでまだ生きていこうとする人は、どうしてもニヒリストになるより仕方が無い気がするね、一番純粋で、おのれを虚しゅうすることのできそうな人こそ、もっとも危険なような気がしている(吉田p275)
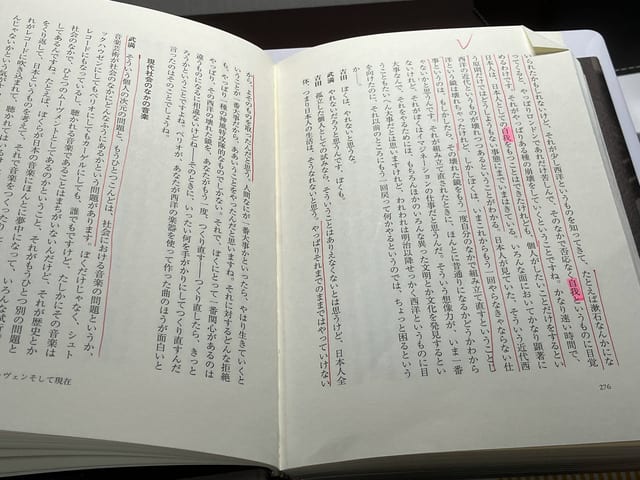
- (日本は近大西洋を手本にしてきて)日本人としての自我をもつことはできた けれども、個人がしたいことだけするという原則だけではどうしようもない事態にまできている(武満p275)。
(コメント)自我は持てたかもしれないが個人の自由のみ強調して規律や責任を論ぜず、日本らしらまでどんどん捨て去るような制度や思想の導入が事態の悪化を招いているのではないか。 - 戦争がいかに残虐で愚かなものであったかについて、今、みんなが語り出している、それはとても大事なことで、いかなる戦争も、愚かで非人間的なものであることは間違いないし、それを伝えることは正しい。けれども誤解を恐れずにいえば、それぞれの戦争には個別の「何か」があって、全ての戦争を「愚か」という一つの色で塗りつぶしてしまうと抜け落ちてしまうこともあるのではないか(吉田p305)
(コメント)その通りだと思う、戦前は軍国主義だったと黒色一色に塗りつぶす議論の乱暴さがが今の日本だ。物事はそんな単純ではないということでしょう。
いろいろ考えさせられるいい本であり、それぞれの対談の内容は深く、何度も読み返して理解を深めるべき本だと思った。









