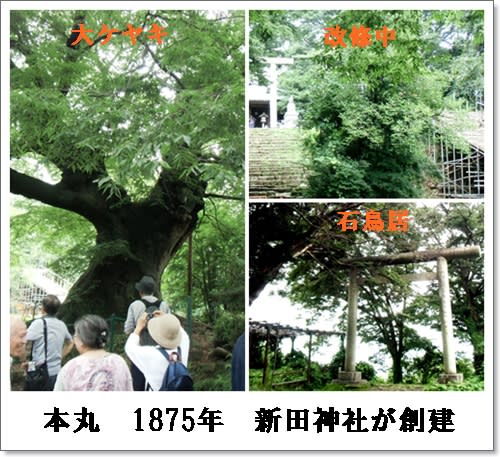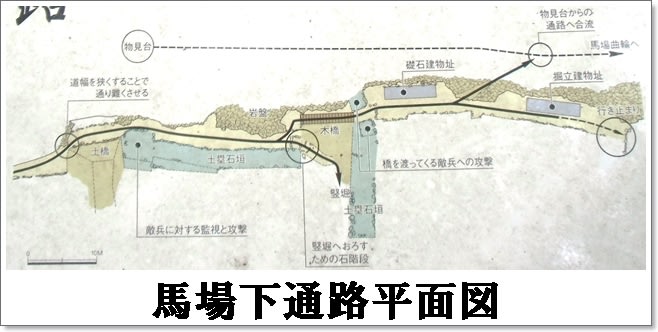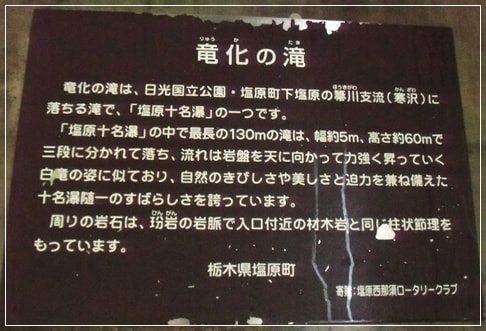手じかな 睡蓮沼は 思いつかず
地元紙の写真で見た 場所を調べて 行ってみた。
宇都宮市 上河内 羽黒山の 麓です。

白い スイレンが 多い。

赤いスイレンは 咲き始めなのか 水面の近くに 顔を出したのが見えた。

ピンクの スイレンも

沼の全景
四角い 沼に Tの字に 桟橋が作られ
交点には ベンチが 設置されていて
誰もいなくて 風が涼しかった。
地元で 一帯は 公園として 整備されていて
桜の季節は 花見も出来るようになっていた。
沼の周囲は アヤメも 咲くようです。
高速道路の すぐ近くで 県道沿いで 車も多いが
駐車スペースも有る 穴場です。
太陽光発電設備が 県道の 反対側に出来ていた。