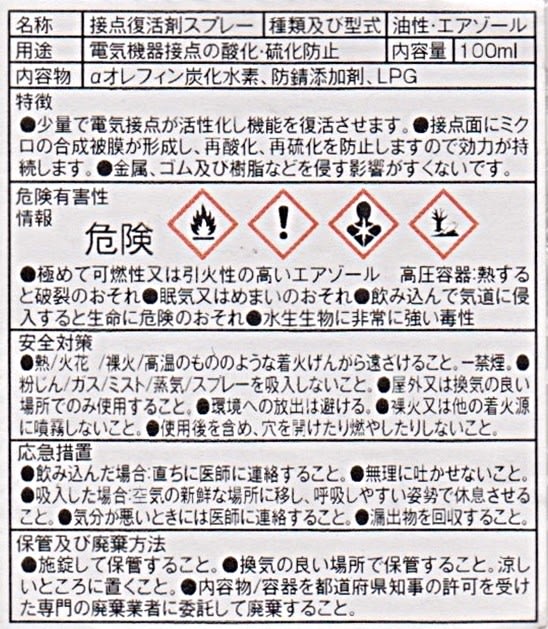ブログを 休んでいた 昨年 2017年の写真で すみませんが
あまりに 素晴らしかったので。
場所は 群馬県の 水沢観音。

巨大な本堂を 建築する為に
周囲の崖を 掘って広げて 建築する平らな場所を
確保したと思われます。
その 崖は 石積で 覆われているのですが
その 崖の 法面(のりめん)全体を ユキノシタが 覆っていて
しかも 真っ白に 開花中でした。
7月の 日差しが 強い日の 真昼でしたが
日差しを避け お堂の脇の 日蔭で 休もうか
として 発見!
数十メートルの幅で 高さは数メートル。

薄暗い部分ですので
三脚も 使用せず 撮影したので
コンデジの 露光不足と 手振れ気味で 残念ですが。
団体での 見学中でしたが
友人達を 招き寄せて 皆で 撮影しました。
本堂の脇に入った
見学コースからは 外れた場所ですが
宣伝しないのは もったいない 圧倒的な景観でした。
植物に 興味が 無い方にも ぜひお勧めしたい 景観です。
雪の下は 暗くて涼しい場所で 繁殖し
白い花が咲く 開花期には
思いがけない長さの 花柄(かへい)を伸ばします。
我が家でも 今 開花中です。