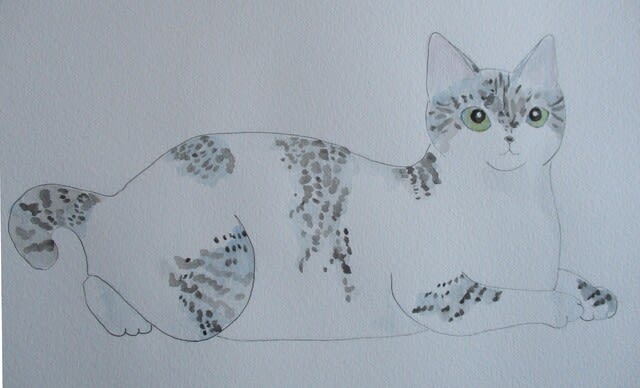夏になると思い出す風景がある。
二十代後半、友人に誘われてひまわり迷路に行った。いつも以上に暑い夏で、こんな時にわざわざ道に迷いに炎天下に行くバカがいるかと思ったが、ケガのために夢を断念して新しい道を模索している彼女の誘いを断る冷酷さなどあるわけはなかった。二十四歳の友人より年上だったが、私も挫折や諦めた夢、まだまだやれるような、今が踏ん切りどころのような、いくつかの問題を抱えていて、適格なアドバイスはできないと思った。だから、道に迷いながら思いのたけをすべてはきだしてもらい、それを受け止める夢の焼却炉にでも、ゴミ箱にでもなるつもりだった。
友人の車に乗せられて行った先は野菜の即売所で、ひまわり迷路は即売所に隣接する畑の持ち主が子供の遊び場として趣味で作ったとのことだった。
「サッカーコート二つ分ですって」
友人が言った。
「…倒れないようにしなきゃ」
迷路は片手を壁につけて歩いてゆけば必ず出口につくものだと知っていたが、そういうことをするために来たのではなかった。
友人が先に、私が後に続いた。並ぶには少し狭かった。
中に入るとみどりの匂いに包まれ、近くに人がいるはずなのにその気配が消えた。
「意外に涼しいですね」
「ひまわりの日陰だからかな」
なんとなくしゃべりながら歩く。身長百七十をこえる友人よりもはるかにひまわりの方が高いせいで迷路の中は日陰になり、ときおり吹く風は涼しかった。二人ともほとんど口をきかなかった。子供達がときおり、私達をぬかして行ったり、戻って来たりした。
蝶が舞い、蜂が耳をかすめ、足元にはトカゲが走りまわる。羽虫が群れをなして飛んでくるのを手でよけながら歩く。
小一時間もうろうろしただろうか。ようやく迷路から出ると、即売所でトマトやきゅうり、キャベツなどを買って、
「堤防に行きませんか?」
と友人が言ったのでそのまま堤防に行った。並んで座り、二人同時にトマトにかぶりつく。濃い味がする。
「トマトって、冷やさない方がおいしいよね」
「これ、朝採りって言ってましたね」
ここは、高校時代に同級生と座り込んではおしゃべりをした場所だ。海のない地方出身の友人は、最初につれて来た時、
「堤防って座れるんですね」
とか、花火の季節には、浜で打ち上げる花火を見ながら、
「花火の向こうに岸がないんですね」
などと、私にとっては当然のことに一つ一つ驚いていた。それから時々二人でこうしてここに座ったが、一人で来てぼうっと海を眺めることもあるそうだ。実家までほんの二時間ほどだが、元旦以外帰ることはないらしい。
満ち潮で堤防のすぐ下まで波がきていた。波の中に大きな海藻が揺れていて、小さな海の生き物がうごめいているのが見えた。
「あっ」
私の帽子が風にさらわれ、波に落ち、どんどんと沖に流されてゆく。
「あららあ、気に入ってたのに」
「どこまで行くかなあ」
しばらくして、友人がポケットから即売所で買った小袋を取りだし、
「ひまわりの種、来年用。半分こね」
と、ティッシュペーパーにざらざらと種を出し、くるんとまるめて私の膝に置いた。
「来年か… ひまわりの種は春植えだっけ」
私の問いには答えず、彼女が言った。
「発芽率八十パーセントですって。二十パーセントは芽をださないって、…多いのかな、少ないのかな」
「え…」
彼女は海を見つめたままひまわりの種の袋をポケットに無造作に突っ込んだ。
「芽を出さない種だって意味はありますよね」
「もちろんあるよ、絶対にあるよ」
「芽が出ても、花が咲かないこともあるし、実を結ばないこともある。全部意味がある」
友人はひとりごとのように言った。
「もちろん、そう。…百パーセントなんてないよ。ダニスプレーも、九十九パーセントダニ除去って書いてあるよ、百じゃないとこが正直って思うし、一パーセントは大切なんだよ、絶対に」
「ダニスプレー? はははは」
友人がようやく笑った。
「百って言われると嘘つけって思うけど、九十九なら、まあ、いいかなって思う」
「ですね。その一パーセントは重要ですよね」
「…おこることすべて重要なんだと思う」
自分に言い聞かせるように答える。
海が波打っている。
私の帽子はとっくに見えない。
二十代後半、友人に誘われてひまわり迷路に行った。いつも以上に暑い夏で、こんな時にわざわざ道に迷いに炎天下に行くバカがいるかと思ったが、ケガのために夢を断念して新しい道を模索している彼女の誘いを断る冷酷さなどあるわけはなかった。二十四歳の友人より年上だったが、私も挫折や諦めた夢、まだまだやれるような、今が踏ん切りどころのような、いくつかの問題を抱えていて、適格なアドバイスはできないと思った。だから、道に迷いながら思いのたけをすべてはきだしてもらい、それを受け止める夢の焼却炉にでも、ゴミ箱にでもなるつもりだった。
友人の車に乗せられて行った先は野菜の即売所で、ひまわり迷路は即売所に隣接する畑の持ち主が子供の遊び場として趣味で作ったとのことだった。
「サッカーコート二つ分ですって」
友人が言った。
「…倒れないようにしなきゃ」
迷路は片手を壁につけて歩いてゆけば必ず出口につくものだと知っていたが、そういうことをするために来たのではなかった。
友人が先に、私が後に続いた。並ぶには少し狭かった。
中に入るとみどりの匂いに包まれ、近くに人がいるはずなのにその気配が消えた。
「意外に涼しいですね」
「ひまわりの日陰だからかな」
なんとなくしゃべりながら歩く。身長百七十をこえる友人よりもはるかにひまわりの方が高いせいで迷路の中は日陰になり、ときおり吹く風は涼しかった。二人ともほとんど口をきかなかった。子供達がときおり、私達をぬかして行ったり、戻って来たりした。
蝶が舞い、蜂が耳をかすめ、足元にはトカゲが走りまわる。羽虫が群れをなして飛んでくるのを手でよけながら歩く。
小一時間もうろうろしただろうか。ようやく迷路から出ると、即売所でトマトやきゅうり、キャベツなどを買って、
「堤防に行きませんか?」
と友人が言ったのでそのまま堤防に行った。並んで座り、二人同時にトマトにかぶりつく。濃い味がする。
「トマトって、冷やさない方がおいしいよね」
「これ、朝採りって言ってましたね」
ここは、高校時代に同級生と座り込んではおしゃべりをした場所だ。海のない地方出身の友人は、最初につれて来た時、
「堤防って座れるんですね」
とか、花火の季節には、浜で打ち上げる花火を見ながら、
「花火の向こうに岸がないんですね」
などと、私にとっては当然のことに一つ一つ驚いていた。それから時々二人でこうしてここに座ったが、一人で来てぼうっと海を眺めることもあるそうだ。実家までほんの二時間ほどだが、元旦以外帰ることはないらしい。
満ち潮で堤防のすぐ下まで波がきていた。波の中に大きな海藻が揺れていて、小さな海の生き物がうごめいているのが見えた。
「あっ」
私の帽子が風にさらわれ、波に落ち、どんどんと沖に流されてゆく。
「あららあ、気に入ってたのに」
「どこまで行くかなあ」
しばらくして、友人がポケットから即売所で買った小袋を取りだし、
「ひまわりの種、来年用。半分こね」
と、ティッシュペーパーにざらざらと種を出し、くるんとまるめて私の膝に置いた。
「来年か… ひまわりの種は春植えだっけ」
私の問いには答えず、彼女が言った。
「発芽率八十パーセントですって。二十パーセントは芽をださないって、…多いのかな、少ないのかな」
「え…」
彼女は海を見つめたままひまわりの種の袋をポケットに無造作に突っ込んだ。
「芽を出さない種だって意味はありますよね」
「もちろんあるよ、絶対にあるよ」
「芽が出ても、花が咲かないこともあるし、実を結ばないこともある。全部意味がある」
友人はひとりごとのように言った。
「もちろん、そう。…百パーセントなんてないよ。ダニスプレーも、九十九パーセントダニ除去って書いてあるよ、百じゃないとこが正直って思うし、一パーセントは大切なんだよ、絶対に」
「ダニスプレー? はははは」
友人がようやく笑った。
「百って言われると嘘つけって思うけど、九十九なら、まあ、いいかなって思う」
「ですね。その一パーセントは重要ですよね」
「…おこることすべて重要なんだと思う」
自分に言い聞かせるように答える。
海が波打っている。
私の帽子はとっくに見えない。
(第62回 岐阜県 大垣市文芸祭 佳作)