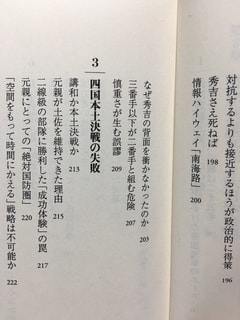新刊のご報告。
お待たせいたしました。
『戦国大名失敗の研究~群雄割拠編』(PHP文庫書下ろし)
発刊いたしました。

実は、最初の『戦国大名失敗の研究』を出した直後に、本作の依頼がありました。
その間、『幕末大名失敗の研究』を挟んで、ようやく完成。
今作のテーマは、「指導者と経営者」。
ある時代の、ある地域(領国)を経営した人物と、
その時代をつくり、日本全体にまで影響を及ぼした指導的人物の差はどこにあるのか。
伊達政宗、長宗我部元親、荒木村重、松永久秀、今川義元。
各々、スペインの独裁者・フランコ将軍や、大日本帝国、ヒトラーに対する各種反乱、第三次中東戦争などと比較をしながら、彼らが「群雄」で終わった理由をさぐりました。
歴史を眺めていると、
「なぜこの人が天下をとれなかったのか、政権を掌握できなかったのか」、
と疑問に思うことがよくあります。
伊達政宗はその好例で、
①政治家としての手腕
②軍の指揮官としての能力
③外交力
④人間としての器
いずれもすぐれていました。
権謀術数に長けた政宗でしたが、
敵に内応した家臣は鮎貝宗信のみで、
弟や母親との確執を含めても、戦国時代には珍しく安定政権を維持しました。
さらに。
政宗は伊達家の家督を継いでわずか五年余で、
伊達家史上最大の所領を得ます。
時に政宗、24歳。
そんな政宗が天下を掌握できなかった理由に、よく
「生まれるのが遅かった」説が多用されますが、
関ヶ原合戦時に、政宗はまだ34歳です。
徳川家康が豊臣秀頼に遠慮をし、正式な書類を出さずに恩賞としての領地を与えていた事実などから、関ヶ原合戦直後には、なお政治は流動的であったと見ることもできます。
その時に34歳という年齢は、若すぎず、また、老齢でもありませんでした。
このことを含め、「遅い誕生説」にはいくつかの疑問があります。
そのほかにも、地理的理由、周辺状況といった、政宗本人ではどうしようもない環境を、政宗が天を掌握できなかった理由に挙げられることが多く見られます。
筆者の見方は、やや違います。
そもそも伊達政宗の政治路線、政治手法に間違いはなかったのか。
秀吉に対するパフォーマンス(白装束や、金箔の十字架)が称賛されますが、本来は、こうしたパフォーマンスをしないでいいように行動するのが、あるべき政治ではないでしょうか。
つまり、選択肢を狭めないようにすること。
政宗は、狭められた選択肢の中で、「これだ!」と決め、実行する能力は高かったのですが、選択肢を多く持つことにあまり大きな関心がなかったのではないか、と思える事象がいくつもあります。
政治では、
選択肢を多く持つことが、とても重要だと思います。
追い詰められた末の決断は、あまり好結果が得られないことが多いからです。
筆者は、実力がありながら豊臣政権の中枢に入れなかった点など、
秀吉との関係性と、領土拡大の失敗、そして、遣欧使節の活用についての疑問を、
政宗の失敗の要因として記述しました。
第2章以下、次回またご紹介いたします。