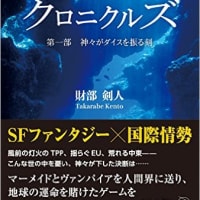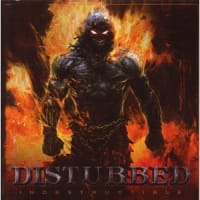一九九〇年十二月。
ナオミは、もう何ヶ月も気が気ではなかった。
八月のイラク大統領サダム・フセインによるクェート侵攻に端を発した国際情勢は、きなくささを増しつつあった。国連安保理事会の大量殺戮兵器の査察団の受け入れを拒否したイラクに対する多国籍軍による軍事介入は、時間の問題と見られていた。
いったん戦闘が始まれば、ケネスが従軍する可能性があった。
すでにシールズ教官として世界を飛び回っていたケネスをつかまえるのは不可能だったし、戦闘が始まってしまえば機密事項に関する「途中経過」を聞くことも出来なかった。
いらいらしながら待っていたナオミの学生寮の電話が、ある夜鳴った。
受話器を取る前から、ケネスからの電話だと確信があった。
「ケネス!?」
「ナオミ、元気か?」
「元気かじゃないでしょ。なぜずっと電話もくれなかったの」
「そう怒るな。お前だって身内が特殊工作部隊にいれば、便りのないのはよい便り(No news is good news.)だと知ってるだろう? 何かあれば家族にはまっさきに連絡が行く。あいにくな結果になっても何としてでも遺体が届けられる。遺体が届けられなくても遺族年金は必ずもらえる。つまり、俺たちは消耗品さ」
「何バカなこと言ってるの。便りのないのは頼りないだよ!(Undependable is unreliable.) まさか従軍が決まったの」
「何も言えることはないし正直なところ、まだ何もわからない。ただ、しばらく連絡が出来なくなるからな。一度とりあえず連絡をしておこうと思ってな」
「死ぬのはコワクないの?」
「国のために死ぬのはコワクない。俺たちがコワイのは政治家のバカな思惑で無駄死にすることだけだ」
「無駄死にって・・・・・・死んだら同じじゃない」
「俺たち特殊工作部隊員はいつでも死ぬ覚悟は出来ているし、苦しい訓練にも耐えてきた。お国のために役に立って死ぬのは本望さ。だけど、政治家の人気取りに使われるのはまっぴらさ」
「それなら、生きて返ってきて。約束して」
「心配するな。シールズの地獄週間(ヘル・ウィーク)はジャングルでの不眠不休のサバイバル・コンバットだ。俺はそれをトップでクリアしたエリートだ。ダイーバーズ・ハイを覚えているだろ。シールズ隊員(フロッグマン)は長時間の素潜りによる戦闘を要求される。海にずっと潜っていると体中が窒素でいっぱいになって脳が酸欠状態になる。そんな状態に陥ることで恍惚感を味わう現象がダイバーズ・ハイだ。何度もそうなるたびにお前の父親のマーライオンに会ってる。あれは幻視には思えない。いつもお前を頼むと言いやがる。何があっても必ず戻ってくる。これまでずっと生き残ってきたんだ。今度だって大丈夫さ。だけどな・・・・・・」
「だけど何?」
「鬼軍曹の役を演じるのも楽じゃないぜ。若い兵たちは大義のためならよろこんで命を捧げようとしやがる。自分が死ぬのはまだしも奴らを見送るのは正直ツライ」
「そんなにつらいんなら、やめちゃったら」
「どんなツライ仕事だとしても誰かに必要とされるのはわるいもんじゃない。それにこの役を降りたら誰かが引き継ぐことになる。どんなツライ仕事でも誰かが引き受けなきゃならないんだ。俺たちが降りたら独裁者やテロリストから誰が年寄りや女子供を守るんだ。理屈やへちまじゃないんだ。それに・・・・・・」
「何?」
「まだお前が俺の生きる理由だってわかってないのか」
それでもナオミには納得がいかなかった。
同時に、彼女は自分に人類を救うための闘いが近づいていることも知らなかった。

ランキング参加中です。はげみになりますので、以下のバナーのクリックよろしくお願いします!
![]() にほんブログ村
にほんブログ村![]()