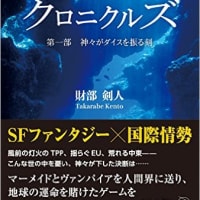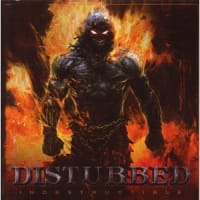強がりながらも夏海を失って、ケネスはすべてにどうでもよくなってしまった。
何をするわけでもなく飲んだくれているケネスにナオミが言った。
「ねえ、海に連れてって」
「うるせえ。そんなに行きたきゃ一人で勝手に行け。どうせクソ野郎に拾われたことを後悔してるんだろ。とっとと海の底に戻っちまえ!」
下を向いているナオミにケネスが言った。
「おい、自分でも口が悪いのはわかってるんだが、今のは言い過ぎた」
「違う・・・・・・」
「違うって何だ?」
「ナオミはね、ケネスを、元気づけられなくて悲しいんだよ」
今度はケネスがうつむく番だった。
「ねえ」
「何だ?」
「ナオミを拾って後悔してる?」不安を隠せない風に言った。
「バカ言ってんじゃねえ。こんないい子が他のどこにいるってんだ」
ケネスは照れ隠しにナオミの髪をクシャクシャにした。
「ウッキッキー! 海に行こうよ」猿まねをしながらナオミが言った。
「オッシャー、シーモンキー!」
ナオミを肩車するとケネスは海岸に走り出した。
実は、ナオミもケネス同様にショックを受けていた。
いつも水深数十メートルの素潜りをしていたナオミが、この日は水深百メートルを超えて海の底を目指してどこまでも潜っていった。
かつて限界四十メートルと言われた人間の閉塞潜水(素潜り)は、天才ダイバーのジャック・マイヨールによって一九七六年十一月十一日に百メートルの記録が作られていた。しかし、彼でさえ水深六十メートルを六六年に達成してから、水深七十メートルを達成するのに二年、百メートルまでには十年の歳月を要した。
禅やヨーガを学んだマイヨールは、「自然と寄り添い調和することで、初めて無限の可能性が生まれる」と語った。彼も海神界の血筋を引く人間の一人だったのかも知れない。
しかし、わずか十才にも満たない少女が百メートルの素潜りを達成したのは世に知られたなら世界的なニュースだったろう。
生命維持に必要な器官に血液を集中させて酸素を確保する「ブラッド・シフト」と呼ばれるイルカやアザラシのような水棲ほ乳類動物の特性が、元々マーメイドだったナオミには不要だった。
音もなく光さえほとんど届かない百メートルの深海が今日のナオミには心地よかった。
アッ、涙がでちゃう。
冷たい海中でもあたたかい涙が出るのがわかるのが意外だった。
その時、祖母トーミの声が聞こえた。

ランキング参加中です。はげみになりますので、以下のバナーのクリックよろしくお願いします!
![]() にほんブログ村
にほんブログ村
![]()