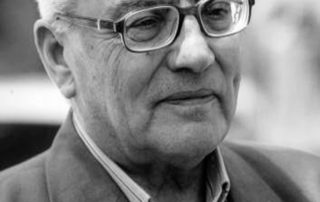CIAのマルウエアはiPhoneやアンドロイド系のスマートフォン、スマートTV、あるいはWindows、OSx、Linux、またWi-Fiルー ターに侵入、その情報を入手することができる。利用者が危機をオフにしたつもりでも、利用者に気づかれずオンにすることも技術的に可能だ。2015年にサ ムスンのスマートTVが利用者の会話をスパイしていると問題になったが、こうした危険性があることはインターネットに接続されている機器全てに当てはま る。
本ブログでは何度も書いてきたが、アメリカの情報機関は1970年代の前半から電子的な監視能力を保有している。エレクトロニクス技術が未発達だった時代には封書の開封工作が行われていたことも判明している。
電子的な監視システムについて日本では関心を持つ人が少なかったが、検察には興味を持つ人もいた。例えば、駐米日本大使館に一等書記官として勤務してい た原田明夫とその下で活動していた敷田稔だ。原田は法務省刑事局長(1996年)、法務事務次官(98年)、東京高検検事長(99年)を経て2001年に は検事総長になっていた。敷田は後の名古屋高検検事長だ。
ふたりが注目したのは不特定多数のターゲットに関する情報を収集、蓄積、分析するシステムのPROMIS。このシステムはアメリカの司法省や情報機関も 注目、法務省は1979年と80年に「研究部資料」として紹介している。こうしたシステムの危険性を話しても「有名ジャーナリスト」は聞く耳を持たなかっ た。
技術の発達は通信傍受を難しくすることも可能だが、そうした能力の発達を支配層は阻止、セキュリティ・レベルを下げさせてきた。例えば、1994年にア メリカでは盗聴を容易にするため、CALEA(法執行のための通信支援法)なる法律が制定されている。1993年から毎年、アメリカはヨーロッパ諸国の捜 査機関ともこの問題に関する会議を開催、日本政府も当然、アメリカの意向に従っている。勿論、住民基本台帳ネットワークも被支配層を監視するために使われ ることになるだろう。
PROMISは1970年代の後半に開発され、80年代には全世界で売られた。その際、開発した会社をアメリカの司法省は1985年に倒産させ、プログラムにトラップ・ドアを組み込んで情報を盗めるようにしていたと言われている。
この倒産は裁判になり、1988年2月にワシントン破産裁判所のジョージ・ベイソン判事は司法省が不正な手段を使って開発会社のINSLAWを破産さ せ、PROMISを横領したと認めた。翌年11月にはワシントン連邦地裁のウィリアム・ブライアント判事も破産裁判所を支持する判決を言い渡し、下院の司 法委員会も1992年9月に破産裁判所の結論を支持する内容の報告書を公表している。
その後、1997年8月に最高裁は司法省の言い分を認める判決を言い渡したが、そう判断する理由とされたのはイラン・コントラ事件で偽証して有罪になっ たロバート・マクファーレン、あるいは証券詐欺や銀行詐欺などでロサンゼルスの連邦地裁で有罪の評決を受けるアール・ブライアンという「信頼できる証人」 の証言だ。
その後も不特定多数のターゲットを追いかけ、分析するシステムの開発は進み、学歴、銀行口座の内容、ATMの利用記録、投薬記録、運転免許証のデータ、 航空券の購入記録、住宅ローンの支払い内容、電子メールに関する記録、インターネットでアクセスしたサイトに関する記録、クレジット・カードのデータなど あらゆる個人データを収集し、分析できるようになっている。
さらに、スーパー・コンピュータを使って膨大な量のデータを分析、「潜在的テロリスト」を見つけ出そうとする取り組みもなされていた。つまり、どのよう な傾向の本を購入し、借りているのか、どのようなタイプの音楽を聞くのか、どのような絵画を好むのか、どのようなドラマを見るのか、あるいは交友関係はど うなっているのかなどを調べ、分析し、国民ひとりひとりの思想、性格、趣味などを推測しようというのだ。当然、日本も同じ政策を推進中のはずで、共謀罪も リンクすることになる。
アメリカの支配層でも大きな力を持っている巨大金融資本は第2次世界大戦の前にナチスを資金面から支えていたことは何度も書いてきた。フランクリン・ ルーズベルトが大統領に就任すると、ニューディール派の排除とファシスト政権の樹立を目指すクーデターを目論んでいる。これは海兵隊のスメドリー・バト ラー少将が議会で明らかにしている。
その巨大金融資本が作り上げたのがCIAであり、大戦の終盤からナチスの科学者、元幹部、協力者を救出、逃亡させて保護、雇用もしている。1945年4 月、ドイツが降伏する前の月ににルーズベルト大統領が急死した後、ウォール街は主導権を奪い返した。それが日本の「右旋回」にもつながる。
アメリカでは戦後、人種差別に抗議する運動が広がり、そのリーダーだったマーチン・ルーサー・キング牧師は1967年4月4日、ベトナム戦争に反対する意思を鮮明に示す演説をした。テネシー州メンフィスで暗殺されたのは1年後の4月4日だ。
この暗殺が切っ掛けになってアメリカ各地で暴動が起こり、アメリカ軍は暴動鎮圧を目的とした2旅団(4800名)を編成したが、ケント州立大学やジャク ソン州立大学で学生に銃撃したことを受け、リチャード・ニクソン政権は1971年に解散させている。その間、令状なしの盗聴、信書の開封、さまざまな監 視、予防拘束などをFBIやCIAなどに許すという内容の法案も成立しそうになるが、これはジョン・ミッチェル司法長官がニクソン大統領を説得して公布の 4日前、廃案にしている。(Len Colodny & Tom Schachtman, “The Forty Years Wars,” HarperCollins, 2009)
このニクソンはウォーターゲート事件で失脚、ジミー・カーター政権になるとサミュエル・ハンティントンとズビグネフ・ブレジンスキーは共同で FEMA(連邦緊急事態管理庁)を組織した。この延長線上に一種の戒厳令プロジェクトであるCOGがあり、2001年9月11日の攻撃を口実にして始動、 愛国者法も成立している。アメリカのファシズム化は第2次世界大戦の前から進められてきたとも言えるだろう。そうしたプランの下で、CIAやその影響下に ある有力メディアは動いている。
もっとも、昨年からアメリカでは民主党や有力メディアは証拠を示すことなく、ロシア政府がドナルド・トランプを支援するためにハッキングしていると叫び続けている。こうしたテクニックを使った工作ではなく、単なる「お話」を流しているにすぎないということだ。
有力メディアの「報道」が正しいなら、彼らはCIA、司法省、財務省などから情報の提供を受けているはずだが、情報公開法に基づいてその件に関する資料の公開を求めても拒否されている。こうしたことから、CIA、司法省、財務省を訴える団体が出て来た。
ところが、先日、トランプ大統領がバラク・オバマによる自分に対するハッキングに言及したところ、有力メディアは「証拠がない」と連呼している。天に向かってつばを吐く行為だ。顔につばが降り注いでも気づかないかもしれないが。
アメリカの電子情報機関NSAが世界規模で通信を傍受し、情報を蓄積、分析していることは1970年代から指摘されている。電子技術の進歩に伴い、そうした情報活動は大規模になってきた。
NSAの存在は1972年8月号のランパート誌に掲載された内部告発で明らかになり、イギリスのGCHQについては、76年にダンカン・キャンベルと マーク・ホゼンボールがタイム・アウト誌で詳しく書いている。ちなみに、この記事が原因でアメリカ人のホゼンボールは国外追放になり、キャンベルは治安機 関MI5から監視されるようになった。キャンベルは1988年8月に地球規模の通信傍受システム、ECHELONの存在も明らかにしている。
NSAとGCHQは緊密な関係にあり、UKUSA(UKとUSA/ユクザ)と呼ばれる連合体を作り、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアの情報機 関を従えて活動している。こうした連合体を編成する目的のひとつは、各国の法律の規制を逃れることにある。自分たちが調べられないターゲットを別の国に頼 むわけだ。
この5カ国は英語圏、あるいはアングロ-サクソン系ということでまとまっているのだが、さらにイスラエルの8200部隊も手を組んでいる。この8200部隊とNSAはイランの核関連施設を攻撃するためにコンピュータ・ウィルス、つまり侵入したコンピュータ・システムに関する情報を入手して外部に伝えるFlameとそのプラグインであるStuxnetを感染させたことがある。この攻撃をニューヨーク・タイムズ紙が初めて伝えたのは2012年6月のことだが、ウイルスが発見されたのは10年のことだった。発見が遅れたなら深刻な核事故が起こっていた可能性が高く、核攻撃に準ずる行為だと言えるだろう。日本も人ごとではない。