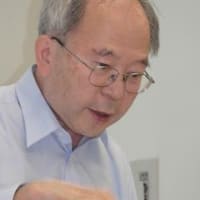2006年3月24日
戦略情報研究所講演会
惠谷治氏講演
米軍対北朝鮮軍事作戦と拉致被害者救出作戦より、
―――――――――――――――――――――
自衛隊による日本人拉致被害者救出作戦の核心
―――――――――――――――――――――
国家の意思と能力
さて、我が自衛隊による救出作戦の活動についてですが、今日の席はシュミレーション講座とありますが、
私も個人的にはそういう作戦を考えるのは大好きなので、色々考えました。
しかしまてよと。どなたでもこの救出作戦を感あげるとぶち当たるのが、ここに最初に書きました、国家の意思と能力といういわば政治の問題です。
本当に、これまでの日本を見ていますと、日本人を救う意志があるのか無いのかというふうに非常に疑問に思います。
個人の経験も含めて、戦後、軍ががなくなったあと、いわば外務省が一等官庁になって、【法人保護という認識がなかった】と、こう私は断言します。
ひとつ実例でいえば、みなさんも経験があるかもしれませんが、国外の大使館に行って、大使館員の対応を見れば、これはあきらかです。
普通にブザーをならしてはいれば、本当に自国民を守る気概があるのかと言いたいぐらいの対応です。
しかし一方で、誰かの紹介があれば、大使が「晩飯を」というぐらいの態度の変わり様を、私も何度も経験したことがあります。
それは別として、戦後日本は敗戦というショックから立ち直ったにも関わらず、国家というものを、どのような方向に持って行くかということが何ら討議されずに、今日まで来ました。
その、いちばん明らかな証拠が、防衛庁と自衛隊を曖昧な状況においたままだと言うことです。
防衛庁が防衛省になりそうだと、今年はなるんじゃないかと思っていたんですが、別の不祥事がでまして先送りになったと言うこともあります。
これは名前だけ、形式の問題でありますが、一番大事な、最大の問題は、日本という国を、世界でどういった位置づけにするのか、あるいは国をどうするのか。
九軍は国体を守るといいながら、住民をどかして自分たちが陣地を敷いたということも実際ありました。
とにかく国を守る、あるいは、国民を守るということが、どういう事かと考えれば、拉致被害者を救出すると言うことは、ごくごく当たり前のことでございます。その発想すら、及ばない。
小泉首相は「対話と圧力」と常に寝言を言っております。「圧力とは何か」と。
外務省の役人は「それは米軍である」と。
そう言うことを平然と言ってのける日本というのは、情けなくなります。
そう言いながらも、すこしづつすこしづつ、自衛隊の組織も変わり、国民の理解も変わり、もう今や、・・や研究は普通にできるようになりました。
作戦研究はというのは、どんどんすべきでありまして、そう言った中で、ここの2行目に書いてある<特種部隊による作戦>と<特殊作戦>この違いを認識していただきたいと思うわけです
テレビその他で言う特種作戦というと何かと言えば、当然特別な作戦と言うことです。
特殊部隊が、まぁ、我が自衛隊にも特殊作戦軍があります。彼らが行う作戦というのは、当然みなさん想像できるでしょう。
ところが<特種作戦>というのはそう言うことではないのです。
いわゆる、特種作戦軍が行う作戦というのは、当然、まぁ、日本で言えば、自衛隊法、あるいは、国際法に則った作戦です。
ところがそれに当てはまらない。つまり国境侵犯をせざるを得ない。しかし、自国民が窮地に陥っている。であれば、どうやってそれをやるのか、といったことを考えてやるのが<特種作戦>。つまりその場合には、身分も全て、軍籍からはずして、それで特別なことを、国家の意思でやるということ。これが特種作戦です。
ですから、特種作戦と特種作戦軍による作戦とは、全く違う。
この日本人拉致救出作戦という事のは、特種作戦でない限りできない。
これは、どこの国も、宣戦布告をしない限り、国境を侵犯すると言うことですから、国際法違反をするということ。
過去の実例をあげれば、ウガンダ、エンテベ空港にいるイスラエル人を救出した例、あるいは失敗しましたけれど、米軍がイランに入った例、これは文字通り特種作戦。
この違いを、明確に区別しないと、まず作戦の・・・がわからない。と同時に、この日本が、あるいは日本政府がどこまで判断できるかという問題に関わってくる。そうしますと、戦後自衛隊、防衛庁というものが曖昧なままでおいてきた、この国がですね、いきなり特種作戦ということは、これは不可能です。
特種作戦軍による作戦、これはやっと国民の理解も得られ、できるでしょう。作戦軍の側は、そう言う意味でいつ命令が下っても、それなりにできる用意はあると思います。しかし、それは、全て政府が決定することであります。
そうではなくて、政府が決定するんですが、「これは特種作戦であって、君たちが自衛隊から除籍する、個人の資格でやってほしい」というところまで決断なんていうのは、これは政府にはとてもできない。
逆に言えば、拉致救出作戦というのは、まずシュミレーションとしてはできますけれども、政府の決断としてはできないということです。
しかし、別に絶望することではなくて、大事なことはですね、特種作戦ではなく、特種作戦軍が動くケースというのを想定して、あらゆる事の備える。そのチャンスが先ほど最初に言いました、5029が発動されたときです。
つまり今北朝鮮でクーデターが起きて混乱が起きているときに米軍との連携で自衛隊が出動する。これはいろいろ難しい法的問題もありますが、しかし、先ほど言った特種作戦を決断するよりは政府も容易にできるだろうというふうに思います。
一方で、私はこの作戦シュミレーションをいろいろ考えてきましたが、一番大事なところはですね、作戦シュミレーションはいわば、ある設定をして、それはできないことはないんですが、やはり一人ないしは数人を救出するのか、あるいは十数人を救出するのかで、もう、この作戦内容は全く変わってきます
ですからこの救出対象をまず設定しない限り、やはり具体的シナリオというのは組み立てられない。そう言ったときに、ここに書きました情報収集の最大のポイントは<位置確認>これは誰でも考えつくと思います。
次ぎに、<意思確認>このほうが重要で、これが見落とされがちということです。つまりそこに拉致された日本人がいることが明らかになる。そこにいきなりパラシュートが降りていき、「日本から救出に来ました」と言ったところで、心の準備もなければ、「じゃぁ、家に帰りたい」、だけど、もう彼らは何十年もそこに生活基盤がありますから、親しい人、いろんな方があるでしょう。ですから、拉致被害者がそこにいることが確認できたら、次ぎに大事なことは、彼らが帰りたいのは当然ですが、帰るに当たって誰々を連れて帰る、これのよってまた作戦はずいぶん変わってきます。
「貴方だけか」「子供だけか」「そのことはこちらの方からできますよ」おばあちゃんと一緒じゃないと帰りたくないと要求する、それを確認しない限り、この作戦は、絶対に成功しません。
となれば、対象と接触して、長いコミュニケーションをとって「本当に帰りたいんだ」「何人なんだ」「誰々なんだ」ということが確認できてはじめて作戦が動き出す。
つまり何人か、そこに老人がいれば、それなりのことをしなければならない。そうすると、一概に拉致人質救出作戦といっても、その状況状況で、無数に変わってきます。ヘリに乗せて、あるいは、荒波を超えるときに、子供達がそれにもつのか持たないのかも含めてですね、とにかくそれによって装備からすべて変わってくる。
作戦軍に対してですね、「何でも良いから、特定をしてこうしろ」と言われても、現実問題として、全く違う作戦にならざるを得ない。
それからもう一つ私がいつも思うことは、特種作戦、一般的に、肉体的、精神的、サバイバル能力も含めてたことは十分訓練でできます。
しかし、私は今日本で一番欠けていることは<国際感覚>。
ですから私は作戦軍の人間は、とにかく暇があれば、海外に行く、個人の旅行でもいいし、あるいは班での研修でも良いし、とにかくあちこちに行って、言葉で言うところの<見聞を広げる>と言いますか、それが一番大切なことだと私は思います。はじめて外国に行くとか言う連中は、作戦と言っても、そんなのうまくいく訳がない。
これは、欧米の特種作戦部隊とは全く違います。もう彼らは世界中を、隣町のように動いています。もちろん、親類係累があちこちにいるというのもありますが。そう言った中で、様々の文化の違い、その他を理解して、いざというときに役立てる。
まだまだ自衛隊も役所ですからそう言うところに行くというのは、認めないのかもしれませんが、とにかく、そういう隊員も普段からですねいろいろ(な国に)行って、研鑽に励んでもらいたいと思います。
次の、軍事オペレーションというのは、これはまぁ、みなさんもイメージする、あるいは、作戦軍であれば、それなりに、イメージする、組み立てる、これが一番基本的には大事になるんですが、まぁ、ここはできるんです。
ここに敢えて米軍との連携と書きましたが、これは、例の衛星通信とか、米軍にしか頼らざるを得ないという部分がありますから、当然ですが。まぁ、単なるオペレーション、それに伴うロジックその他というのは十分作戦軍はできると考えています。
で、先ほど言った、特種作戦に当たって、何より独身であるとか、あるいは、こういう特技があるとか、あるいはこうだ、とかいうふうに絞り込んで、本来の意味での自衛隊を除隊したことにしてですね、というようなある意味での<特種作戦>ができるようにまでなってもらえればと思います。
訓練も同じですが、その時に、常に、どういうケースでもありうるということを想定して頂ければと思いますが。
とにかく常時体制、これはもう、軍というものは、いつ命令が下っても対応できるように、日常に、シュミレーションその他を研究している。それが三谷研究の騒ぎ以来できなかったと言うことでありまして、もう今やできますから。今の状況では、「ここまでできます」という風に、特にこの人質救出というのは、このバリアがとれれば動けるんですと言ったところまで、やっておくべきだというふうに思います。
それから最後の、<秘密保全>これ何故敢えて書いたかと言いますと、私は人質救出作戦というのは、本気でやるのであれば、本来の意味での、<特種作戦>にしかできない。
そう言う決断ができる大物政治家が首相になれるのかどうかわかりませんが、それしかできないとなるとですね、その決断する首相と、ことに官房長官、自衛隊のオペレーションを遂行する部隊をですね、政府内部でも数人、10人ぐらいしか知らない、そう言った中で警察庁にはどの段階まで言っておくかとか、いろいろ本当に政治の駆け引きと言うことになりますが。
まず、大事なことは、外務省には一切つたえないこと。
これは基本中の基本、ところがなかなか政治というのはそうはいかない。
だけれども、秘密保全を考えれば、これは基本です。
とにかく可能な限り少なくする。しかし少なくすれば、それだけ運用はうまくいかないでしょうから、非常に難しいけれども、とにかく拉致被害者の救出作戦を考えれば、特種作戦を前提に、そうすると秘密保全というのをどこまで絞って、それで実際特種作戦軍が動けるのか、あるいは特種作戦軍から何人を抽出するのかを、あるいはそう言う作戦というのを、伏せながら、海空(海自・空自)が、現場地域に何ら疑問も持たずに配備されるという、こういったことが必用になる。
ですからシュミレーションというのは、もちろんいろんなシュミレーションができますから、今日ここで、平壌に報告が行く人もいるでしょうから、具体的に話しができないんですが、まぁ、考えられるというのは、大きな声で話市ができるというのは、ここまでということにして、あとは質問でやっていきたいと思います。
(拍手 講演終了、質疑応答へ)
◆―――――――――――――――――――――――――◆
この記事が参考になった方は、下記バナーをクリックしてください。

戦略情報研究所講演会
惠谷治氏講演
米軍対北朝鮮軍事作戦と拉致被害者救出作戦より、
―――――――――――――――――――――
自衛隊による日本人拉致被害者救出作戦の核心
―――――――――――――――――――――
国家の意思と能力
さて、我が自衛隊による救出作戦の活動についてですが、今日の席はシュミレーション講座とありますが、
私も個人的にはそういう作戦を考えるのは大好きなので、色々考えました。
しかしまてよと。どなたでもこの救出作戦を感あげるとぶち当たるのが、ここに最初に書きました、国家の意思と能力といういわば政治の問題です。
本当に、これまでの日本を見ていますと、日本人を救う意志があるのか無いのかというふうに非常に疑問に思います。
個人の経験も含めて、戦後、軍ががなくなったあと、いわば外務省が一等官庁になって、【法人保護という認識がなかった】と、こう私は断言します。
ひとつ実例でいえば、みなさんも経験があるかもしれませんが、国外の大使館に行って、大使館員の対応を見れば、これはあきらかです。
普通にブザーをならしてはいれば、本当に自国民を守る気概があるのかと言いたいぐらいの対応です。
しかし一方で、誰かの紹介があれば、大使が「晩飯を」というぐらいの態度の変わり様を、私も何度も経験したことがあります。
それは別として、戦後日本は敗戦というショックから立ち直ったにも関わらず、国家というものを、どのような方向に持って行くかということが何ら討議されずに、今日まで来ました。
その、いちばん明らかな証拠が、防衛庁と自衛隊を曖昧な状況においたままだと言うことです。
防衛庁が防衛省になりそうだと、今年はなるんじゃないかと思っていたんですが、別の不祥事がでまして先送りになったと言うこともあります。
これは名前だけ、形式の問題でありますが、一番大事な、最大の問題は、日本という国を、世界でどういった位置づけにするのか、あるいは国をどうするのか。
九軍は国体を守るといいながら、住民をどかして自分たちが陣地を敷いたということも実際ありました。
とにかく国を守る、あるいは、国民を守るということが、どういう事かと考えれば、拉致被害者を救出すると言うことは、ごくごく当たり前のことでございます。その発想すら、及ばない。
小泉首相は「対話と圧力」と常に寝言を言っております。「圧力とは何か」と。
外務省の役人は「それは米軍である」と。
そう言うことを平然と言ってのける日本というのは、情けなくなります。
そう言いながらも、すこしづつすこしづつ、自衛隊の組織も変わり、国民の理解も変わり、もう今や、・・や研究は普通にできるようになりました。
作戦研究はというのは、どんどんすべきでありまして、そう言った中で、ここの2行目に書いてある<特種部隊による作戦>と<特殊作戦>この違いを認識していただきたいと思うわけです
テレビその他で言う特種作戦というと何かと言えば、当然特別な作戦と言うことです。
特殊部隊が、まぁ、我が自衛隊にも特殊作戦軍があります。彼らが行う作戦というのは、当然みなさん想像できるでしょう。
ところが<特種作戦>というのはそう言うことではないのです。
いわゆる、特種作戦軍が行う作戦というのは、当然、まぁ、日本で言えば、自衛隊法、あるいは、国際法に則った作戦です。
ところがそれに当てはまらない。つまり国境侵犯をせざるを得ない。しかし、自国民が窮地に陥っている。であれば、どうやってそれをやるのか、といったことを考えてやるのが<特種作戦>。つまりその場合には、身分も全て、軍籍からはずして、それで特別なことを、国家の意思でやるということ。これが特種作戦です。
ですから、特種作戦と特種作戦軍による作戦とは、全く違う。
この日本人拉致救出作戦という事のは、特種作戦でない限りできない。
これは、どこの国も、宣戦布告をしない限り、国境を侵犯すると言うことですから、国際法違反をするということ。
過去の実例をあげれば、ウガンダ、エンテベ空港にいるイスラエル人を救出した例、あるいは失敗しましたけれど、米軍がイランに入った例、これは文字通り特種作戦。
この違いを、明確に区別しないと、まず作戦の・・・がわからない。と同時に、この日本が、あるいは日本政府がどこまで判断できるかという問題に関わってくる。そうしますと、戦後自衛隊、防衛庁というものが曖昧なままでおいてきた、この国がですね、いきなり特種作戦ということは、これは不可能です。
特種作戦軍による作戦、これはやっと国民の理解も得られ、できるでしょう。作戦軍の側は、そう言う意味でいつ命令が下っても、それなりにできる用意はあると思います。しかし、それは、全て政府が決定することであります。
そうではなくて、政府が決定するんですが、「これは特種作戦であって、君たちが自衛隊から除籍する、個人の資格でやってほしい」というところまで決断なんていうのは、これは政府にはとてもできない。
逆に言えば、拉致救出作戦というのは、まずシュミレーションとしてはできますけれども、政府の決断としてはできないということです。
しかし、別に絶望することではなくて、大事なことはですね、特種作戦ではなく、特種作戦軍が動くケースというのを想定して、あらゆる事の備える。そのチャンスが先ほど最初に言いました、5029が発動されたときです。
つまり今北朝鮮でクーデターが起きて混乱が起きているときに米軍との連携で自衛隊が出動する。これはいろいろ難しい法的問題もありますが、しかし、先ほど言った特種作戦を決断するよりは政府も容易にできるだろうというふうに思います。
一方で、私はこの作戦シュミレーションをいろいろ考えてきましたが、一番大事なところはですね、作戦シュミレーションはいわば、ある設定をして、それはできないことはないんですが、やはり一人ないしは数人を救出するのか、あるいは十数人を救出するのかで、もう、この作戦内容は全く変わってきます
ですからこの救出対象をまず設定しない限り、やはり具体的シナリオというのは組み立てられない。そう言ったときに、ここに書きました情報収集の最大のポイントは<位置確認>これは誰でも考えつくと思います。
次ぎに、<意思確認>このほうが重要で、これが見落とされがちということです。つまりそこに拉致された日本人がいることが明らかになる。そこにいきなりパラシュートが降りていき、「日本から救出に来ました」と言ったところで、心の準備もなければ、「じゃぁ、家に帰りたい」、だけど、もう彼らは何十年もそこに生活基盤がありますから、親しい人、いろんな方があるでしょう。ですから、拉致被害者がそこにいることが確認できたら、次ぎに大事なことは、彼らが帰りたいのは当然ですが、帰るに当たって誰々を連れて帰る、これのよってまた作戦はずいぶん変わってきます。
「貴方だけか」「子供だけか」「そのことはこちらの方からできますよ」おばあちゃんと一緒じゃないと帰りたくないと要求する、それを確認しない限り、この作戦は、絶対に成功しません。
となれば、対象と接触して、長いコミュニケーションをとって「本当に帰りたいんだ」「何人なんだ」「誰々なんだ」ということが確認できてはじめて作戦が動き出す。
つまり何人か、そこに老人がいれば、それなりのことをしなければならない。そうすると、一概に拉致人質救出作戦といっても、その状況状況で、無数に変わってきます。ヘリに乗せて、あるいは、荒波を超えるときに、子供達がそれにもつのか持たないのかも含めてですね、とにかくそれによって装備からすべて変わってくる。
作戦軍に対してですね、「何でも良いから、特定をしてこうしろ」と言われても、現実問題として、全く違う作戦にならざるを得ない。
それからもう一つ私がいつも思うことは、特種作戦、一般的に、肉体的、精神的、サバイバル能力も含めてたことは十分訓練でできます。
しかし、私は今日本で一番欠けていることは<国際感覚>。
ですから私は作戦軍の人間は、とにかく暇があれば、海外に行く、個人の旅行でもいいし、あるいは班での研修でも良いし、とにかくあちこちに行って、言葉で言うところの<見聞を広げる>と言いますか、それが一番大切なことだと私は思います。はじめて外国に行くとか言う連中は、作戦と言っても、そんなのうまくいく訳がない。
これは、欧米の特種作戦部隊とは全く違います。もう彼らは世界中を、隣町のように動いています。もちろん、親類係累があちこちにいるというのもありますが。そう言った中で、様々の文化の違い、その他を理解して、いざというときに役立てる。
まだまだ自衛隊も役所ですからそう言うところに行くというのは、認めないのかもしれませんが、とにかく、そういう隊員も普段からですねいろいろ(な国に)行って、研鑽に励んでもらいたいと思います。
次の、軍事オペレーションというのは、これはまぁ、みなさんもイメージする、あるいは、作戦軍であれば、それなりに、イメージする、組み立てる、これが一番基本的には大事になるんですが、まぁ、ここはできるんです。
ここに敢えて米軍との連携と書きましたが、これは、例の衛星通信とか、米軍にしか頼らざるを得ないという部分がありますから、当然ですが。まぁ、単なるオペレーション、それに伴うロジックその他というのは十分作戦軍はできると考えています。
で、先ほど言った、特種作戦に当たって、何より独身であるとか、あるいは、こういう特技があるとか、あるいはこうだ、とかいうふうに絞り込んで、本来の意味での自衛隊を除隊したことにしてですね、というようなある意味での<特種作戦>ができるようにまでなってもらえればと思います。
訓練も同じですが、その時に、常に、どういうケースでもありうるということを想定して頂ければと思いますが。
とにかく常時体制、これはもう、軍というものは、いつ命令が下っても対応できるように、日常に、シュミレーションその他を研究している。それが三谷研究の騒ぎ以来できなかったと言うことでありまして、もう今やできますから。今の状況では、「ここまでできます」という風に、特にこの人質救出というのは、このバリアがとれれば動けるんですと言ったところまで、やっておくべきだというふうに思います。
それから最後の、<秘密保全>これ何故敢えて書いたかと言いますと、私は人質救出作戦というのは、本気でやるのであれば、本来の意味での、<特種作戦>にしかできない。
そう言う決断ができる大物政治家が首相になれるのかどうかわかりませんが、それしかできないとなるとですね、その決断する首相と、ことに官房長官、自衛隊のオペレーションを遂行する部隊をですね、政府内部でも数人、10人ぐらいしか知らない、そう言った中で警察庁にはどの段階まで言っておくかとか、いろいろ本当に政治の駆け引きと言うことになりますが。
まず、大事なことは、外務省には一切つたえないこと。
これは基本中の基本、ところがなかなか政治というのはそうはいかない。
だけれども、秘密保全を考えれば、これは基本です。
とにかく可能な限り少なくする。しかし少なくすれば、それだけ運用はうまくいかないでしょうから、非常に難しいけれども、とにかく拉致被害者の救出作戦を考えれば、特種作戦を前提に、そうすると秘密保全というのをどこまで絞って、それで実際特種作戦軍が動けるのか、あるいは特種作戦軍から何人を抽出するのかを、あるいはそう言う作戦というのを、伏せながら、海空(海自・空自)が、現場地域に何ら疑問も持たずに配備されるという、こういったことが必用になる。
ですからシュミレーションというのは、もちろんいろんなシュミレーションができますから、今日ここで、平壌に報告が行く人もいるでしょうから、具体的に話しができないんですが、まぁ、考えられるというのは、大きな声で話市ができるというのは、ここまでということにして、あとは質問でやっていきたいと思います。
(拍手 講演終了、質疑応答へ)
◆―――――――――――――――――――――――――◆
この記事が参考になった方は、下記バナーをクリックしてください。