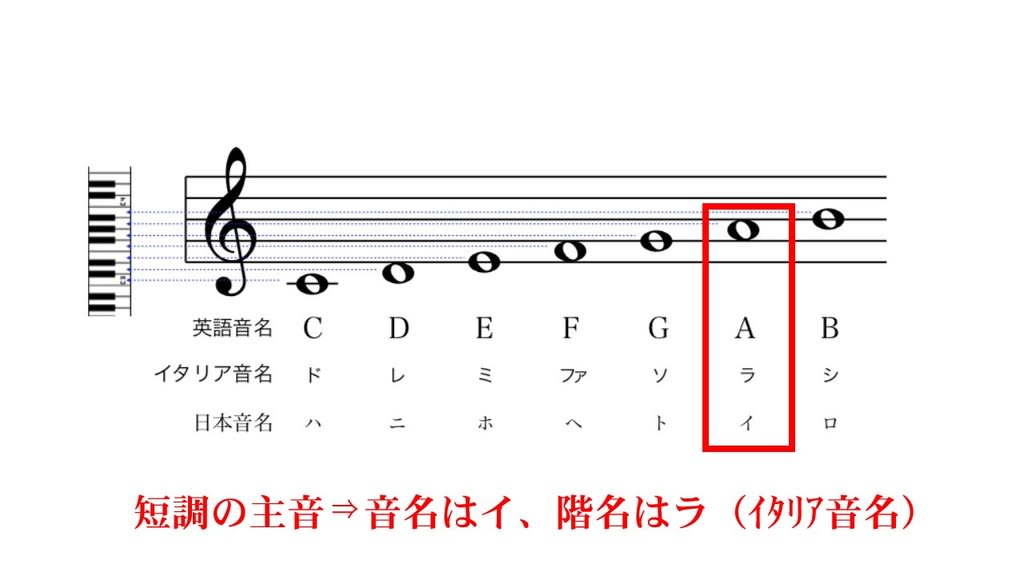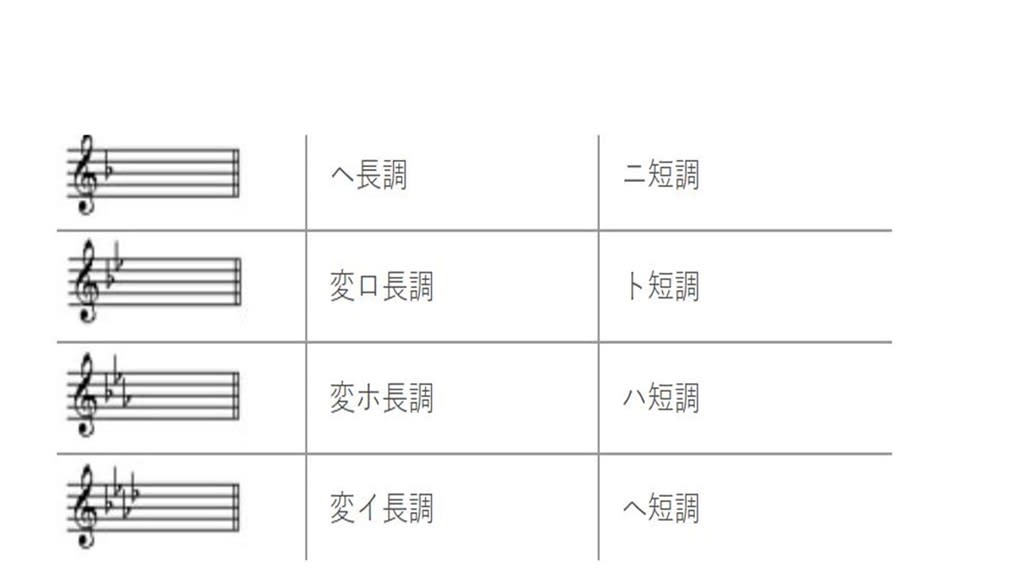母の実家は、桧原村という自然豊かな美しい村で、夏休みには電車やバスで遊びに行くのが楽しみだった。そこには、祖父や仲良しの従兄たちがいた。
祖父は、山師、と言っていわゆる「木こり」だった。納屋にはクジラの赤ん坊のような形をしたギザギザ歯の鋸がいくつも壁に掛けてあった。床には木っ端やおが屑が所々落ちていた。
ぶっきら棒で無骨な祖父は、僕の顔を見ても「おうっ。」とだけ言って、仕事の手を休めなかった。それでも僕は、祖父が背中を丸めて大きな木を切っている姿が好きだった。たくましくて、強そうで、鋸がみるみる木の内部に切り込んでいくのを見て気持ちがよかった。
小学校6年生の夏休みも、お盆が近づくといつものように電車やバスを乗り継いで田舎へ行った。待っていてくれた従兄たちと、近くの川に釣りに行ったり、裏山にセミやカブトムシを取りに行ったり、夜には盆踊りに参加して、楽しく過ごした。
帰る日、納屋で仕事をしているお爺さんに挨拶した。
「今度、いつ来られそうじゃ。」
「そうだな、お正月はお父さんほうの実家に行くし、春休みは、中学校の入学準備があると思うからまた、来年の夏休みに来るよ。」
「そうか、じゃあ達者でいろや。」
そう言うと、腰に下げた巾着袋から皮の財布を取り出し、中にあったきれいな500円札を出した。
「これで、何か好きな物を買え。中学校へ行くんじゃからしっかり勉強せにゃな。」
お札を差し出した手は真っ黒に日焼けして、しわだらけ、傷だらけで、親指の爪は真ん中が途中まで縦に割れていた。僕はうまい言葉が見つからず、それでも精一杯の感謝の気持ちを表そうと思い、両手でお爺さんの手を包み込むようにしてお札を受け取った。ざらざらな手だったが、お爺さんの心のように温かく感じた。
「どうもありがとう。お爺さんも元気でね。」と言い、しわ一つない500円札を持ってきた日記帳に挟んで帰った。
2学期が始まり、運動会、写生会、社会科見学、修学旅行と、楽しい行事が続き、田舎のことはあまり思い出さなかった。そのころから、授業でシャープペンシルを使う友達が何人かいて、それがめずらしく、だんだん使用者が増えていった。当時のシャープペンシルは、上の部分を回して芯を出すのもので、今のようにノック式ではなかったが、僕も欲しくなってきた。放送委員会の取材で図書室へ行って調べ物をする時や社会科見学でメモを取る時も便利だと思った。持っている友達に値段を聞くと500円だった。その金額を聞いて、お爺さんにもらったお金が頭に浮かんだ。
「シャープペンシル、買っていいかな。みんな使ってるし、便利だと思うんだけど・・・。」
「お母さんは、まだ早いと思うけどね。鉛筆でしっかり字を書いて、きちんとノート取ることのほうが大事じゃないの。」
「普段はみんなも鉛筆がほとんどだよ。でもちょっと記録したり、見学の時メモを取ったり、便利な時もあるんだよ。ねー、お爺さんにもらったお金で買うからいいでしょう?」
「まあ、勉強道具なら、いいけど。」
母からその言葉を聞いた土曜日の午後、さっそく500円札を持って文房具屋に行った。
店内に入ってガラスケースの中に並べられているシャープペンシルを見ていると
「上に出してあげるから、握ったり、芯を出したり、紙に書いたり、いろいろやってみなよ。」と店番をしていたお婆さんが出してくれた。
その時のお婆さんの手を見てはっとした。あかぎれのような傷と親指がささくれになっていた。左手の人差し指に巻いた絆創膏は周りが黒く汚れていた。
僕は、急に田舎のお爺さんのあの傷だらけの手を思い出した。あの時くれた500円札もお爺さんの傷だらけの手で一生懸命働いて作ったお金だろう・・・そう思うと急にシャープペンシルが欲しくなくなり、財布から出しかけたお札をまた戻した。
「ごめんなさい、僕は、このお金、使えなくなって・・・。ほんとにごめんなさい。出してもらって、書いてみたのに、すみません。」
途切れ途切れにそんな意味の言葉を言った。
「ああ、いいんだよ。きっと、あんたにとって、大事なお金なんだろうね。」
優しくそう言ってくれたお婆さんの言葉もあり、帰りの自転車をこぎながら涙がボロボロこぼれて仕方なかった。
お爺さんに会いたいと思った。今すぐ田舎に行きたいと思った。電話も車も家にはまだない時代、どうしようもない気持ちで家に帰り、母にシャープペンシルを買わなかったことを話した。
「修学旅行で買ってきた絵葉書があるでしょう。それでお爺さんに手紙を書いたら。」
母に言われさっそく手紙を書いた。お小遣いのお礼、手の傷を大事にしてほしいこと、寒くなるので風邪をひかないでください、また夏休み、会いに行きます・・・そんなことを。
一週間ぐらいしてお爺さんから、返事の手紙が来た。
「元気で働いている。手の傷はわしの自慢じゃ。かわいい孫たちも、わしの自慢じゃ。お前の手紙は、わしのお守りにした。」それを読んで、僕はうれしくて、ほっと気が休まった。
年も明け、2月になった寒い朝、一通の電報が届いた。お爺さんが亡くなった知らせだった。朝、眠るように静かに息を引き取ったということだった。お爺さんの枕元には、従兄たちが書いたであろう、誕生日を祝う色紙と汚れた巾着袋、その中には僕が送った絵葉書が入っていた。お爺さんの手を握って、最後のお別れの言葉を言いながら遠慮なく涙を流した。涙ってこんなに出るものかと思うくらい泣いた。従兄たちも一緒に泣いてくれた。
そして僕は僕だけの思い出として、あの500円札でお爺さんが好きだった菊の花を一輪買って、棺の中に入れさせてもらった。
今でも、僕の机の引き出しの片隅に、お爺さんからもらった最初で最後の手紙が入っている。