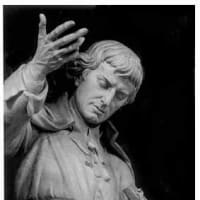『アジア専制帝国 世界の歴史8』社会思想社、1974年
15 イスラムとインド
2 デリーの王たち
ヒンズー教という宗教には寛容であったとはいえ、北インドに権力をうち立てたスルタンや貴族たちは、中世のどの国の支配者とも同じように、主権者としては、あくまで絶対的な強権をもって相手にのぞんだ。
また権力をめぐって、貴族同士がその派閥をつくって争ったが、そうした面では、力の政治や策略がものをいったのである。
十四世紀の前半にアジアを旅行したモロッコ生まれのアラブ人、イブン・バツータの有名な旅行記から、その頃かれが仕えたツグルク朝のムハンマッドについての記述を、すこし引用してみよう(引用には、前島信次訳『三大陸周遊記』を参考)。
ムハンマッド・ビン・ツグルクは、なんびとにもまして、人に物をあたえることを好むとともに、他人の血を流すことがもっとも好きである。
王宮の門からは、たえず、この王によって富をあたえられた貧乏人が出ていくかと思えば、王によって命を絶たれたものの死体も運び出されている。寛大で勇敢、しかも残虐で、横暴の君主である。
インドの国王は、大小の諸侯のもとに密偵をおいて、あらゆることを報告させるのが常である。
それには奴隷をつかうとともに、女奴隷を下女としてもぐりこませてある。
また掃除婦たちをいたるところに入りこませ、その女たちが、女奴隷からの情報をあつめて歩く。
つまり権力者は、スルタンから有名な貴族にいたるまで、みんなスパイをやとっていて、たがいに探(さぐ)り合いをしているのである。
このツグルク朝のムハンマッドという王を、「天才と狂人」の性格をあわせもった支配者といった人もいる。
かれのやったことのなかで目だつのは、せっかく大都城をつくりあげたデリーから、十年もたたないうちに、首都を遠くインドのまんなか、デカン高原西部のドーラターバードヘ移してしまったことである。
「三日後には、デリーには、だれひとり残らぬようにせよ」というお触書(ふれがき)がまわされたと、イブン・バツータは書いている。かれの記録には、つぎのような話も記された。
大部分の市民たちは出発したが、なお家にかくれているものもあったので、くまなく家さがしをせよとの命令がでた。
王宮の奴隷たちが、町で二人の男を見つけたが、そのひとりは半身不随の身で、もうひとりはめくらであった。
王のもとへつれていくと、半身不随の男のほうを大砲の弾のかわりにうちとばし、めくらのほうは、デリーからドーラターバードまで、四十日行程の道をひきずってゆけと命じた。
あわれにも、この男は途中で、体がパラパラとなり、ドーラターバードについたのは、なんと、その男の片足だけだった。
ある信用できる人が私に語ったところでは、ある晩、王が、王宮の高楼に立ってデリーの町をながめていたところ、火の気も煙も、まったく絶えはてていた。
国王は、これでわしもやっと満足し、気持も落着いたぞ、と述懐したそうである。
この話は、ときにイブン・バツータの旅行記にみられる独特の誇張があるかもしれない。
しかし中世インドの支配者の性格の一端を、まことによく示しているエピソードといえないことはあるまい。
さてデリーを中心に、およそ三百余年にわたって、トルコ人やアフガン人の五つの王朝がつづいたことから、イスラム系の王権の支配も、しだいに定着していった。
アラブ人やペルシア人、それにアフリカからやってきた人たちも、官吏として、あるいは文人や学者や思想家として、インドに住みついた。
モンゴル人が、アッバース朝の都バグダードを占領した十三世紀の後半からは、西アジアや中央アジアにおけるイスラム系の王国の諸都市にかわって、デリーはイスラム世界における文化の一中心として、西方の諸国にも知られるようになっていたのである。
イスラムというと、日本人は、すぐに、アラブや中近東の諸民族、諸国家のことを考えてしまう。
これまで、欧米の名の知れたイスラム学者でも、インドや東南アジアのイスラム教徒というと、ややもすれば、「田舎イスラム」というふうな扱いをしてきた傾向がないではない。
しかし、すくなくとも、国の人口の大きさからいうと、世界の国々でイスラム教徒がいちばん多いのは、アラブや中近東の諸国どころか、インドネシアとパキスタンとが、トップに立っているのである。
しかも三番目は、パキスタンとわかれて独立したインド連邦なのである。
インドというと、すぐにヒンズー教徒のことを考えてしまうが、この国の十三世紀以降の歴史は、もはやイスラム教徒の政治的支配や、イスラム文化の影響を考えずして語ることはできない。
音楽・絵画・建築などの芸術や技術の面で、イスラムの影響は、しだいにインドに根をおろしていった。
ペルシア語の詩文も、さかんにつくられた。
今日のパキスタンの国語の一つになっているのは、アラビア文宇をつかうウルズー語であるが、これが成立したのも、この時代であった。
そればかりか、一般の民衆の衣食住の生活にも、イスラムふうの影響はしだいに浸透していった。
こうして、もともと多様であったインド人の生活は、この新しい宗教にともなう生活文化の諸要素を受けいれて、ますます多彩なものとなっていったのである。