第5回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会(
議事録全文)
1 日時 令和4年2月21日(月)15時00分~16時31分
2 場所 オンラインにより開催
傍聴会場 労働委員会会館講堂(東京都港区芝公園1-5-32 7階)
3 出席委員
公益代表委員
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授 寺田一薫
慶應義塾大学法務研究科教授 両角道代
労働者代表委員
日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長 久松勇治
全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
使用者代表委員
西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春
4 議題
(1)改善基準告示の見直しについて
(2)その他
【次第】第5回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会
【資料1】改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)
【参考資料1】改善基準告示の見直しについて(参考資料)
【参考資料2】改善基準告示の内容(一覧表)
○両角部会長 ありがとうございました。前回の作業部会等での議論を踏まえ、ただいま事務局から修正案の提案の説明がありました。この分科会での議論は3月末までに取りまとめる予定になっていますので、本日、委員の皆様におかれましては、取りまとめに向けて議論していただくようにお願いいたします。それでは、資料1の順番で御議論いただきたいと思います。
まず、資料1の1ページ、1か月の拘束時間については288時間を超えないものとするという案が示されていますが、これについていかがでしょうか。久松委員、お願いします。
○久松委員 これについては、これまで議論してきた中でも労使ともにさほど争いはなかったと思いますので、これでよいのではないかと考えます。以上です。
○久松委員 松永さんの意見については、私も本当にそのとおりだとは思っています。しかしながら、これまで、現場の実態等も踏まえた中で、本当に労使で真摯に議論してきたと思っていますが、諸手を挙げてこのままというわけにはいかないというところも少しあるので、最後どうまとめるかということは別として、せめてなのですが、「勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることとし」となっている部分を、「原則、継続11時間以上の休息期間を与えることとし、継続9時間を下回らないものとする」ということで、「努める」という言い回しではなく、「原則、継続11時間」ということで、少しメッセージを強くしてもらいたい。これができれば、使用者側のお考えも踏まえて検討できると思います。
今、自動車運転者の職場環境良好度認証制度というものも国土交通省を主体として進めていますが、労使の中でも先進的な事業者や、優良事業者では、武居委員がおっしゃったように、拘束時間は13時間を前提に労務管理をしてくださっている事業者も多々あるということですから、休息期間11時間というのは絵空事ではなく実態として可能な部分であると思います。ですから、しっかり従業員の健康管理を考えている事業者があるということも踏まえて、「努めること」というよりも、「原則」としていただいても十分ついてこれる事業者はたくさんあると考えていますので、文言の修正をお願いしたいと思います。以上です。
○両角部会長 ありがとうございました。今、久松委員から、取りまとめに向けて御意見があったと思いますけれども、それに対して、あるいはその他の点について委員から御発言はありますか。武居委員、どうぞ。
○武居委員 久松さん、原則11時間とすると、9時間という数字の意味はなくなってしまうのではないですか。原則11時間で9時間を下回らないというのは文言的に理解できないのです。原則11時間以上確保するということは、11時間は最低だけれども、例えば労使協定があれば9時間でもOKだよという意味ですか。11時間原則という形を取ってしまうと、9時間というのは基本的に特例になりますよね。そこは、受け入れ難いというのが本音です。努めることにしても、11時間というのを入れたということに大変大きな意味があるのではないかと私は思っています。原則ということで、努めるということはなくそう、11時間が最低義務で特例的に9時間ということは、日によっては9時間のときもあって、でも原則は11時間以上与えなければ駄目と、こういう意味で久松さんはおっしゃっているのだと思いますが、そういう理解でよろしいですか。
○両角部会長 久松委員、お願いいたします。
○久松委員 その趣旨です。理想というか、原則として11時間という休息期間を与えることとするが、継続9時間を下回らないものとすることで、拘束時間の延長で一定の制限とか条件を付けられると思いますので、その裏返しとして休息期間を9時間とすることも可能であるようにするということです。
○両角部会長 今、久松委員から御説明がありましたが、武居委員、いかがでしょうか。
○武居委員 もともと私どもは当初から、都心部のほとんどの事業者は13時間拘束でやっています。都心部は1日の拘束時間を13時間としても実車率も含めて生産性が高いですからやっていけますが、地方は曜日によって拘束時間がかなり変わるのではないかと思っています。そういう意味で、休息期間を8時間から急激に11時間とするいうことは拘束時間の延長ができなくなってしまう。久松さんが言うように、曜日に応じて15時間までできるといっても、その回数が非常に少ない部分になっていってしまうので、9時間を原則にしてもらわないと同意できないというのが、今のところ私どもの考え方です。
○両角部会長 ありがとうございます。この点につきまして、ほかに委員から御意見はありますでしょうか。そうしましたら、久松委員からは修正案の表現をもう少し強いものにできないかという御提案があり、武居委員からはその趣旨がどういうことかということでしたが、ほかに御意見はございませんか。松永委員。
○松永委員 ありがとうございます。今、そういう話が出たのですが、私たちは労働者として命を預かる仕事をしているのだというのを常に考えてきました。仕事をするということにおいて、しっかりした休息を取ることが一番必要であって、例えば今まで出てきた議論の中で、長時間働かないと歩合給だから給料にならないのだとか、そんな議論は基本的にこの場での議論の中に入れるべきではないと私たちは思っています。前も申し上げたとおり、自宅に帰ってから次の日の朝までに人は何を行うのかということを訴えてきたつもりです。そういった意味で、休息期間は11時間を原則にして9時間という定義も置くということは、私ども労働側から言えば大変前進した議論だと思っていますので、そこは是非、公益委員の方たちも声を出していただきながら、しっかりと協議をしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
○両角部会長 久松委員、どうぞ。
○久松委員 もう一度確認をしたいと思います。まず、日勤の拘束時間ですが、1日についての拘束時間は13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は15時間とする。これを押さえた上で、この反対側が休息期間になるかと思いますが、勤務終了後、原則11時間以上の休息期間を与えるよう努めることとし、継続9時間を下回らないものとするということで言えば、9時間ができないという読み取りにはならないと思っていますので、武居委員がおっしゃったほど厳しくしてくれと言っているわけではないつもりです。
○両角部会長 ありがとうございます。今の久松委員の御意見は9時間が例外であるという趣旨ではないということでしょうか。武居委員、お願いいたします。
○武居委員 今は日勤の1日の拘束時間は13時間から16時間で、休息期間は8時間以上確保するということです。この休息期間について、都心部では基本的に11時間以上与えているだろうというご指摘です。だから、休息期間は原則11時間でも問題ないという論議はなかなか難しい。というのは、今まで8時間だったものを、急激に3時間延長しても、今までどおり拘束時間を13時間以内でできるよねと、なおかつ1時間短くなったけれども拘束時間は15時間まで延長できるから、ある意味で拘束時間13時間と休息期間11時間、最大拘束時間15時間と休息期間9時間とで実務的にもやっていけるといういうことを久松さんはおっしゃっているわけですね。
最大拘束時間が15時間だと休息期間は9時間になりますし、拘束時間が13時間だと休息期間は11時間になるのだから、原則11時間で9時間を下回らないというのは、全然おかしくないですねと話されているのだと思っているのですが、私どもがもともと言っているのは、少なくとも休息期間は3業態一緒というのが労働者側としての意見であったということが1つと、もちろんタクシーの部会ですからタクシーのことだけ考えればいいと言うかもしれませんが、タクシー会社にはバス事業もやっている所が結構あるのです。タクシー事業とバス事業の両方ともやっているという会社は結構あるわけです。路線をやっている会社でタクシー事業をやっている会社はものすごく多いのです。そこでバスのほうからも、休息期間は現状維持をしたいのだという要望が全国から私どもには入ってきている。
私どもは、1日の拘束時間が13時間ですから、休息期間も9時間以上、11時間に近い実態があるのですが、数字的には9時間を超えて11時間を努力義務ということにすれば、今よりも過労防止という意味においては前に進んでいると私ども使用者側としては思っています。
ですから、8時間だったものが急に11時間まで取らせなければいけないということでは、全国的にシフトを組みづらい、実態的に問題があるという声が大きいです。案の内容である程度やむを得ないと思っていますが、これを原則11時間で9時間を下回らないものとなると、逆に9時間が特例で原則11時間を取らせなければいけないとなって、ある意味で基本的に拘束時間を13時間以上に延長することは確実にできないことになります。拘束時間13時間を延長する労使協定はありますけれども、休息期間は原則11時間ということにしてしまうと、実務的に1日の拘束時間13時間を延長することはできないということになります。拘束時間13時間を超えてしまったら休息期間11時間の確保はできないわけです。拘束時間13時間を1分でも超えたら休息期間は11時間を下回ってしまうわけです。だから、私どもはのめないと言っている。11時間が原則となると、13時間拘束すらもなかなかできないという論議になってきます。例えば何かの事情で確実に超える場合が出てきますからね。それを考えると、今の現状として追加案がぎりぎりのところだというのが私どもの今の考え方です。以上です。
○両角部会長 ありがとうございます。今の御意見に対して、あるいはほかの観点から御意見はありますでしょうか。久松委員。
○久松委員 武居委員の思いとうまく噛み合っていないように感じているのですが、今までは継続8時間以上の休息期間を与えるということで、これは絶対でした。今回、案と追加案があって、案のほうは原則11時間、週3回まで9時間で、追加案のほうは継続11時間以上の休息期間というのが基準としてあるけれども、継続9時間を下回ったら絶対駄目だとなっていて、最低基準が9時間を下回らないものになっていると思っています。その上で、「努めること」という部分を「原則」とできないかと、9時間を絶対に下回ってならないでも、努力してもらうというメッセージとして、原則11時間としようという思いで私は言いました。
今、武居委員がおっしゃったように、9時間は絶対守ってもらわなければいけないとしても、「努めること」よりも「原則」という言葉になると、それをしなくてはならないと思ってもらえる事業者もあればいいなと私は思って、「努めること」よりも「原則」とするほうが、そう思ってもらえる事業者がたくさん増えるのではないかという期待を込めた発言でした。そういう意味です。
○両角部会長 ありがとうございます。今、久松委員が御提案の趣旨を説明されましたけれども、武居委員の理解としては整合していますでしょうか。武居委員は、そのように久松委員の御意見を理解された上で、先ほど御発言されたということでよろしいでしょうか。お願いします。
○武居委員 原則と言ったとき、11時間を下回らないということになる。全国の事業者も、原則となると11時間を確実に下回ってはいけないと受け取る。努めるということになると、11時間となるように努力しなければいけないとなり、9時間を絶対下回ってはいけないとなる。つまり、久松さんがおっしゃるように、11時間以上の休息期間を与えるような意味、原則として継続9時間を下回らないものとするという形で事業者側が理解してくれるのかどうか。
逆に言うと、事業者側の受け止め方として、努めるということと原則という言葉でかなり受け止め方が違ってくるのではないかという感じを受けています。原則ということになると、通常は11時間で基本的にやりましょう、やむを得ない事情があったときだけ9時間を認めますという考え方に私は取ってしまう。だから、それはいくら何でも急激すぎるのではないですか、休息期間が8時間から11時間が原則になりますねというふうに受け止めてしまうのではないかと思うし、私もそう取ってしまいます。
ですから、「努めること」ということで、もし推進という意味で言うならば、何も原則という言葉を入れる必要はないのではないかと思っています。ここは、9時間は確実に下回らないようにしましょうと、そういう言葉だけでよくなってしまうのではないかという感じがしてならないです。11時間以上の所も地方の事業者ではあるのではないですか。原則というふうに入れると、11時間が基本的な休息期間の原則であると、特例のときだけ9時間を認めますと受け止めてしまうので、厚生労働省のほうでもう一度、文章的にうまく調整してもらえませんか。久松さんがおっしゃるように、なるべく11時間に向かうように推進するのだということならば、もう一度提案していただければ有り難いです。以上です。
○両角部会長 ありがとうございます。清水委員、どうぞ。
○清水委員 清水でございます。原則という言葉が将来的に独り歩きしてしまって取扱いが個々に異なった場合、いろいろな問題が生じるのかなと思っています。11時間という数字が入れば私はいいのかなと。特に9時間にこだわるというのは、現状いろいろシフトの組替えというのがありまして、例えば今日は8時に出庫だという車が、明日の朝はどうしても予約があって6時に来なさいということになると、2時間の前倒しということになるわけで、その場合は9時間確保できていれば前倒しは可能になりますけれども、地方の都市、ゴルフ場等々がある場所ではクラブバスというのが経費の節減で廃止されていますが、そういう地区は結構その手の予約が多いと聞いていますので、9時間を下回らないという、努力目標として11時間を入れるということで、是非御検討いただきたいと思っています。以上です。
○両角部会長 ありがとうございました。ほかに御意見はございますか。松永委員。
○松永委員 先ほど武居委員のほうから、原則11時間というふうに原則と付けると1分でも超えてしまうとという問題点を言っていただきましたが、これは例えば10時間にしても9時間にしても同じことであって、11時間だから守れない、10時間なら守れるという議論ではないと思っています。久松さんが丁寧に説明しているように、原則というのを、もう少し厚生労働省のほうから提案の内容を再度出していただきたいと思います。それから、私どもも全国を回っていますので全国の事情はよく分かっているのですが、例えばゴルフ場もそうですし、ホテル送りや空港送りも数多い仕事ではなく、本当に特例としてある仕事なのです。常時あるものではないので、本当に回数の少ないものを精一杯、それぞれの地方の事業者が苦労して労使で対応しているという実態でありますから、私は原則11時間、そして9時間という定義を付けても、この範囲で対応できると全国を回ってみて思っていますので、是非その対応でお願いしたいと改めて申し上げます。
○両角部会長 どうぞ。
○武居委員 久松さん、勤務終了後、原則継続11時間以上の休息時間を与えるよう努めることでは駄目なのですか。継続の前に原則と入れれば、原則11時間以上の休息期間を与えるよう努めることという形では駄目ですか。私から言うと、原則11時間の原則を後ろに持ってくるか前に持ってくるかによって、事業者側の受け止め方は大分違うと思っています。私どもとすると、事業者側から、シフトが組めないとか、こういう実態があるから守れないと後から言われても困るので、今の休息期間以上に与えなければいけない、休息期間は9時間以上となったということを確実に全国の事業者に説明しに上がりますし、少なくとも原則11時間以上与えるように努力してくださいという形を話すにしても、「努める」ということを入れないと正直言って説明が難しいというのが本音です。ですから、原則を入れて、「努める」ということで何とか御理解いただけないかなというのが私の提案です。以上です。
○両角部会長 ありがとうございます。久松委員、お願いします。
○久松委員 私が原則という言葉にこだわった理由というのは、将来にわたって次の改善基準告示の見直しがいつになるか分からないような中で、1つでも多くの事業者に11時間以上となるように頑張っていただきたいと、そういう強いメッセージができたらいいなという思いの発言です。今、武居委員のおっしゃっていただいた提案は十分評価させていただきたいと思いますし、公益委員の皆様と事務局には文言について検討いただけたらいいなと思います。
○両角部会長 ありがとうございます。今、久松委員からの御提案があり、武居委員からも御提案がありました。それぞれ意図していらっしゃる内容は、もちろん言ってはいませんけれども、私が伺うところ、かなり前よりは近付いてきているように思います。双方の御意向をうまく反映できるような表現ということが、今、課題になっているかと思いますので、久松委員、武居委員からもありましたように、事務局のほうと、もちろん公益委員もですが、検討させていただきたいと思います。もう一度機会がございますので、そのときまでに改めて検討させていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございました。
○両角部会長 ありがとうございます。ほかには御意見はいかがですか。よろしいでしょうか。久松委員、お願いいたします。
○久松委員 武居委員、清水委員から、隔日勤務について過酷な労働だという認識をしっかりしていただいた上で、一定、休息期間の見直しは必要であるという考え方を出していただいたことは非常にうれしいのですが、やはり24時間という数字については、労側としてはまだまだこだわりはあります。しかも、その上で、現状の拘束時間について、大きな緩和ではありませんが、一定の緩和の御提案を頂いたというところも非常に悩ましいところかなと思っているところです。
○久松委員 タクシーの労働実態は、乗合バスや貸切バスと違いまして、乗合バスのように系統ごとに組んだダイヤや、貸切バスのように運行計画によって運転士さんが拘束されるのではなくて、お客様を乗車させ、降車させ、次のお客様を乗せるまでの間のその辺のペース配分というのは比較的やりやすいところもありますので、連続運転時間とか、運転時間といった規制はなじまないとか、そこまではいらないのかなと労側としても思っているところです。
○久松委員 例えばですが、現場の運用上の部分で、拘束時間について2暦日の2つ分の勤務で調整するというのは、実務的にはありうるのかなということも理解はできます。しかし、私どもとしては休息期間24時間というところは少しこだわりがあるということで、例えばですが、日勤の休息期間の修正案である文言について、継続11時間のところを、隔日勤務では24時間と読み替えていただいて、そして下回らないものとするというところの9時間というのを22時間に読み替えていただくことはいかがでしょうか。したがいまして、勤務終了後、継続24時間以上の休息期間を与えるよう努めることとし、継続22時間を下回らないものとするという文章です。
○久松委員 もし、仮に使用者側の拘束時間の提案を受け入れるとすればですが、先ほど申しました読み替え、2日勤の休息期間の追加案の記載を24時間と22時間との読み替えをお願いしたいという趣旨です。
○両角部会長 ありがとうございます。ハイヤーについては、今日出ておりますこの案で労使ともに問題がないということで承ります。それでは、車庫待ちについてです。車庫待ちも日勤と隔勤がありますが、まずは車庫待ちについては今回初めて定義が案として出てきています。この定義について御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。久松委員、お願いします。
○
久松委員 定義の中で人口要件が入っています。人口30万人以上という要件、以前事務局のほうでは中核市でしたか、その要件に合わせて20万という数字になっていて、今回は30万というふうになりますと、流し営業はあるかないか際どいところの数字になるのではないかということをちょっと心配しますが、使用者側の委員の皆様がこれで大丈夫ということであれば、これで異存はありません。
○両角部会長 分かりました。それでは、最後の論点にまいります。例外的な取扱いについてです。資料の6ページにありますが、これも長いので読み上げませんけれども、この案の例外的な取扱いについて御意見があればよろしくお願いします。久松委員、お願いします。
○久松委員 内容的には問題ありません。ただ、文言の部分なのですが、予期しえない事象に遭遇した場合の2行目、「1日または2暦日」となっています。しかしながら、次の「ただし」からの行ですが、「勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるものとする」ということで、日勤の休息期間の数字しかここには入っていないということになりますので、先ほどの議論の結論ということになるのかとは思うのですが、2暦日の場合の休息期間を「又は」で入れるべきではないかと思います。











![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30350359.a1eb9a3d.3035035a.a2aa6d16/?me_id=1212505&item_id=10000480&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fzensho%2Fcabinet%2F2021%2F2021_10_11%2Fr-ast0040520_600.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




























































































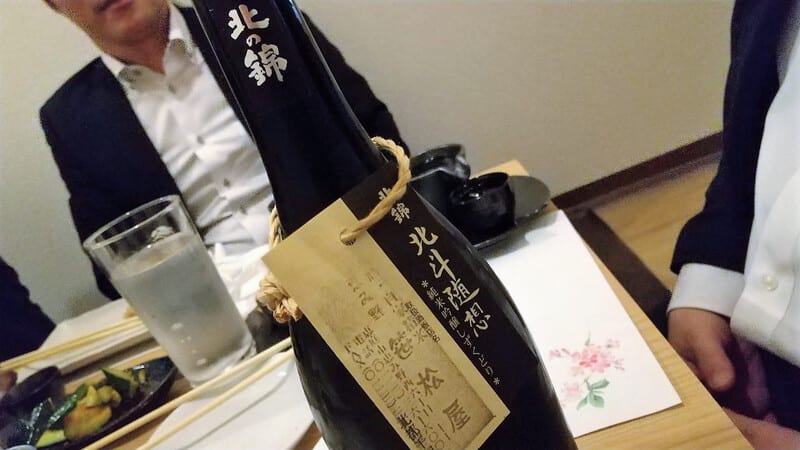




































![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f543022.d706cfca.1f543023.e2acb091/?me_id=1319439&item_id=10002505&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcicib%2Fcabinet%2F08712830%2F20ranking-1221.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/23f519dc.1c98bff3.23f519dd.5ced71b7/?me_id=1351180&item_id=10001030&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhayaritsushin%2Fcabinet%2F07054508%2F204-2-1-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)









