(これまでは7割、さらにその前はその割合に達しても、3ヶ月の期限が経過しないと運賃改定手続を開始されなかった)
〇運賃ブロックを統合することとなった。
(各地方運輸局管内で、あとから運賃改定申請した運賃ブロックの運賃改定手続が少しでも早く処理できるようになった)
これで、必要な運賃改定が、より迅速に進むことを期待している。
とはいえ、うちとしては歓迎している反面、課題もあって、国土交通省に対しては、
『運転者の賃金・労働条件やタクシー事業の経営環境の改善を行うためには、周期的な運賃改定は必要であるが、一方で、高齢者や障害者、子育て世帯など、日常的にタクシーが必要な方たちにとって運賃改定は負担増となるため、運賃に対しての公的支援を創設されたい。」
という要請を、継続して行っている

以下は、令和6年11月の物流・自動車局旅客課のパブリックコメントの内容。
「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について」の一部改正について
1.背景
一般乗用旅客自動車運送事業の現行制度においては、各地域の需要構造や原価水準等を勘案して、運賃料金を適用する地域(以下、「運賃料金適用地域」という。)を細かく区分しており、運賃料金適用地域内の運賃改定の申請を行った法人事業者の車両数の割合が7割以上となった場合に、運賃改定手続を開始することとなっている。
この度、現行の運賃料金適用地域の区分を見直す予定であるが、あわせて運賃改定手続を開始するために必要な条件を見直すこととする。
2.概要
運賃改定手続の開始に必要な条件を以下のとおりとする。
・運賃適用地域において運賃改定の申請を行った法人事業者の車両数の割合が5割以上となった場合
3.今後のスケジュール(予定)
公布:令和6年12月中旬
施行:公布の日
結果、2024年12月24日付で、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請の審査基準について」が以下のとおり、改正された。(抜粋)
1.運賃適用地域
運賃改定(需要構造、原価水準等を勘案して運賃改定手続をまとめて取り扱うことが合理的であると認められる地域として近畿運輸局長が定める別添の地域(以下「運賃適用地域」という。)において普通車(普通車の車種区分がない地域においては地方運輸局長の定める区分による車種別)の最も高額の運賃よりも高い運賃を設定することをいう。以下同じ。)申請については、運賃適用地域ごとに行う。
2.運賃改定手続の開始等
(1) 運賃適用地域ごとに、最初の申請があったときから3ヶ月の期間の間に申請を受け付けることとし、申請率(当該運賃適用地域における法人事業者全体車両数に占める申請があった法人事業者の車両数の合計の割合をいう。以下同じ。)が5割以上となった場合には、3ヶ月の期限の到来を待たずに直ちに運賃改定手続を開始することとする。
(2) 運賃適用地域ごとに、運賃改定手続開始後において、申請の取り下げにより申請率が5割を下回る事態となった場合には、次のとおり取り扱うこととする。
① 申請率が5割を下回った時点で、運賃改定手続を一時的に中断するものとする。
② 当該運賃改定手続を中断したときから3ヶ月の期間の間に、追加的な申請により申請率が5割以上となった場合には、直ちに当該運賃改定手続を再開するものとする。
③ 当該運賃改定手続を中断したときから3ヶ月の期間の間に、申請率が5割以上とならなかった場合には、当該運賃改定手続を中止するものとする。(3) なお、(1)において運賃改定手続の開始に至らなかったとき及び(2)③において運賃改定手続が中止となったときは、それぞれ申請事業者について、道路運送法第9条の3第2項第1号の規定に適合しないものとして却下処分を行うものとする。
なお、上記パブリックコメントの下線部である「この度、現行の運賃料金適用地域の区分を見直す予定であるが」については、以下のとおり、全国で101あった運賃ブロックは、69ブロックに変更がなされた。
〇北海道運輸局
札幌・小樽地区(札幌市・小樽市等) ⇒ 札幌A地区と札幌B地区が統合
千歳・空知・後志地区(千歳市、岩見沢圏、夕張圏、美唄圏、芦別圏、滝川圏、当別圏、余市町・ニセコ町等) ⇒ 札幌C地区と札幌D地区と札幌E地区が統合
旭川地区(旭川市、名寄市、稚内市、富良野市等) ⇒ 旭川A地区と旭川B地区が統合
函館地区(函館市、松前圏・桧山圏・奥尻島等) ⇒ 函館A地区と函館B地区が統合
室蘭地区(室蘭市、登別市、苫小牧交通圏など)
釧路地区(釧路市、釧路町など) ⇒ 釧路A地区と釧路B地区が統合
帯広地区(帯広市、音更町、芽室町、幕別町、広尾町、足寄町、清水町等) ⇒ 帯広A地区と帯広B地区が統合
北見地区(北見市、常呂圏・網走市・斜里圏等) ⇒ 北見A地区と北見B地区が統合
〇東北運輸局
青森地区
岩手地区 ⇒ 岩手県A地区と岩手県B地区が統合
仙台地区 ⇒ 旧の宮城県A地区
宮城地区(仙台地区を除く県全域) ⇒ 旧の宮城県B地区
秋田地区 ⇒ 秋田県A地区と秋田県B地区が統合
山形地区 ⇒ 山形県A地区と山形県B地区が統合
福島地区
〇関東運輸局
特別区・武三地区
多摩地区
東京島しょ地区(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島及び母島)
京浜地区
相模・鎌倉地区
小田原地区(小田原市等)
千葉地区 ⇒ 千葉A地区と千葉B地区が統合
埼玉南部地区(県南中央、県南東部、県南西部) ⇒ 旧の埼玉県A地区
埼玉北部地区(県北、秩父) ⇒ 旧の埼玉県B地区
群馬地区 ⇒ 群馬県A地区と群馬県B地区が統合
茨城地区
栃木地区
山梨地区 ⇒ 山梨県A地区と山梨県B地区が統合
〇北陸信越運輸局
新潟地区 ⇒ 新潟A地区と新潟県B地区が統合
長野地区 ⇒ 長野県A地区と長野県B地区が統合
富山地区
石川地区 ⇒ 金沢地区と石川地区が統合
〇中部運輸局
名古屋地区(名古屋市)
尾張・三河地区(小牧市、豊田市、豊橋市等)
静岡地区(静岡市、浜松市等)
伊豆地区(伊豆交通圏)
岐阜地区 ⇒ 岐阜地区と飛騨地区が統合
三重地区
福井地区
〇近畿運輸局
大阪地区
京都市域地区(京都府京都市、向日市、長岡京市、宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡等)
京都北部地区(京都市域地区を除く県全域)
神戸市域地区(神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、明石市、川西市、川辺郡)
兵庫地区(神戸市域地区を除く県全域) ⇒ 姫路・東西播地区と淡路島地区と兵庫北部地区が統合
奈良地区
滋賀地区 ⇒ 大津市地区と滋賀県北部地区が統合
和歌山地区 ⇒ 和歌山市域地区と和歌山県有田御坊地区と和歌山県橋本地区と和歌山県紀南地区が統合
〇中国運輸局
広島市域地区 ⇒ 旧の広島A地区
広島地区 ⇒ 旧の広島県B地区
鳥取地区
島根地区 ⇒ 島根県本土地区と島根県隠岐地区が統合
岡山地区
山口地区
〇四国運輸局
徳島地区 ⇒ 徳島県市部と徳島県郡部地区が統合
香川地区 ⇒ 香川地区と小豆島地区が統合
愛媛地区 ⇒ 愛媛県東予地区と愛媛県中予地区と愛媛県南予地区が統合
高知地区 ⇒ 高知市域と高知県郡部地区が統合
〇九州運輸局
福岡市域地区(福岡市、大野木市、太宰府市等) ⇒ 旧の福岡県A地区
福岡地区(福岡市域地区・北九州市域地区を除く全域) ⇒ 旧の福岡県B地区
北九州市域地区(北九州市、中間市、遠賀郡)
佐賀地区
長崎本土地区(長崎県本土地区) ⇒ 旧の長崎A地区
長崎離島地区(五島市、壱岐市、対馬市等) ⇒ 旧の長崎B地区
熊本地区(熊本県全域)
大分地区(大分県全域)
宮崎地区(宮崎県全域)
鹿児島地区 ⇒ 鹿児島A地区と鹿児島B地区が統合
奄美地区(奄美群島内)
〇内閣府沖縄総合事務局
沖縄地区 ⇒ 沖縄本島地区と沖縄県離島地区が統合










![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bfa755.bb912127.18bfa756.dcb862a9/?me_id=1224379&item_id=10034443&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F11667147%2F11667148%2F2536-main-250117-1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)










![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44177f18.fa96bc7e.44177f19.4dfcda91/?me_id=1239219&item_id=10034616&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fangelsdust%2Fcabinet%2F10321283%2F2310270-b-1000.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)




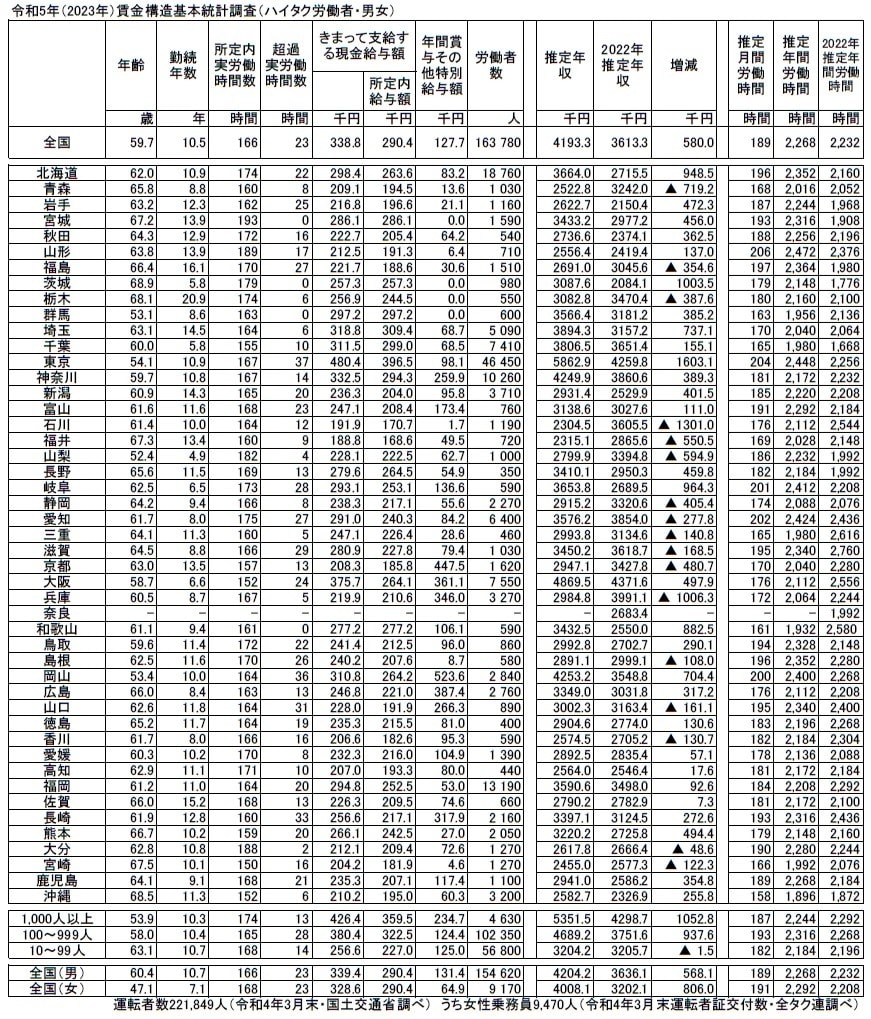











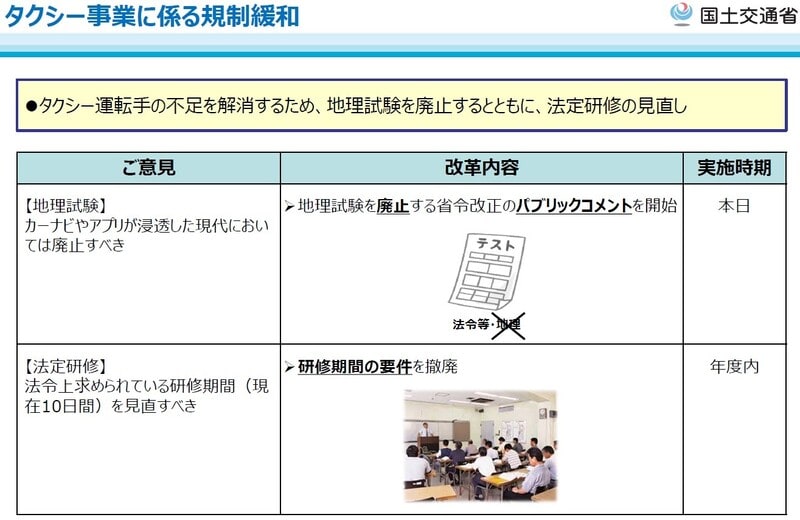
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3857c014.eee9f4f7.3857c015.609ce2dc/?me_id=1365778&item_id=10000535&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff172049-wajima%2Fcabinet%2Fwajima.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)































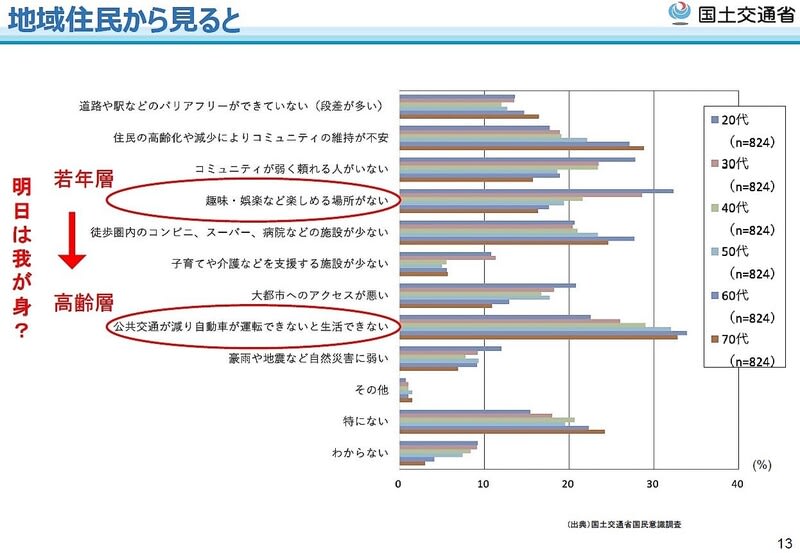
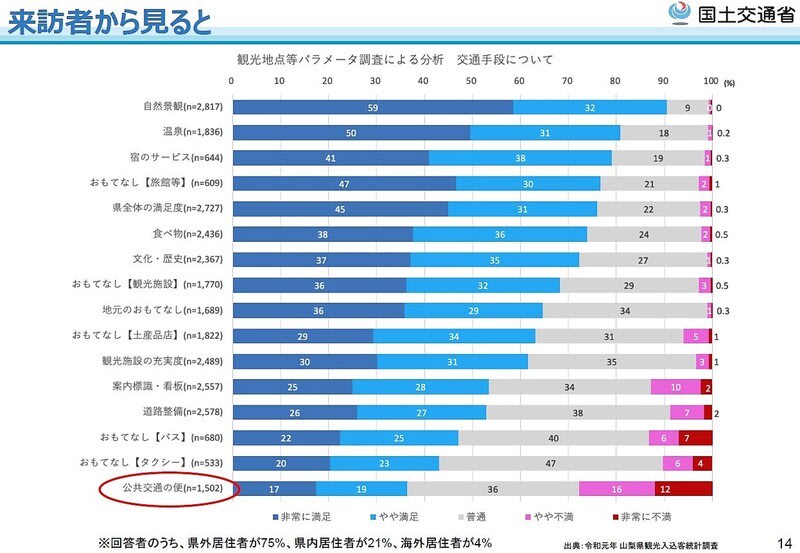


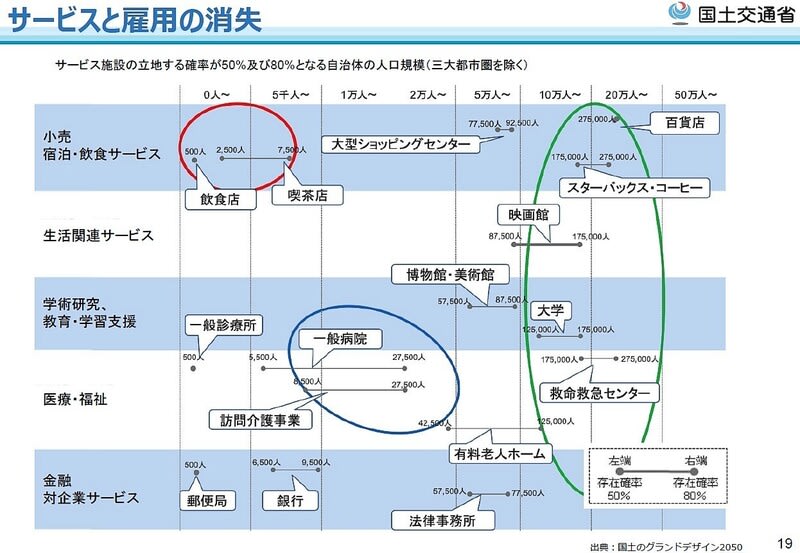









![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3278b3a7.4cb5dd8c.3278b3a8.6d0e9227/?me_id=1257668&item_id=10000495&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fotsumami-gallery%2Fpage%2Fgift%2Fbest9%2Fbest9_cart_haya_f.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)




























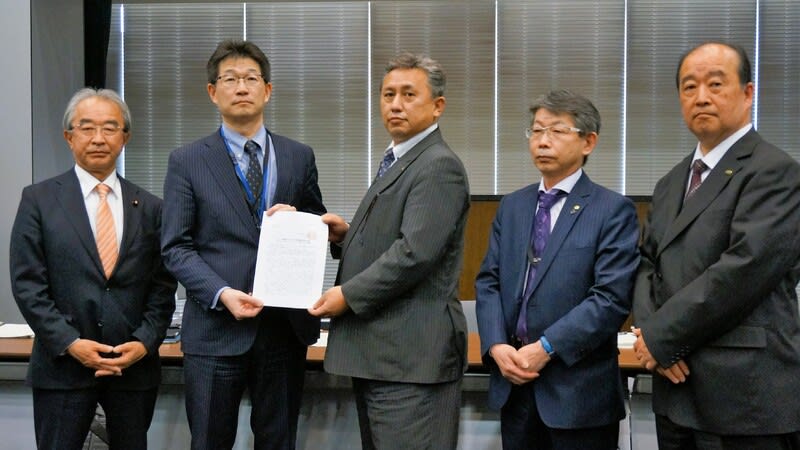






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/29af61fd.907bdf9b.29af61fe.ba1d7bc9/?me_id=1228660&item_id=10000699&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshoe-square%2Fcabinet%2Fitem17%2Fze2set_01_8960_n.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)





