
| 城名 |
| 忍田城 |
| 読み |
| おしだじょう |
| 住所 |
| 津市芸濃町忍田 |
| 築城年 |
| 白河天皇の時(1072~1086) |
| 築城者 |
| 忍田入道 |
| 形式 |
| 山城 |
| 遺構 |
| 郭、土塁、堀切、井戸 |
| 規模 |
| 東西110m×南北80m(北方の堀切を含むと200m) |
| 城主 |
| 忍田氏の居城。 |
| 標高 200m 比高 50m |
| 歴史 |
| 忍田入道が白河天皇の時(1072~1086)にここに築城し、歴代が居住した。その後裔は美濃守、また平左衛門尉と称す。のち平左衛門尉は藤堂藩に仕える。なお美濃屋神社の棟札に康和5年(1103)忍田地頭宗重とあるがこれも関係するのではないか(勢陽五鈴遺響) |
| 経緯 |
| 中勢の雄、長野氏の分家・雲林院氏が進出してくる以前からの地侍であったと思われる。しかし、この忍田氏と雲林院氏の関わりについて何も伝えられていない。 |
| 書籍 |
| 勢陽五鈴遺響 三重の中世城館 日本城郭体系 |
| 環境 |
| 安濃の平野部の北部を見おろす位置にある。また、関に抜ける街道を2Km東に見る。その反対側の東に椋本城がある。 |
| 現地 |
| 城は山地の頂部を切り込んで三方を土塁とした主郭が最高部にあり、その背後にあたる北側には幅広い堀切がある。その北方へは狭い尾根が続き100mほど離れた所にも堀切があって背後を固めている。これより北方は自然地形となって人為的な構造物は無い。 |
| 主郭から東へは尾根筋に30m程土塁が続き、その南側斜面には大小の郭が階段状に切り込んで造られている、山の南側麓を中心に帯郭状の削平地が取り巻いているがここまでが城域と考えら、頂部から山の裾まで全体が城郭を成すものと推定できる。 |
| 所々に井戸跡が見うけられ水は城内で賄われたと見受けられる。一部コンクリート製の洗い場があるのでこれは考えから除外する。 |
| 考察 |
| 規模は大きくはないが郭、土塁、堀切、削平地などキメ細かな縄張りに思われる。戦国時代より古い時代の創設という解説があるが残り方の具合といい完成度の高さといい中世にリフォームされた可能性もあるのではないだろうか。 |
| 感想 |
| 南に街道と安濃川を望み、南向きの斜面に順に郭を切込み、当時の忍田城の姿を想像すると南から東にかけての眺望良く、小さいながらも堅固で見ごたえのある城であったと想像する。 |
| 主郭を取り巻く三方の土塁はこの城の見どころの一つと思う。 |
| 地図 |












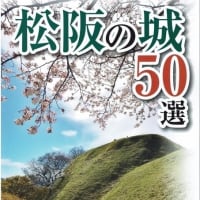

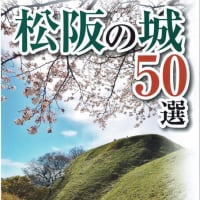
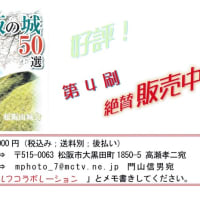




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます