
☝ 中世の頃、城は笠木川と大内山川にはさまれた中州にあったという。標高差に陰影をつけたソフトで見るとわずかにその様子が伺える。現在、その様子はうかがい知れないが図のような中州を想像すると、なるほど要害の地であったという記述もまんざらでもないのかもしれない。

☝ 崎城の航空写真による様子

☝ 北から。1.5~2mの石垣で囲まれている

☝ 大内山川の上流側の屹立。草に覆われた石垣。当初は土塁だった。

☝ 上流側の隅。まるで船の切先を想像した。

☝ 庭に通じる門。
| 城名 |
| 崎城 |
| 読み |
| さきじょう |
| 住所 |
| 度会郡大紀町崎 |
| 築城年 |
| 寛永14年(1637) |
| 築城者 |
| 山崎権太夫守正 |
| 形式 |
| 居館 |
| 遺構 |
| 曲輪、石垣、内空堀、内枡形跡 |
| 規模 |
| 東西90m×南北60m |
| 家系 |
| 山崎式部大輔(兄)(三瀬)ー大炊之守久(弟)(阿曽村出)ー権太夫守正(崎)ー長猪之助ー守正ー守道ー守長ー包守ー衛忠ー盛徳ー守義ー義守ー徳守ー曾氏ー ー - ー |
| 家臣 |
| 北畠家臣 |
| 標高 140m 比高 2~3m |
| 歴史 |
| 山崎式部大輔・大炊之佐は永禄12年(1569)の大河内城籠城戦に参陣している。(勢州軍記) |
| 経緯 |
| 三重の中世城館によると以下の記述がある。 |
| 主君北畠具教が天正4年(1576)織田信長に謀殺された時、山崎式部大輔は主君と共に三瀬城にあり、主君に殉じた。 |
| 弟山崎大炊之佐、後を継ぎ、大内山御阿曽村村出に住す。衆人元屋敷と称し、当時田畑に開墾、反別凡そ五反分余、後ろは川を以て周囲なり。地面より屹立すること七・八尺は丈あり。 |
| 三代権太夫守正、寛永14年(1637)に至り家来19家を伴って当地に移住す。独礼格士族を拝命する。 |
| 現在の山崎氏宅はその時に構築されたものだが、当時は大内山川、笠木川の中州にあって要害の地であった。 |
| 天下統一後も山崎氏は2百数十年、連綿と継がれ地元の実力者として大いに活躍され、現在に至る。 |
| 書籍 |
| 三重の中世城館 宮川流域の遺跡を歩く 山崎家歴系統概略記事 権太夫屋敷の紹介 「戦国時代の館だった」夕刊三重 |
| 環境 |
| 三重の中世城館が指摘する「大内山川、笠木川の中州にあって要害の地であった」があらわすように平地の少ない崎村の中にあっては防御の機能を備える自然に与えられた適地であったと考えられる。 |
| 現地 |
| しかし今はその様子を見ることはかなり難しい。苦肉の策としてカシミールのソフトを使ってかろうじてその様子を想像した。 |
| 考察 |
| 三瀬館から南西に伸びる熊野街道に並ぶ城。野後城-阿曽城-阿曽元屋敷-浅間山砦(柏野城)-崎城-大内山城となる。崎城は熊野街道をおさえるルートの一端を担っていた。 |
| 感想 |
| 各学識者が研究対象にしたいと考える貴重な史料だと考えられる。松阪大学の上野教授が表現されるように「全国で唯一の現存例」は現在も尚良好な状態で保存されている。現在はまちかど博物館になっている。 |
| 備考 |
| 大内山城-7Km(1.5Hr)-崎-7Km(1.5Hr)-阿曽元屋敷-10Km(2Hr)-三瀬館 |
| 地図 |











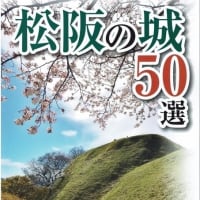

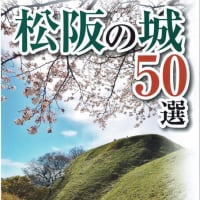
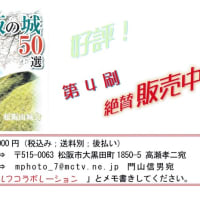




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます