
| 城名 |
| 大石御所 |
| 住所 |
| 松阪市大石町御所屋敷 |
| 築城年 |
| 永生8年(1511)か |
| 築城者 |
| 北畠材親(きちか) |
| 形式 |
| 居館 |
| 遺構 |
| 曲輪、切岸 |
| 規模 |
| 東西100×南北100m |
| 城主 |
| 北畠材親 儒学に通じた文化人である一方、仏教に深く帰依した信心厚い人物でもあったといわれている。真盛上人(注1)に諭され隠居を決意し大石に館を建てたのではないか。 |
| 標高 |
| 100m |
| 比高 |
| 10m |
| 歴史 |
| 永正8年(1511年)、病を理由に剃髪し、家督を嫡男の晴具に譲って飯高郡大石村に隠居し7年間位をここで暮らした。永正14年(1517年)に死去。享年50。 |
| 経緯 |
| 北畠材親(1468-1517)は永正7年に権大納言に任ぜらたが、翌年腫れ物を患い44歳で落飾し法号を心江と称し、飯高郡大石村の山上に隠遁した。そこは大石御所と呼ばれた。永正14年(1518)50歳で死去しました。材親の国司在任期間は永生7年~8年のたった2年間くらいという短期間でった。 |
| 若い頃から父と共に二元政治を行い、また父と共に伊勢北部の神戸氏や長野氏らの領土に侵攻して勢力を拡大した。伊勢南部においても、宇治山田の神人層と対立して抗争し勢威を拡大した。永正5年(1508年)の父の死去により、家督を継いで当主となる(実際にはかなり前に譲られていたとの説もある)。この際、伊勢守護職に任じられた。又、細川高国と結んで伊勢に軍を送って三好長秀を打ち滅ぼした。 |
| 書籍 |
| 三重の中世城館 大石公民館だより |
| 現地 |
| 蓮浄寺の西の小山平坦地にある。 |
| 考察 |
| 北畠材親は真盛上人から神宮の尊厳を悟され、武将のあるべき姿を説かれて仏門の道に入ったのだろうか。 |
| 感想 |
| 大石御所で数年間わが人生を振り返って何を思ったのだろうか。 |
| 注1 |
| 天台真盛宗の開祖である真盛上人(1443〜1495)は一志町大仰生まれ。比叡山で19歳の時から20年間厳しい修行に励み、天台教学の奥義を究める。僧侶としてエリートコースを歩んでいたが、母親の死をきっかけに下山。念仏に救いを求め、念仏の信心を体得する。庶民から武士まで幅広く慕われた。 |
| 中でも国司北畠氏が伊勢神宮外宮と内宮の紛争に出兵したことに対し、神宮の尊厳を悟し、武将のあるべき姿を説いた。当の北畠材親(きちか)は怒るどころか、信者に名を連ねている。 |
| 地図;<!-- 大石御所 --> |











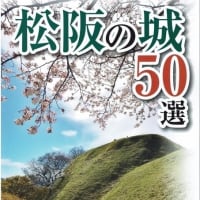

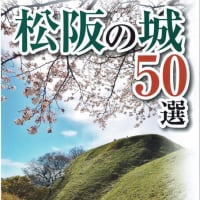
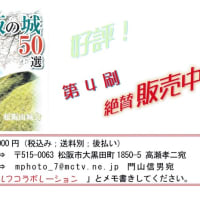




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます