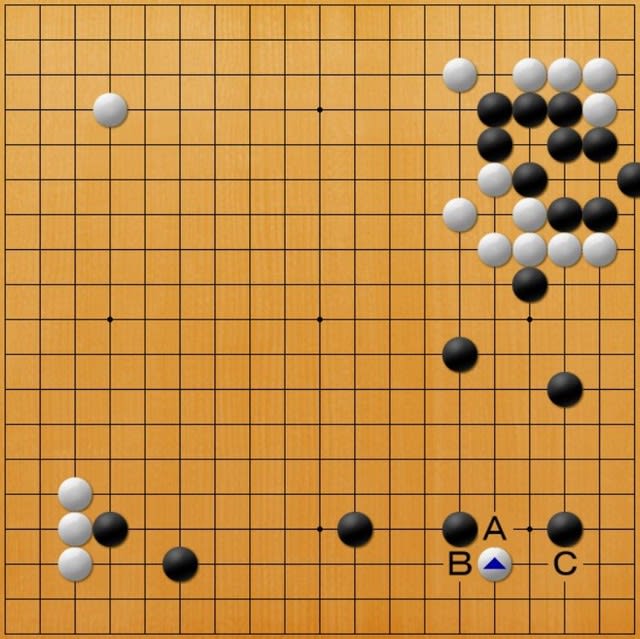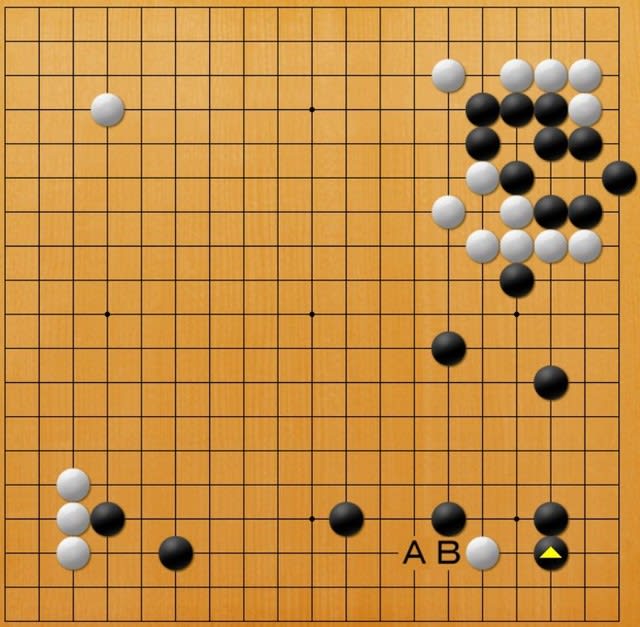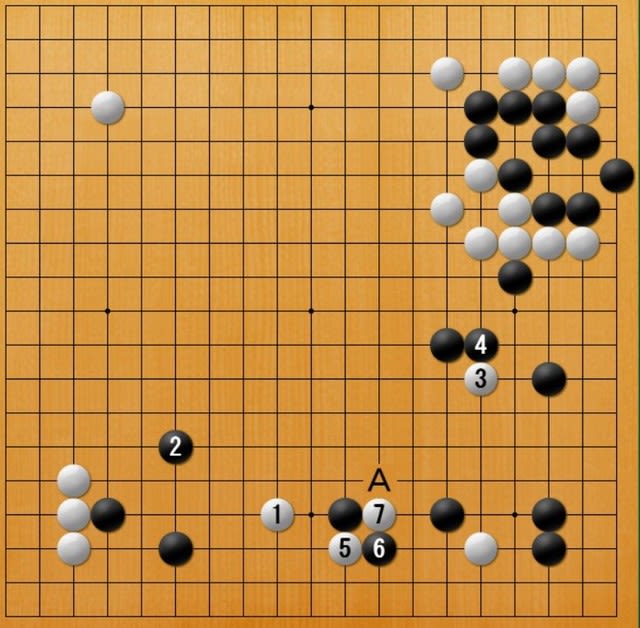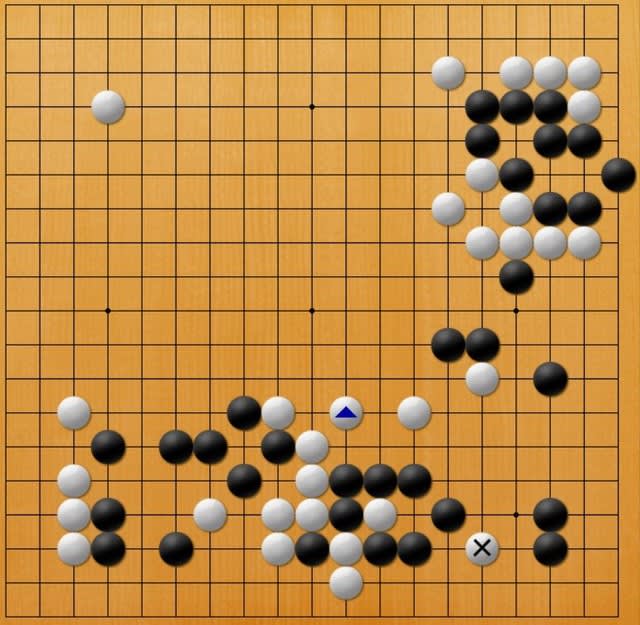<本日の一言>
暑い日が続きますね。
外出すると、自分の感じている以上に汗をかいているようです。
水分補給を怠らないように気を付けたいですね。
皆様こんばんは。
昨日は久しぶりにお休みしました。
お休みする際にはFaceBook、Twitterでお知らせしようと思っていたのですが、家に帰ったらバタンキュー(死語)でした。
さて、本日のテーマは棋力と上達です。
上達すればその分だけ棋力も上がるのか、ということについてお話ししたいと思います。
ただ、その前に棋力の定義をはっきりさせておきましょう。
私は、棋力とはその人が平均的にどれだけの勝率を期待できるかを示すものと定義しています。
別の言葉を使うなら、期待値や相場ですね。
単純にランダム性だけ考えても、5連勝したり5連敗することは当たり前に起こることです。
また、囲碁は人間が打つものですから、その時々の体調、心理状態などによって調子の良し悪しも変わります。
ただ、何百回、何千回も打てばほぼ収束するはずですね。
長期的にみて、その人がどれぐらいの段位級位で打てば勝率が丁度良くなるかを判断して棋力が決まっているわけです。
この判断は主観的に行われることもあり、システム的に行われることもあります。
前者は、例えば指導者が生徒と対局して棋力を決めるケース、後者はレーティングや勝敗によって段級位が変わるネット対局などがありますね。
実際には数百局打った結果ようやく段位が決まるようなことは無いので、正確な評価ができるとは限りませんが。
さて、前置きが長くなりましたが本題に入りたいと思います。
上達した分、そのまま棋力は上がるかどうか?
つまり、成績が真っ直ぐの右肩上がりで上がっていくかどうか?
その答えは否です。
棋力向上のためには、正しい考え方を知り、それを実践することが欠かせません。
しかし、それですぐに結果が付いてくるとは限りません。
何故なら、それは今まで用いてきた方法を修正したり、捨てたりすることでもあるからです。
それが間違った考え方であっても、今まで練習してきたわけです。
例えば、最高でも50点しか得られない考え方をしていて、その習熟度が7割という方がいたとします。
その方が100点の考え方を学び始め、その習熟度がまだ2割だとします。
その場合、短期的には勝率が上がらなかったり、場合によっては下がってしまうこともあるでしょう。
(他には技術全体のバランスという問題もありますが、今回は割愛します。)
例え話ばかりで恐縮ですが、料理では猫の手というものがありますね。
始めて包丁を握った人があの方法で食材を切ろうとすると、確実に遅くなりますし、かえって危なくなることもあるでしょう。
自己流でもなんでも、持ちやすい方法で切りたいと感じるはずです。
少なくとも私はそうでした。
ただ、正しい方法を学んでいけば、一時的にやりにくくとも、長い目で見れば料理の上達につながるということでしょう。
ちなみに、私自身は猫の手習得を早々に放棄しました(笑)。
自身の食事作りでは、火が通っていてまずくなければ良いと思っているからです。
つまり上達自体を放棄したわけですね。
まあ私の料理の腕はさておき、囲碁の上達に関しても同じようなイメージを持っているわけです。
ですから、付け焼刃の段階ではすぐに結果が出るとは限りません。
でも、技術が向上していれば、いつか必ず棋力も向上し、結果が出るようになるはずです。
停滞期間がある分、その上昇幅は非常に大きく、別人の碁のように見られることもあるでしょう。
個人的にも、定期的に指導している方がある日を境に急に強くなった経験は珍しくありません。
ただし、注意点があります。
目先の勝敗にこだわる必要はありませんが、正しく上達できているかどうかは常に確認しておくべきです。
成績が停滞しているのを一時的なことだと思っていたら、実は学んでいることや理解の方法が間違っていて、後ろ向きに進んでしまっていることもあるのです。
指導碁を受ける際には、そのあたりを確認して頂くと効果的です。
ちなみに、死活や手筋、攻め合いなどの基礎分野を学んでいる限り、効率の良し悪しはあっても、後ろ向きに進んでしまうことは少ないです。
それは皆無ではなく、例えば死活を意識するあまり隅で小さく生きようとしてしまうケースがありますが、これも一時的なものです。
死活の力が上がれば自然と改善しますし、改めて正しい考え方を教えても良いでしょう。
基本的に、基礎分野は裏切らないと思って良いです。
このような理由もあり、棋力向上のためには、まず基礎分野を学習することが推奨されています。
長年棋力が向上しないという方のほとんどは、基礎分野を学習していなかったり、学習していてもかける時間が極めて少ないです。
基礎の力が上がれば、棋力は確実に向上します。
とは言え、ほとんどの方にとって囲碁は楽しむことが第一だと思います。
無理に嫌いな分野に取り組み、囲碁が苦痛になっては本末転倒というものです。
ご自身のペースで、楽しめる範囲で取り組んで頂けば十分でしょう。
ところで、あれこれ考えながら書いていた結果、1時間半以上経過したことに気が付きました。
文章力も向上させたいものです。
暑い日が続きますね。
外出すると、自分の感じている以上に汗をかいているようです。
水分補給を怠らないように気を付けたいですね。
皆様こんばんは。
昨日は久しぶりにお休みしました。
お休みする際にはFaceBook、Twitterでお知らせしようと思っていたのですが、家に帰ったらバタンキュー(死語)でした。
さて、本日のテーマは棋力と上達です。
上達すればその分だけ棋力も上がるのか、ということについてお話ししたいと思います。
ただ、その前に棋力の定義をはっきりさせておきましょう。
私は、棋力とはその人が平均的にどれだけの勝率を期待できるかを示すものと定義しています。
別の言葉を使うなら、期待値や相場ですね。
単純にランダム性だけ考えても、5連勝したり5連敗することは当たり前に起こることです。
また、囲碁は人間が打つものですから、その時々の体調、心理状態などによって調子の良し悪しも変わります。
ただ、何百回、何千回も打てばほぼ収束するはずですね。
長期的にみて、その人がどれぐらいの段位級位で打てば勝率が丁度良くなるかを判断して棋力が決まっているわけです。
この判断は主観的に行われることもあり、システム的に行われることもあります。
前者は、例えば指導者が生徒と対局して棋力を決めるケース、後者はレーティングや勝敗によって段級位が変わるネット対局などがありますね。
実際には数百局打った結果ようやく段位が決まるようなことは無いので、正確な評価ができるとは限りませんが。
さて、前置きが長くなりましたが本題に入りたいと思います。
上達した分、そのまま棋力は上がるかどうか?
つまり、成績が真っ直ぐの右肩上がりで上がっていくかどうか?
その答えは否です。
棋力向上のためには、正しい考え方を知り、それを実践することが欠かせません。
しかし、それですぐに結果が付いてくるとは限りません。
何故なら、それは今まで用いてきた方法を修正したり、捨てたりすることでもあるからです。
それが間違った考え方であっても、今まで練習してきたわけです。
例えば、最高でも50点しか得られない考え方をしていて、その習熟度が7割という方がいたとします。
その方が100点の考え方を学び始め、その習熟度がまだ2割だとします。
その場合、短期的には勝率が上がらなかったり、場合によっては下がってしまうこともあるでしょう。
(他には技術全体のバランスという問題もありますが、今回は割愛します。)
例え話ばかりで恐縮ですが、料理では猫の手というものがありますね。
始めて包丁を握った人があの方法で食材を切ろうとすると、確実に遅くなりますし、かえって危なくなることもあるでしょう。
自己流でもなんでも、持ちやすい方法で切りたいと感じるはずです。
少なくとも私はそうでした。
ただ、正しい方法を学んでいけば、一時的にやりにくくとも、長い目で見れば料理の上達につながるということでしょう。
ちなみに、私自身は猫の手習得を早々に放棄しました(笑)。
自身の食事作りでは、火が通っていてまずくなければ良いと思っているからです。
つまり上達自体を放棄したわけですね。

まあ私の料理の腕はさておき、囲碁の上達に関しても同じようなイメージを持っているわけです。
ですから、付け焼刃の段階ではすぐに結果が出るとは限りません。
でも、技術が向上していれば、いつか必ず棋力も向上し、結果が出るようになるはずです。
停滞期間がある分、その上昇幅は非常に大きく、別人の碁のように見られることもあるでしょう。
個人的にも、定期的に指導している方がある日を境に急に強くなった経験は珍しくありません。
ただし、注意点があります。
目先の勝敗にこだわる必要はありませんが、正しく上達できているかどうかは常に確認しておくべきです。
成績が停滞しているのを一時的なことだと思っていたら、実は学んでいることや理解の方法が間違っていて、後ろ向きに進んでしまっていることもあるのです。
指導碁を受ける際には、そのあたりを確認して頂くと効果的です。
ちなみに、死活や手筋、攻め合いなどの基礎分野を学んでいる限り、効率の良し悪しはあっても、後ろ向きに進んでしまうことは少ないです。
それは皆無ではなく、例えば死活を意識するあまり隅で小さく生きようとしてしまうケースがありますが、これも一時的なものです。
死活の力が上がれば自然と改善しますし、改めて正しい考え方を教えても良いでしょう。
基本的に、基礎分野は裏切らないと思って良いです。
このような理由もあり、棋力向上のためには、まず基礎分野を学習することが推奨されています。
長年棋力が向上しないという方のほとんどは、基礎分野を学習していなかったり、学習していてもかける時間が極めて少ないです。
基礎の力が上がれば、棋力は確実に向上します。
とは言え、ほとんどの方にとって囲碁は楽しむことが第一だと思います。
無理に嫌いな分野に取り組み、囲碁が苦痛になっては本末転倒というものです。
ご自身のペースで、楽しめる範囲で取り組んで頂けば十分でしょう。
ところで、あれこれ考えながら書いていた結果、1時間半以上経過したことに気が付きました。
文章力も向上させたいものです。